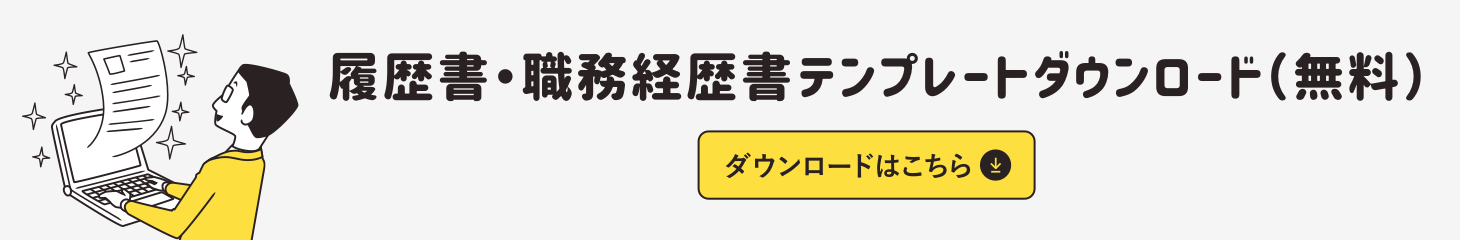「何のとりえもない自分…“強み”ってどうやって作ればいいの?」【シゴト悩み相談室】
キャリアの構築過程においては体力的にもメンタル的にもタフな場面が多く、悩みや不安を一人で抱えてしまう人も多いようです。そんな若手ビジネスパーソンのお悩みを、人事歴20年、心理学にも明るい曽和利光さんが、温かくも厳しく受け止めます!

株式会社人材研究所・代表取締役社長。1995年、京都大学教育学部教育心理学科卒業後、リクルートで人事コンサルタント、採用グループのゼネラルマネージャー等を経験。その後、ライフネット生命、オープンハウスで人事部門責任者を務める。2011年に人事・採用コンサルティングや教育研修などを手掛ける人材研究所を設立。『「ネットワーク採用」とは何か』(労務行政)など著書多数。
目次
CASE17:「アルバイトから正社員になりたいけれど、強みと呼べるものがない」(26歳女性・コンビニエンスストア勤務)
<相談内容>
地元のコンビニエンスストアでアルバイトをしています。
大学卒業後に人材派遣会社の営業職に就いたのですが、激務で体を壊し1年で辞めてしまいました。その後、今のコンビニエンスストアに務めて3年が経ちましたが、そろそろ正社員として就職したいと思っています。
ただ、転職マニュアルなどを読むと、「応募書類や面接で自分の強みをアピールしよう」と書いてありますが、アピールすることがありません。
初めの会社は1年で辞め、その後はアルバイト生活…客観的に見ても、強みと呼べるものなんてありません。とはいえ、何らかの強みをアピールしないと採用されないのはわかっていますので、これから何とか作りたいと思います。
どのように、強みを作ればいいのでしょうか?具体的な方法が知りたいです。(コンビニエンスストア・販売スタッフ)

人には強み、弱みなんてない。あるのは「特徴」だけ
私は、「人間には強み、弱みなんてない」と思っています。
人間が持っているのは「特徴」です。何をやるかによって、その特徴が「強み」になったり「弱み」になったりするだけです。
人を表現する言葉には、「社会的望ましさ」という概念がついて回ります。例えば、「性格が明るい」は社会的望ましさが強く、「性格が暗い」は社会的望ましさが低いとされています。よく心理テストや適性テストなどで、いくつかの項目から自分に合うものを選ぶとき、「こちらを選んだほうが印象がいいだろうな」と思うことはありませんか?それは、「社会的望ましさ」の概念に左右されている状態です。
だからと言って、「性格が明るい」は強みで、「暗い」が弱みかというと、決してそんなことはありません。なぜなら、「暗さ」が強みとして活きる環境もあるからです。
わかりやすい例で言えば、葬儀社のスタッフが明るく元気で快活だと、違和感がありますよね。一方で「暗い」人は、物静かで落ち着いていて、他人の悲しみに寄り添うことができるという印象を与えます。従って、このケースでは「暗い人」に強みがあると言えます。
「社会的望ましさ」が高い強みとして、よく「知的好奇心が旺盛です」とアピールする人がいますが、これも「強み」であるとは言い切れません。10年携わらないと一人前とは言えないような、専門性の高い仕事においては、知的好奇心は邪魔と判断されがちで、「変化がないとダメな人」「飽き性」などとマイナス評価されることもあります。
いろいろ話しましたが、つまりは「物は言いよう」なのです。人間のすべての特徴は、必ずプラスの言い方と、マイナスの言い方がある。それを「強み」「弱み」と表現しているだけなのですから、「強みがない」と悲観的に捉えないことです。
では、何をアピールすればいいのか。
どんな人にも、その人ならではの「特徴」があります。紙などに、自分の特徴をどんどん書き出していって、一つひとつ、プラスに言い換えてみましょう。
もしうまく言い換えられなかったら、家族や友人など、あなたのことをよく知る第三者に頼んでもいいでしょう。そうすれば、あなたの「プラスの特徴」が洗い出されるので、そのプラスの特徴が活かせそうな環境を探して応募すれば、好意的に受け取られ、プラス評価してくれるはずです。
仕事を楽しみ、面白がろうと工夫する「意味づけ力」は高く評価される

相談内容を見ると、「強みがない」という相談者の悩みは、「就職先を1年で辞めたうえに、3年もアルバイトをしてきた」という職務経歴に対する自信のなさに起因しているように思われます。「アルバイトだし、責任ある仕事をしているわけではないし…」と自分を卑下しているようですが、そのように思う必要はありません。
コンビニで3年も働き続けてこられたのは、素晴らしいことです。新卒入社者の離職率は「3年3割」と言われていますが、飲食サービス業は「3年5割」であるというデータがあります。3年間で5割もの人が辞めている中、相談者は頑張って働き続けているのですから、少なくとも「継続する力」は高いと言えます。
「誰にでもできる仕事だから、スキルなんてついていない」と思っておられるのかもしれませんが、3年間同じ仕事を続けてこられたのには何らかの理由があるはず。
きっと、自分なりにこの仕事を楽しもう、面白がろうと工夫してきた経験があるのでは?例えばですが、常連客の顔を覚えて挨拶をしてみたり、商品陳列の際に見栄えが良くなるよう工夫を凝らしてみたり、混み合うお昼どきに1秒でも早く来店客をさばくことを自分に課してみたり…なんてことをしてきませんでしたか?
「日々のルーティンワークを楽しく、面白くできる人」は、意味づけ力がある人だと高く評価されます。「意味づけ力」とは、どんな地味な仕事でも「自分にとって意味がある仕事だ」と捉え、楽しめるよう自ら工夫できる力のこと。これができるか、できないかで仕事のパフォーマンスは大きく変わるため、どの企業の人事担当者も必ずチェックし、高く評価しています。
相談者はまだ26歳。スキルよりもポテンシャルが評価される年齢です。どんな小さな工夫でもいいから、応募書類や面接で、自分なりに考え実行してきたことを、ディテールまで語りましょう。
オタクに倣って、仕事で工夫したことを熱っぽく語ろう

「ディテールの語り方」ですが、ここはオタクに倣いましょう。
好きなものの魅力を他人に伝えるときって、熱量が高くなりますよね?アニメファンやアイドルファンに「どんなところが好きなの?」と聞くと、ものすごい熱を込めて詳細まで語ってくれたりします。そのアニメやアイドルのことをまったく知らなくても、「ここまで熱く語るほど魅力があるのか。一度くらい、見てみようかな」と思えます。
ここまでの「マニア的な熱量」でなくとも構いませんが、コンビニのバイト経験も、こういうふうに語れると相手の心をつかめると思います。
例えばですが、「商品パッケージが見やすいよう、この棚の陳列をこう変えたら、これぐらい売り上げが上がったんです!」「この新商品を売り出すためにこんなPOPを考えたら、すごく評判が良くて!本部の社員まで見学に来ちゃったんです!」なんてキラキラした目で熱っぽく語られたら…あなたが採用担当者だったら、どう思うでしょうか?「どんな仕事でも、彼女なりに工夫して楽しんでくれそうだな。インプットの機会を与えれば、頑張ってくれそうだな」と入社後の活躍に期待しますよね。
阪急グループの創業者で、宝塚歌劇団の創設者でもある小林一三の名言に、「下足番を命じられたら、日本一の下足番になってみろ。そうしたら、誰も君を下足番にしておかぬ」というものがあります。どんな小さな仕事であっても、日本一になる気概で徹底的にやれば、さらに大きな、やりがいのある仕事が与えられるということ。
仕事を与える側である企業のトップや上司は、こういう視点で社員を見ているのです。それがわかれば、今の仕事にもっと自信と誇りを持てるようになるはず。自分の特徴とともに、経験を前向きに、イキイキとアピールできるようになりますよ。
アドバイスまとめ
どんな些細な経験でもOK!
自ら工夫したことを熱を込めて語り
あなたの「特徴」を伝えよう
こちらの記事も読まれています
新着記事
 2025年6月24日履歴書の「学歴・職歴欄」の書き方│ケース別見本・Q&Aあり
2025年6月24日履歴書の「学歴・職歴欄」の書き方│ケース別見本・Q&Aあり 2025年5月23日やりたい仕事がない。やりたい仕事の見つけ方と転職する場合の注意点
2025年5月23日やりたい仕事がない。やりたい仕事の見つけ方と転職する場合の注意点 2025年3月27日応募書類が自動で作成できる!リクナビNEXTの「レジュメ」機能とは?
2025年3月27日応募書類が自動で作成できる!リクナビNEXTの「レジュメ」機能とは? 2025年3月14日転職活動で役立つ!無料の自己分析ツール厳選5種を紹介
2025年3月14日転職活動で役立つ!無料の自己分析ツール厳選5種を紹介 2024年12月17日第二新卒の転職理由・退職理由|本音も交えた上手い答え方&NG例文
2024年12月17日第二新卒の転職理由・退職理由|本音も交えた上手い答え方&NG例文 2024年12月3日盛り上がらず淡々と終わった面接は、不合格?それとも合格?
2024年12月3日盛り上がらず淡々と終わった面接は、不合格?それとも合格? 2024年11月29日コンサル業界の面接特徴|企業のチェック観点と答え方、準備・対策のコツ
2024年11月29日コンサル業界の面接特徴|企業のチェック観点と答え方、準備・対策のコツ 2024年11月27日自分に合う「ニッチな企業」「隠れた優良企業」の探し方
2024年11月27日自分に合う「ニッチな企業」「隠れた優良企業」の探し方