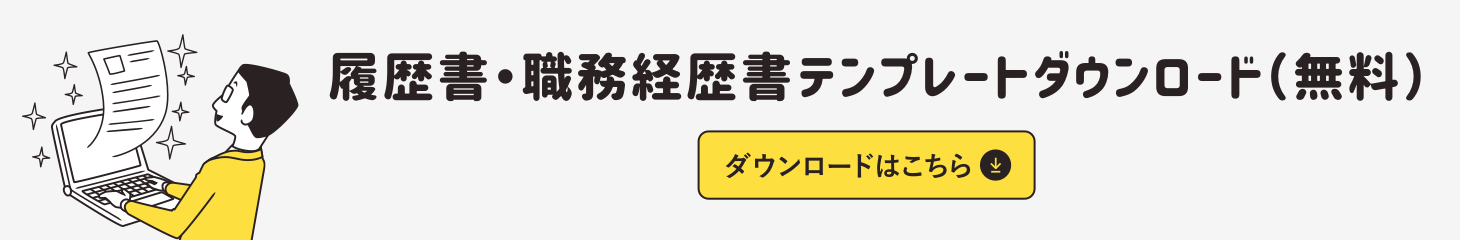盛り上がらず淡々と終わった面接は、不合格?それとも合格?

転職活動をしていると、面接中の会話がいまいち弾まず、面接担当者の反応も薄いなど、盛り上がりに欠けたまま、淡々と終わってしまうこともあるでしょう。
なぜそうした面接が起こるのか、候補者はどう対応するべきなのか、組織人事コンサルタントの粟野友樹氏に聞きました。
会話が弾まずに終わった面接は、不合格?合格?
面接中の会話が弾まず、手応えなく終わってしまった面接は「きっと不合格だ」と思いがちです。
しかし、面接の進め方は企業の選考スタンスにも依るため、盛り上がりを感じていても不合格になる人もいれば、淡々と面接を終えても合格になる人もいます。
つまり、明確な合否のサインはありません。
ただ、盛り上がりに欠けた面接は、「何らか、期待に沿わない回答があったのかも」「話し方や表情はどうだっただろう」と自分を振り返るチャンスになります。
淡々と終わってしまったと思うのなら、自分の対話姿勢に改善点はなかったかを考えてみてもいいかもしれません。
また、候補者が「盛り上がらなかった」と捉えるということは、その場の空気感や面接担当者とのやりとりに「違和感があった」とも考えられます。
それでも選考に通過した場合、「社風やカルチャーと本当に合うだろうか」と一度立ち止まって検討してみるのもいいと思います。
なぜ、会話が盛り上がらず、淡々と終わってしまう面接があるか
面接は、面接担当者と候補者との「人と人のやりとり」であり、面接の数だけ、その場で生まれる空気は異なります。
すべての面接が、質疑応答のやりとりがスムーズに進んだり、会話のテンポよく共感が生まれたりなど、“盛り上がり”を感じる場になるとは限りません。
では、候補者が「淡々と終わってしまった」と思う面接は、なぜ起こるのでしょう。
考えられる企業側の背景
考えられる企業側の背景には、次の内容が挙げられるでしょう。
①企業の面接手法・選考スタイルによるもの
企業の中には、「淡々と聞くべき質問を聞く」というスタイルの構造化面接を取り入れているところもあります。
構造化面接とは「あらかじめ設定した質問項目や評価基準に沿って実施する」面接手法。面接担当者の経験やスキルに依存することなく、誰でも一定の基準で候補者を評価できるなどの特徴があります。
候補者からすると、この構造化面接は「雑談もなく質問だけされる」「面接担当者の感情が見えない」「機械的で冷たい感じがする」という印象を抱くこともありますが、雑談などから候補者の本音を引き出す…といったやり方は、面接担当者の力量に大きく左右されます。
また、あらかじめ評価基準が定まっていないと、面接担当者の好みで合否が決まる可能性もあります。
構造化面接のメリットは、そうした、面接担当者による評価のばらつきを抑えられるところにあります。
②面接担当者のタイプや志向性、面接スキルによるもの
企業の面接手法とは関係なく、面接担当者が面接に不慣れだったり、合理的に情報を知りたいタイプだったり、事務的に進めたいタイプだったりすると、面接が淡々と終わってしまうこともあるでしょう。
候補者からすると、答えた内容について突っ込まれることなく進んでいくため、「何が不要なことを言ってしまったのではないか」「自分に興味を持ってくれていない」と不安になってしまいがちですが、面接は様々な人が担当するもの。
特に、面接が一次、二次、最終と進んでいくと、現場の責任者や役員など、本来は採用活動をすることが主な業務ではない人も面接を担当するケースが増えていきます。
中には、面接自体に不慣れで、一つの回答を、深堀りするスキルを持ち合わせていない担当者がいても不思議ではありません。
企業の質問意図を理解して回答することが大事
ここまで企業側の背景を紹介してきましたが、「淡々と進んでしまう面接」の原因が候補者にあるケースもあります。
例えば、企業側の質問に対して、論点がズレた回答を繰り返したり、具体性のない話ばかり続いたりすると、面接担当者は「質問を重ねてもほしい情報が得られそうにない」と思ってしまいます。
面接が進むにつれ、質問のやりとりはますます淡々となっていくでしょう。
そのため、面接では、企業側がどんな意図で質問をしているのかを理解した上で、答える姿勢が大切です。項目ごとに、想定される意図や、答えるときのポイントを考えていきましょう。
「自己紹介」の質問意図と答える時のポイント
企業が自己紹介を求める意図はさまざま。「緊張をほぐす」「人物の印象をつかむ」「面接で深堀りしたいポイントをつかむ」「プレゼン能力をチェックする」などがあります。
簡潔に要約して話す力を見られているので、面接で深掘りしてもらいたい要点を1分程度でまとめ、すべてを伝えようと盛り込みすぎないことがポイントです。
表情や話し方からも、普段の仕事ぶりが見られています。
「これまでの経験内容」の質問意図と答える時のポイント
「経験・スキルが求める要件に合致しているか」「これまでの経験を活かして入社後に活躍できる人材かどうか」を判断しようとしています。
職務経歴は、時系列で長々と話すことは避け、応募企業で活かせる経験については厚めに、それ以外の経歴は簡単に触れる程度にしましょう。
アピールしたい経験は、「担当業務」「組織での役割」「成果」「成果に至ったプロセス」をセットで具体的な数字などとともに伝えましょう。
未経験の仕事への転職を目指す場合は、応募企業でも活かせる「ポータブルスキル(業種・職種問わず持ち運びできるスキル)」として、コミュニケーション力、折衝力、調整力などを培った業務内容にフォーカスして伝えてください。
「転職理由・退職理由」の質問意図と答える時のポイント
自社に入社しても、また同じ理由で辞めてしまうようなことにならないか、入社後に意欲的に働けそうかを確かめる狙いがあります。
転職理由を聞かれたら、「退職理由(転職を考えたきっかけ)2割+転職で実現したいこと8割」で話すのが理想です。
退職理由だけになると、不平不満などネガティブな内容が多くなる方もいるからです。
「志望動機」の質問意図と答える時のポイント
自社についてどれだけ研究しているかをチェックし、興味の度合いや、仕事に取り組む姿勢がどれくらいあるかを見ています。
志望動機では、応募企業に応募した理由、応募企業に貢献できる理由、入社後に実現したいことを伝え、転職理由や自己PRとの一貫性を持たせた内容にしましょう。
漠然とした企業や仕事内容への憧れではなく、企業・仕事理解を元に、自身の経験やスキルなどとの接点を伝えられているかが大切です。
「キャリアプラン/将来の目標」の質問意図と答える時のポイント
「入社後、どうなりたいですか」「5年後・10年後に何をしていたいと思いますか」といった質問をする意図には、
| ・キャリアの志向が、自社のキャリアパスと一致するかどうかを確認したい ・自社の社風・文化に合うかどうかを見極めたい ・応募者の「成長意欲」を確認したい |
の3点があります。
キャリアプランを伝える際は、転職理由や志望動機と一貫性を持たせ、将来実現したいことと転職で実現したいことが重なっているかを確認します。
さらに、応募企業での実現可能性も加味していきましょう。
「仕事での成功体験」の質問意図と答える時のポイント
成果を挙げた経験からスキルレベルを測るとともに、成功体験を通じて身に付けたスキルやノウハウを自社でも再現して活躍できるかを見ています。
成功体験を聞かれたときには、「自己PR」を伝える機会と捉え、
| ・自身のこれまでの経験を通じた強み ・根拠となるエピソード ・強みを活かして貢献できること |
を話します。
数字や固有名詞を出し、できるだけ具体的な情報を伝えることがポイントです。
単なる実績自慢にならないように、応募職種との接点を見出し、転職先でいかに貢献できるかを伝えましょう。
「仕事での失敗体験」の質問意図と答える時のポイント
トラブルの乗り越え方、ストレス耐性など見ているほか、失敗の要因を分析し、そこから学んで成長できる人材であるかどうかにも注目しています。
失敗体験そのもの以上に、「失敗に対して、どのように捉えどのような対処をしたか」「失敗経験から学んだこと」「失敗による心境や行動の変化」「二度と失敗しないために心がけていること」などを整理して伝えるといいでしょう。
「長所・短所(強み・弱み)」の質問意図と答える時のポイント
長所(強み)からは、人柄のほかに、自社とのマッチ度を見ています。
「こんな強みを持った人材がほしい」といったニーズがあり、それに合致する人物を探していることもあります。
短所(弱み)から知りたいのは、「自己認識力」です。
冷静に自己理解を深め、「自身の改善点を認識しているかどうか」「伸びしろはありそうか」を見ています。
強みを整理する際は、企業側のニーズや接点を意識します。
例えば、自分にとっての強みが「チームを裏側で支える力」だったとしても、組織を先頭で引っ張るリーダータイプを求めている応募企業には強みにならないことがあるでしょう。
一方、弱みを伝える際は、改善策や、乗り越えるために取り組んできたことをセットで伝えましょう。
「ストレスを感じるとき/ストレスの解消法」の質問意図と答える時のポイント
ストレスの感じ方、ストレスへの対処法を確認することで、職種や社風に合うかどうかを見極めようとしています。
自己認識力や問題解決能力を測ろうとする意図もあります。
ストレスを感じる事象や場面だけではなく、対処法もあわせて伝えることが大切です。
「希望条件(年収・勤務地・残業への対応・入社時期など)」の質問意図と答える時のポイント
自社の労働条件・労働状況に合致しているかを確認します。
条件面は希望がすべて通るわけではありませんが、年収なら希望と再下限、希望する理由なども伝え、企業側が検討しやすい情報を提供できるといいでしょう。
入社日も、希望日と最短可能日を、理由や状況も添えて共有すると検討されやすくなるかもしれません。
「逆質問」を促す意図と答える時のポイント
面接の最後に「何か質問はありますか?」と聞かれる逆質問は、入社にあたり疑問点を解消しておくことを意図しています。
候補者にとっては、「理解度」「入社意欲」「質問力」をアピールするチャンスともいえるでしょう。すでに聞いたことや、HPや求人を見たらわかることは避け、「こういう情報から、こう考えたのですが、実際はどうですか?」と仮説をぶつけるのもいいと思います。
また、仕事内容の詳細は現場の社員に聞き、最終面接の社長には事業の方向性について聞くなど、相手の立場に応じた適切な質問を心がけましょう。
- タグ:
こちらの記事も読まれています
新着記事
 2025年6月30日履歴書での教員免許の書き方|正式名称と種別一覧表
2025年6月30日履歴書での教員免許の書き方|正式名称と種別一覧表 2025年6月30日履歴書の簿記は何級から?書き方と仕事別レベル目安
2025年6月30日履歴書の簿記は何級から?書き方と仕事別レベル目安 2025年6月30日履歴書のTOEICは何点から?書き方注意点・志望企業別スコア目安
2025年6月30日履歴書のTOEICは何点から?書き方注意点・志望企業別スコア目安 2025年6月30日英検を履歴書「資格欄」に書けるのは何級から?志望企業別スコア目安・注意点
2025年6月30日英検を履歴書「資格欄」に書けるのは何級から?志望企業別スコア目安・注意点 2025年6月24日履歴書の「学歴・職歴欄」の書き方|ケース別見本・QAあり
2025年6月24日履歴書の「学歴・職歴欄」の書き方|ケース別見本・QAあり 2025年5月23日やりたい仕事がない。やりたい仕事の見つけ方と転職する場合の注意点
2025年5月23日やりたい仕事がない。やりたい仕事の見つけ方と転職する場合の注意点 2025年3月27日応募書類が自動で作成できる!リクナビNEXTの「レジュメ」機能とは?
2025年3月27日応募書類が自動で作成できる!リクナビNEXTの「レジュメ」機能とは? 2025年3月14日転職活動で役立つ!無料の自己分析ツール厳選5種を紹介
2025年3月14日転職活動で役立つ!無料の自己分析ツール厳選5種を紹介