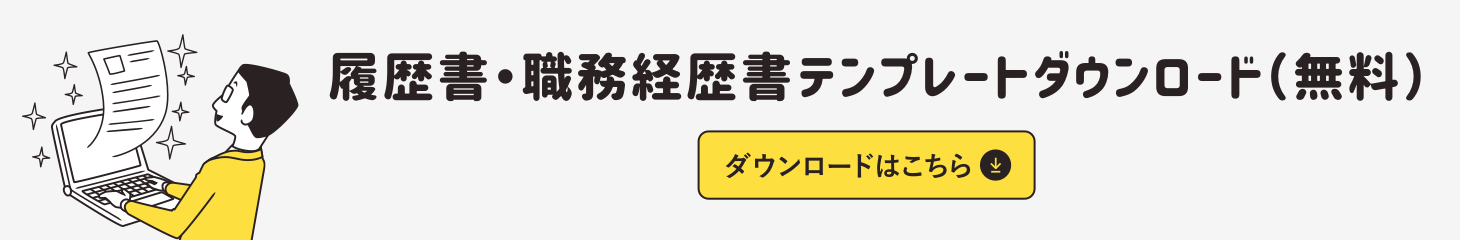自分に向いている仕事がわからない時の見つけ方
 仕事がうまくいかないことは誰しもありますが、上司から注意されたり、同僚からミスを指摘されたりすることが重なると、「自分にはもっと向いている仕事があるのではないか」、「自分に向いている仕事がわからない」と思うこともあるでしょう。
仕事がうまくいかないことは誰しもありますが、上司から注意されたり、同僚からミスを指摘されたりすることが重なると、「自分にはもっと向いている仕事があるのではないか」、「自分に向いている仕事がわからない」と思うこともあるでしょう。
そもそも、「向いている仕事」とはどんなものなのでしょうか。人事歴20年超、現在は人事領域支援会社を経営する「人事・キャリアのプロ」、曽和利光さんに、向いている仕事の見つけ方について伺いました。
アドバイザー

株式会社人材研究所・代表取締役社長
株式会社人材研究所・代表取締役社長。1995年京都大学教育学部教育心理学科卒業後、リクルートで人事コンサルタント、採用グループのゼネラルマネージャー等を経験。その後、ライフネット生命、オープンハウスで人事部門責任者を務める。2011年に人事・採用コンサルティングや教育研修などを手掛ける人材研究所を設立。『「ネットワーク採用」とは何か』(労務行政)、『コミュ障のための面接戦略』(講談社)など著書多数。
自分に向いている仕事とは?
まず、「向いている仕事」とは、自分がパフォーマンスを十分に発揮して、そのプロセスや成果に満足ができる仕事と定義します。
これまではよく、仕事でパフォーマンスを十分に発揮するためには、その仕事に求められる能力に自分の能力が見合っているか、業種・職種の特徴が自分の志向と一致しているかで語られてきました。
しかし昨今、グローバル企業で「一緒に働く人との相性」が仕事のパフォーマンスに大きく影響していると注目されるようになり、日本企業の人事関係者も、一緒に働く人との相性が、従業員本人の能力を発揮できるかどうかに関わる大きな要素だと認識し始めています。
これを踏まえて、向いている仕事を決める要因は次の3つだと設定することができます。
・志向
・一緒に働く人との相性
この3つの要素が、すべてフィットしていれば、自分にとっての「向いている仕事」と捉えることができます。
特に、人事関係者の中では、高度な専門性を求められる職種以外は、性格や特性の影響は大きいと認識され始めているため、転職においてのカルチャーフィット(企業文化に合うか)を採用側が重視する傾向が強くなってきています。
自分に向いている仕事の見つけ方
では向いている仕事を決める3つの要因ごとに、自分が希望職種に向いているかを判断する方法を見ていきましょう。
「能力」から向いている仕事を見つけるには
能力は、「ナレッジ(知識)」「スキル(技能)」「コンピテンシー(高い成果を出す行動特性)」の有無で決まってきます。
ナレッジ、スキルについては、その業種や職種で必要とされる知識や技能を身に付けているか否かです。ナレッジは、その仕事の現場で求められる専門的な知識のことです。例えば、人事であれば、採用・育成・評価・労務管理・人事制度など人事に関わる業務知識が必要とされます。これらを習得していれば、ナレッジの面で、人事の仕事に向いていると捉えられます。
スキルは、その仕事の現場で成果を出すための行動が取れるかどうかです。同じく人事で見てみると、新卒採用に関する計画を立てて成果につなげることができれば、「スキル」の面でノウハウがあり、人事に向いていると捉えられます。希望職種に向いているか考える場合は、ナレッジ・スキルを身につけているかどうか、客観的に整理してみましょう。
コンピテンシーに関しては、ジョン・L・ホランドが提唱するRIASECというキャリア理論に基づく理論やSPIを含めた適性検査で職務適性を見極めていく方法などがあります。
「志向」から向いている仕事を見つけるには
志向は、その業種・職種が好きか否か、志したいか否かです。例え能力が足りなかったとしても、ナレッジ、スキルを身に付けようと努力するモチベーションやエネルギーが沸くかどうかと考えてみましょう。
自分の志向を深堀するために、5回「なぜ?」を繰り返してみてください。「なぜこの仕事を希望しているのか?」「それはどうしてなのか?」を繰り返していきます。
結果、その志向を持つ理由が憧れや机上論ではなく、自分の経験に紐づいて語れるようであれば、その仕事に向いていると捉えることができます。
例えば、Webエンジニアになりたかったとしましょう。「なぜ?」を自問していく過程で、「学生時代にWebデザインのアルバイトをしていて、想像を超えたWebデザインに出会い衝撃を受けた。今の自分では表現できないけれども、挑戦していきたい」と、経験とつながった答えが出てくる場合は、あなたの中に志が根付いています。しかし、「これからはデザインに価値がある時代で、ITでそれを実践することが社会で求められているのでやってみたい」と、自分の経験と紐づかない一般論でしか語れない場合は、あなたの中に志が根付いていないため、何か壁に出会ったときに、乗り越えられるほどのエネルギーが沸かずに諦めてしまうことが多いものです。
「一緒に働く人との相性」から向いている仕事を見つけるには
どのようにすれば「一緒に働く人との相性」から、向いている仕事を見つけられるのでしょうか。転職の場合は、求人ポジションが明確で、上司になる人も決まっている場合がほとんどです。ここでは、一緒に働く人の中でも特に重要な「上司との相性」にフォーカスして、相性の合う仕事の見つけ方を考えてみましょう。
まず、興味のある求人があった場合、「一緒に働く人」はどんな人なのかという視点で、事前に情報収集をしましょう。企業のホームページで経営者・人事インタビューや社員紹介を見ると参考になるでしょう。求人サイトに、上司になる人のインタビューが出ていることもあります。
一方で、「自分はどのようなタイプの上司と一緒に働いたとき、活躍できたのか」も、自分で理解しておきましょう。
面接は、転職先の企業の人と、自分との相性を判断するチャンスです。求人ポジションの上司に当たる人が面接官であれば、その人と対話がうまくいくかどうかは大きなポイントですし、直属の上司ではなくても、企業の文化が見えてきます。
また、面接官からも相性を判断してもらえるよう、適切なタイミングで、自分が働くうえでの「上司との相性」にまつわる情報を伝えてみましょう。
例えば、仕事の中での成果を聞かれた際に、能力を発揮できたポイントと、そこでの上司との相性を話すなどの方法です。
自分で工夫した成果を話した上で、「現場に任せながらも、いざという時はフォローをしてくれる上司のおかげで、自分が強みとするプロジェクトの具体的な進行やスケジュール調整、関係各所との調整で力を発揮することができました。」など、自分の特性と自分に合う上司の特徴を言語化して伝えます。
さらに、「今後は自分もプロジェクトを俯瞰しながら、リーダーシップをとってプロジェクト管理できるよう、守備範囲を広げていければと思っています。」など、今後の成長の意欲まで伝えられるとよりよいでしょう。
従来、面接の中では能力や志向を伝えることが中心でしたが、「一緒に働く人との相性」が重視されるようになった昨今、あえて、通常の面接では言語化されない、特性や相性についての情報を伝えることで、より自分に合った仕事に出会える可能性が高くなります。
向いている仕事を見つけるには過去の経験を紐解く
ここまで、向いている仕事を判断する「能力」「志向」「一緒に働く人の相性」という3つの要素について見てきました。今の仕事で何か合わないと感じていることがあり、転職を考えているのであれば、3つの要素を掘り下げてみましょう。
一緒に働く人との相性について、社会人経験が少ない20代の人は、学生時代の先生やアルバイト先の上司でもいいので、成果を出した時に一緒にいた上司を分析してみてください。向いている仕事は、過去を分析することから見つかります。
- タグ:
こちらの記事も読まれています
新着記事
 2025年10月21日リクナビNEXTの「オファー」とは?
2025年10月21日リクナビNEXTの「オファー」とは? 2025年10月16日2005年(平成17年)生まれの学歴・職歴用の入学・卒業年度早見表
2025年10月16日2005年(平成17年)生まれの学歴・職歴用の入学・卒業年度早見表 2025年10月16日2004年(平成16年)生まれの学歴・職歴用の入学・卒業年度早見表
2025年10月16日2004年(平成16年)生まれの学歴・職歴用の入学・卒業年度早見表 2025年10月9日履歴書で「以上」はどこに書く?書き方のポイントや書き切れない場合の対処法を紹介
2025年10月9日履歴書で「以上」はどこに書く?書き方のポイントや書き切れない場合の対処法を紹介 2025年9月5日履歴書の封筒の書き方、入れ方【記入サンプルあり】
2025年9月5日履歴書の封筒の書き方、入れ方【記入サンプルあり】 2025年9月5日事務職の自己PR例文|職種別のアピールポイントと書き方
2025年9月5日事務職の自己PR例文|職種別のアピールポイントと書き方 2025年9月5日履歴書|基本情報欄の書き方ガイド(日付・メアド・電話番号・印鑑など)
2025年9月5日履歴書|基本情報欄の書き方ガイド(日付・メアド・電話番号・印鑑など) 2025年9月5日企画職の自己PR例文|業界別のアピールポイントと書き方
2025年9月5日企画職の自己PR例文|業界別のアピールポイントと書き方