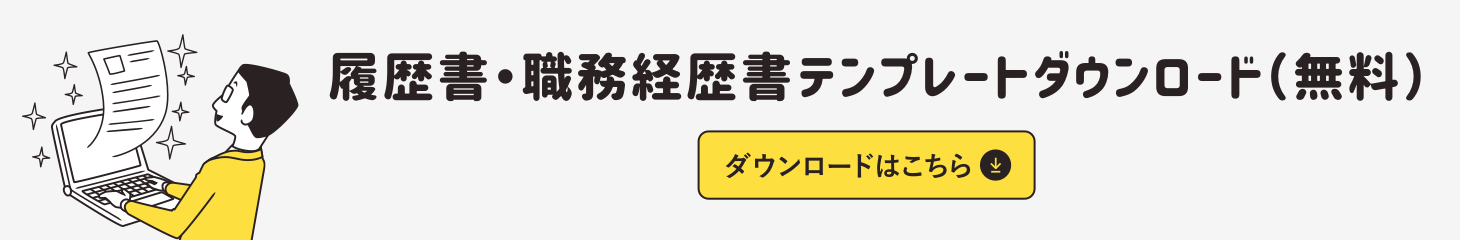人間関係が変わる!?「共感力」をアップさせるための3つの方法
インターネット全盛の現代。そんなデジタル時代だからこそ、デジタルでは割り切れないアナログの「気づかい」に悩まされる人が増えています。自分ではよかれと思って行動したのに、裏目に出てしまい、恥をかいたり、かかせたり。それだけに止まらず、相手の期待を大きく裏切り、信頼を失ったなんて経験をした方もいると思います。悲しいですが、自分の気づかいが、必ずしも相手に喜ばれるわけではありませんよね。そこで『損する気づかい 得する気づかい』 (ダイヤモンド社刊)の著者 八嶋まなぶさんに、損しないための気づかいの極意を教えてもらいました。

プロフィール
八嶋まなぶ(やしま・まなぶ)
サラリーマン作家。「気づかいLabo」主宰。広告業界の第一線で営業職として勤務するサラリーマン作家。東証一部上場企業の経営者、世界的企業のCEO、政治家、医師、弁護士、大物俳優・女優、クリエイター……など、総勢3500名を超える「鬼のように気をつかう」クライアントと仕事をともにし、その過程で気づかいやダンドリといった対人スキルを磨く。その結果、「業界平均3割で上々」と言われる競合プレゼンにおいて、勝率は7割超をキープ。近年では口コミでクライアントから「直接指名」で仕事を獲得するようになる。そうした経験を通し、「そつなく気をつかい、うまいことやっていく人」と、「気はやさしいのに、よかれと思ったことが裏目に出る人」には決定的な共通点があることを実感。「空気を読む」「あうんの呼吸」といった概念を、極めて具体的なアクションに起こし、紹介する活動を開始。プライベートレッスンでは「コミュニケーションが苦手だった人が無理なく人と話せるようになる」「新卒の大学生が飛び込み営業のエースになる」など、実績を残している。2019年4月より国内最大級のメルマガ「まぐまぐ」からオファーを受け、より突っ込んだ内容の気づかいメルマガも配信。
【共感の気づかいPOINT】
損する人は、「〇〇してみたら」とアドバイスする
得する人は、「××なんだ」とあいづちを打つ
共感の気づかいは、「アドバイスを減らすこと」で始まる
「普段のコミュニケーションにおいて、なんとなく伝わっていない気がする」
「同じことを言っているのに、同じ職場のAさんの方がうまく周りを巻き込んで仕事を円滑に進めている」
「上司から『正論ばかりで配慮が足りない』と叱られた」。
なんて経験のある方もいると思います。そんな方はもしかすると「共感力」が足りていないのかもしれません。
「共感」を国語辞典で調べると、「他人の意見や感情などにそのとおりだと感じること」と書いてあります。つまり共感力とは、相手の気持ちに寄り添うことと言えます。もしあなたが「共感力が不足している」と思うなら、“気持ちに寄り添う”というスタンスではなく、相手の気持ちに踏み込んで変にアドバイスし過ぎているのかもしれません。
例えば、私が考える「共感力を持っている人」の特徴としては以下のようなことがあります。
- 相手が7割、自分が3割の配分で会話をする
- 相手の話を頭ごなしに否定しない
- 求められない限り、こちらからアドバイスしない
つまり、自分ではなく相手が主役。他人の意見や感情などにそのとおりだと感じるためには、自分の意見を話し過ぎては、コミュニケーションで損してしまいます。自分の好きな話題を話し、テンションを高めるのもいいのですが、人間関係をよりスムーズにしていくためには、「変にアドバイスせず、相手の話をまずはじっくり聞く」くらいがちょうどいい塩梅です。特にお客様との打ち合わせ、会社の会議、上司との飲み会……などなど、気をつかうようなこれらの場面では、ある程度合わせにいくのが、損しないための気づかいだと言えます。
また逆に相手の気持ちがわかり過ぎて、自分の考えが出せないという「ある意味共感力の高い(?)人」もいます。そんな人は「もらいっぱなしのプレゼント」をイメージしてみましょう。会話は相手との情報のプレゼント交換とも言えます。相手の話をよく聞くのが基本スタンスでも、一方的に話を聞き続けるのはかえって相手に失礼というもの。ときには相手に会話のプレゼントをお返ししなくては、無礼となり、損する人付き合いとなってしまいます。
共感力をアップさせる3つの方法
では実際にどのように共感力をアップさせればいいのか?その方法を3つ紹介します。どれも簡単ですぐに使える方法なので、ぜひあなたの生活に取り入れてみてください。今まで損していた人の「勘違いコミュニケーション」をぐんと減らすことができると思います。
【共感力をアップする方法1】「主語」を入れ替えて観察する
人は誰でも自分の話をしたい生き物です。共感力を上げるために、相手を主役にして会話すると言われても、無意識のうちに「自分が主役」の話をしてしまうものです。だからこそ「主語」を入れ替えて観察する工夫をしてみましょう。たとえばこんな感じです。
- 「相手は、なぜこの話題を選んだのだろう?」
- 「相手は、今、どんな気持ちなんだろう?」
- 「相手は、なぜそれを私に話しているのだろう?」
いかがですか?主語を自分から相手に入れ替えて、話を観察するだけで相手に寄り添う姿勢が自ずと身についていきます。「あなたの気持ちが知りたい」というあたたかい目で、主語を入れ替えてみてください。
【共感力をアップする方法2】話しを聞くときは「繰り返し」を使う
安心感を持って、相手に話をしてもらうためには、相手が7割・自分が3割の配分で会話をすることが有効です。そのために心理学者やカウンセラーが使う「バックトラッキング」という方法を使ってみましょう。やり方は簡単で、相手が話したことを「繰り返す」だけ。たとえばこんな感じです。
- 相手:「最近、残業がきつくて」 ⇒ 自分:「残業がきついんだ」
- 相手:「プレゼンが通って嬉しかった」 ⇒ 自分:「嬉しかったんですね~」
- 相手:「面白い話があってね」 ⇒ 自分:「面白い話なんだ」
と、いう感じです。相手が話したことを繰り返すだけで、面白いように相手が言いたいことを中心に会話を進めることができるようになります。深刻な相談事の場合でも大丈夫です。人は誰かに相談する際には、実は心の中で自分の答えを見つけているものです。であれば変にアドバイスばかりせず、繰り返しを使って、相手の言いたいことを「うんうん」と聞いてあげる方が、相手と深いコミュニケーションができるものです。
【共感力をアップする方法3】「ひょっとしたら」を付け加える
とはいえ、相手の話を一方的に聞くだけでなく、あなたの意見をいう必要もあります。そんなときに使えるのが「ひょっとしたら」を付け加えるという方法です。
主語を相手に入れ替え、話を聞きながら相手を観察していると「ひょっとしたらこの人は〇〇と考えているのかもしれない」という疑問が出てきます。それに対して意見すればよいのです。
- (疑問があるとき)「ひょっとしたら××に困っていない?」
- (ちょっとした意見の言い方)「ひょっとしたら××が役立つかも」
などという感じです。この「ひょっとしたら」という意見が一致すると、「自分のことを理解してくれる」と相手は想い、あなたに対しての好感度がぐんと高まりますので、ぜひ使ってみてください。
【チェックポイント】
- 相手が7割、自分が3割の配分で話す
- 相手の話を否定しない
- 「主語」を入れ替えて観察する
- 「繰り返し」を使う
- 「ひょっとしたら」を付け加える
まとめ
気づかいに才能は必要ありません。「損する」地雷を避け、「得する」型だけを実践していけば、だんだんと、そして自然と、「あっ、この場合は、こうしておいたほうがいいかな……?」という感覚が、磨かれていくのです。ぜんぜん乗れなかった自転車に、急に乗れるようになる。そんな感覚が必ず訪れます。気づかいは、そんなに難しいことではない。そして、気づかいがうまくいくと、人生こんなに楽しいことはない! あなたにも、そんな心境になってほしいなぁと思い、ビジネスの気づかいからプライベートの気づかいまで、幅広く使える気づかいの型を「損する気づかい 得する気づかい」に凝縮しました。あなたの人生に幸あれ! バラ色の日々が訪れることを祈りながら、ぜひ、本書を活用してください。
参考図書
『損する気づかい 得する気づかい』
著者:八嶋まなぶ 出版社: ダイヤモンド社
こちらの記事も読まれています
新着記事
 2025年6月30日履歴書での教員免許の書き方|正式名称と種別一覧表
2025年6月30日履歴書での教員免許の書き方|正式名称と種別一覧表 2025年6月30日履歴書の簿記は何級から?書き方と仕事別レベル目安
2025年6月30日履歴書の簿記は何級から?書き方と仕事別レベル目安 2025年6月30日履歴書のTOEICは何点から?書き方注意点・志望企業別スコア目安
2025年6月30日履歴書のTOEICは何点から?書き方注意点・志望企業別スコア目安 2025年6月30日英検を履歴書「資格欄」に書けるのは何級から?志望企業別スコア目安・注意点
2025年6月30日英検を履歴書「資格欄」に書けるのは何級から?志望企業別スコア目安・注意点 2025年6月24日履歴書の「学歴・職歴欄」の書き方|ケース別見本・QAあり
2025年6月24日履歴書の「学歴・職歴欄」の書き方|ケース別見本・QAあり 2025年5月23日やりたい仕事がない。やりたい仕事の見つけ方と転職する場合の注意点
2025年5月23日やりたい仕事がない。やりたい仕事の見つけ方と転職する場合の注意点 2025年3月27日応募書類が自動で作成できる!リクナビNEXTの「レジュメ」機能とは?
2025年3月27日応募書類が自動で作成できる!リクナビNEXTの「レジュメ」機能とは? 2025年3月14日転職活動で役立つ!無料の自己分析ツール厳選5種を紹介
2025年3月14日転職活動で役立つ!無料の自己分析ツール厳選5種を紹介