「モノづくり×イノベーション×はたらく」をテーマに、日本のメーカーでイノベーションの現場や最前線で活躍する方々をゲストに迎え、『リクナビNEXT』編集長・藤井薫が「イノベーションを生み出すために必要なものとは」「個の力と組織の力が響き合う鍵とは」についてお話を伺います。
今回は、JXTGエネルギー取締役常務執行役員の宮田知秀氏です。エネルギー業界を代表する大手メーカーの革新への源泉を伺いました。
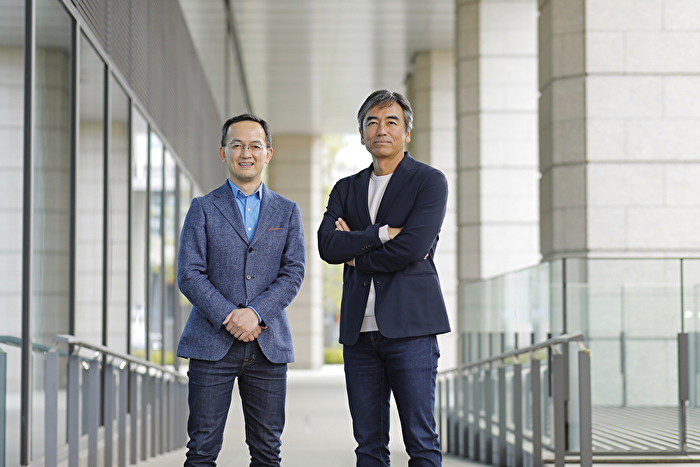
プロフィール
JXTGエネルギー株式会社 取締役 常務執行役員
水素事業推進部・FCサポート室・中央技術研究所 管掌
宮田知秀氏(写真右)
1990年、東京工業大学原子力工学修士課程修了後、東燃株式会社入社。総合研究所配属。2004年、東燃ゼネラル石油株式会社和歌山工場保全部長、2006年和歌山工場長、2008年執行役員、2011年取締役和歌山工場長。2012年、取締役・川崎工場長、同年常務取締役・川崎工場長。2013年、常務取締役として 精製・物流本部長兼川崎工場長などを務め、2016年、専務取締役精製・物流本部長に就任。2017年、JXTGエネルギー株式会社取締役常務執行役員製造本部副本部長に就任。2019年より現職。
株式会社リクルートキャリア 『リクナビNEXT』編集長
藤井 薫(写真左)
1988年にリクルート入社後、人材事業の企画とメディアプロデュースに従事し、TECH B-ing編集長、Tech総研編集長、アントレ編集長などを歴任する。2007年からリクルート経営コンピタンス研究所に携わり、14年からリクルートワークス研究所Works兼務。2016年4月、リクナビNEXT編集長就任。リクルート経営コンピタンス研究所兼務。著書に『働く喜び 未来のかたち』(言視舎)。
目次
同質的ではなく「異質な意見」をぶつけ合うことが革新につながる

藤井薫編集長(以下、藤井)
グループを挙げてイノベーションに取り組んでおられるJXTGですが、その“エンジン”の役割を担うのが中央技術研究所。宮田さんはこの研究所ご出身であるとか。これまでどんな経験を積んでこられたのか、お聞かせいただけますか?
宮田知秀氏(以下、宮田)
大学、大学院と原子力工学を専攻し、東燃(現・JXTGエネルギー)入社後は当時の総合研究所(現・中央技術研究所)に配属、燃料電池の研究開発に携わっていました。その後、工場でエンジニア職に就いていた2000年に、東燃とゼネラル石油が合併し東燃ゼネラル石油に。その前年にそれぞれの大株主であるエクソンとモービルが合併していたことから、資本的には4社が1つになった格好。その日から上司は外国人になり、文化や風土もがらりと変わりました。
藤井:ある日突然、勤務先が外資になったのですね。
宮田:その通りです。レポートラインもすべて英語になったことから、必死で英語を勉強しましたね。その後、アジアパシフィックのエクソンモービルのプロジェクトを担当していた時期があったのですが、部下の半数は外国人で、しかもオーストラリアやタイ、シンガポールなど国籍もさまざま。いろいろな文化や考え方に触れ、知見を増やすことができました。このようなチャレンジの機会をもらえたのは、いい経験でしたね。
その後、和歌山工場の工場長となりましたが、ちょうど国内の石油需要がしぼみ始めたころで、合理化の対象として和歌山工場の名前が挙がっていました。そこで、工場としてのあらゆる可能性を検討、海に囲まれた立地で、大型の製品船が着桟できる桟橋が多い点を活かし、“輸出の拠点”として生まれ変わらせました。また潤滑油においては、日本一の製造能力まで増強しました。
藤井:変化を機会に転換する。危機を再成長に転換する。宮田さんの変革の歩みは、若い時から続いているのですね。
宮田:その後、東燃ゼネラル石油とJXグループの経営統合に伴い、JXTGエネルギーの取締役となり、現在に至ります。私は転職したことがないのですが、この30年の間に何度も合併を経験し、文化や風土、仕事の進め方もガラリと変わるという経験をしてきたので、もう何度も転職してきたような気分です。
藤井:御社は合併によりいろいろなバックグラウンドを持つ人が集まっているので、同質的ではなく異質な意見をぶつけ合い、革新を続けているという印象を持っています。
宮田:そうですね。会社としても、イノベーションを生み出しやすいよう組織変革を行っています。例えば昨年、JXTGホールディングスに「未来事業推進部」を設置。革新的事業アイデアを事業化につなげるとともに、JXTGグループ一丸となって長期ビジョンの確実な実行を推進したいと考えています。また、JXTGエネルギーでは中央技術研究所内の技術戦略室に「事業創出推進グループ」を設置、戦略的な新商品・新サービスを創出する体制を整え、新規事業の創出に注力しています。
とはいえ、イノベーションはそんなに簡単に起こせるものではない、とも実感しています。イノベーションを起こすには失敗するのが当たり前であり、減点主義からは何も生まれない。そして、すぐに思いつけるようなことは「誰かがすでに挑戦したこと」である可能性が高く、イノベーションを起こすには今まで誰も考えたことがないようなことに着眼することが重要です。そのため、メンバーには常に頭を柔軟にして発想をがらりと切り替えてほしいと伝え続けています。
中長期視点で未来を見据え、技術革新に取り組み続ける

藤井:2019年に発表されたJXTGの長期ビジョンでは、2040年に向けグループとして「低炭素・循環型社会の達成」を掲げていらっしゃいますね。
宮田:国内燃料油需要の構造的減退、グローバル市場での競争激化、資源価格変動など、今後当社を取り巻く事業環境は厳しさを増していくと想定しています。またその中で、エネルギー産業全体として低炭素化、温室効果ガス削減が供給・消費の両面で求められていると考えています。
SDGs、ESGの観点も踏まえ、エネルギー企業として社会的責任を果たしながら当社が生き残っていくためには、中長期での革新的技術への挑戦が必須。R&Dセンターとしての中央技術研究所の重要性はこれまで以上に増しています。新規分野に関する研究開発費や投資の増額により技術革新を後押しするとともに、イノベーションを生み出せる人材育成、環境整備もスピード感をもって実施していきたいと考えています。
藤井:長いレンジで物事を見据え、挑戦し続けようとするJXTGの「胆力」を感じます。
宮田:これは合併を繰り返す中でもずっと当社の土台を支え続けてきた姿勢です。例えば、「CO2フリー水素」は地球温暖化対策に貢献する技術として注目されていますが、この水素を運搬するには、水素をいったん有機ハイドライドの一種であるMCH(メチルシクロヘキサン)に変換する必要があります。
このMCHの研究には、14,5年前から取り組んでいます。当時は「実を結ぶことはないんじゃないか」と思われていた研究ですが、今では注力テーマとなっています。そして、MCHの製造工程を大幅に簡略化する製法も確立、CO2フリー水素製造の低コスト化を実現する技術検証にも成功しました。
これで水素社会の実現に一歩近づきましたが、日本国内で求められるエネルギー量のボリュームは非常に大きいため、さらに中長期視点をもって技術革新に挑戦し続け、CO2フリー水素の社会実装に取り組みたいと考えています。
藤井:全体ではキャッシュフロー経営を重視しながらも、今すぐキャッシュ化できないけれど未来を見据えた「中長期の挑戦」も複眼的に行っているのですね。短期と中長期。こうした“時間の二重奏”の視座と実践こそ、持続的なイノベーションのカギなのですね。
「外向きのネットワーク」が、日本の製造業全体に求められている
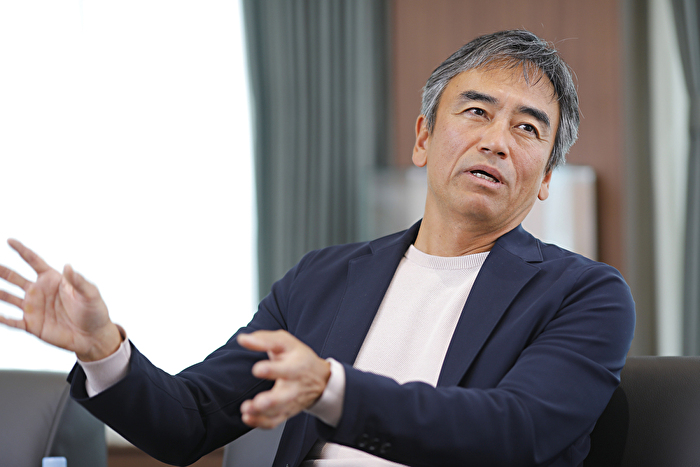
藤井:日本はそもそも資源が少ないため、「今あるものをうまく使いまわす」ことが得意です。従って「循環型社会」というテーマにおいては、もっと強みが活かせる場面があるのではないかと思うのですが…宮田さんはどう思われますか?
宮田:確かに、日本が得意な分野だと思いますし、その強みを伸ばすのも大事だと思いますが、もっと外に目を向けないとイノベーションという意味では世界に後れを取ると思っています。当社の社員にも、自社のこれまでの知見や成果にこだわることなく、積極的に外部リソースを活用するよう伝えています。
そして会社としても、ベンチャーキャピタルファンドへの投資やアクセラレータプログラム(ベンチャーやスタートアップ企業との事業共創)を積極化しています。昨年から、ディープラーニングの研究開発を行うスタートアップ企業Preferred Networks社と、AIを活用した製油所の最適化・自動運転と、材料開発の効率化を目指したMI(マテリアルズインフォマティクス)技術に関する共同研究を進めています。
Preferred Networks社のボードメンバーは皆研究者で、MIT(マサチューセッツ工科大学)の論文を片っ端から読み込むなど、いろいろな情報をどん欲に取り込んでいます。当社の製油所にお連れしたことがあるのですが、現場のベテラン・エンジニアにどんどん質問して話し込み、何時になっても帰ろうとしないんです。年次や年齢に臆せず、一方でリスペクトして学ぼうとする。彼らのようにどんどん外に目を向け、外の情報を積極的に取りにいく「外向きのネットワーク」を作ることが、今の日本の製造業全体に求められていると感じますね。外に出ていく勇気さえあれば、強みを武器に「覚醒」することができると思っています。
藤井:異なる業界、職種、領域。異なる年次、年齢、世代。異界に越境し、異質と共鳴する好奇心と行動力。これは、働く一人ひとりが明日からできるイノベーションですね。
反対したくなる部下のアイデアこそ、敢えて全部やらせる
藤井:JXTGグループとしてアクセラレータプログラムを積極化しているとのことですが、実にさまざまなテーマのビジネスプランを検討されているのですね。電動マイクロモビリティのシェアリングサービスや、マインドフルネス対話型AIによるメンタルトレーニングサービス、訪日外国人向けレンタカー旅行ドライブルートプランナーなど、「こんな分野にまで挑戦されているのか」と驚きました。
宮田:「地球の未来を創るイノベーション」をキーワードに置き、グループの中核企業(エネルギー、石油開発、金属事業)のバリューチェーン(調達、研究開発、製造技術、物流および販売等)を活用するビジネスプランをベンチャー企業から募集し、事業化を目指しています。
少し「飛び地」と思われる分野にも投資をしているのは、これらの未来事業が最終的につながってくると考えているから。基盤、インフラ、モビリティ…すべてはエネルギーという軸でつながっていくと思っています。
藤井:これらの未来事業の現場では、社内外の若手ビジネスパーソンが「イノベーション」を目指して多数活躍されていると思いますが、この記事を読んでいる若手読者に対して「個の力を活かす方法」についてアドバイスいただけないでしょうか。
宮田:若手に言い続けているのは、「チャンスがあったら逃さず獲れ」ということ。「今は忙しいから止めておこう」と見逃す人と、すぐにチャンスをつかめる人には大きな差がつくと思います。我々を取り巻く環境は大きく変化しており、変革に乗れるいいタイミングでもある。だからこそ若い人には失敗を恐れずどんどんチャレンジしてほしいですね。受け身ではなく、自らチャレンジできる人は、絶対に伸びます。
ただ、変化や変革を面倒くさがる風土の会社では、なかなかチャレンジし難しいかもしれませんね。その点当社では、マネージャー層に「反対したくなる部下のアイデアこそ、敢えて全部やらせてみよ」と言っています。我々ぐらいの世代が「これいいな」と思うものは、絶対に今までに誰かが必ずやっているはず。イノベーションにはつながらないからです。
そういう意味でも経営陣が、「失敗しても大丈夫。どんどん挑戦してほしい」とメッセージを出し続け、若手の力を引き出すことが重要だと感じています。いろいろなところに、アイデアの芽が存在するし、何が未来につながるかわからない。その可能性を大切にしたいですね。

【取材を終えて・・・】
地球の力を、社会の力に、そして、人々の暮らしの力に。これは「JXTGグループの使命」の初文です。
まさに私たち人類は、地球のエネルギー・資源・素材を、社会の力・暮らしの力に変換し、文明を発展してきたことに改めて気づかされました。AIも5Gも自動運転も企業の未来も。そして、私たち働く一人ひとりの毎日も、エネルギーなしでは、電池の切れたスマホのように駆動することができません。そのエネルギーを充電し、発露し、変革にどうつなげるか?
脱減点主義、中長期の時間軸、機会を見逃さず異界に飛び込む。貴重なキーワードを伺いました。いずれも、エネルギーを現在の正解にとどめず、未来の機会につなげてゆく、循環哲学にあると実感しました。冒頭の文を後ろから読めば、人々の暮らしの力を、社会の力に、そして、地球の力に。となります。働く一人ひとりのエネルギーの発露が、世界のイノベーション・地球の力を輝かせる。人と組織のエネルギーを循環する。そんな同社のエネルギー・サービス・プラットフォームの未来が楽しみになりました。(藤井)

























