働き方改革には、根本的な「働き方の多様性」が必要だ。それにはまず、日本の雇用形態がどういう仕組みで成り立っているかを理解することが必要だ。人事管理のプロ、海老原嗣生氏が語る。

ジョブ型雇用と日本型雇用
日本最大の人事コミュニティ「グローバル人事塾」の2017年を締める勉強会に、HRコンサルティング会社ニッチモ代表取締役の海老原嗣生氏が登場した。
いま日本で働くというと、働く側の立場からするとまず長時間労働、適切なワークライフバランスが取りにくいという問題がある。
一方、企業側に起きているのは人材不足。中途採用が難しく、全体的な労働力も不足している。そこで働き方の多様化などが提唱されているのだが、そもそも正規雇用と非正規雇用の格差などの問題が解決されていない。
海老原氏は雇用の問題を語るにはまず雇用形態、その構造を知ることから始めるべきという。
たとえば、欧米と比較してよく言われる「なぜ日本は転職が少ないのか?」。その理由は、日本人および日本社会特有のメンタルな問題だとされる。
「ポイント制退職金の導入も進んできて、若い人は損をするから転職しないなんて考えていない。ではなぜ、転職しないのか。問題はそこで、日本は転職しなくても済むからだというのは、人事管理の面から見るとすぐにわかるはずだ」と。
 ▲株式会社ニッチモ 代表取締役 海老原 嗣生(えびはら つぐお)氏
▲株式会社ニッチモ 代表取締役 海老原 嗣生(えびはら つぐお)氏
これらは決してメンタリティの問題ではない。
雇用のメカニズムを理解することで、問題がはっきり見えてくる。
そもそも「ジョブ(職務)」は「タスク(課業)」を集めてパッケージにしたもの。課業というと聞き慣れないかもしれないが、細かな業務のこと。たとえば、「採用広報を行う」というのはジョブ。その中の「採用媒体を決める」「求人情報を作る」「求人広告を発注する」「求人広告制作における取材対応」、これらはタスクだ。
つまり、仕事の最小単位がタスクで、「あなたはこれとこれをやってください」というタスクのパッケージがジョブ、その詳細を具体的に記述したものがジョブディスクリプション(JD)となる。
欧米は、ジョブディスクリプションがきちんと用意されているジョブ型なので、超負荷な仕事を押し付けられることもない。それが欧米の良いところだと一知半解な解釈をされる。
海老原氏は、ジョブ型の本質をわかっていない人が多いという。

「デビット・グリルマンは『80年代にジョブディスクリプションはその役割を終えている』と言いました。なぜ終わったか。
ブルーカラーには完璧に使えます。ネジをしめる、塗る。ところがホワイトカラーが労働の主流になってくると、たとえば営業は人によってやり方が違うから、ジョブディスクリプションに書けるわけないのです」
逆に、職務を詳細に書くことで、「それ以外はやらない」となりかねない。そのため、現在のJDには職務範囲と責任など、上位概念を書くことが多い。あくまで、そのポストの担当ということを明確にするものという位置付けだ。
佐藤博樹さんの比較研究によると、各国の状況は次のとおり。
- フランス――採用後の柔軟な変更を予定して、職務の名称や肩書程度の一般的な内容に留める
- アメリカ――ホワイトカラーの職務記述書はある程度概括的、抽象的に書かれている。職務記述書の内容は包括的なものに留まっており、職務内容が厳格に特定されているわけではない
- ドイツ――職務内容を明確にしつつも、その範囲が狭くならないようにバランスに留保する
つまり欧米でも、やるべき仕事を決めてタスクとして羅列するという仕組みにはなっていないのだ。では、ジョブ型の本質は何かというと、「本人の同意がない限り他の職務には動かせない」ことだ。

「他の職務と聞くと、経理から人事とか、そういうことだと思うかもしれませんが、そうではありません。同じ営業の中でもいろいろな担当があります。その中でも動かせないのです。
たとえば、派遣の人を雇ったときに『◯◯課の庶務』ということで契約します。
同じ営業職だからといって隣の部署に動かしていいかというと、これは契約上NGです。つまり、そういう仕組みです。勝手に動かせない。企業が勝手に動かしてはいけない。それがジョブ型の根源です」
ジョブ型雇用の場合、昇進・異動は本人の意思確認を行った上で、拒否しても不利益を受けない、基本的に、昇進や異動は社内公募などで労働者との合意でなされる。職業キャリアの形成については労働者個人の選択に委ねるべきで、人事権は企業にはないということ。
日本型雇用とジョブ型の最大の違いはここで、日本型雇用の場合、労働者は「会社に入る」という契約であり、企業は人事権を持つ。ジョブ型はそうではなく、この仕事(ジョブ≒ポスト)で雇われているということになる。
職務主義と職能主義
次に、職務主義と職能主義の違いについて。
日本企業の組織運営において特徴的な考え方の1つに「職能主義」がある。では、職務主義とはどう違うだろうのか。職務主義と職能主義、この2つがわかるといろいろな疑問が氷解していくという。
ポストの数が(業務上必要なだけ)あらかじめ細かく決まっているのが職務主義、一方、日本では社員が持つ能力に応じて職能等級を定める。どういうことかというと、この人は能力的に上がったので、と課長と同等の等級にする(しかし、課長ではない)。職能等級をもって、給与や処遇などモデルとして定めるのが日本型の職能主義だ。

「たとえば課長並みというので4級、でも実際課長になってはいない人は『見なし課長』とか『専任課長』と呼ばれます。これはポストではありません。課長というポストは課に1つしかないわけです。
ところが、この人は能力が高いから職能等級上は課長と同じにする、これは日本型の職能等級という考え方です。職務主義の場合、ポストに重みがついていて、そのポストになったらその給与、その役職になりますということ。課長のポストにいるならば課長だし、係長のポストなら係長になります。係長のポストにいるけど課長(職能等級上)だという人はいないわけです」
この違いから何が言えるかというと、職務に重みがついているポスト主義では「ポストをもらえない限り、昇進しない」のだ。
昇進も給与アップもポストにひも付き、そのポストの数は人事編成会議、経営会議などで組織の必要性で決まってくる。リーダーならリーダーの給与となる。この人はリーダーだけど職能等級は課長並みなので給料も課長のレンジになる、ということはない。
職能主義の場合、ポストでは決まらない。それは職能等級による。等級だけアップしていって平社員でも課長並みの給与をもらうということが普通に起こる。

当然、職能主義では「ポスト=職務」とはならないということ。同じ平社員ポストの中に課長並みの能力(等級)を持っている人がいれば、その人はクレーム処理もするし、教育指導もやる。
一方、同じ平社員ポストでも、1年目の人は言われてやるだけの仕事しかしない。つまり、日本は社員の処遇と業務内容が明確になっていない。

「外国から見ると、同じ平社員ポストなのになぜあの人は給与が高いのか、それがわからない。日本人的に見れば、等級が違って違う仕事をしているから不思議ではないのですが、欧米ではポストで仕事が決まってくるから、(同じポストで同じ仕事をしているはずなのに)なぜ給与があんなに高いのか、それは年功的だからだと誤解を受けるのです。給与が職能についているか、ポストについているかという差です」
ここまでひもといてきて、冒頭の転職の謎が解明される。
なぜ、欧米では転職が非常に多いのか、日本では起きないのか。
つまり、ポスト主義の欧米では給与を上げるには自分のポストを上げていくしかない。自動的にあげていってはくれない。能力がアップしてもポストは新たに作ってもらえない。もし能力アップしたのに上のポストが埋まっていた場合、給与を上げる方法は、上のポストの空いている会社に行くしかない。だから、人が辞めるのだ。

「逆にポストが空いている会社はそれを埋めなければいけないわけです。日本みたいに、誰かが上がるまで兼務でしのぐということはできない。向こうも必死に取ろうと思っています。
つまり転職が起きるのはメンタリティではなく、こういう給与の決定の仕組みが違うから。日本の場合、がんばっていればポストがなくても給料は上がります。本当に能力のある人であれば、ポストがなくとも。そうしたら、社内にいるほうがいいですよ。つまり、こういうことが転職が起きない理由です」
限定されているのか、限定されていないのか
では、ジョブ型/ポスト型雇用、日本型雇用の本質はどこにあるのか。
ジョブ型/ポスト型雇用
- 企業側に人事権がない
- ポストの数は決まっている
- ポストが給与、職務内容にひもづく
⇒ 限定
日本型/職能主義
- 企業側に人事権がある
- ポストの数は決まっていない
- ポストで給与、職務内容は決まっていない
⇒ 無限定
このように、ジョブ、職能、職務と3つを合わせて考えると非常にクリアになる。ジョブ型は職務も給与もポストも限定されている。日本の場合は職務内容も決まっていない、ポスト数も決まっていない、限定されていない。
限定されているのか、限定されていないのか、ということ。
ただ、日本の職能給も昨今では状況が変わってきている。がんばって能力アップしていけば、給与が上がり、誰でも歳をとるとそこそこの給与になる。
しかし、役割が不明確だったため、職能等級だけ上がって何をしているかわからない人が出てきてしまう。一度上げてしまった等級は下げられず、企業は人件費が増えて困る事態になっていく。
それなら役割を明確にしようということで、職責給あるいはミッショングレード(役割給)を定める、ミッションベースの等級制度が登場する。

「何人でも任用できる、役職もフレキシブルに与えられる、ポストで職務が決まってこないという職能等級では、高資格なのに何もやらないという人がかつてたくさん生まれたから。
リクルートの制度も、ポスト数があらかじめ決まっていて、それ以上の人を上げられないかというとそうではないわけで、成長すればみんな上げることができる。また、たとえば「A支社平社員」という同一ポストにも、グレードの違う人がたくさんいるという状況になる。同じ平社員ポストなのに、君はランクが上だからこれをやらなきゃいけない、となる。そう考えると、やはり日本型の延長といえる。
そこで、職能資格の要件をより厳格にし、資格ごとにやるべきこと、なれる人を明文化したということです」
しかし誤解されがちだが、これは職務主義ではない。「たとえば、リクルートもミッショングレード制でうちは職務主義だと言っているが、実際、そうではない」と海老原氏。あくまで日本型無限定雇用だ。
コストで上限が決まっていて、それ以上に人を上げられないかというとそうではないわけで、成長すればみんな上げることができ、結果、同じ平社員でグレードの違う人がたくさんいるという状況になる。同じポストで同じ平社員なのに、君はリーダーだからこれをやらなきゃいけない、となる。そう考えると、やはり日本型の延長といえる。
外部労働市場と内部労働市場
もう一歩進んで、外部労働市場と内部労働市場というものを考えてみよう。
日本型雇用は定着率が高いといっても、日本を代表する大手自動車メーカーでさえ、毎年1,000名くらいの欠員が出る。その多くは定年退職だ。
たとえば、自動車の最終組立ラインの職長が辞めてしまったとする。最終組立ラインの職長というと、かなり高度な仕事を任されている。混成ライン(1つのラインで、2種類のクルマを作る、など)の段取り替えができるような人でなければならない。そのポジションの人が辞めてしまったら、どうやって補充するか?
たとえば、クルマの内部機構の設計におけるプロジェクトリーダーを長年やっていたエンジニアが辞めてしまったら?
機構設計の主査クラス、トランスミッションの機構設計をやっている課長、あるいは系列ディーラーの管理、販売統括をやっている部長が抜けてしまったら?

「中途採用で採るのは、正直難しいです。同じメーカーでもパソコンメーカーには自動車系のエンジニアはいません。もちろん、リクルートにも商社にもいない。ここなのです。
よく経済学者、識者という人たちは『労働市場で採れ』と言いますが、採るとしたら同業同職しかいないわけです。欧米の場合は流動性が高いから採れますが、その分抜ける人も多い。3倍抜けたら、3倍採らなきゃいけない。その3倍も生まれる欠員の補充は、同業同職での取り合いになります」
どこの国でもそうだが、企業にとって中途採用は非常にコストがかかる、大変なことだ。中途入社の場合、「入ったポストの仕事を、明日からできなければ」ならない。そんな人は同業・同職に基本は限られる。そうすると、競合企業から引き抜かねばならず、大変に手間がかかるのだ。
そのため、欧米ではサクセスションプランという重要ポストの後継者候補を確保・育成する仕組みを用意しているが、一番簡単なのは、欠員、抜けた穴を内部労働市場から補充する方法だ。

「そのポストの1つ下には、3~4倍の部下がいるわけです。その中の一番優秀な人をポンとあげるのが一番簡単です。技術力もほぼ近いし、言葉も通じるし、顔も知っているし、仕事内容もわかっているのだから。下からあげるのが一番簡単。これだけなんです、補充というのは」
現実的な人事管理だと、欠員の補充は基本、横から動かす。たとえば、神戸支社長が抜けたら広島支社長から、といった具合に。こうして横で埋めていくと、どこかの支社には、頃合いよく、ちょうど支社長になれそうな人物がいる。
だからその支社では支社長が横異動して空いた空席を下からの補充で埋める。今度はその「下」たとえば係長ポストに空席ができる。これも横異動で補充していくうえで、どこかの部署では頃合いのよい「リーダー」がいるので彼を係長に上げる。
こんな形で、横・縦に空席が玉突きさせながら補充を重ねていく。一つの部署で欠員ができると、人事的にはこんな補充をその6~8倍やらねばならなくなるだろう。
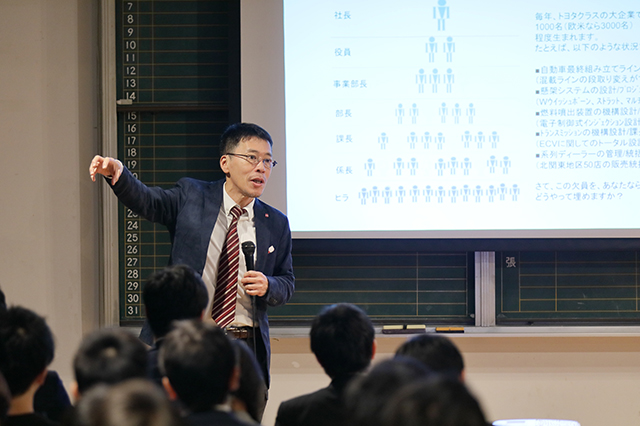
実は、ここがポイントだ。
日本は、横でも縦(上下)でも異動が自由にできる。本人同意も関係なく埋められる。6から8、その数倍の空席ができても、内部の人事異動だけで済む。
一方の欧米は、動かすときには本人同意が必須。昇進ならみんな同意するかもしれないが、横では「どうして?」となってしまう。玉突きなんてとても、ということになる。それが外部労働市場に採りに行く理由だ。課長が抜けたら外からその「課長」に人を入れれば終わり、だからだ。ポスト主義という人事制度が基本にあるからだ。

「日本の場合、どこが抜けようが簡単に横、縦とパズルみたいに寄せていって、最終的に一番末端に空席ができるだけです。部長が抜けようがスペシャリストが抜けようが、どこが抜けても、末端に1席空席ができるだけ。
部長やスペシャリスト・役員が抜けても多々空席ができたとしても、最終的に玉突きで空席を下に寄せて、新卒採用するだけなのです。
ここで気づいてほしい。競合から1000人を採りにいくという大変な行為と、大量採用可能な新卒を1000人採用するのと、どちらがラクか」
海老原氏はこれを「魔法の杖」と表現する。そして、それがいまだに日本の企業が新卒採用、年功序列を止めない理由とする。不況のたびに減って、そのたびにこれで新卒採用は終わりと言われるが、好景気になるとまた大量の新卒採用が行われる。
そうして考えると、簡単な話なのだ。
こうしてメカニズムで考えれば簡単にわかること。それはメンタリティやジェンダーの話ではないということ。

「内部補充の場合、日本は3月、9月の人事異動で一発です。欧米では、玉突きでもタイムラグが発生する。その間、半年だけでも兼務しておいて、というのもポスト型では難しい。
だから外から埋めて、内部で玉突きはしないのです。日本の場合、兼務でしのいでおいて、3月、9月の人事異動で埋める。採用は新卒の一発で多くがすみます」
つまり、なぜ日本は中途採用で埋めないのか。下から上げれば済むので簡単だから。日本型企業がなぜ新卒採用を止めないのか、内部に人材を貯めて育成していけば、これほど補充がラクなことはないから。
そして、人もなぜ転職しないのか。能力アップさえしていれば、ポストがなくても、給与は上がる。業績不調な企業ではそれがなかなかかなわないかも知れないが、そうではない限り、普通の企業はがんばっていれば給与が上がる。だから何年経っても、転職が増えないということなのだ。
いま中途採用が活発に行われているが、それがどういうことかというと、下にいないような人たち、たとえばM&Aのプロとか女性管理職、社内にいない人材を外部労働市場から採っている。女性のラインはできていないため社内にいない。そのため、(女性管理職を増やせと今言われているので)外から採るしかないのだ。
後半では、もう少し日本の雇用問題について掘り下げていこう。
⇒後編「なぜ、日本は解雇が難しいのか?」を読む
※本記事は「CodeIQ MAGAZINE」掲載の記事を転載しております。




















