人手不足の折、「仕事が忙しいのに、どんどん追加の仕事を振られる」と疲弊している若手ビジネスパーソンは少なくありません。自分ばかり仕事を押し付けられていると感じ、不満を抱いている人もいるようです。
「仕事を押し付けられている」と思ったら、どのように対応すればいいのでしょうか?人事・採用コンサルタントの曽和利光さんに伺いました。
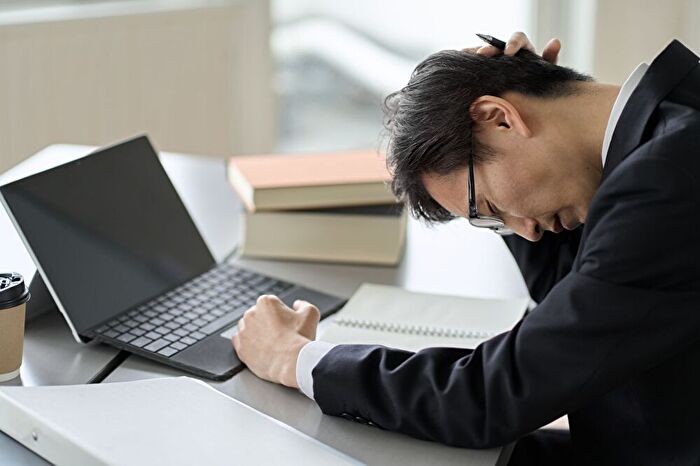
目次
仕事を押し付けられやすい人の「二大特徴」とは?
仕事を頼む側からすれば、「頼みやすい人に頼む」のが基本です。つまり、どんなことでも「はい!わかりました!」とポジティブに対応してくれる人には仕事をお願いしやすいため、雑務を含め依頼が集中しやすい傾向にあります。
逆に、「こんなお願いをしたら嫌な顔をされそうだな。文句を言われそうだな」と思う人には、たとえ部下であっても依頼をためらうものです。
「仕事を押し付けられたくないから、上司の依頼でも安易にハイと言うのはやめよう」と思った人もいるかもしれませんが、雑務でもポジティブに受け入れるのはキャリアにとってプラスであり、決して頼まれ損ではありません。仕事を受ければ受けるほど、依頼側の中で信頼残高が積み上がり、「この人はどんな仕事も嫌がらず、前向きに引き受けてくれるから、今度は大きな仕事も任せてみよう」と思ってもらえるようになります。つまり、「押し付けられている」と感じるぐらいいろいろな仕事を頼まれるのは決して悪いことではなく、むしろチャンスが広がっていると言えます。
また、「忙しそうに見えず、常に暇そうにしている」人も仕事が振られやすい傾向にあります。本当は忙しくても、周りからそう見えていないから、「この仕事も任せて大丈夫だろう」と次々と仕事を振られている可能性があります。
これは、実は「デキるビジネスパーソン」に共通する特徴でもあります。忙しい中でも悠然と仕事ができる人は、周りが声をかけやすいため、仕事のチャンスも回ってきやすいからです。一方、必死の形相でピリピリしながら働いている人に、追加の仕事を依頼する人はまずいません。「面白そうな仕事があるけれど、あいつに声をかけるのはやめておこう」と思われてしまうでしょう。忙しくても暇に見えるぐらい落ち着いて仕事ができるのは、一つのビジネススキルと言えます。
「仕事を押し付けられた」と感じたときの対処法
上司や先輩が、部下や後輩に仕事を振る際、多くの場合は「この人は、これぐらいのレベルの仕事であればうまくこなしてくれるだろう」と期待して任せています。「押し付けられた」と感じたとしても、基本的には可能な範囲で引き受けたほうがいいと思います。
そのうえで、次のような対応を心がけるといいでしょう。

無下に断らず、「条件つき」で引き受ける姿勢を示す
忙しい中、追加で仕事を振られると「忙しいのでできません!」とビシっと言ってやりたくもなりますが、無下に断ると二度と仕事を頼んでもらえなくなる恐れがあるので要注意です。
上司といえども、部下に拒否されるのは嬉しいことではありません。それに、なぜ「できない」のかがわからないので、今後仕事を頼むことを躊躇してしまいます。その結果、いわゆる「いい仕事」「やってみたい仕事」も、回ってこなくなるかもしれません。
ただ、上司が部下のキャパを間違って見立てている可能性はあるので、言われるがまますべて受け入れるのは多少リスクがあります。
この場合は、「こうしてもらえればできます」と条件を付けて対応するのが良策です。
そもそも本来、いくら今の仕事が忙しかろうが、新しく振られた仕事が「できない」はずはありません。たとえば今やっている別の仕事を後回しにしてもいいならば「できるはず」ですし、締め切りを延ばしてもらえるのであれば「できるはず」。その条件を、こちらから提示するのです。
ポイントは、「〇〇という条件でないとできない」ではなく、「〇〇ならばできます」とポジティブな言い方で返すこと。引き受けるのが難しいと感じた要望もいったん受け止め、ポジティブに返す。これはビジネスの基本中の基本です。
たとえば、「締め切りを延ばしてもらわないとできない」と、「締め切りを延ばしてもらえればできます」は、全く同じことを言っていますが、後者のほうが断然印象がいいと思います。しかも、仕事を振った上司にあなたの現状が正しく伝わり、条件を受け入れてもらえる可能性も高まるでしょう。「たとえ忙しくてパツパツでも、前向きに検討できる人」との評価も得られると思われます。
「成長チャンスを多くもらっている」と捉える
とはいえ「なぜ自分ばかり仕事を押し付けられるのか。同僚のあいつのほうが暇なのに」と言いたくなる気持ちもわかります。
ただ、「仕事の報酬は、より良い仕事」という言葉もあります。特に若手時代は「あいつはヒマなのに不公平だ」ではなく「あいつよりチャンスをもらっている」と受け止めたほうがお得だと思います。
仕事を引き受けた結果、残業は多少増えるかもしれませんが、日本企業の労働環境は未だ、労働時間に比例して収入も増える構造になっています。「仕事はあくまで生活のためで、仕事は最低限にしてプライベートを充実させたい」という考えならば別ですが、それ以外の人にとっては仕事を多く振られたからといってプラスにはなれど、そうマイナスにはならないはずです。ぜひチャンスと捉え、条件を提示しながら前向きに引き受けることを、念頭に置いてみてください。
もちろん、キャパを大幅に上回る業務量を引き受けてしまうと心身ともに疲弊しパンクする恐れがあるので、自分で上限を決めてバランスを取るのは大前提。もしバランスを崩し、辛くなってしまったら、人事部門や産業医に早めに相談しましょう。
明らかに悪意がある場合は、上役や人事に相談を
ここまでのアドバイスは、あくまで性善説に基づいたものです。残念ながら明らかに悪意を持ち、いやがらせ的に雑務を押し付けてくる人もゼロではありません。
もし不運にもそういう人に当たってしまったら、まず直属の上司に相談して対応してもらうべき。万が一押し付けてくる相手が上司である場合はさらに上役、つまり「上司の上司」に現状を訴えるのが基本です。
人事部門に相談するのも一つの方法。仕事を押し付けられた結果、残業が増えているのであれば、人事もそのデータを確認できるはず。現状をフラットに伝え、対応をお願いしましょう。
予防策として、現状キャパ〇%にあるのか発信することをお勧め
そもそも仕事を押し付けられないために、普段からできる予防策はいくつかあります。たとえば、現在抱えている業務やスケジュールを進捗管理ツールで共有する、スケジューラーをオープンにして見える化する、ビジネスチャットのステータスメッセージで今日の忙しさを示しておく…などの方法が考えられます。
中でもお勧めしたいのは、「自身の現状のキャパを発信すること」です。
私の会社では、ミーティングの場で定期的に、メンバー全員に現在のキャパをパーセントで申告してもらっています。「今週はキャパ70%ぐらいなので、もう少し仕事を受けられます」「現状100%近いのでパツパツです」などと本人に具体的に示してもらうことで、無理のない仕事の割り振りができるようになっています。
上司は、部下一人ひとりの強みや志向、キャパを測りながら適切にマネジメントするのが仕事ではありますが、抱えている業務やスケジュールだけでは部下のリアルな現状まではつかみ切れないものです。現状のキャパを自分で可視化し、数字でわかりやすく示しておけば、周りにそれが伝わり、余分な仕事を押し付けられにくくなるでしょう。定例ミーティングの場で発信したり、日報や週報などで報告したりすれば、上司にも意図は伝わります。
相手に悪意があろうがなかろうが、プラスに捉えることで成長できる

悪意のもと仕事を押し付けられているのか、それとも期待され任されているのか、仕事を受ける側が判断するのは難しいものです。こちらは悪意に感じていても、実は「能力的にもパワー的にも、少しストレッチすればやり遂げてくれるだろう」と期待され、重たい仕事を任されているケースは決して少なくないからです。
ただ、どんな動機で振られた仕事であろうが、本質的にはあまり関係ありません。
仕事ができる人の特徴の1つに、「どんな仕事でも楽しめる意味づけ力」が挙げられます。たとえ誰でもできそうな雑務やルーティン業務であっても、自分なりに意味を見つけてやる気を鼓舞したり、ゲーム感覚で楽しめたりするよう、自ら工夫しています。
意味づけ力のある人は、どんな仕事でもモチベーション高く取り組めるので、自然と成果も付いてくるようになります。そして、その姿勢や実績は必ず見られていて、より大きな仕事、面白い仕事が回ってくるようにもなります。たとえ悪意を持って押し付けられた仕事であっても、意味づけして楽しんでしまうことで、自分の糧にしてしまいましょう。
仕事を押し付けられている、やらされていると感じている人こそ、この意味づけ力を鍛えれば視野がぐんと広がるはず。繰り返しになりますが、仕事の報酬は仕事です。どんな仕事を押し付けられても、楽しみながら軽やかにこなす姿勢を大切にすれば、必ずや道は開けると思います。
▶あなたの隠れた才能を見つけ出す。転職活動にも役立つ!無料自己分析ツール「グッドポイント診断」
 曽和利光さん
曽和利光さん
株式会社人材研究所・代表取締役社長。1995年、京都大学教育学部教育心理学科卒業後、リクルートで人事コンサルタント、採用グループのゼネラルマネージャーなどを経験。その後、ライフネット生命、オープンハウスで人事部門責任者を務める。2011年に人事・採用コンサルティングや教育研修などを手掛ける人材研究所を設立。『「ネットワーク採用」とは何か』(労務行政)、『人事と採用のセオリー』(ソシム)、『コミュ障のための面接戦略』(星海社新書)、『人材の適切な見極めと獲得を成功させる採用面接100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)など著書多数。最新刊『定着と離職のマネジメント』(ソシム)も話題に。




















