OEMとは、Original Equipment Manufacturing(Manufacturer)の略称で、他社ブランドの製品を製造すること、またはその企業を示します。なぜ、このようなビジネスモデルがあるのか、そのメリットやデメリットについて、日本総合研究所の吉田賢哉さんが解説します。
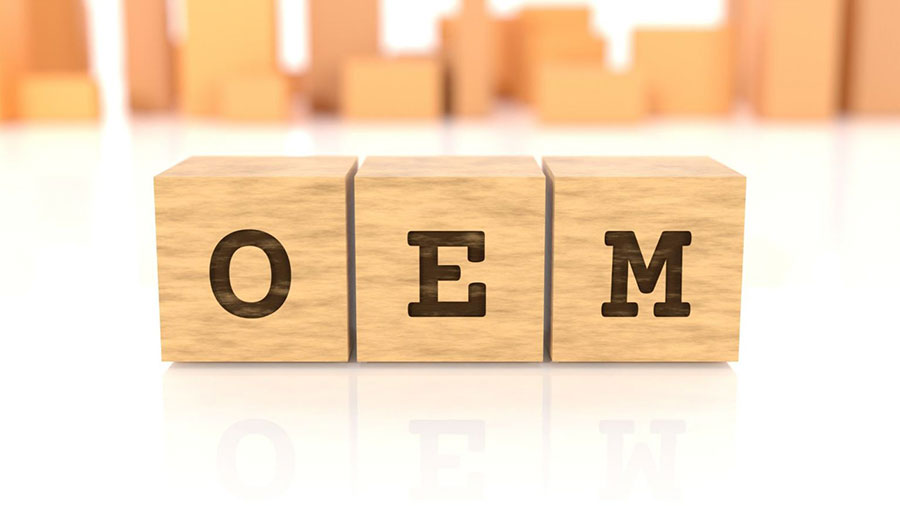
OEMというビジネスモデルが生まれた背景とは
そもそも他社のブランド製品を製造する「OEM」というビジネスモデルは、なぜ生まれたのでしょうか。その背景には、製造設備を持つ側と、製造を依頼する側のWin-Winなやりとりがあります。
製造設備を導入、維持運用するにはコストがかかります。製造設備を持つ企業は、できるだけ稼働率を上げて売上につなげたいと考えます。しかし、自社商品・ブランドの製造販売だけでは、設備を使いきれず、稼働しない”無駄な時間“ができてしまう場合もあります。
そこで、他社からの製造を受託して設備稼働につなげれば、効率的に利益を得ることができる──こうした発想から、他社から仕事を受託するOEMというビジネスモデルが生まれました。
OEMを依頼する企業にとっても、製造設備を新たに導入することなく、自社ブランドの製品を製造することが可能になります。「商品が売れず、設備投資分を回収できない」といったリスクを回避することができ、製造面の負担から解放される。さらに、ブランドの管理やマーケティング、販売、流通に注力することが可能になります。
OEMの形態と製造工程について
OEMの形態には、大きく分けると以下の2つが存在します。
- 自社ブランドを持ちながら、他社の依頼を受ける企業
- 自社ブランドは持たず、他社からの依頼に基づいて製造を担う企業
商品の企画や製造、販売などについては、製造する側と依頼する側が相談しながら決めていきますが、主に下記のようなケースがあります。
- OEMメーカーが製造している自社製品とほぼ同じものを、見た目のパッケージのみ変えて作る
- OEMを依頼する企業のブランドに合わせて設計や仕様を作り込んで製造する
- 基本的な設計・仕様として共通なものを用意するが、OEM製品ごとにユーザーの好みに合わせた違いを出して表現する(例:食品で原材料の配分を変えて味に違いを出す)
どの程度作り込むかは、OEMメーカー側が提案することもあれば、OEMを頼む側の企業が指定することもあります。
ODMやPBとの違いとは
OEMと似た概念に、ODMやPBがあります。ODMは、Original Design Manufacturerの略で、「デザイン」が関わってくる点がOEMとの大きな違いです。OEMでは、決められた設計・仕様に基づき、製造部分のみを担います。
一方、ODMでは製造だけでなく、設計や仕様の提案、商品の企画などにおいても委託関係があります。OEMメーカーには「言われたものを作るだけでは付加価値を提供しにくい」側面がありますが、自社に競争力を持たせるために、もともと顧客(依頼する企業)が担っていた業務へと対応範囲を広げることで、一部のOEMメーカーは、設計や商品の在り方にも関与するようになり、ODMメーカーと呼ばれるようになりました。
PBはPrivate Brandの略で、小売・流通業が自社で企画し、製造は外部に委託し、自社独自の商品・ブランドを作って販売するケースを指します。
一般に、小売・流通業は、さまざまなメーカーが製造した製品を仕入れて販売をするため、販売品には様々な会社の商品・ブランドが並ぶことになります。特に、全国どこでも見かけるような有力なものはNP(National Brand、ナショナルブランド)と呼ばれます。
それに対し、PBは、それを企画した特定の小売・流通チェーン内でのみ見かけることになります。最近では、PBの独自性・限定性を他社との差別化のために活かそうと、PBの品質や求めやすい価格に一層のこだわりをみせる小売・流通業も増えてきています。
OEMに依頼する側のメリット・デメリット
ブランドを持つ企業にとって、OEMメーカーに依頼する際、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょう。

メリット
ブランドを持つ企業の主なメリットは、以下の3つが挙げられます。
1.製造設備を持つ負担を避けて、自社ブランド品を展開できる
最大のメリットは、自社で製造設備を持たなくていいところです。設備投資分の回収を考えなくていいので、少量生産も可能で在庫リスクを避けることができます。自社商品ラインナップの拡充にも挑戦しやすくなります。
2.素早くブランドを展開、立ち上げることできる
OEMメーカー側が必要な製造設備をすでに持っているので、設備検討・導入などに時間がかかりません。ブランド企画から実際の製造までのスピードが早く、もしうまくいかなければ撤退の決断の素早くできます。
3.マーケティング、販売に注力できる
小売・流通業がPBを立ち上げるような場合には、自社の専門ではない「製造分野」の業務から解放され、得意とするマーケティング・販売に注力することができます。
デメリット
デメリットについては、以下の3つが挙げられます。
1.価格面や生産数などについて、自由度が低い
製造面を他社に依存するので、製造計画の自由度は低めになります。
2.製造関連のノウハウが自社にたまらない
製造ノウハウが蓄積されず、自社主導で製造関連の新たな取り組み、イノベーションを起こすことが難しくなります。
3.OEMメーカーにノウハウが蓄積され、競合製品が生まれるリスクがある
委託段階で技術流出を防ぐ秘密保持契約はもちろん交わされます。しかし、OEM側に製造ノウハウがたまることで、間接的に、新しい商品開発のヒントにつながる可能性はあるでしょう。
OEMを受託する側のメリット・デメリット
では、OEMを受託する側のメリット・デメリットにはどんな点が挙げられるのでしょうか。
メリット
OEMを受託する側のメリットとしては、主に以下の4つが挙げられます。
1.設備の稼働効率を高め、より多くの売上・利益を見込むことができる
設備が使われなければ維持費だけがかかります。できるだけフル稼働できる状態を作ることがOEM側にとって重要です。
2.自社ブランドの認知度が高くなくても、売上増につなげられる
自社ブランドも他社ブランドの製品も製造しているOEMメーカーの場合、他社のブランドを製造していることが強みになるケースもあります。自社ブランドの認知度があまり高くなくても、「うちは人気メーカーの〇〇製品も作っています」とアピールし、顧客層を広げられるかもしれません。
3.製造に集中することができる
得意な製造分野に集中することができ、ブランド管理やマーケティングなどの業務負荷が軽減されることもメリットの1つです。
4.製造面に対するノウハウが蓄積される
製造に関するノウハウがたまり、自社製品の開発や他のOEMの依頼に対する提案に活用することができます。
デメリット
デメリット面では、以下の2つがデメリットとして考えられます。
1.製造のみを担う場合、他のOEMメーカーとの競争が激しくなる
OEM委託側が各種設計・仕様を定め、工場での製造のみを担う場合、他のOEMメーカーとの価格競争にさらされ、利益を得にくいこともあります。
2.自社のブランドが育ちにくい
自社ブランドを持つOEMメーカーの場合、委託側のブランドに隠れてしまい、自社の認知度向上が図られないということもあります。
OEMの業界別の特徴・トレンド
OEMが広がっている業界には、どんな特徴や事例があるのか。特にOEMが普及している業界を中心にご紹介します。

自動車業界
「すべての車種を自社で開発・製造・販売する」ことが各メーカーにとって理想ではありますが、設備投資上、現実的ではありません。そこで、経営資源の分散を避けるため、特定の車種を他社OEMに依存することが少なくありません。
例えば、軽自動車をダイハツ工業が製造してトヨタ自動車が販売し、逆にセダンをトヨタ自動車が製造してダイハツ工業が販売しているOEMが代表的なケースと言えるでしょう。
半導体業界
半導体は生産設備が巨額となるため、設計後の製造は、設備が充実した施設を持つ他社に依頼するケースが多くあります。
家電・電子機器業界
有名な例として、HP(ヒューレットパッカード)のプリンターの製造をキヤノンがOEMで手掛けたケースが挙げられます。プリンターの販売面において、HPとキヤノンは競争する関係にありましたが、プリンターの製造面において、HPとキヤノンは協調する関係を築き上げました。一見するとライバル関係にある企業間においても、OEMの関係が成立しているケースがあります。
食品の小売・流通業界
食品関連の小売・流通業では、PBを販売するケースが増えています。大量発注により製造価格を下げた、自社の販売網で売り切ることで、利益を生み出すというビジネス戦略です。
コンビニなどは、商品の売れ筋情報を持つ強みを活かし、売れる商品の企画・開発に関与しながら、製造はOEMに委託するケースが多く見られます。
化粧品業界
化粧品業界はブランドマネジメントが重要と言われています。そのため、製造面については他社に任せてしまう会社が少なくありません。一方でOEM側も、設備の稼働率を高める観点から、受託するメリットを感じやすく、自社ブランドを持たず、OEM生産のみを行うメーカーも存在します。
製薬・健康食品業界
研究開発の技術・ノウハウと、商品を量産するノウハウは異なるものであるため、医薬品や、医薬部外品、健康食品、サプリ等を扱う企業の中には、商品の研究開発は自社で進めて、市場に流通させるための量産についてはOEMに依頼するケースもあります。
このように製造を依頼する側、受託する側、それぞれのWin-Winを目指し、さまざまな業界で広がっているOEM。身の回りの商品が、どう作られているのかに関心を持ってみると面白いかもしれません。
▶あなたの知らない自分を発見できる。無料自己分析ツール「グッドポイント診断」
株式会社日本総合研究所
リサーチ・コンサルティング部門 シニアマネジャー 吉田賢哉氏
 東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了後、日本総合研究所に入社。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長や、産業振興・地域振興・地方創生などを幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな業界のビジネスチャンス・トレンドについて多角的・横断的な分析を実施。
東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了後、日本総合研究所に入社。新規事業やマーケティング、組織活性化など企業の成長や、産業振興・地域振興・地方創生などを幅広く支援。従来の業界の区分が曖昧になり、変化が激しい時代の中で、ビジネスの今と将来を読むために、さまざまな業界のビジネスチャンス・トレンドについて多角的・横断的な分析を実施。




















