ネットの閲覧制限をする、リモートワークを禁止する、外部の勉強会への参加を禁止する…さらには紙とハンコの事務作業だらけ。「働き方改革」を叫びながらも、未だに前近代的な考え方にとらわれ、社員のやる気やチャレンジ精神を削いでいる企業は少なくありません。
このような非効率な企業体質を“大企業病”の病理を解説するとともにその対処法について話し合う座談会を、年間300回近くのプレゼンテーションを行っている“プレゼンの神”澤円さん、業務プロセス&オフィスコミュニケーション改善士の沢渡あまねさん、そしてFilament.inc 代表取締役CEOの角勝さんが開催。ぶっちゃけトークを繰り広げました。

目次
ネット閲覧禁止、Skype禁止…なんてもったいない!

今回の企画のきっかけは澤さん、沢渡さんと、ネット閲覧禁止、テレカン禁止、SkypeやZoomが使えないという企業が実は多いという話をしたことから。具体的に大企業病とはどんなものなのか、事例を挙げながら処方箋を3人で考えていきたいと思っています。
で、大企業病というものは何か、定義を考えてみたんです。これどうですか?

お役所感が漂ってくる感じがいいですね~!

言い換えると、「自ら作った仕組みや制度に縛られて、身動きが取りにくくなっている組織の状態、そして、そうした組織に最適化した人間の行動」。
あくまで僕の解釈ですけれどね。

Filament.inc 代表取締役CEO 角 勝(すみ まさる)さん
オープンイノベーションデザインスタジオ「フィラメント」代表取締役CEOにして元公務員(大阪市職員)。前職では「大阪イノベーションハブ」の立上げと企画を担当し、西日本を代表するイノベーション拠点に育てた。 現在は、「共創の場をつくる」、「共創の場から生まれたものを育てる」をミッションとして、共創人材の育成や共創ベースでの新規事業創出を主導するオープンイノベーションオーガナイザーとして活躍している。

人は最適化するからね。僕が考える大企業病とは、「ぼんやり生きているおじさんが支配する世界」。ぼんやり生きている人が何に頼るかというと「肩書き」。
〇〇部長と呼ばれることに命をかけているので、言い間違うと激怒する。
〇〇課長補佐、〇〇課長代理なんて、誤差じゃない?って思うけど、大企業の7割はそうなんですよね。

職位順にメールアドレスを並べるっていうのもありますね。
もちろん、いわゆる軍隊的な組織においてや緊急事態が起こったときなど、誰の指示を聞けばいいのか統制を取りたい場合に役職で呼ぶのはリーゾナブル(合理的)だけど、すべてにおいて当てはまるわけではないんですよね。ここに「思考停止」がある。
こういう会社がグローバル化すると厄介なんですよね。課長代理とか、課長心得なんていう職位もあるでしょう?「英語ならばどういう表現になる?」なんて考える時間がムダ。

英語だと、マネージャー、サブマネージャーとか、ディレクターぐらいしかないですよね。フラットな組織ならばいいけれど、階層が深いと大変。

階層が深いと、意思決定の場面でボトルネックが起こるだけなんですよね。そして、なかなか先に進まないから、課長を飛び越して部長に話を通すと、課長から必殺技「俺、聞いてない」を食らう。部長も部長で、「ごめんごめん」と言いながらせっかく決まったことを差し戻しちゃう。
会議の場で説明しても「俺、聞いていない」と言う上司

会議でもそういうシーンありますね。説明しても「俺、聞いていない」という上司。会議って、部下の話を聞いて判断する場なのに。

そもそも「その場で聞いていないことがある」時点で終わっているんですよ。本来は会議室に入るまでに、全部頭に入っていないといけないはず。会議の場で一から共有されるなんて時間の無駄でしかない。

情報は事前にオープンにしておいて、会議に出る人はあらかじめ読んでインプットしておくと。

会議の場では、「あの議題についてどうしよう?」という話から始まるのが本来です。でも、大企業病にかかっている企業ではそうはいかないんですよね。
先日ある大手企業から出向している28歳の男性と一緒に会議に出たら、「会議で何かが決まるの、初めて見ました!」って言うんです。彼が所属する会社では、会議は「緩やかな」情報共有の場であり、結論が出ないものなんだって。

それならリモートでいいじゃん、って思うけどなあ。そういうのを僕は「企業ごっこ」「仕事した感」と表現しています。会議に出ているだけで働いている気分になるし、業務時間が消費できるんですよね。

【左】あまねキャリア工房代表 沢渡(さわたり)あまねさん
業務プロセス&オフィスコミュニケーション改善士。人事経験ゼロの働き方改革パートナー。日産自動車、NTTデータなどで、広報・情報システム部門・ITサービスマネージャーを経験。現在は全国の企業や自治体で働き方改革、社内コミュニケーション活性、組織活性の支援・講演・執筆・メディア出演を行う。趣味はダムめぐり。著書『職場の問題地図』『マネージャーの問題地図』(技術評論社)、『ドラクエに学ぶ チームマネジメント』(シーアンドアール研究所)ほか多数。
【右】澤 円(さわ まどか)さん
大手外資系IT企業 テクノロジーセンター センター長。立教大学経済学部卒。生命保険のIT子会社勤務を経て、1997年より、現職。情報共有系コンサルタントを経てプリセールスSEへ。競合対策専門営業チームマネージャ、ポータル&コラボレーショングループマネージャ、クラウドプラットフォーム営業本部本部長などを歴任。著書に「外資系エリートのシンプルな伝え方」「マイクロソフト伝説マネジャーの世界No.1プレゼン術」

僕は、残業はできるだけしたくなかったタイプですけどね。でも、僕がいた部署は当時、制度改正が相次いでいて、昼間はその説明対応に追われる。だから、事務作業が後ろにずれ込んでしまい、夜中に会議を設定されることもかなりありました。今はかなり改善されているはずですが、当時は明らかにブラックな職場でしたね。

私もそういう環境を経験したことはあるけれど、まだブラックという言葉はなかったな。「言語化」って大事ですね。「ブラック」という言葉がないと、自分たちの会社がブラック企業だとは気づけないですものね。
今日のテーマである「大企業病」も同じで、皆さんが「うちの会社は大企業病だ。組織の課題として問題化していいんだ」と共通のキーワードを持って帰るのが大事だと思っています。でないと、ぼーっと生きている人は組織の問題点に永遠に気づけない。

セクハラも言語化されて、共通化されたからね。でも、セクハラをしている本人は「オレはセクハラおやじだからさ!」と開き直って笑っている。古い企業体質に最適化されちゃっているんです。かわいそうなのは被害に遭っている側も最適化されてしまって、「これぐらい仕方ない」と思っているから、問題が表面化せず組織として回っている。でも、結局誰も幸せになっていないんです。

セクハラ問題って、どうすれば解決するんですかね?
セクハラって相当昔から言語化されているけれど、現存していますからね。

ある30代の女性と「セクハラ経験ってある?」という会話をしたことがあるんです。彼女は、「私はされたことないですね。せいぜい『いつまでたっても嫁にいけないのは、女としての魅力が足りないからだ』と言われたぐらいで」と言うんですよ。びっくりして、「それがセクハラだよ!我慢してるんじゃない?」と言うと、泣き出しちゃった。実は傷ついていて、「いけないことだ」と初めて言ってもらえた、と。

そういうセクハラ発言をする人がいる組織で働きたいと思う人がいるかって話ですよね。どうせ仕事をするならばイケている新入社員や中途入社者に来てほしいし、イケているブレーンや社外の専門家と一緒に働きたい。エンジニアなんて特にそうで、すごいエンジニアと切磋琢磨できることに喜びがある。なのに、ハラスメントが邪魔して優秀な人が来てくれなくなったら…本当にもったいない!

「外のモノサシ」を知らないと、社内最適化されてしまう

最近、若手エンジニアと話をする機会が多いのですが、こんな声をよく耳にします。「うちの会社は外の勉強会に行くのを良しとしない。なぜなら、情報が漏れるかもしれないから」。アホか!と。井の中の蛙になるだけですよ。
外に出れば、世の中ではこんな技術が主流で、こんな考え方があるんだとわかるし、自分がイケているかイケていないかも相対的につかめます。それを阻害するということは、個人と組織のアップデートを妨げるということ。

日本法人を立ち上げた元AWS(Amazon Web Services)小島英揮さんは、よく「外のモノサシを知るべき」と話していますね。社外から見たときに自分がどうメジャーメント(評価)されるか、モノサシを持っていないと井の中の蛙になり、社内で最適化されてしまい、定年退職後に昔の名刺を持ち歩くじいさんになってしまう。

なるほど。「組織に最適化する」って、組織のルールに最適化した振る舞いをするようになるということだから、ルールが異なる自社組織以外でどう振る舞えばいいのかわからなくなってしまいますね。

そういう組織ほど、「イノベーション」とか言い出すんですよね。

「イノベーション 叫べば下がる モチベーション」ですね(笑)。
イノベーションを起こせと叫ぶ一方で、勉強会に出ちゃダメ、情報発信しちゃダメなんて言う。自分たちでやれ、予算はない…だと、モチベーションは下がる一方ですよ。もはや、企業としての「徳」がない。

なのに国は、「なんで日本からはビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズが生まれないのか」なんて平気で言う。こんな環境で生まれるかいな!

外のモノサシを持つのは個人にとって大事だし、組織は外に出ていくことを推奨するべきですね。

ノウハウや気づきなどの情報発信をしてくれる会社や組織、個人のほうが価値が高いですよね。「価値」って受け取る相手が決めるものなので、どんなに広報が自社をPRしても、有意義な情報発信ができない会社はブランド価値が上がらない。
イベントで登壇する側や運営側になってみよう

ぜひやってほしいのは、こうしたイベントで登壇する側や運営側になってみると、見え方がまた変わってきます。あるいは、「自分が、自社が情報発信するためのプロセスになる」というスタンスで参加すると、景色が全然変わります。
僕がプレゼンで提供しているのは、汎用的な情報。多くの人にわかりやすく伝わるように工夫しているからです。もし、カスタマイズされた情報を手に入れたいと思うならば、「楽屋に入る」ことです。楽屋トークって、発信者にだけ許されている情報共有の場なので、有益な情報が得られることが多いんです。しゃべる側でなくとも、運営スタッフになれば楽屋に入れるから盗み聞きすればいい。

僕と角さんとの出会いも、楽屋ですものね! 2015年の神戸ITフェスティバルの登壇者控え室だった。

「発信する者」同士って、すごく仲良くなれるんですよね。でもなかなか登壇の機会や運営側に入る機会がないならば、自分でイベントを企画すればいいと思います。しっかりテーマがあるちゃんとしたイベントであれば、登壇をお願いされればみんな「できれば出てあげたい」と思うもの。
そして、話す側になってみると、自分が持っている情報を発信できるし、周りの人の情報も得られるし、自分のポジションも何となく高くなっていく。ほかのイベントに呼ばれる機会も増え、さらにインプットが増えると思います。
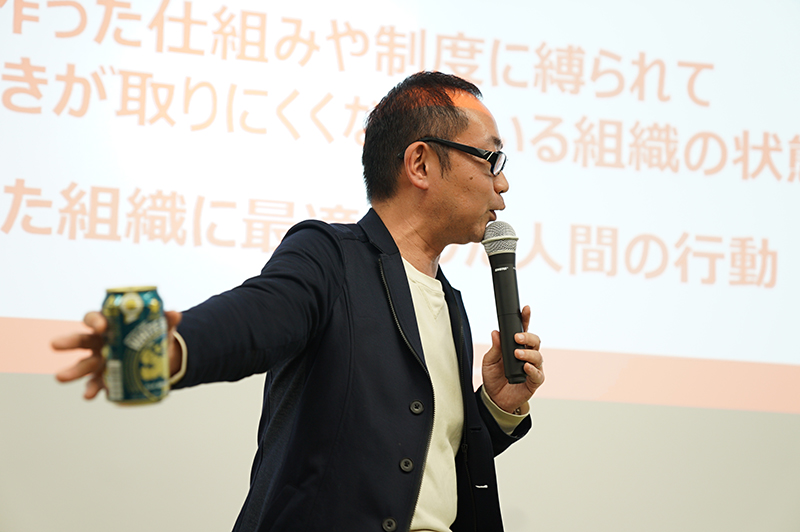
迅速なコラボレーションを阻害する事務業務や慣習

「大企業病」の事例の話に戻ると、私の定義は「企業ごっこ、仕事した感」ですが、事務業務などの間接業務において特に「大企業病」を感じます。
企業に請求書を郵送するのを例にとっても、捺印して、郵送して…とすごく時間を取られるし、トナーが切れた、プリンタが紙詰まりした、企業内で郵便物が迷子になった、挙句の果てには「宛先を一文字修正してください」と差し戻されたり…とトラップがたくさんある。その作業のためにわざわざオフィスに戻らないといけない。電子でやればすべて解消できるのに!
ただ、先日嬉しいことがあって。あるメディアから取材を受けて「取材謝礼の請求書を郵送で送ってくれ」と言われて「電子で勘弁願えないですか?私、出張多くて物理的な紙作業が無理なので」とお願いしたところ、先方担当者が経理と掛け合ってくれて、PDFでいいということになった。

声を上げることで、現状が変わることがあるんですよね。

このルールが当たり前だと思い込んでしまうから、それまで変わらなかったのでしょう。こうした思考停止は、迅速なコラボレーションを邪魔してしまいます。
社内の体制が、社内同士の迅速なコラボレーションを阻害しているケースもあります。部署間でファイルが共有されていないとか、メールの宛先は「〇〇部長から順に書かないと」なんて考えている間に機会はどんどん失われてしまいます。
結果、新しい仕事を経験できない、チャレンジできない、本業にコミットできない、組織も個人もイケていない…。「迅速なコラボレーションができない組織は、個人を不幸せにする」ぐらいの意識を持ったほうがいいと思います。


日本は「未完成のものは外に出してはならない」という意識が強いんですよ。以前、情報共有基盤のコンサルティングをしていたとき、欧米と日本の違いをすごく感じました。
欧米の企業からは「どうやったら広く情報共有ができるか」という質問が来るのに対し、日本企業は「どうやったら情報を絞れるか、見えないようにできるか」と権限設定を求めてくる。情報共有基盤なのに、情報閲覧制限を気にしてくるんです。

いわゆる100点主義ですね。

完全、完璧になっていないとダメという考え方ね。ビジネスマナー研修で、「名刺入れの上に相手の名刺を乗せる」なんてあるのも意味がないよね。あれって、名刺は分身であり、神聖なもので、神聖なものを地べたに置いてはいけないという考え方らしいんだけど、名刺なんてそこらへんに置いて「ご自由にお持ちください」でいいじゃない?QRコードでもいいかもしれない。

なくすとセキュリティ云々言われますからね。

僕はイベント後に、参加者が登壇者との名刺交換のために一列に並ぶのも時間の無駄だと思っているんです。名刺交換している間に質問をされてそれに答えるのですが、同じ質問に10回答えなければならなかったりする。だから僕は、「名刺はあとで渡すから、質問がある人は扇形になってくれ」と伝えています。
欧米では講演後、登壇者を中心に参加者が扇形に集まって、その場でディスカッションが始まることも多い。一気に話が進むから短時間でも有益な場になりやすいんです。

一対一の対面を大事にするのは、まさに大企業あるあるですね。講演ではないですが、20分の情報共有のためにクライアントに呼ばれて、片道2時間かけて出向くとかね。しかも、呼ばれた結果「もっとコスト下がらないの?」なんて言われる。いやいや、この打ち合わせを止めてくれれば下げられますよ!と思う。

年末年始は「ご挨拶に伺いたいのですが」という依頼も多いでしょう?挨拶だけなら来ないでください、時間の無駄なので。来るなら何か決めましょうよ。

大企業病の中で思考停止しているおじさんは、こういう申し出を喜んで受けちゃう。応接室でお茶飲んで話をしていると、仕事した感を味わえるから。

…時間のロスですよね。「5分でいいから」なんて言われるけど絶対に5分じゃすまないし、そういうのがアポがいくつも重なるとそれだけで1日が終わる。

もちろん対面には対面の良さがありますが、コミュニケーション戦略として必要な時に使えばいいと思います。「コミュニケーション」は、初期の信頼構築期とパフォーマンス期に大きく分けられますが、信頼関係が出来上がるまでは対面を挟み、ひとたび信頼関係が構築できたら、対面ではなくクラウドサービスを使って情報を出し合い、ディスカッションすればいい。
もうパフォーマンス期に入っているのに、毎回対面で打ち合わせをしようというのはコミュニケーションロスだし、コストでしかないと思います。

僕はいま大阪に住んでいますが、仕事相手は東京が多いんですよね。だから、初回は訪問し、対面で話しますが、そのあとは徐々にリモートに移していくようにしています。それが許されないと、東京の企業とは仕事ができなくなってしまいます。

さっきの「挨拶」の話も、単に挨拶ではなく「何かを作り出すために会おう」と言ってくれればいいのにね。「うちの会社の勉強会に一緒に出てほしいから、打ち合わせがしたい」と言われれば、こっちも必死になって企画考えるし意見を出そうと思えます。そしてゴールが共有できた後は、リモートに切り替えればいい。

日本の組織って、総じて「設計」が苦手。僕は、コミュニケーションは「設計8割、スキル・メンタリティ2割」と思っているのですが、日本人は「取りあえず会って、あとはスキル・メンタリティだけで何とか解決しようとする」傾向にある。
でも本来は、最初の打ち合わせは「共に作る場」にするべきで、そのためには当日どんな議題について話し合うかなど「設計」が必要です。会議も一緒で、スキル・メンタリティ依存ではなく事前の設計があってこそ有益なものになる。


沢渡さんの「企業ごっこ」で思い出したけど、さっき話した出向中の28歳の彼によると、自社では夜7時以降でないとミーティングが始まらないんですって。「外回りしている人が戻るのを待ってから」という理由はわかるのですが、よくよく聞くと夕方5時には帰社しているらしい。7時までの空白の2時間に何をしているのかというと、会議用の資料を作っているんだとか。
データベースからデータを引っ張り出して、Excelでグラフ化して、グラフをパワポに貼り付けて、印刷して会議で配るんだって。この儀式に2時間かかるとか。でも、データベースがアップデートされている可能性があるわけで、その2時間の間にデータはもう古くなっているんですよね。その分が反映されていないから、本当に無駄な時間。

資料作成もそうだし、ハンコ押して請求書を郵送するというのも時間の無駄。ハンコなんて今いくらでも複製できるし。そういう意味のない習慣があまりに多い。みんな無駄だとわかっているのに、「商慣習」という言葉で済まされてしまう。

現状を変えなければならない、でも、一社員だからどこから変えていいのかわからない。そんなとき、皆さんにはぜひテーマを持ってほしいと思います。「仕事した感」をなくしたい、とテーマを決めたら、きっと明日からの仕事の中で「仕事した感」にすぎなかったものがたくさん見えてくるはずです。
テーマを決めて、アンテナを立てて「自身の成長を阻害しているもの」を洗い出し、言語化することで、「実は私もそう思っていた」という賛同者が集まってくる。小さな例ですが、「請求書を郵送ではなくPDFで送りたい」という個人の問いかけで、PDF対応がOKになり、一歩前進できました。悪気なく人の時間を奪う慣習に風穴を開けるのは、個人からでも十分可能です。

その通り。疑問を持ったらまずはアウトプットしてほしいですね。とりあえず言ってみるだけでも全然違うはず。過去と他人は変わらないんです。過去は変えようがないし、他人も変えられないから自分が変わるしかない。自分の振る舞いを変えることで、それを見た他人が振る舞いを変える可能性はゼロではない。だから、まず自分が行動してみること。自分がロールモデルになるのも大切です。

大企業病を何とかしたいという人は、必ず社内にいます。これは大企業ならではの強みで、従業員が10万人いたら1000人ぐらいは志の高い人が存在するはず。だからこそ自分から声を上げ、言語化しないと。「言わなくても思いは伝わる」なんて恋愛物語みたいなのは、組織においてはないですからね(笑)。ぜひ自分から発信して仲間を見つけ、組織改革につながればいいなと思います。

改めてですが、なぜ「大企業病」ができたのか、原因は2つある気がしています。
1つは「何か問題を起こったことを機に、ルールが急にでき上がる」ケース。例えば、誰かが情報漏えいしてしまい、二度と起こしてはならないからと厳しいルールを設けるというパターンです。そして、もう1つは「そのルールができたときにはまだなかったテクノロジーが後に生まれたけれど、古いルールのまま続けてしまっている」というケース。
書類への捺印も、ハンコというテクノロジーしか、個人の同一性を確保できるものがなかった時代の慣習が残っているだけだと思うんです。本来であれば、古いテクノロジーは新しいものに代替していくべきで、その過程で時間が生まれ、世の中がより良くなるんです。
今は、時間を生み出せるさまざまなテクノロジーが生まれているから、新しいものをどんどん取り入れたほうが時短につながるのに、「使うリスク」を考え、悩む時間が長すぎる。

石橋を叩いて叩いて、少しでも欠けたら「崩れるから渡らない」というのが日本人。でも、インド人や中国人は、橋があるのもわからないのに走っていき、もし落ちたらその場で「泳げばいいか、助けを呼べばいいか」と生存方法を考える。失敗は多いけど、何度も失敗を経験するからタフになるんです。

日本企業は、失敗を共有するカルチャーや仕組みがないところが多いですね。うまくいったら打ち上げしてビール飲んで終わり、ダメだったら黒歴史になる。

「失敗は隠そう」という恥の文化がありますからね。誰も失敗から学べないのはよくない傾向ですね。

失敗の分析をしたとしても、たいてい個人攻撃になってしまうのも悪い傾向。結局、失敗した人が「私のスキルが足りませんでした、これから〇〇と△△に気をつけます」と言っておしまいになるけれど、これって失敗経験が属人化するだけなんですよね。
社内ルールへの固執が「残念な組織」「残念な人材」を生む

「大企業病の中でぼんやりと生きているおじさんは、肩書にこだわる」と話しましたが、これは自分がいた意味、達成した何かに固執してしまうから。これは企業も同じで、一つのことに固執することが大企業病になるんだなと改めて思いました。一度決めたルールがあり、それが伝統として積み重なることで「こだわり」になり、そのこだわりを社員にも強いるようになってしまう。これが大企業の一つの正体かもしれません。

今の日本は走っていたらゴールがどんどん延びていくという状態で、定年退職後にどこかに再雇用してもらえる人材になることが大切。でも、大企業病の中でぼーっと生きてきた人が、「大企業の看板があるから大丈夫だろう」とのんきに構えていると、箸にも棒にもかからない人材になってしまい、路頭に迷う恐れがあります。

まさにそう!自分の仕事ぶりがイケてなかったとしても、社内ではルール通りだからそれなりに評価されてきた。でも社内でしか通用しないルールは、外に出ると全く意味をなしません。社内ルールばかりを身につけてしまい、そのルールに心が捕らわれてしまうのが、大企業病の「一番の害」だと思います。

社内でしか通用するスキルではなく、どこでも通用する「汎用スキル」を身につける必要があります。では汎用スキルとは何か?バカにしているように聞こえるかもしれないけれど、まずは「挨拶すること」なんです。

わかる!挨拶できない人、結構多いですよね!
以前、さくらインターネットの田中社長が、「社長の仕事は、機嫌よくしていること」と言っていてすごくいいなと思いました。一人ひとりが機嫌よくいるだけで、どれほど組織のコミュニケーションが活性化するか。
朝から眠そうな顔をしてすごく不機嫌な顔の人は、朝から泥酔しているのと同じぐらいダメだと思う。チーム全体の空気が悪くなるし、生産性も下げてしまう。とっとと帰って寝てもらったほうがマシ。

さらにいえば、「一人ひとりが機嫌よく働ける環境」を作るべきだと思います。固定席で、毎日イヤな上司の不機嫌そうな顔を見なければいけない環境だと、仕事がはかどるはずがありません。
フリーアドレスなど、自主的に景色を変えられる職場環境があるだけでも、機嫌よく仕事ができるはず。環境を変える提案はした方がいいと思います。私はダム好きで、よく移動中にダム際に車を止めて仕事をしていますが、めちゃくちゃはかどりますよ(笑)。

ご機嫌で面白い人材は最強。人が寄ってきますからね。

気持ちよく仕事ができる環境も、声を上げてこそですね。社外と比較して自社の問題を洗い出し言語化して、「ここが問題だ」と言ってみる。そうすることで、初めてその事実に気づく人が出てくるはず。大企業病と同じで、言語化されたから認識できることって、実はとても多いんです。
さらに簡単な方法は、「自分が機嫌よく過ごす」ことかもしれませんね。機嫌よく仕事をしていれば、面白いことをしたい人が集まってきて、組織の活性化につながります。大企業病から脱するきっかけになりそうです。

問題点を言語化する際は、ぜひ僕が作った「職場の問題かるた」の活用を!「これ、うちの会社に当てはまるんじゃない?」という札を見つけてください(笑)。

▶あなたの知らない自分を発見できる。無料自己分析ツール「グッドポイント診断」




















