2017年12月下旬、メルカリが新たな研究開発組織「mercari R4D」を設立した。「R4D」は調査・開発・実装・破壊など4つの英語表記の頭文字「D」をとったもの。R4D設立に準備段階から関わってきたR4Dオフィサーの木村俊也氏とxR領域のリサーチエンジニア諸星一行氏に話を聞いた。
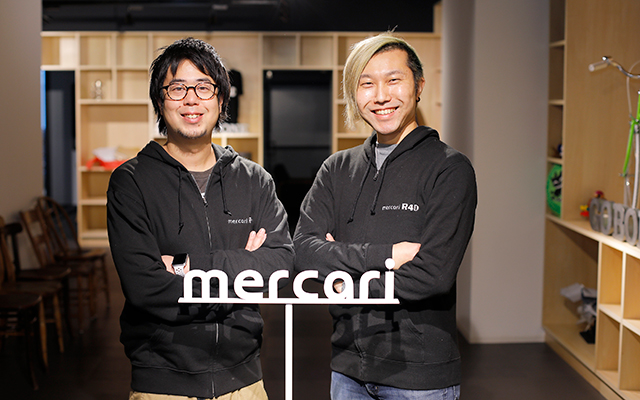
目次
企業・大学研究所と連携し、8つのテーマを攻める
メルカリはこれまでもフリマアプリにAIや機械学習などの技術を活用してきたが、R4Dの発足によりその技術基盤を強化すると同時に、外部の企業・教育機関と共同してさまざまなテクノロジーの社会実装・事業化を目指すとしている。
シニアフェローとしてアーティストのスプツニ子!氏や京都造形芸術大学教授の小笠原治氏が参画していることはもちろん、シャープ・研究開発事業本部、東京大学の川原圭博准教授、筑波大学の落合陽一准教授、慶應義塾大学の村井純教授、京都造形芸術大学のクロステック研究室、東北大学の大関真之准教授という、そうそうたる研究機関との連携も注目を集めた理由の一つだ。
従来の中央集権型の研究所ではなく、最初からネットワーク型の共同研究、オープンイノベーションを意識したスタイルになっている。
「こうした共同研究を通して得た知見は、メルカリや子会社のソウゾウ、メルカリファンドなどによる事業化に止まらず、さまざまな形で社会実装していく」
と語るのは、R4Dオフィサーに就任した木村俊也氏。2017年8月まではミクシィで自然言語処理やレコメンデーションの技術をサービスに応用する仕事に携わっていた。
 ▲株式会社メルカリ R4D オフィサー 木村俊也氏
▲株式会社メルカリ R4D オフィサー 木村俊也氏
「現時点ではメルカリのアプリで、xR技術を使っているものはない。しかしテックカンパニーを目指すメルカリとしては、xRの研究は欠かせない。これまでゲームやエンタメ領域が注目されがちだったxR技術の利用用途を広げるためにもそれは必要だ。さらに私たちの研究はメルカリアプリという狭い領域に止まることはない」
と、VR、AR、MRなどいわゆる「xR(xリアリティ)」技術のエキスパートとしてR4Dに参画する諸星一行氏も、新しい事業開拓を含めた社会実装に重点を置きたいと言う。
 ▲株式会社メルカリ R4D xR リサーチエンジニア 諸星一行氏
▲株式会社メルカリ R4D xR リサーチエンジニア 諸星一行氏
発表時には、企業・大学研究所など6機関との連携による8つのテーマが示された。どのような形で共同研究が進められるかは、テーマによってさまざまだ。
例えば、慶應大・村井純研究室を中心とした「ブロックチェーンを用いたトラストフレームワーク」の共同研究では、信頼できるフレームワークを創造するためのルール化・標準化の議論を進め、カンファレンスや論文発表の形でアウトプットしていくことになる。東大の川原圭博研究所とは、「無線給電によるコンセントレス・オフィス」で協業する。
「コンセントでなく無線給電で、携帯端末などを充電できるオフィスを実際に作り、誰もが無線給電の世界を体験できるような形を目指すことになる」(木村氏)

製品が完成してからそれを市場展開するというのではなく、研究開発段階からその原型を示すことで、世の中の関心を高めていくというスタイル。これも社会実装の一つのあり方といえよう。
シャープの研究開発事業本部との「8Kを活用した他拠点コミュニケーション」研究も可能性を期待させるテーマだ。8Kカメラの解像度は、これまでのオフィスでのテレビ会議などを使ったコミュニケーションや、遠隔医療などのメディカルの現場を大きく変えるといわれる。
まずはシャープがハード技術を、メルカリがソフトウェア技術を提供し合い、快適なオフィス環境のモデルを示すことで、8K技術の社会実装を担う。
落合陽一研究室と「画像解析技術」を共同研究
一方、筑波大学の落合陽一研究室との「類似画像検索のための Deep Hashing Network」の共同研究は、最初の応用はおそらくメルカリのアプリにつながる。
Deep Hashing Networkのような高速なアルゴリズムを使えば、メルカリでバッグを探すときに一瞬で関連商品を示すことができる。さらに、出品された商品写真を3Dにモデリングして見せる商品画像から背景を特定して、商品だけを目立つように処理することなども容易になる。1日に100万品も出品されるメルカリならではの必要な技術だ。
「落合研究室の研究領域は幅広く、xR領域への活用も今後は期待できます。例えばメルカリには商品のモデルデータと価格帯のデータを紐付けたデータベースがあります。それとマイクロソフトのHoloLensのようなデバイスを連動させることで、商品を見ただけでメルカリに出品したら、それがおよそいくらぐらいで取引されるかがわかるようになるかもしれません」(諸星氏)

量子アニーリング技術とアートの融合
東北大の大関真之准教授は、量子アニーリングや機械学習の研究で知られる。
今回、R4Dとの共同研究では「量子アニーリング技術のアート分野への応用」をテーマに設定した。量子コンピュータとアートというのは、かなりエッジなテーマ設定ではあるが、ここでは今回R4Dシニアフェローに招かれたスプツニ子!氏とのコラボに注目したい。
「将来的には量子アニーリングが得意とする最適化問題に関連する研究も深めていきたい。量子アニーリングは商品配送や商品レコメンデーションの最適化などにも応用できるのではないかと考えています」(木村氏)

xR領域の人材獲得にも貢献するか
R4Dの設立が外部に対してだけではなく、メルカリ内部に与えた影響も小さくない。
「これまでもメルカリでは機械学習やAIのプロダクトへの応用を日々進めてきました。将来的にはこれらの技術はプロダクトへの応用に留まらず、R4Dでさらに研究開発の幅を広げていくことで開発者のモチベーションが高まると思います。
社内には大学院などで量子コンピューティングや最適化などの専門領域を研究していたメンバーもいますが、僕らの業界ではすぐにはその知見を仕事に活かすことができません。R4Dではそういったメンバーの力を最大限に活かして、夢の実現につなげていきたい。そういう点でR4D設立の話は社内にポジティブな影響を与えています」と、木村氏。

一方、xR研究者・エンジニアというマーケットへのインパクトを語るのは、諸星氏だ。
「アカデミア領域でxRを専攻してきた人材って結構いると思うんです。しかし、それをプロダクトに応用することがなかなかできなかったし、メルカリとしてもなかなかそこにリーチできていなかった。
メルカリがxR技術に本格的に取り組み始めたということで、自分たちの研究をプロダクトやサービスに結び付ける、いわば“出口”が見えてきたと感じる人たちもいるのではないでしょうか」
近年、エンジニア転職マーケットにおいて、メルカリが社外にいる人材を集める“吸引力”は目をみはるものがあるが、R4Dの設立はさらにそれを加速することになるかもしれない。
諸星氏自身が、前職ではWebフロントエンドに注力していた傍ら、WebVRの技術開発を行ってきた人。R4D設立準備の段階でメルカリから転職のオファーがあったが、「メルカリのショッピングをVR化する」だけでは話に乗りきれなかったという。

「中の人たちと話すと、もっと先を見据えている。スゴイ技術を持つエンジニアも多い。xR技術の展開に新しい光明が見えた気がして」転職を決めたという。
木村氏も同様にR4D準備の段階からメルカリにジョインしたわけだが、彼の場合は自然言語処理の専門家というだけでなく、情報処理学会など技術コミュニティの運営でアカデミア領域との接点もあることが、オファーのポイントになったようだ。
今回は研究所のオフィサーとして、ビッグネームを集めた研究組織づくりに関わることになったが、「他の会社ではなかなかできない、得がたい経験だった」と振り返る。
従来の企業内研究組織のあり方を「破壊」するインパクト
R4Dに関わる予算については公表されていないが、世間では「数億円ではきかないだろう」とも噂されている。
「テーマによってゴール設定はさまざまであり、あえて予算は決めていない。例えば無線給電施設も1つ作るだけなら数千万円レベルだろうが、これを各地に展開するとなると桁が違ってくる。ゴールをどこに求めるかで違ってくるので、現時点で予算規模を言っても噓になってしまう。もちろん、研究投資のリターンは考えないといけないが、先端技術を社内に獲得するだけでなく、人材採用への好影響やエンジニアのモチベーション向上、企業ブランディングなど副次的な効果もある。
むしろ直近のリターンというよりは、この投資によってどれだけの市場規模を作れるかが重要だ。企業のR&Dは、場合によっては損をしてでも攻めなければならないときもある。先行投資として経営層には判断してもらっている」と、木村氏は語る。
R4Dの4つのDの一つには「破壊(Disruption)」という意味もある。
「既存のやり方を変えるという意味での破壊、たえずスクラップ&ビルドを続けていくという意味での破壊などいろいろな意味が含まれている。それだけ柔軟な組織にしたい。共同研究のテーマも現在は8つだが、今後さらに増えることもありうる。将来は宇宙開発だってテーマに上るかもしれない」と、諸星氏はR4Dの未来像を語る。
「フリマのメルカリだから、こんな研究は絶対にしないだろう」という思い込みは禁物。どこまで進むか予想しえないその発展力に、すべての技術領域のエンジニアは目を離してはならない。
※本記事は「CodeIQ MAGAZINE」掲載の記事を転載しております。




















