自分の意見や考えを、うまく言葉にできず悩む人は少なくないようです。頭の中には伝えたいことがあるのに説明できず、言語化自体に苦手意識を持っている人もいるようです。そこで、「言語化力」を身に付けるメリットや鍛える方法などについて、『「うまく言葉にできない」がなくなる言語化大全』の著者であり、伝える力【話す・書く】研究所所長、山口拓朗ライティングサロン主宰・山口拓朗さんに伺いました。

目次
ビジネスには「言語化力」が必要不可欠
SNSやチャットツールなど短文でやり取りする機会が増えるにつれ、「頭の中にある気持ちや考えを、うまく言葉にできない」という悩みを持つ若手ビジネスパーソンが増えていると感じます。言いたいことはたくさんあるのに、スムーズに言葉が出ない、文章にできない…という相談を受ける機会も、以前に比べて増えています。
頭の中にどんなに素晴らしい意見やアイディアがあっても、それを言葉にして相手に伝えることができなければ、意味がありません。厳しい言い方をすれば、「言語化できない人は、何も考えていないのと同じ」。伝わらなければ、意見やアイディアを評価しようもないからです。
「言語化が苦手であれば、その分、専門性を高めればいいのでは?」という人もいますが、どんな仕事も周りとコミュニケーションを取り、意見をすり合わせながら進める必要があります。たとえ仕事に関する専門的なスキルがあっても、言語化力が低いと周囲から思ったような協力が得られなかったり、仕事が見当違いの方向に進んでしまったりして、成果が上がりづらく評価もされにくくなる可能性があるでしょう。
もしあなたが今、言語化に苦手意識を持っているならば、ビジネスパーソンとしてより評価され、成長するためにも、できるだけ早く言語化力を上げるトレーニングを始めることをお勧めします。
言語化力を高めるメリット
頭の中にある意見や考えをうまく言葉で伝えられるようになれば、周囲とのコミュニケーションが円滑になり、仕事がスムーズに回るようになります。アイディアが認められ採用されたり、意見が通って評価されたりする機会も増えるでしょう。人間関係における誤解やトラブルも減ると考えられます。
そして、言語化力が高い人の周りには、人が自然に集まるようになります。仕事での意思疎通がスムーズにできるのでストレスなく働けるうえ、成果も出やすい。すると、上司や同僚、取引先などに「この人と仕事がしたい」と思われやすくなるのです。もちろん、より大きな仕事が回ってくるチャンスも高まるでしょう。
言語化力がある人は、頭の中の考えを整理して論理的に伝えられるため、重要な場面で意見や考えを聞かれる機会もおのずと増えます。そういう機会が増えるとともに自己肯定感が高まり、ビジネスパーソンとしての自信につながると考えられます。
言語化力を上げる3つのStep
言語化力とは、頭の中にある考えや思い、情報などを的確に言葉にし、相手にわかりやすく伝える力のことです。この力を上げるのに欠かせないのが、次の3つのStepです。
Step2:「具体化力」を鍛える
Step3:「伝達力」を磨く
そもそも語彙が乏しいと、考えや思いを表現する際にピッタリくる「言葉」を見つけられないため、うまく言語化することができません。そして、頭の中を整理して言葉にする際には、どれだけ考えや思いを具体化できるかが勝負。特にビジネスでは抽象的な表現で物事が進むことはなく、言葉の解像度を上げることが重要です。
語彙力を伸ばし、具体化力を鍛えれば、「何を伝えるか」が明確になります。そのうえで、伝達力を磨けば、「この相手ならば、この言い方のほうが刺さるな」「誤解されないよう、最大のポイントである○○をまず伝えよう」などと、相手により伝わる表現や順番を考えられるようになります。
この3つのSTEPそれぞれの鍛え方について、簡単にご紹介しましょう。
Step1:「語彙力」を伸ばす
語彙力を伸ばすためには、日常生活の中で次の3つを意識するといいでしょう。
新しい言葉に「出会う」
新しい言葉に出会う方法は、人と会話をする、様々な体験をする、読書をする、意識して情報のアンテナを張る…などの方法があります。
中でも気軽に日常生活に組み込めるのが、「人との会話を増やす」という方法。
リモートワークの拡大などで、人と会話する機会が減っている今は、意識しないと言葉がどんどん頭の中から失われていきます。それを阻止して新たな言葉との出会いを増やすためには、人と会話すること。そしてオンラインよりも、できれば会って会話をすることをお勧めします。対面での会話は、オンラインに比べて内容が濃くなりやすいので、新しい言葉に出会える可能性が高いのです。
勉強会やセミナーなどに積極的に足を運ぶのも有効。普段仕事でかかわる人とは別の領域の人と会話をすることで、新鮮な「言葉のシャワー」を浴びることができ、刺激も得られるでしょう。
知らない言葉を「調べる」
言葉に出会っても、意味がわからなければ使うことはできません。知らない言葉に出会ったら、すぐに調べる習慣を付けましょう。
スマホやパソコンで「○○とは」で検索するだけでなく、類語や対義語・反対語も調べると、より深く意味が理解でき、言葉のストックも増やせます。
GhatGPTなどのAIチャットサービスも、 知らない言葉を調べるのに便利。表示された回答をさらに深掘りすれば、質の高いインプットが得られるでしょう。
脳に定着させて「覚える」
前述の「新しい言葉に出会う」「調べる」ができても、「覚える」ことができなければ語彙力は向上しません。大切なのは、「よし、覚えたからOK!」で終わりにしないこと。覚えたつもりでも、実際は覚えていないことが大半だからです。
言葉を覚えるために重要なのは、その言葉を「使う」こと。言葉を脳内で待機させず、話したり書いたり、人に教えてみたりして脳から引き出しアウトプットすることで、記憶に定着します。
ポイントは、新しい言葉をインプットしたら「間髪を入れずに使ってみること」と、「くり返し使ってみる」こと。これにより、新しい言葉を「重要な情報だ」と脳が認識し、側頭葉の長期記憶に保存されます。
Step2:「具体化力」を鍛える
「具体化」とは、言葉の解像度を上げることです。言葉の解像度が高ければ、相手にわかりやすく、かつ的確に物事が伝わります。
解像度を上げて物事を伝えるには、具体的な情報を3つ以上含めるのが有効。これにより伝えたいことと、相手が受け取ることのズレが減り、コミュニケーションにおける誤解が生まれにくくなります。
その際に有効なのが、5W3Hを活用する方法。
5W3Hとは、「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(誰が)」「What(何を)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」「How many(どのくらい)」「How much(いくら)」で情報をわかりやすく伝える基本です。
相手に何か伝えたり報告したりしたときに、「それってどういうこと?」などと聞き返される場合は、この5W3Hのいずれかが抜けているケースが多いのです。
事実を具体化する際には、まずこの5W3Hに当てはめるといいでしょう。これにより伝えたいことが整理され、解像度も高まります。すべての項目に当てはまらないかもしれませんが、まずは当てはめてみようとする姿勢がトレーニングになります。
Step3:「伝達力」を磨く
言語化のゴールは「相手に正しく伝わる」こと。相手の立場に立ち、欲しい情報をわかりやすく届けることで伝達力が高まり、誤解やすれ違いがなくなります。
その際の大原則が、次の5つ。これらを普段から意識することで、着実に伝達力が磨かれます。
●相手が理解しやすい言葉を使う
相手の知識レベルに合わせ、相手のバックボーンに応じて使う言葉を選ぶこと。相手の知識レベルやバックボーンがわからない場合は、「中学生でもわかる言葉」を意識してかみ砕いて伝えると良い。
●一文は60~70文字を意識
メールなど文章で物事を伝える際には、「一文一義」(1つの文章の中に1つの意味だけを盛り込む)が基本。1つの文章に複数のメッセージが入り混じると、相手が理解しにくくなる。文字数の目安は60~70文字。70文字を超えたら「文章を分けることはできないか」「余計な話や無駄な修飾語が入っていないか」とチェックしてみよう。
●「アサーティブ」に伝える
「伝える」ことに意識が向き過ぎると、自分の主張をバーっと伝えてしまい、相手が意見を投げかけてきても聞く耳を持たず否定してしまいがちになる。
アサーティブとは、相手のことを尊重しながら自分の意見や主張、感情を伝えること。アサーティブを意識することで、建設的なコミュニケーションが可能になる。
●相手に「伝わっているか?」を確認する
伝える最中には、相手の表情や姿勢を観察しながら「本当に伝わっているかどうか」を確認することが大切。あまり伝わっていない様子であれば、説明の仕方を変えたり、情報を補足したりしよう。このようにPDCAを回すことで、言語化力はどんどん磨かれる。
●相手の「ニーズ」を把握する
相手のニーズを把握する=「相手にとって必要な要素を見極める」こと。ニーズがわかれば、不要な要素をばっさり切り捨てることができるほか、相手に喜ばれる「要約」ができるようにもなる。Step2で具体化力が磨けていれば、具体化した情報を見渡しながら相手に合わせて厳選できるはず。
特に重要なのは「具体化すること」
言語化力を高めるために、手っ取り早く語彙力や伝え方を身に付けようとする人が多いですが、それだけでは「うまく言葉にできない」を解決することはできません。語彙力を伸ばしてぶつけるだけでは、相手にうまく受け取ってもらうことはできないし、伝え方だけを覚えても「伝える中身」が伴わなければ相手に理解してもらえません。
「語彙力」「具体化力」「伝達力」、この3つのSTEPを踏むことで、頭の中をうまく言葉にできるようになり、言いたいことがぱっと伝わるようになります。
中でも重要なのが、頭の中にある「伝えたいけれどモヤっとしている」ものの正体を見極め、思考や情報の解像度を上げていくSTEP2の「具体化力」。これこそが言語化の本丸であると、まずは理解するところから始めましょう。
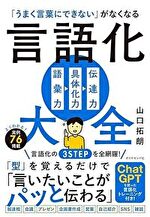 山口拓朗さん
山口拓朗さん
伝える力【話す・書く】研究所所長。「論理的に伝わる文章の書き方」や「好意と信頼を獲得するメールコミュニケーション」「売れるキャッチコピー作成」などの文章力向上をテーマに執筆・講演活動を行う。『伝わるメールが「正しく」「速く」書ける92の法則』(明日香出版社)のほか、『残念ながら、その文章では伝わりません』(だいわ文庫)、『何を書けばいいかわからない人のための「うまく」「はやく」書ける文章術』(日本実業出版社)、『書かずに文章がうまくなるトレーニング』(サンマーク出版)などがある。2023年11月に最新刊『「うまく言葉にできない」がなくなる 言語化大全』(ダイヤモンド社)が発売。
公式サイト:http://yamaguchi-takuro.com/




















