読書は大切だと思うけど本に手が伸びない。なかなか1冊が読み切れない…。それはもしかすると、本の読み方や選び方を、自分で難しくしているせいかもしれません。ビジネスパーソンが多忙な中で効率的に本を読み、読書習慣を楽しみながら、知見を広げていくにはどうしたらいいのでしょうか。本の要約サービスを運営する、株式会社フライヤー代表取締役CEOで、大の本好きでもある大賀康史さんに、大人におすすめの読書術を聞きました。
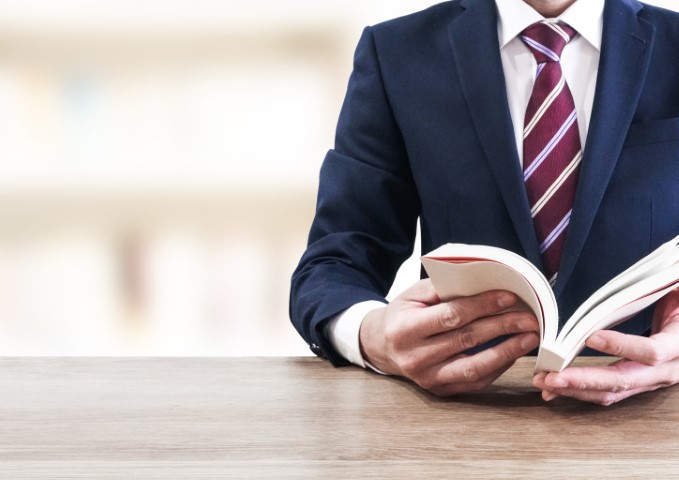
ビジネスパーソンがもっと本を読んだ方がいい理由
残念なことに「日本人は本を読まない」と言われて久しいようですが、私は忙しいビジネスパーソンほどできるだけたくさん本を読んだ方がいいと考えています。
自分が体験しきれない知識や経験を得られる
変化の激しい現代に、ビジネスパーソンが活躍していくためには、日々学ぶことが欠かせません。学びには「人から学ぶ」「体験から学ぶ」「本から学ぶ」などの方法がありますが、人に教わる機会や、自分の人生で体験できることには限りがあるものです。
それに対して本は、さまざまな作家や有識者、研究者が長い年月をかけて学んだことを、いわば結晶化したものです。1冊あたりわずか数時間の読書で、「すごい人」が人生を懸けて学んできたエッセンスを摂取し、体験だけではカバーしきれない知識や経験を「疑似体験」することができます。それによって、ビジネスで未経験の状況に遭遇したとしても、知の蓄積の中から回答や解決策を導き出すことができるようになるのです。
本は断トツに信頼性の高い学びのツールである
世の中には学びのためのツールやコンテンツが数多くありますが、本ほど時間をかけて制作されるものはないかもしれません。多くの本は出版までに数年の年月がかけられ、その間に著者と編集者が何度も打ち合わせを重ね、構成の見直しや原稿の修正、事実関係の確認や表現のチェックなど、非常に多くのプロセスを経て出版されます。世に出てからも多くの読者に評価され、後に改訂されることもあります。
その意味で本は、情報としての信頼性が非常に高いツールではないでしょうか。私は、今も本が学びの中心にあるのが自然なことだと思いますし、もっと多くの人に本を有効活用して欲しいと考えています。
「本が読めない」のは読み方を間違えているから
なかなか読書ができないという人からは、よく「読み始めても時間がかかる」「途中で挫折する」という声を聞きます。ここでの最大のつまずきポイントは「本は最初の1ページ目から真面目に読むもの」という思い込みではないでしょうか。まずはそこを改めましょう。
小説とノンフィクションは読み方が違う
「でも、小説は最初からちゃんと読まないと話の筋がわかりませんよね?」というのは正解で、フィクションは、頭から順番にストーリーを追いかけていくのが楽しく読めるポイントです。ネタバレが怖いなら、事前に書評も見ない方がいいでしょう。
しかし小説以外のノンフィクション、例えばビジネスやサイエンス、哲学や生活などさまざまなジャンルがありますが、これらはみんな最初から律儀に読む必要はありません。私がおすすめする読書法は、まず本の概要を掴み、次に最も大切な中核部分、自分が興味を持った部分を優先的に読んでいくことです。
最初に本の「幹」を把握するとスラスラ読める
本を手にしたら、まずタイトルと著者の略歴を見て、この本がどんな経験やモチベーションから書かれたものかを理解しましょう。次に目次をよく読んで構成を把握し、主要な主張が書かれた章がわかったら、そこを最初に読みます。そして頭の中に地図をつくってから、自分の興味が湧いたところを中心に読んでいきます。この読み方なら、むしろ積極的にネタバレを読むのがおすすめ。本の概要を知るために、書評を読むほか、私たちが運営する「flier(フライヤー)」のような本の要約サービスも活用できるでしょう。
このように「この本で何が得られるのか」を事前に理解した上で読み始めると、読むペースが格段に速くなり、吸収力も上がります。また、無理に全編を読む必要もありません。読書の時間は有意義ですが、一字一句逃さず読もうとするあまり、読みにくいところまで時間をかけると、逆にモチベーションが下がったり、途中で挫折したりしがちです。
本はもっと自由に気楽に、興味の赴くままに読んでいいのです。

忙しいビジネスパーソンにおすすめの「本とのつき合い方」5つ
本の読み方の次に、ビジネスパーソンにとってプラスになる本の選び方とつき合い方について、私が考える5つのコツをご紹介しましょう。
1. 自分が一番興味のある領域から読書を広げる
これから本を読む習慣をつけたい人は、シンプルに、今一番興味があるジャンルの本から読むことをおすすめします。人が知的好奇心でワクワクしているときは、脳内にドーパミンなどの神経伝達物質が出て、思考力や記憶力がグンと上がると言われるからです。まずは面白そうだと思う本を1冊読めば、周辺領域にも自然に興味の輪が広がっていくでしょう。
好きなジャンルから1冊を選ぶときは、書店や有識者のおすすめ、世の中の評価を参考にするのも一案です。世間で評判の良い本は売れるだけの理由があるからです。本の要約サービスである「flier」も、著者が伝えたいことがコンパクトにまとまっているので、本を選ぶツールとして有効活用できるでしょう。
大人の読書は「学校の宿題」などではなく、人生を豊かにする楽しみのひとつ。まずは読書の楽しさを覚えることを優先して選んでください。
2. 本を読む時間を決めて習慣にしてしまう
人はある日突然に変わることはできません。人を変えるのは「習慣」をおいてほかにはなく、まさに読書も習慣化することがとても大切です。まずは「朝の1時間」「寝る前に1時間」など、生活リズムに合わせて時間を押さえ、自分が読みたい本を毎日開いてみましょう。就寝前に寝床に入ったときや、通勤時などのすき間時間は、耳で読める音声コンテンツを活用してもいいでしょう。
習慣は最初の3週間ほどを越えると、割と苦もなく定着することが多いものです。そのまま半年、1年と楽しく続けることができれば、きっと人生の背中を押してくれる効果が期待できるでしょう。あらゆる習慣の中でも、読書の習慣は最も優先していいもののひとつだと思います。
3. 気になったらアクションで記憶に定着させる
本の中で気になった部分があったときは、すぐに何らかのアクションを起こしましょう。例えば付せんを貼っても、線を引いても、思ったことを書き込んでもOK。自分のやりやすい方法を選んでください。私の場合は、手っ取り早くページの隅を折り、特に印象的な部分は2重に折るのが習慣になっています。すると、次にその本を開いたとき、印象に残った箇所をパッと見つけることができます。
この行動はしおりの意味合いもありますが、それ以上に、脳を活性化させる効果を期待するものです。脳の「思考」と「運動」を司る部分は密接に結びついているため、手を動かすことで脳が多面的に働き、記憶に残りやすくなるのです。本は、知識や経験を自分のモノにするためのツールなので、どんどん線を引いたり汚したりしてもいいと思います。
4. 読んだ数ではなく考えた量が重要
読書のスピードは人それぞれですが、「月に○冊」と冊数を目標にすることはあまり意味がありません。読書の目的が知見を広げることや思考力を鍛えることだとすれば、「考え事をした量」が最も大切だからです。たとえ1時間で5ページしか進まなくても、その間に「この本は人生に影響しそう」とか「別の本には違うことが書いてあったな」などと考えを巡らしていれば、それはとても貴重な時間です。
読書の醍醐味のひとつに「知と知が繋がった瞬間」があります。「あの経験はこの本のこれのことだったのか!」と気づいたときや、複数の本から共通する事象が3つ、4つと見つかり、自分の中に新たな概念が浮かんだときなどは、とても興奮するものです。そんな喜びを味わうためにも、読書中はどんどん寄り道や脱線をして構いません。
5. アウトプットを意識しなくても学びは蓄積する
前提として、本で学んだことを何かの形でアウトプットするのはとても良いことです。読書メモを書く、人に内容を話す、SNSで発信するなどは、学びを定着させるための素晴らしい習慣です。さらに、ビジネス書などのノウハウを翌日の仕事にすぐ生かせれば、それは最も有効なアウトプットとなるでしょう。
一方で、本は100冊、200冊と読んでいくことにより、人生のあらゆることに応用がきく、判断や行動の拠り所が無意識に蓄積されていきます。一字一句を憶えてなくても、頭の奥底に引き出しが整備されていき、あるとき「ヒラメキ」という形で姿を現すことがあります。
ですから直後のアウトプットは必須ではありませんし、内容を忘れて「読んだのは無駄だった」と残念がることもありません。読んだ本はすでに、あなたの価値観や思考をつくるひとつの要素になっているからです。
社会人はできるだけ若いうちから本を読んでおこう
読書は人生のいつ始めても遅くはありませんが、私は特に20代のビジネスパーソンこそ、読書をして欲しいと考えています。それは生涯にわたる資産になるものです。
新人の頃は、上から言われた仕事さえきちんとやれば、それなりに評価されます。しかし、数年後にリーダーやマネジャーを任されると、ほとんどのケースで自分が経験したことのない課題が一気に降ってきます。そうなると、どのくらい本を読んで考えてきたか、知見を広げてきたかで差が表れてくるでしょう。
ジャンルは何でも構いませんが、ビジネスパーソンの「心構え」をテーマにした本は、1冊読んでおくことをおすすめします。「この人はすごい」「信頼できる」と思った著者の本を、ぜひ手に取ってみてください。
 株式会社フライヤー 代表取締役CEO 大賀 康史(おおが・やすし)氏
株式会社フライヤー 代表取締役CEO 大賀 康史(おおが・やすし)氏
2001年早稲田大学理工学部機械工学科卒業、2003年早稲田大学大学院理工学研究科機械工学専攻修了。2003年にアクセンチュア株式会社 製造流通業本部に入社。同戦略グループに転属後、フロンティア・マネジメント株式会社を経て、2013年6月に、株式会社フライヤーを設立。“1冊10分で読める”本の要約サービスを展開し、ビジネス書を中心に3300冊以上の要約を公開している、著書に『最高の組織』(自由国民社)、共著に『7人のトップ起業家と28冊のビジネス名著に学ぶ起業の教科書』(ソシム)などがある。




















