話し手・聞き手に加えて第三者を想定したプレゼンの「核」。澤さんは、それを「第三極の思考」と表現します(詳細は第7回記事をご覧ください)。技術者のプレゼンを魅力的にするために必要なメソッドとは何か?
澤円のプレゼン塾・第8回は、オーディエンスを意識したプレゼンの「核」について、解説していきます。

「第三極の思考」で本質的なプレゼンを
前回(前回の記事はこちら)は、技術者のプレゼンを魅力的にするために有効な「第三極の思考」について紹介しました。実はこの内容は、これまでお伝えしてきた「伝言ゲーム」を思い出していただきたい部分です。
前回紹介したプレゼン(※以下参照)の内容を誰かに伝言するのは、営業部長さんには難しいチャレンジです。何せ、初めて聞く言葉が混じっていたりするわけですから。
インメモリデータベースの話題を例にしたプレゼン例
<例1>技術情報だけで伝えた場合
「インメモリOLTPエンジンでは、メモリ最適化記憶域の中にテーブルとインデックスを持ち、メモリ上でトランザクション処理を行うため、非常に高速な処理が可能となっています」
<例2>導入メリットと合わせて伝えた場合
「インメモリOLTPエンジンという素晴らしい技術革新により、多くのデータをより高速に処理することができるようになりました。
その結果として、処理時間が短くなるため、コスト削減やビジネスのスピードアップにもつながります」
しかし、後者のプレゼンなら「これ入れると、我々はいい仕事ができるらしいぜ」という伝言はできます。そして伝言されればされるほど、プレゼンテーションの価値が上がる。これはこの連載を読んでくださっている皆さんなら、きっと賛同いただけると信じてます(笑)。
もっと風変わりな「第三極の思考」を用意してもかまいません。例えば、小学生たちが聴きに来ていると仮定してもいいのです。そうすれば、さらに噛み砕いた説明が必要になりますよね。裏を返せば、それだけ本質的なプレゼンテーションができ上がるはずです。
言葉は平易になり、難解な用語は少なくなり、写真や図がふんだんに取り込まれることになるでしょう。数値データの使い方も変わってくるかもしれません。
多面的なプレゼンテーションの表現方法を考える
では実際に小学生たちが聴いていると仮定して、クラウドストレージサービスの説明をしてみることにしましょう。
これでは分かる小学生はほとんどいなさそうです。
では、下記ならどうでしょう。
ドラゴンクエストなどのゲームでボスキャラを前に悔し涙を流した小学生は、きっと夢のような世界だと感じてくれるのではないでしょうか。
これこそが、「第三極の思考」の極意たるものです。その場にいるはずのない人までも感動させるのですから。
この「第三極の思考」を取り入れれば、多面的なプレゼンテーションの表現方法を考えるきっかけを手にすることができます。
「思考を飛ばす」という発想
「第三極の思考」をするために必要なメソッドを、私は「思考を飛ばす」と呼んでいます。
例えば誰かに質問を受けたとき、「あ、私が言いたいのは…」を最初に持ってくるのではなく、「それはもしかしてこのような考え方ですか?」と第三者の思考を仮説として提示するやり方です。
プレゼンテーションを作っているときも、脳内に浮かんだ文字列をダウンロードしてキーボードをたたき続けるだけでなく、
- 「これを部長はどう見るかな?」
- 「競合相手はビビってくれるかな?」
- 「うちの子供にも分かるかなぁ」
と、まずはランダムに思考を飛ばしてみるわけです。プレゼンテーションを作っているとき、どうしても主観が思考の大半を占めることになります。
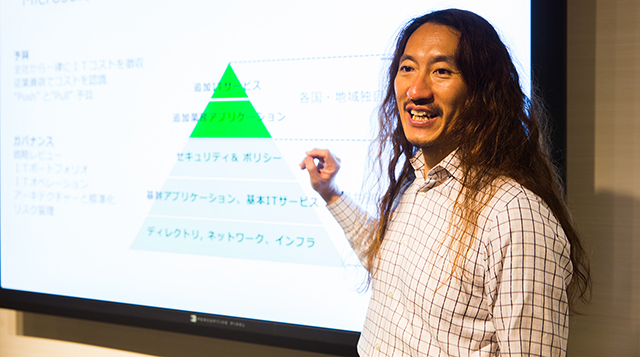
そのまま作業を進めてしまうと、かなりの確率で
- 「押しつけがましいプレゼン」
- 「自社の製品の宣伝ばかりのプレゼン」
- 「オーディエンスを意識していないプレゼン」
が、でき上がってしまうのです。
プレゼンテーションがある程度できたら、まず自分の思考をできる限り遠くに「飛ばして」みてください。
- 「ウォールストリートの超エリートがこれを読んだらどう思うのか?」
- 「中国の高校生はこれを見て何を感じるのかな?」
- 「サバンナの狩人は、これに賛同してくれるのだろうか」
とか、もう自由に飛ばしまくりましょう。
あなたのプレゼンテーションを聴く人たちは、決して同じ価値観を持ってはいないでしょう。同じ言葉でも、まったく違う受け取り方をするかもしれません。そのためにも、あちこちに思考を飛ばしてほしいのです。
それが皆さんの視野を広げ、視座を高くし、より多くの人に伝わるプレゼンテーションが生まれます。なるべく遠く、それも違う方向にたくさん飛ばすことで、全方位的に伝えることができるプレゼンテーションができ上がります。
飛ばす思考パターンは多い方がいい
まったく違う価値観を持っている人たちにも伝わる、素晴らしいプレゼンテーションにどんどん近づいてください。以前紹介した織田信長さんの話も、私が思考を「飛ばした」結果として生まれたストーリーです。思考は時空を越えて飛んでいきます。
ちなみに、この「思考を飛ばす」という行為は、プレゼンテーションをやっている最中でも有効です。「あ、このフレーズはノンテクの営業部長にも分かるかな?」とか、「このデモをディープな技術者に伝えるにはどんな言葉が適切かな?」とか。
そうすることで、自分のプレゼンテーションを客観視することができます。実際のプレゼンテーション中の思考や立ち居振る舞いについては、また別途詳しくお伝えします。
プレゼンテーションは、オーディエンスに伝わらなければ意味はありません。伝えるためには、なるべく多くの思考パターンを想定する必要があります。
そのパターンを多く持てば多く持つほど、プレゼンテーションの質が向上するのです。次回は、第三極の思考を持つために必要なメソッドについて、考えていきたいと思います。
連載:澤円のプレゼン塾 記事一覧はこちら
著者プロフィール
 澤 円(さわ まどか)氏
澤 円(さわ まどか)氏
大手外資系IT企業 テクノロジーセンター センター長。立教大学経済学部卒。生命保険のIT子会社勤務を経て、1997年より、現職。情報共有系コンサルタントを経てプリセールスSEへ。競合対策専門営業チームマネージャ、ポータル&コラボレーショングループマネージャ、クラウドプラットフォーム営業本部本部長などを歴任。著書に「外資系エリートのシンプルな伝え方」「マイクロソフト伝説マネジャーの世界No.1プレゼン術」
Twitter:@madoka510
※本記事は「CodeIQ MAGAZINE」掲載の記事を転載しております。




















