仕事があるのに億劫で手が着けられない。いざ始めてもスマホなどに気を取られて全く進まない…。そんな自分の「先延ばし癖」が嫌になることはありませんか? ついグズグズしてしまう自分を変えて「すぐやる人」になるにはどうしたらいいのでしょうか。脳のリハビリを専門とし、『「やらなきゃいけないのになんにも終わらなかった……」がなくなる本』の著者である作業療法士の菅原洋平さんに、そのヒントをうかがいました。
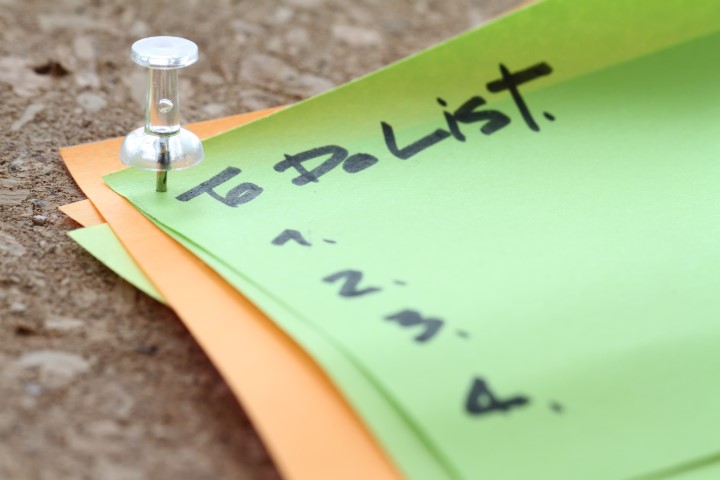
先延ばし癖は「性格」ではなく「脳の仕組み」が原因
私は多くの企業で、生産性向上などをテーマに研修をしてきましたが、その度に「私はギリギリにならないとやらないタイプ」「小さい頃から先延ばし癖があります」と悩みを打ち明ける方にたくさん出会います。そしてほとんどの場合、これは性格だから仕方がないと諦めてしまっています。
しかし、私たちに先延ばし行動をさせているのは、決して性格や意志の弱さなどではありません。人の臓器の一つである「脳の仕組み」がそうさせているのです。
脳は予測ができないと指令が出せない
私たちのあらゆる行動は、脳が指令を出すことで成り立っていますが、脳には「次の出来事を予測して指令を出し、予測通りに進めたがる」という特徴があります。脳はとても燃費の悪い臓器なので、体に指令を出すときは常に、過去の記憶と新たな情報をつなぎ合わせて次の展開を予測することで、エネルギーの消耗を抑えようとしているのです。
ところが、全く新しいことを始めたり、経験があることでも予測できない情報が入ってきたりすると、脳はどうしたらいいかわからなくなり、体にうまく指令を出せなくなってしまいます。その結果「面倒くさい」という感情が沸き起こって、私たちは先延ばしをしてしまうのです。
脳にお膳立てをしてあげれば先延ばしは避けられる
では、面倒くさいという感情から解放されて、やるべきことをすぐにやるには、どうしたらいいのでしょうか。それは、「予測する」という脳の機能を利用して、この先に起きること=「やるべき行動」が具体的にわかるような設定をすることです。そうすれば脳は、たくさんある過去の経験の中から「これが使えそうだ」という記憶を引き出し、体に指令をしてくれます。
このときに重要なのは、自分自身を切り離して一段高いところから客観視する「メタ認知」。自分が脳のマネージャーになり、お膳立てをしてあげる感覚です。いくつかの方法を試して、自分に合うものを色々な場面で応用すれば、少しずつ脳を操縦できるようになるでしょう。
先延ばし癖を解消して「すぐやる人」になるための3つの習慣
先延ばしを防ぐために、私が多くの社会人におすすめしている基本的な3つの習慣があります。どれも簡単にできるので、ぜひ試してみてください。
次の仕事に少しだけ手を着けて区切りとする
「会議をして議事録を書く」「調査してレポートをまとめる」という場合、会議や調査の次にやるべきことはわかっているのに、面倒でなかなか手が着けられないことがありませんか?
人が新たな仕事に取りかかる場合、脳は「次に何をするか」を一から考えて指令を出すため、多くのエネルギーを必要とします。それが脳の負担となり、「面倒くさい」という感情が湧くのです。
この場合は、仕事をどこで区切るかがポイントです。たとえば会議の議事録を書くとき、一連の仕事の区切りがどこにあるかを脳は判断できませんが、私たち自身は好きなように設定することができます。
そこで「会議が終わったら、その場で一行だけ議事録を書く」までをセットにして一区切りとします。メタ認知の視点で言うと、次の展開を少しだけ「脳に下見させてあげる」ということです。
すると次に議事録を開いたときに、脳は次にするべき行動を予測して準備ができているため、新しい仕事を一から始めるよりも、ずっと楽に作業を始めることができるのです。
大切なことをする場所では他のことをしない
仕事や勉強をサクサクと進めたいときは、家やオフィスに「それしかやらない場所」を作り、「そこでは他のことを一切しない」と決めましょう。私はそれを「1作業1スペースの法則」と呼んでいます。
脳は、過去に「そこで○○をした」という経験をすると、場所と行為をセットで記憶します。
ですから、同じ場所でスマホや映画を見たことがあると、「今から勉強する!」「企画を考える!」という意志とは関係なく、スマホや映画を見る準備をしてしまいます。選択肢が多いほど脳はその抑制にエネルギーを使うため、本来やるべきことに集中しようとすると、どっと疲れてしまいます。
それを防ぐためには、「この席は仕事専用」と決め、スマホを触ったりコーヒーを飲みたくなったりしたら別の場所に移動し、終わったら手ぶらで戻ることです。その場所でする行為を限定して、脳に明瞭な記憶を一つ定着させると、そこに行くことによって自然にスイッチが入り、「やる気」に頼らなくても作業に集中できるようになります。
一人暮らしなどで専用スペースが確保できない場合は、同じテーブルでも座るイスを変えたり、座る向きを変えたりするだけで効果があります。脳は、見えている景色の違い=視覚情報の違いを場所の違いと認識して、行動を変えてくれるからです。
「○○しなくちゃ」ではなく「する」とつぶやく
私たちは無意識に「企画書を書かなきゃ」「机を片付けなくちゃ」とつぶやくことがありますが、先延ばしをしないためには「企画書を書く」「書類をファイルする」と言い切ることが大切です。
基本的に脳は、自分の使った言葉から記憶を検索します。脳にとっては言語が情報へのアクセスコードになるため「しなくちゃ」では、「する」のか「しない」のかがわかりにくく、すぐに体に指令を出すルートが作れないのです。
このとき「ちゃんとやる」「しっかりやる」と言いたくなることもありますが、これも脳にとっては曖昧です。「ちゃんと」では、どの記憶を検索すればいいのか判断できず、「何をすればいいのだろう」と立ちすくんでしまうことがあるのです。したがって「10分間企画を考える」「テキストを5ページ読む」「○○の書類をファイルする」など、できるだけ具体的につぶやくようにしましょう。
まずは実行できなくてもいいので、口に出して言ってみてください。それだけで「あれ?今までと感覚が違う」「なぜかすんなり始められた」という方はたくさんいます。そうなればしめたものです。

先延ばしをしやすくなる3つのシーンとその対処法
上述したように、先延ばしをする行動には脳の仕組みが大きく関与しています。ですから、脳の状態や周囲の環境、課題設定のミスなどによって、先延ばしは誰にでも起きることです。
ちなみに脳がやる気になる条件は、(1)脳が適度に覚醒していること、(2)予測可能な既知のことと、未知のことが五分五分の状態であるといわれています。
ここでは、やる気のバランスが崩れて先延ばしをしやすくなる3つのシーンと、その対処法をご紹介します。「今の自分はこの状態かな」と思ったら、ぜひ提案した方法を試してみてください。
【シーン1】変化に対応しようと頑張りすぎている
春先に多い現象ですが、環境が大きく変化したとき、それに対応するために脳が過度に覚醒し続けることがあります。新たな職場や同僚など、周りは未知なことだらけなのに、張り切って新しい勉強や習い事を始めてしまい、自分から未知の領域を増やしてしまう方もよく見られます。
このとき脳は、予測不能な未知のことで容量が一杯の状態。それが原因で、普段はありえないミスをしたり、気が散ってやる気が起きなかったり、大切な決断を先送りしたりすることも起きがちです。
【対処法】日常に「小さな不変」を増やす
身の回りに未知な状況が多いときは、自分の中に変わらないもの=既知な状況を増やすことが大切です。
たとえば、朝と昼は同じメニューしか食べない、毎日同じ色の服を着る、メールチェックは○時だけにするなど、日常生活の中で不変のことを増やし、脳が選択する負担を減らしましょう。そうすれば脳は、不測の事態への対応や、重要な決断のためだけにエネルギーを使うことができます。
逆に、自分の意志で新しい勉強や習い事などのチャレンジを始めたいのであれば、転職や配置転換、転居などのタイミングを避け、未知の状況が少ない時期を選ぶのがおすすめです。
【シーン2】同じことの繰り返しで退屈している
脳が最もワクワクを感じるのは、「50%はやればできそうだけど、50%はやってみなければわからない」という、いわゆる「最近接領域」と呼ばれる課題設定です。
しかし会社の業務には、解決済みの課題を何度も繰り返すルーティンワークが少なくありません。上の【シーン1】とは逆に、既知のことだらけで未知のことが少なすぎても、脳のパフォーマンスは低下します。退屈を感じてしまうために、「今やらなくてもいいや」「ギリギリでも間に合えばいい」などと先延ばしをしがちになってしまいます。
【対処法】ルーティンに「小さな変化」を組み込む
この場合は、意識的に新しいことを取り入れることが大切です。たとえば、普段と違う場所で違うデバイスを使って仕事に臨むなど、環境に変化をつけてあげると、脳はそれを新たな課題だと認識してくれます。
取り組む環境だけでなく、成果物を少しアレンジするのも一案です。同じテーマの資料でも、毎回スライドを1枚だけ新しくしたり、原稿の一文を変えてみたりなど、少しの未知を足すだけで、モチベーションが上がることがあります。「あれ、いつもと少し違うぞ?」と脳に思わせることができれば、先延ばしを避けることができるでしょう。
【シーン3】忙しすぎて常にToDoリストがいっぱい
忙しすぎて疲れているはずなのに、寝る前につい動画をダラダラ観てしまったりする場合、24時間神経が鎮まっていない可能性があります。そうなると周囲の変化に関係なく脳が過度に覚醒を続けてしまいます。
常に情報過多の状態にあるため、何かしていても次の仕事が気になって身が入りません。やることをリスト化しますが、タスクの多さにやる気を削がれ、ぐるぐると考えるだけで行動に移せない状態に。その結果「リストが全然消せなかった」「今日も何もできなかった」という状況に陥りがちです。
【対処法】意識的に課題を区切って情報を消化する
脳の覚醒度が高すぎる人は、休憩を取らずに過度な集中状態を続けていることが多いものです。脳も胃袋と同じで、情報を取り入れるだけでなく、消化する時間が必要です。
脳のために効果的な休憩を取るには「5分」「15分」「30分」「90分」というタイミングがあります。
まず、人が一定の脳波の状態をキープできる時間は4分半まで。考え事をして良い考えが浮かばなければ、一旦5分で切りましょう。また、16分に1回は集中が切れて他のことを考える「マインドワンダリング」という状態になるため、同じ作業を続けるのは15分までとし、画面や資料から目を離して休ませましょう。
イスに座る姿勢が30分続くと脳への血流量が下がって疲労物質が蓄積するため、30分に1回は立ち上がって少し歩くことが大切です。そして、人が知的作業を継続する集中力の限界が90分と言われます。少なくとも90分に1回は、軽い散歩や運動をしたり、デスクの片付けなどの手作業を挟んだりするといいでしょう。
「すぐやる人」になるには脳を疲れさせないこと
先延ばし癖を治したいなら、「新しいツールを取り入れて解決しよう」とするのはおすすめできません。なぜかというと、新たに何かを始めること自体が脳の負担になるからです。きちんと脳の仕組みに合わせた設定をするだけで、行動を変えることはできるので、小さな実験をするつもりで試してください。少しずつ感覚が変化して面白くなってきたら、もう先延ばし癖は大分改善されているはずです。
 作業療法士、ユークロニア株式会社代表 菅原洋平さん
作業療法士、ユークロニア株式会社代表 菅原洋平さん
国際医療福祉大学卒業。国立病院機構にて脳のリハビリテーションに従事した後、ベスリクリニック(東京都千代田区)で薬に頼らない睡眠外来を担当するかたわら、生体リズムや脳の仕組みを活用した企業研修を全国で行う。リモートワークにおける生産性向上にも取り組み、テレビや雑誌でも注目を集める。著書に『あなたの人生を変える睡眠の法則2.0』(自由国民社)、『「やらなきゃいけないのになんにも終わらなかった……」がなくなる本』(WAVE出版)など。




















