周りの環境や人のせいにする人などと、ネガティブに捉えられがちな「他責思考」ですが、実際にはビジネスシーンにおいて必要な要素が多くあります。どんな考え方の特徴があり、自責思考とどうバランスを取ると強みを発揮できるものなのか、企業や組織における若手ビジネスパーソンの育成にも詳しい人事・採用コンサルタント曽和利光さんに聞きました。

他責思考の人って本当に無責任なの?
そもそも「他責思考」とは、どんな考え方を指しているのか。「自責思考」と合わせて解説していきましょう。何らかの出来事が生じたとき、その責任の所在がどこにあると考えるのかによって、「他責」か「自責」かが分かれます。
他責思考の人は「当事者意識」が強い?
「自責思考」の人は「自分の責任だ」と感じますが、「他責思考」の人は周りの環境や他人の責任だと感じたり、あるいは「仕方ない」「誰のせいでもない」という無責思考でものごとを捉えたりします。
ビジネスシーンにおいては、何事も「自分に原因がある」「自分の責任だから自分で何とか解決しよう」と思う自責思考の人の方が、他責思考の人よりも、実は一緒に仕事をしやすいように思われるでしょう。
ただ、“責任”という言葉には2つの意味があります。その意味合いにより、「他責思考」「自責思考」の捉え方が変わってきます。
他責思考の責任はどこにあるのか
“責任”には、「原因の所在がどこにあるのか」に加えて、「解決の主体はどこにあるのか」という意味があります。「このミスは〇〇の責任です」といえば、原因の所在を指しますし、「〇〇は、このプロジェクトの管理責任者です」というと、解決の主体を指します。
以下2つの視点をマトリックスで考えていくと、「他責思考」と一言でいってもさまざまなパターンがあることがわかります。
- 原因の所在が自分にあるか、他人にあるか
- 解決の主体が自分にあるか、他人にあるか
もっとも無責任なのが、「原因の所在は自分にあるけれど、解決の主体は他人にある」という考え方です。この思考で仕事をされては、周りが大変な思いをするのは当然でしょう。
一方で、「原因の所在は他人にあるけれど、解決の主体は自分にある」というのも、責任を2つの意味で捉えれば、他責思考の一つです。
原因という点では当事者ではないけれど、自分が取り組むべき課題の主体者として取り組む。「高い当事者意識を持っている」という点で、周りと協業しながら仕事をする上で、高く評価される思考の持ち主と言えます。
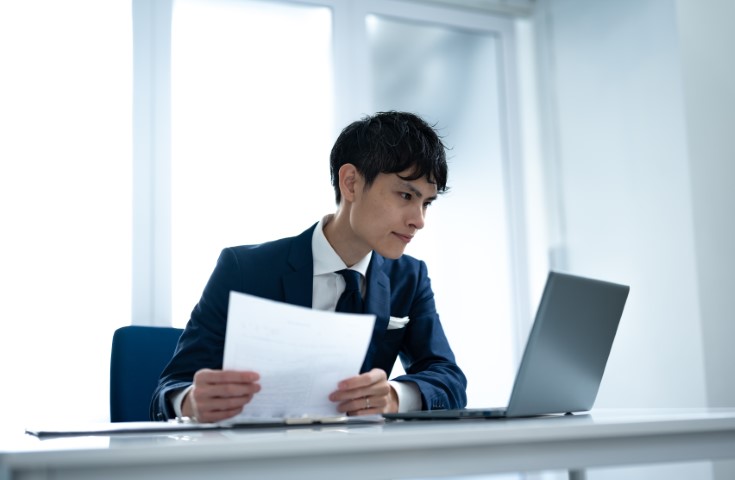
他責思考の強みと弱みとは
原因の所在が自分にあるにもかかわらず、そう認めない、あるいは他人のせいにする「他責思考」には、以下のようなネガティブな面が多くあります。
- 改善すべき点に向き合わず、成長が見られない
- 周りから信頼されず、人が去っていく(仕事を任されなくなる)
ただし、世の中の事象のすべては、さまざまな因果関係が複雑に絡み合って起こっています。すべての原因の所在が誰か一人にあるということはほとんどないのが現実です。
仕事上でミスが起こってしまったとき、「ヒューマンエラーは誰にでも起こること。ミスが起こる仕組みを放置していた組織側にも責任がある」「ミスが起こるような仕事の任せ方、業務量だった点で、マネジメント側にも責任がある」というのも、一つの大切な観点となります。
一定の他責思考があれば、「そもそも、仕組み自体を変えていかなければ、ミスした本人が反省して改善しても、また同じことが繰り返される」と考えます。原因の所在が他人にあったとしても、解決の主体は自分にあるという「当事者意識」は、環境や仕組み自体を変えようというモチベーションにつながるのです。
また、原因の所在を自分以外に持てる点で、精神的に強いとも考えられます。他責思考のメリットや強みとしては、以下のようなことが挙げられるでしょう。
- 環境を変える変革意欲が高い
- 必要以上に自分を追い込まないメンタルタフネスを持っている
自責思考の強みと弱みとは
「原因の所在は自分にある」と考える自責思考は、担うべき業務や裁量がきっちりと決まっている仕事において力を発揮します。
仕組みやルール、マニュアルが定められているインフラやメーカー、チェーン展開のサービス業などでは、自責思考で自分に任せられた業務範囲内で改善していこうというマインドの人のほうが、企業側としても管理がしやすく、向いているでしょう。
ただし大きな欠点としては、自分の影響を及ぼせる範疇でしか変えようとしないところです。環境自体を変えていこうという考える人は少ないので、組織変革を期待する幹部人材や新規事業開発などの領域には不向き面もあるかもしれません。
また、必要以上に「全部自分の責任だ」と考えすぎるあまり、他責思考の人よりもストレスを抱えやすいとも言えます。
自身の思考を理解して仕事に取り組もう
「他責思考」にも「自責思考」にも、それぞれ向き不向きがあります。他責思考の人に、「与えられたルールの中だけで、自分の責任に向き合え」というのはとても窮屈で酷ですし、本来の変革力を発揮できずに、組織としても損失になります。
自分はどんな思考の持ち主なのかを理解した上で、仕事に取り組むことが、パフォーマンスの向上につながっていくでしょう。
株式会社人材研究所・代表取締役社長 曽和利光氏
 1995年、京都大学教育学部教育心理学科卒業後、リクルートで人事コンサルタント、採用グループのゼネラルマネージャーなどを経験。その後、ライフネット生命、オープンハウスで人事部門責任者を務める。2011年に人事・採用コンサルティングや教育研修などを手掛ける人材研究所を設立。『「ネットワーク採用」とは何か』(労務行政)、『人事と採用のセオリー』(ソシム)、『コミュ障のための面接戦略』(星海社新書)、『人材の適切な見極めと獲得を成功させる採用面接100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)など著書多数。最新刊『定着と離職のマネジメント』(ソシム)も話題に。
1995年、京都大学教育学部教育心理学科卒業後、リクルートで人事コンサルタント、採用グループのゼネラルマネージャーなどを経験。その後、ライフネット生命、オープンハウスで人事部門責任者を務める。2011年に人事・採用コンサルティングや教育研修などを手掛ける人材研究所を設立。『「ネットワーク採用」とは何か』(労務行政)、『人事と採用のセオリー』(ソシム)、『コミュ障のための面接戦略』(星海社新書)、『人材の適切な見極めと獲得を成功させる採用面接100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)など著書多数。最新刊『定着と離職のマネジメント』(ソシム)も話題に。




















