ルーティンワーク以外に飛び込んでくる急ぎの仕事や、複数のプロジェクト。ビジネスの現場ではマルチタスク型の働き方や業務が増えていますが、「マルチタスクはできない」といった苦手意識を持っている人も少なくないようです。マルチタスクとシングルタスクとでは何が違い、どう対応したらこなせるのか、数多くのライフハックに関する著書を執筆している堀正岳さんに聞きました。
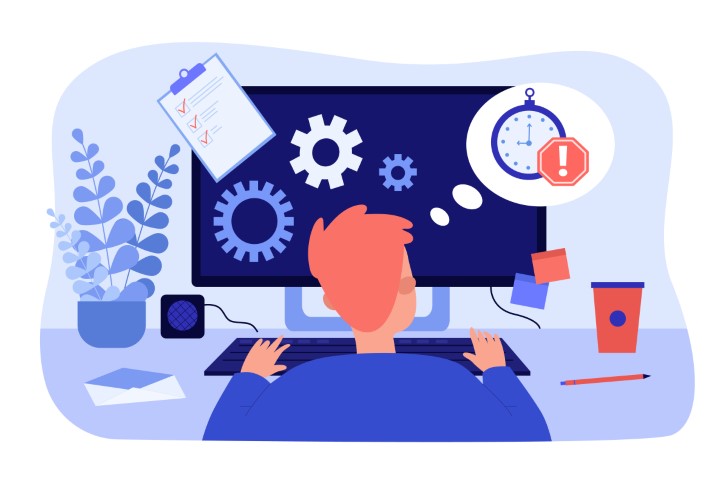
目次
マルチタスクとシングルタスクの違い
もともと、マルチタスクとは「一台のコンピュータで、二つ以上のプログラムを同時に実行すること」(出典:小学館『日本国語大辞典』)を指す言葉で、ビジネスの現場でも使われるようになりました。
例えば、ホテル勤務でフロント業務とマーケティング業務というように、一人で複数の業務を担当するマルチタスクもあれば、広告代理店で社内の業務改善プロジェクトとA社向けの新規案件、B社の販促提案、C社へのフォローなど複数プロジェクトの担当を同時に進行させるといったマルチタスクもあります。
さらに中堅以上のビジネスパーソンになれば、業務の推進や改善に加え、人事調整や部下の指導も任せられるようになり、それもマルチタスクになっていきます。それぞれゴールやスケジュールが異なるため、自分でタスク管理をコントロールしていく必要があります。
これに対してシングルタスクは、一人の人が1つの業務に専念したり、1つの作業に集中したりすることをいいます。1つのタスクが終了してから他のタスクに取り組む仕事の仕方そのものを、シングルタスクと呼ぶこともあります。
マルチタスクは複数の仕事を同時にするわけではない
A社の新規案件の打ち合わせを終えると同時に、B社の販促資料に着手し、合間にC社へフォローの電話を入れている──そんな人を見ると、同時にいくつもの仕事をこなすことができる有能な人だからであって、自分には無理だと感じてしまう人もいるかもしれません。
しかし、実は複数の仕事を“同時に”しているわけではないのです。厳密な意味で同時に二つのことをしている人はいません。フロントの仕事をしながらルームサービスの仕事をできないのと同様、A社にプレゼンしながらB社の販促資料を作ることはできません。
できているように見えている人も、実際はシングルタスクを上手に切り替えているだけです。その鍵となるのが、「切り替え」です。マルチタスクが得意な人は、「短時間で頭を切り替えて集中する」ことが非常に上手なので、同時にこなしているように見えるのです。
マルチタスクをこなす「切り替え上手」になるには?
個々に見れば、A社へのプレゼンも、B社の調査設計も、C社の見積もりもシングルタスクでしかありません。複数タスクが苦手な人は、「短時間で頭を切り替える」こと、もしくは「集中すること」のいずれかがやりにくい状況にあるだけなのです。
例えば、午前中はプレゼン用の企画書を書くことに集中し、午後はミーティングの資料作成に切り替えようと思っていても、デスクに向かっているとメールや電話対応など、外的要因で否応なく他のことに切り替えざるを得なくなり、集中は途切れてしまいがちです。状況によっては元の集中した段階に戻るのに時間がかかってしまうこともあるでしょう。
まず大切なのは切り替え回数を減らすこと。そこで、タスクの効率を高め、集中しやすい環境をつくるコツをお伝えしていきます。
メールボックスを確認する時間を決める
切り替え回数を減らすために、集中を途切れさせてしまうものを排除していきましょう。例えば、メールが入るたびにチェックしていると、その都度、意識はいったん今目の前で取り組んでいる仕事から離れてしまいます。
例えば、メールボックスの確認は10時、14時、17時の3回だけにするなど、時間を決めておきましょう。なお、メールを受信した際に音やポップアップで通知する機能はオフにする、アイコンに未読マークがつくことも気になるようなら、タスクバーへの表示も解除するとよいでしょう。
また、ポモドーロ・テクニックを使って、集中時間を設定し、その間はメールをチェックしないようにするのも1つの方法です。
【関連記事】
生産性がグングン上がる!「ポモドーロ・テクニック」って知ってる?

電話をとる前に、doingメモをとる
電話も、携帯電話なら決めた時間は留守電で対応するという方法もあります。しかし、会社のデスクの電話をとらないわけにはなかなかいかないでしょう。とはいえ、電話が入ってタスクが中断すると、元の状態に入るまでに時間のロスが生じます。
中断が入っても戻りやすいようにするには、メモが有効です。手元のメモ帳に「パワポに商品サイズ追加」など走り書きでよいので、ひと言で今やっていること(doing)を書いてから電話をとるようにします。今からやろうとしていたことではありません。「今やっていたこと」を書くのです。
それくらい覚えていると思っても、実は忘れてしまい、復帰ができなくなって大きなロスを生み出すのが私たちの記憶です。
すると、電話中に他の案件に気を取られたり、別の画面をパソコン上に開いたりすることになっても、終わればそれまでやっていた作業に復帰しやすくなります。
doingメモはデスク上の紙でも、パソコンの画面上のメモパッドでも構いません。今やっていることを書きながら進めると、上司に呼ばれたり、同僚から話かけられたりと、急な割込みがあっても元に戻りやすく、作業が終わったらメモを消すことで、達成感も生まれます。
時間割を考える
切り替え回数を減らすもう1つの方法が、時間に合わせて業務を割り振ることです。
例えば、朝一番は眠っている間に脳は記憶を定着させたり、ストレスの緩和をさせたりしているため、最もクリアな状態です。集中しやすく企画書を考えたり、調査の設計をしたりなど、たくさんの情報を処理し複雑なことを考える余裕があります。
一方、外部からの電話が増える午後や、取引先など外に出ていた社員が戻る夕方は、仕事が途切れやすい時間帯です。Excelの入力やPowerPointの体裁を整えるなどの作業を割り振っておくと、切り替え回数を減らすことができるでしょう。
マルチタスクの効率を高めるコツとは?
続いては、マルチタスクの効率を高める業務管理のコツをご紹介します。
タスクを書き出し、脳の処理能力を上げる
脳には、記憶や情報をいったん整理したり、まとめたりする仮置き場、ワーキングメモリの機能があります。いわば脳のメモ帳ですが、容量が限られているため、入力情報が多すぎるとオーバーワークで処理能力ががくんと下がってしまいます。
そこで、「やるべきこと」や「今やっていること」、「気になっていること」などのタスクを実際に書いてリストにすることで、ワーキングメモリの外部拡張領域を確保しましょう。
タスクが片付いたわけではなくても、書き出して客観視できるようにするだけで、脳への負荷が減り、状況を整理する力が増します。タスクを書き出すことは、自分を助けるツールになるといえます。
1プロジェクトに1リストで集中する
A社のプレゼン、B社の調査設計、C社の見積もりなど、複数のタスクはプロジェクトごとにタスクリストを分けるのが基本です。シングルタスクに切り分けましょう。そして、タスクには実行すべき動詞を入れると、中断が入っても復帰しやすくなります。
リストは「やるべきこと」と「できればいいこと」は別ものと考え、書き出したらまず、「今」「ここ」で実行可能なものに集中しましょう。いくら気になっていても、職場で家の戸締りはできないのと同じです。
今できること、自分でコントロールできることに集中することで、仕事と時間を制御できているという安心感や自信につながります。タスクリストの項目を実行したら、線を引いて消すことで気持ちのいい達成感が生まれます。
1日の終わりに、書いて切り替えの練習を
マルチタスクの切り替え上手になるためのポイントは、毎日の仕事終わりにあります。業務やプロジェクトは1日で終わることはなく、1週間、1カ月、3カ月に渡ることもあるでしょう。
進捗状況などに不安があると、いつまでも残業をして粘ったり、帰宅してからも仕事のことを引きずったりしがちです。集中の限度を超えてタスクに向き合うことは、生産的ではありません。
1日の仕事を終えて帰るとき、今日まで終わったことと、明日何から手をつけるかをメモしていきましょう。明日の自分への申し送りを書くことで、いったん今日は仕事のことを忘れていい状態になります。
1日の終わりで区切りをつけ、翌日に改めて集中する。1日単位の切り替えができるようになると、午前と午後で切り替えることや、1時間単位での切り替えも次第にできるようになっていきます。
すると、会議の前に仕事の状況をメモしてから会議に出席し、終えたらサッとメモに目を通すだけで頭を切り替えてすぐにスタートができます。シングルタスクの切り替えが細かくなっているだけですが、周囲から見ればあたかもマルチタスクをこなしているように見えるのです。
【まとめ】マルチタスクに効率的に向き合うには
タスクを書き出したにもかかわらず、手が付けられなかったり、気持ちが乗らなかったり、先に進まないこともあるでしょう。そんなときは周囲に助けてもらうのも一つの対策です。

周囲の声に助けてもらう
作業の先送りは心の不安が生み出している見えない壁のようなもの。先送りしたくなったら、感じている不安や怖れを言葉に書き出してみましょう。客観視することで対処の仕方が見えてくることもあるはずです。
それでも、どうしたらいいかわからないときは、ひとりで悶々とするよりも、先輩や同僚に聞いて、周囲の知恵を借りましょう。解決できない自分を責める必要はありません。
周りに相談することで、むしろ周囲の人もまた相談しやすくなります。組織全体の心理的安全性が高まるのです。ひとりで考えていても堂々巡りになってしまい、自分では解決策が見えなかったり、問題の先送りになってしまったりするもの。周りに聞いてタスクを進めればいいのです。
異なる時間の自分に助けてもらう
答えがない課題に向き合うことが多い現代では、実は進みながら答えが見えてくることも少なくありません。アイデアが出ない、別の方法が思いつかないといったときは、いったん別の作業に向き合うのも対処法の1つです。
せっかく切り分けたはずのシングルタスクを引きずって全てが前に進めなくなるよりも、いったん脇に置いて、他のシングルタスクに向き合いましょう。時間を置くことで、違う発想や解決策が見えてくる。異なる時間の自分に助けてもらうことも有効な対策なのです。
堀 正岳さん
 研究者・ブロガー。北極における気候変動を研究するかたわら、「人生を変える小さな習慣」をテーマとしたブログ、Lifehacking.jpを運営。知的生産、仕事術、ソーシャルメディアなどについて著書多数。理学博士。著書に『ライフハック大全―人生と仕事を変える小さな習慣250』『知的生活の設計―「10年後の自分」を支える83の戦略』『仕事と自分を変える「リスト」の魔法』(以上、KADOKAWA)など
研究者・ブロガー。北極における気候変動を研究するかたわら、「人生を変える小さな習慣」をテーマとしたブログ、Lifehacking.jpを運営。知的生産、仕事術、ソーシャルメディアなどについて著書多数。理学博士。著書に『ライフハック大全―人生と仕事を変える小さな習慣250』『知的生活の設計―「10年後の自分」を支える83の戦略』『仕事と自分を変える「リスト」の魔法』(以上、KADOKAWA)など




















