「頑張っているのに、なぜか仕事が終わらずいつも残業している」「サボっているわけでもないのに仕事がなかなか終わらない」。そんな状況が続くビジネスパーソンが抱える要因とは? 仕事が終わらない理由と改善に向けた考え方を、『スピードハックス』『チームハックス』の著書で心理系ジャーナリストの佐々木正悟氏に伺いました。

目次
そもそも仕事量は適正なのか、業務量をチェックしよう
仕事が終わらないと悩むビジネスパーソンの多くは、「要領が悪い」「スケジュール管理が苦手」など自分の対処能力に原因があると思い悩みがちです。しかし、まずは「そもそも仕事量は適正なのか」をよく検討することが大事です。
仕事量をチェックするには、「1日でやろうとしていたこと」と「実際にやれたこと」をリストアップして比較してみましょう。リストアップする項目は、大まかな内容で構いません。例えば、以下のようにざっくりとやるべきことを決めます。
「お客様先を2件訪問して、提案資料を1つ仕上げる」
「午前中に会議資料と企画書を作成して社内に共有し、午後に見積書を2つ完成させる」
やろうとしていたことの半分以上が残っていて終えられなかったのであれば、単純に1日の仕事量が多すぎると考えられます。「サボっているわけではないのに仕事が終わらない…」という人は、まずは仕事量を減らすことから始めましょう。
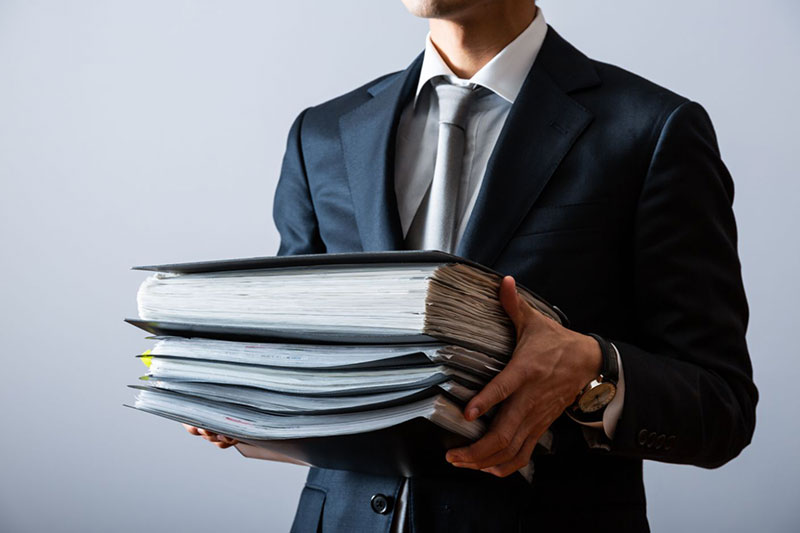
「この仕事を引き受けるべきか」常に考えるクセをつける
仕事量を減らそうと言われても、「頼まれると断れない」という人も少なくないでしょう。とはいえ、自分の処理能力(キャパシティ)は1日や2日で大幅に高まるわけではありません。1日にできる仕事量は限られているのですから、終わらない量の仕事を引き受けることは、結局は締め切りや納期の遅れにつながり、自分の首を締めるだけでなく、相手にも迷惑をかけてしまいます。
そこで、新たな仕事の依頼が入ってきた際は、必ず「引き受けるかどうか」を考えるクセをつけましょう。1日でできる仕事量から逆算して、納期までにできるかどうか。できないのであれば、引き受けられないことをしっかりと伝えます。あるいは、「△△までの範囲なら、〇日までにできます」とできる範囲や納期を区切り、仕事の依頼者側が求めているゴールをすり合わせることが重要です。
今日依頼された仕事は、明日以降にしかやらない
仕事が終わらない人の中には、「予定外の業務が舞い込んできて、対応に追われるうちに1日が終わってしまう」「自分の仕事が進まない」と嘆く人も多くいます。
ただし、予定外に舞い込んできたり降りかかってきたりする業務も、予定を立ててやろうとしていた業務も、すべて「仕事」であることは変わりません。他者から依頼されるものである以上、どんなに小さな案件でも「引き受けてできるかどうか」を判断して決めることが大切です。
また、どうしても即時対応すべき内容以外は、「当日依頼された仕事を、当日にはやらない」と決めるのも一つの手です。私自身は、「新たな仕事の依頼メールの対応は翌日以降にやる」と決めており、それを周りにも共有しています。そうした仕事のスタイルを確立するのも、1日の仕事をその日のうちに終えるコツかもしれません。
仕事の依頼主の要望、求めているゴールをきちんと聞こう
仕事内容によってはその場、その時間、その日のうちに対応しなければいけないものもあるでしょう。そうしたケースでも、仕事の依頼主と依頼内容をきちんとすり合わせし、「いつまでに、どんな内容のアウトプットが必要か」を確認しましょう。
仕事が終わらない人の中には、自分にとっての「理想の形」を追求するあまり、いつまでも辞められない(提出ができない)というケースもあります。「自分は完璧主義だから仕事が遅い」と表現する人もいます。
完璧主義とは、自分にとっての“完璧なゴール”を頭の中で作り上げてしまうところから始まります。でも、どんなアウトプットを求めているのかは、依頼者に確認しなければ分かりません。自分が作り上げたゴール像を手放し、仕事の依頼者が示す完成形は何か、理解を深めることが大事です。
その上で、それを期限内に仕上げられるかを確認してから引き受けること。それが、仕事を終えられるようになるための第一歩です。

丁寧に焦らず、仕事に打ち込むように心がける
仕事の処理能力は、すぐに上げられるものではありません。1日1日、経験とスキルを積み重ねて少しずつ広がっていくものなので、仕事量を調整しないまま、何とか終わらせようと焦っても結果は変わりません。
現時点での処理能力を最大限に発揮し、パフォーマンスを上げるには、「目の前の仕事に十分な時間をかけること」が一番の近道です。1日という小さな時間軸で見れば、焦って仕事をしても、ゆっくり丁寧に仕事をしても、かかる時間はそう変わらないはず。確実にパフォーマンスが出せるように仕事に取り組むことが、長期的に能力を高めることにつながるのです。
仕事と向き合えていれば、罪悪感を抱えなくていい
仕事が終わらない要因に、「嫌な仕事をつい後回しにしてしまって、なかなか終わらない」「仕事をしなきゃと思っていても、ついネットサーフィンやSNSに時間を使ってしまう」という理由を挙げる人もいます。
目の前の仕事から逃げようとするのは、「(仕事という)ストレスを一時的に追い出したい」からです。サボる内容には、ネットニュースを見る、SNSをチェックする、コーヒーなど嗜好品をとるといったさまざまな行動があり、人によって異なります。まずは、自分の習性を知り、「私はストレスを追い出すために**サイトを見てしまうのだな」と認識することが大事です。
ストレスは内面から作り出されるものです。「この仕事は嫌だな」とストレスを感じるのも、自分が生み出したもの。多少のサボり行為があったとしても、仕事に向き合えているのであれば、それは対峙できるストレスであるということです。
「自分にはストレス耐性がある」「ストレスを抱えながらでも仕事ができる」ということに気づけば、ストレスを追い出すための脱線行為も減っていくのではないでしょうか。
自分を助けてくれる人は、必ずいる
仕事量が多いと分かっていても、責任感が強く自分一人で抱え込んでしまう人や、分からないことを周りに聞けずに仕事をどんどん溜めてしまう人もいます。
周りに相談するのに躊躇している人は、何かを怖がっているのでは。自分が何を恐れているのか、その原因に向き合い、助けてくれる人はどこにいるのかを改めて考え直してみてはいかがでしょう。
心理学ジャーナリスト 佐々木 正悟氏
 「ハック」ブームの仕掛け人の一人。専門は認知心理学。1973年北海道旭川市生まれ。97年獨協大学卒業後、ドコモサービスで働く。2001年アヴィラ大学心理学科に留学。同大学卒業後、04年ネバダ州立大学リノ校・実験心理科博士課程に移籍。2005年に帰国。帰国後は「効率化」と「心理学」を掛け合わせた「ライフハック心理学」を探求。執筆や講演を行う。著書に、ベストセラーとなったハックシリーズ『スピードハックス』『チームハックス』(日本実業出版社)のほか、『イラスト図解 先送りせず「すぐやる人」になる100の方法』(KADOKAWA)『やめられなくなる、小さな習慣』(ソーテック)『不安ゼロで生きる技術』(知的生き方文庫)『つい顔色をうかがってしまう私を手放す方法』(技術評論社)など。
「ハック」ブームの仕掛け人の一人。専門は認知心理学。1973年北海道旭川市生まれ。97年獨協大学卒業後、ドコモサービスで働く。2001年アヴィラ大学心理学科に留学。同大学卒業後、04年ネバダ州立大学リノ校・実験心理科博士課程に移籍。2005年に帰国。帰国後は「効率化」と「心理学」を掛け合わせた「ライフハック心理学」を探求。執筆や講演を行う。著書に、ベストセラーとなったハックシリーズ『スピードハックス』『チームハックス』(日本実業出版社)のほか、『イラスト図解 先送りせず「すぐやる人」になる100の方法』(KADOKAWA)『やめられなくなる、小さな習慣』(ソーテック)『不安ゼロで生きる技術』(知的生き方文庫)『つい顔色をうかがってしまう私を手放す方法』(技術評論社)など。




















