「仕事を効率化する手法を学んだのに長続きしない…」「資格取得・スキルアップのための勉強を始めたいけれど…」「在宅勤務での運動不足を解消したいのに…」 というように、やりたいことが「続かない」と悩む人は多いようです。そこで今回は、習慣化コンサルタントの古川武士さんに、習慣化の効果やメリット、やりたいことを習慣化するためのコツをアドバイスいただきました。
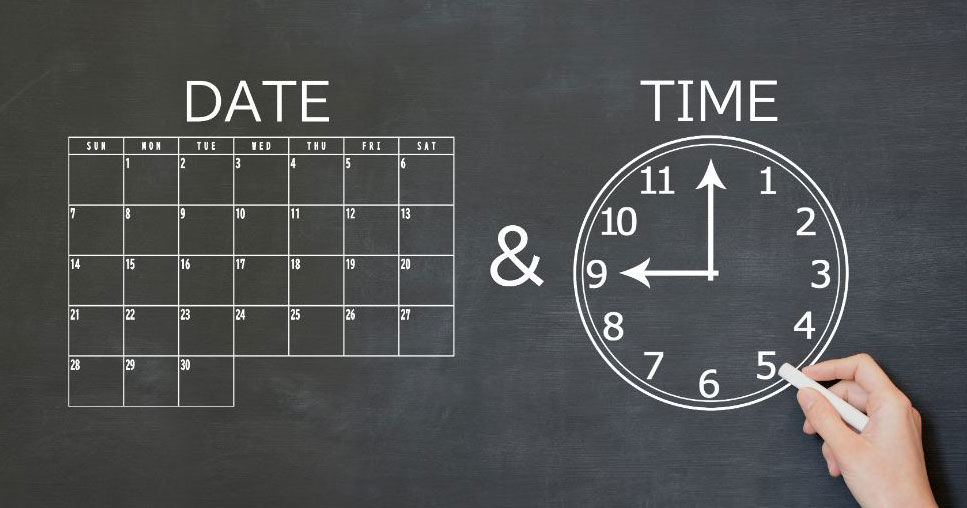
そもそも「習慣化」とは?
突然ですが、皆さんは朝晩の「ハミガキ」を、毎回苦痛に感じていますか。おそらく、ほとんどの人は当たり前の日常習慣として、歯を磨いています。「習慣化する」とは、毎日のハミガキのように、「自分が続けたいと思っていることを、意識せずに楽々続く状態に導くこと」です。
そもそも「習慣」とは、「脳が作りだしたプログラム」です。朝起きる時間、通勤ルート、食事をとる時間など、一定期間繰り返し行われた行動は、無意識のうちに繰り返すことができるようにプログラミングされます。習慣化とは、自動的に行動を継続するプログラムを脳内に作り上げることなのです。
多くの人が「やるべきだと思うのにできない」となりがちな運動、片付け、食事制限、節約、日記、勉強、早寝早起きなども、習慣化してしまえば、すべてストレスなく自然に続けることができます。心理学においても、人の行動の95%は無意識によるものだと言われており、無意識のほとんどは「習慣」からできています。
仕事で「習慣化」するメリットとは?
脳は、良い習慣・悪い習慣の区別はしません。単に、一定期間繰り返されたから、自動プログラム化(習慣化)するだけ。つまり、良い習慣でも悪い習慣でも身に付いてしまいます。ですから、自動的にプログラム化されている習慣のうち、ムダな習慣をやめ、効率的な習慣を取り入れれば、生産性がアップします。
まずは、現在の仕事効率を3%ほど改善する習慣を考えましょう。3%であれば、「ネット・スマホを見る時間を減らす」「会議を10分早く終わらせる」「始業前に仕事の計画を立てる」といった些細な行動でOKです。
たとえ一つひとつが3%でも継続すれば、複合的に作用し、倍の生産性を生み出せるわけです。しかも、当初は意識して始めた行動も、5カ月も続ければ無意識のうちに、負担なくできるようになるでしょう。
こうして仕事にかける時間を高密度化すれば、より自分がやりたいことに時間をかけることができ、生活や人生が豊かになっていきます。
「飽き性」な性格タイプでも、習慣化はできる
今では習慣化コンサルタントとして活動している私も、もともとは「究極の飽き性」でした。「自分を成長させよう」と始めた英会話・ビジネス講座・社会人勉強会などは、ほとんどは途中で挫折。趣味として通い始めたゴルフ教室・絵画教室・料理教室は2カ月と続かず。スポーツジムは会費だけ払って通うことなく、ダイエットを目標に掲げながら1年で7キロ体重が増えたこともありました。
当時は、自分の性格や意思のせいだと考え、コツコツ続けられるタイプの人や意思が強い人をうらやましく思っていました。しかし、ビジネスコーチとして多くの人と接している中で、優秀な経営者やビジネスパーソンは良い習慣を身に付けていることに気づいたのです。そこで彼らの行動や考え方をもとに、「習慣化」メソッドを研究したところ、究極の飽き性だった私も、5年間で50個以上の習慣を身に付けることができました。
ちなみに、最も高い効果を得られた習慣化が「朝、15分メールを見ない」です。仕事を効率化するコツは、「シングルモードで徹底的に集中する」こと。例えば「メールのチェック・返信」「簡単な資料作成」などの単純作業は分散させず、固めて行うほうがはかどります。
一方で、企画立案など論理的思考やクリエイティブなパワーを使う仕事は、朝の方が集中できて成果が上がりやすい。そこで、朝はメールの送受信に時間を使わず、講演資料の作成や原稿執筆などの作業に集中することを目指しました。
メールを見るとその内容について考えたり返信に時間を取ることになるため、メールフォルダを開くことを、15分我慢する。15分我慢できれば1時間我慢できるようになり、メールチェックをしなくても重要な仕事に集中して取り組めるようになります。メールフォルダ内にある資料を確認したい場合は、オフラインに切り替えて未読メールを受信しないように徹底しました。
朝、メールの対応に時間をとられ、重要なタスクが後回しになり、取りかかる頃には脳がパワーダウンしている。そんな状況に陥りがちな人におすすめしたい習慣化です。
そのほかにも、朝の習慣として「15分間の瞑想」「人生の計画や今年の目標をノートに書く」「古典など骨太な本を読んで集中モードに入る」なども取り入れました。こうして朝からすばやくクリエイティブモードに入って重要な仕事を早く完了させ、夕方以降には子どもと過ごす時間を長くとれるようになったのです。
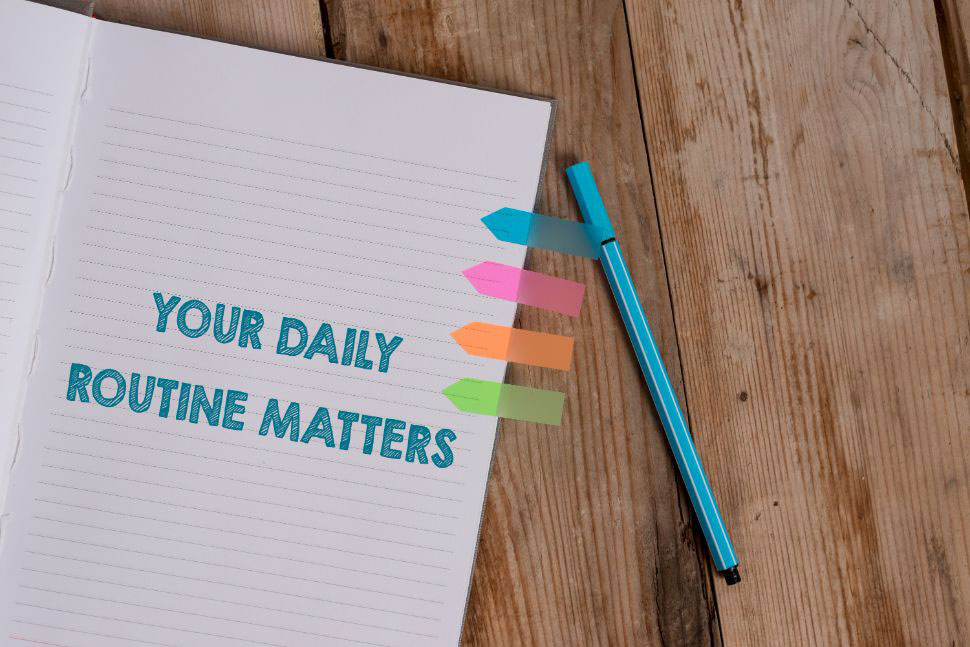
「習慣化」を実現するためのテクニック
仕事の効率化やスキルアップのために勉強を始めたけど、「なかなか続かない」という人もいるでしょう。実は、こうした挫折率がもっとも高いのは、始めてから1週間後。従って、1週間続けることが最大のハードルであり、この壁を乗り越えればずっと続けられると信じて行動してください。
今回は、三日坊主にならずに続けるための6つのテクニックをご紹介します。
1.「ベビーステップ」で始める
習慣化において大切なのは、やはり目標設定。「ベビーステップ」とは「赤ちゃんの一歩」。「目標設定を小さく始めましょう」ということです。「面倒」「不安」など、行動を妨げる要因となっているブレーキが外れるまで、ハードルを低くするのです。
例えば、「資格の勉強を毎日1時間する」→「10分だけ勉強する」、「ジョギングを1時間する」→「10分だけ走る」、「部屋を片付ける」→「5分だけ片付けをする」といったように、目標時間を低く設定することで達成感を味わうことができます。
もう一つの目標設定のコツは「難易度を下げる」こと。「毎朝5時に起きて勉強する」→「今より15分だけ早起きして勉強する」、「ランニングをする」→「ウォーキングから始める」、「腕立て伏せを1日50回する」→「1日5回から始める」など、これなら絶対にできるとことまで難易度を下げた目標設定をします。このように手軽な目標設定で達成し続けると、いずれ本来の難易度もこなせるようになっていきます。
なお、このベビーステップは、「先送りにしがちな面倒な仕事」にも効果的です。報告書作成になかなか手を付けられないときなど、「5分だけやってみる」「まず報告事項を箇条書きにする」「フォーマットだけ作る」といったステップから始めてみることをお勧めします。興味がない仕事でも、やっているうちに集中力が出てくるという「作業興奮」と呼ばれる心理現象に基づいた理論です。
2.シンプルに記録する
節約をするなら「家計簿をつける」ことで効果が見えますし、ダイエットであれば、食べたものや摂取カロリーを記録する「レコーディングダイエット」で有効性が認められています。
習慣化したい行動をしたら、内容や時間などを簡単でいいので記録しましょう。記録を続けていくと、客観的に自身の行動を管理でき、目標とのズレを把握できます。実行できていない日の「空欄」を見ると、罪悪感を覚えて、行動のムラの改善にもつながります。
また、成果や努力の量を「数値化」することで、モチベーションが上がります。行動を可視化することで自信がつき、毎日の行動に意味を見出せます。数値をグラフ化するなどの工夫を加えれば、さらに効果的です。
3.「やる気アップ」ツールを活用する
習慣化したい行動をするとき、気分が上がるツールやアイテムを使うのもお勧めです。私は資料を作成する際には時間を決め、カウントタイマーをセットしてとりかかるのですが、その時計はデザイン・機能面で気に入っているものを使っています。
「スリッパやクッションで心地よい作業環境をつくる」「集中力が落ちたときに聞く音楽や自然音を決めておく」など。仕事や勉強においても、お気に入りのツールやアイテムを導入することを試してみてはいかがでしょうか。
4.「ながら作業」にしてしまう
「時間がない」は、行動の障壁となります。忙しくて時間を捻出できない人は、今やっていることに「ながら作業」として付け加える「一石二鳥作戦」を試してみてください。
ながら作業の絶好のタイミングは、「通勤時間」「歩く時間」「待ち時間」「食事の時間」「お風呂の時間」など。例えば、様々な講演の音声をスマホに入れて、こうした時間に聴くなど、「学び」の行動を習慣づけるのに適しています。
5.皆から「いいね」をもらう
ある人は、朝ジョギングしたらスマホから記録を取り出し、SNSに投稿しています。それは先ほど挙げた「記録する」の効果もありますが、つながっている友人からの「いいね」やコメントがモチベーションになっているそうです。
特に景色の写真をアップすると反応が良いので、どこで写真を撮ろうか探すこともジョギングの楽しみの一つになっているようです。SNSには、同じ目標を持つ人が集まる「○○部」といったコミュニティもありますので、そうした場を活用してもいいでしょう。

6.例外ルールを設ける
突然の仕事や予定が入ったことでリズムが崩れ、習慣化したい行動がフェードアウトすることもありがちです。そこでお勧めなのが、「例外ルールを設ける」こと。「できないとき、やる気がないときは、せめて○○○だけはする」といった代替行動を決めておくのです。
「資格の勉強を毎日1時間」が急な残業などでできなくなった場合、「帰りの電車でテキスト1ページだけ読む」と決めておき、それを実行することで自分にOKを出してあげるのです。それだけでクリアした達成感が味わえて、継続できるようになります。
非効率な習慣を見直し、良い習慣を置き換えよう
日々行っている仕事は、「習慣の塊」です。意図して行っている作業は、全体の5%ほどしかありません。そして、無意識にやっている作業が非効率であったり、残業を生み出していたりします。
ですから、まずは日頃の習慣を一つひとつ見直して、「悪い習慣」になっていないかを考えてみてください。悪循環を生み出している習慣があれば、それを意識的にやめて、良い習慣に置き換えていきましょう。
プロフィール
習慣化コンサルティング株式会社
代表取締役 古川 武士(ふるかわ・たけし)氏
 米国NLP協会認定NLPマスタープラクティショナー。関西大学卒業後、日立製作所などを経て2006年に独立。約5万人のビジネスパーソンの育成と1万人以上の個人コンサルティングの経験から「続ける習慣」が最も重要なテーマと考え、日本で唯一の習慣化をテーマにしたコンサルティング会社を設立。オリジナルの習慣化理論・技術を基に、個人向けコンサルティング、習慣化講座、企業への行動定着支援の事業を開始。『理想の人生をつくる習慣化大全(⇒)』『成果を増やす 働く時間は減らす 高密度仕事術(⇒)』など著書多数。
米国NLP協会認定NLPマスタープラクティショナー。関西大学卒業後、日立製作所などを経て2006年に独立。約5万人のビジネスパーソンの育成と1万人以上の個人コンサルティングの経験から「続ける習慣」が最も重要なテーマと考え、日本で唯一の習慣化をテーマにしたコンサルティング会社を設立。オリジナルの習慣化理論・技術を基に、個人向けコンサルティング、習慣化講座、企業への行動定着支援の事業を開始。『理想の人生をつくる習慣化大全(⇒)』『成果を増やす 働く時間は減らす 高密度仕事術(⇒)』など著書多数。
▶あなたの知らない自分を発見できる。無料自己分析ツール「グッドポイント診断」

























