今、世界のエリートたちが社交の場において口にする話題は、アート、映画、音楽、そして「ワイン」なのだとか。そして、グローバル市場においては、ワインがビジネスを左右する重要なアイテムにもなっているのだそう。
クライアントを接待する際にテーブルに着く人の国籍は実にさまざま。欧米系、アジア系、インド系など異なるバックグラウンドを持つ人たちに対して、適切なワインを選ぶための知識が問われるのだそうです。ゴールドマンサックスなど海外のグローバル企業では、社員にワイン教育プログラムを取り入れているほど、ワインはビジネスにおいて重要視されているのだとか。
米ニューヨークの大手オークションハウス「ニューヨーククリスティーズ」で、アジア人初のワインスペシャリストとして10 年以上のキャリアを持ち、前述のゴールドマンサックスなどウォール街のエリートたちにワイン教育を行ってきた渡辺順子さんは、「今や、一流のビジネスパーソンにとってワインは『お酒』ではなく、グローバルに活躍するために身につけておくべき万国共通のソーシャルマナーの一つ」と指摘しています。
そんな渡辺さんがこのほど、『世界のビジネスエリートが身につける教養としてのワイン』という著書を出版しました。ご自身の経験から、今、ビジネスパーソンとして最低限知っておきたい「ワイン」の知識を解説しています。今回はこの本の中から、ワイン初心者でも役に立つ情報を一部抜粋し、ご紹介します。

ワインの知識が、コミュニケーションの大きな武器に
渡辺さんによると、「教養としてワインを身につけることは、ワインのみならず幅広いジャンルを包括的に学ぶことにつながる」とのこと。地理、歴史、言語、文化、宗教、経済、投資など、ワインの知識は各分野に横断的に関わっているので、ワインの知識を知ることで、国際的な問題や教養さえも得られ、コミュニケーションツールとしての大きな武器になるのだとか。
「特に欧米では、最強のツールと言えるほど重要」とのこと。政治や宗教はもちろん、多種多様な人種が暮らし、考え方もさまざまな欧米では、時事問題を気軽に話すのが難しいのが現状。ビジネスの場面でもインサイダーの意識が強いため、仕事の話も敬遠されがちなのだそうです。
そこで選ばれる話題が、スポーツ、アート、音楽、映画、そしてワイン。日常的にワインに親しむ欧米では、特にエグゼクティブなポジションの人との会話になればなるほど、ワインが話題に上がってくるそうです。
今回は、「そうはいっても、ワインの知識なんて全然ない!」「何から学べばいいかもわからない」という人のために、本書から「超初心者向けの基礎知識」をいくつか抜粋してご紹介しましょう。
最低限知っておきたいぶどうの品種

クライアント接待の席でワインリストを渡され、何を選べばいいのか困った…という経験を持っている人、意外に多いのでは?こういうとき、ゲストの好みを聞きながらセレクトできるとスマートな印象を残せます。
まずは最低限、主なぶどうの品種について押さえておきましょう。
<赤ワインで使われる主な品種&基礎知識>
●カベルネソーヴィニヨン
世界で最も生産量が多く、ほぼすべてのワイン産地で栽培されている品種。タンニンを豊富に含み、濃厚でしっかりした味わいが特徴で、さまざまなワインに幅広く使われている。
●ピノノワール
フランス・ブルゴーニュ地方原産で、栽培が難しく繊細なぶどう品種。一方で、世界一のワインと言われる「ロマネ・コンティ」にも使われる、ポテンシャルの高い品種でもある。基本的に他品種とのブレンドはせず、単一で醸造される。
●メルロー
栽培面積で世界2位。気候に対する柔軟性があり、産地を選ばない品種として知られる。その栽培のしやすさから、世界中のワイン醸造化に支持され、フランスのボルドーを始めアメリカ、イタリア、チリ、アルゼンチン、オーストラリアなどほぼ全域で栽培されている。
<白ワインで使われる主な品種>
●シャルドネ
幅広い地域で使われる白ワインの王道品種。産地によって味わいが大きく異なるのが特徴。冷涼な気候のブルゴーニュやシャンパーニュ地方ではミネラルと酸味が豊富なワインが作られ、日射量の多いカリフォルニアやチリでは、トロピカルフルーツのようなふくよかな味わいとなる。
●ソーヴィニヨンブラン
カジュアルな白ワインから超高級白ワインまで幅広く使用される品種。温暖な地域から冷涼な地域まで環境適応力が高いため、産地によって個性が際立ち、その味わいの違いを楽しめるのが魅力。
●リースリング
冷涼な気候を好み、ヨーロッパ北部のドイツを筆頭に隣接するフランスのアルザス地方などで使われる白ワイン向けのぶどう品種。辛口から甘口まで幅広い白ワインに使われるほか、極甘口の貴腐ワインや遅摘みワインにも使用される。
正しい「テイスティング」の仕方とは?

クライアント接待の場では、ホストとしてテイスティングを任されるケースがあるかもしれません。正しいテイスティング方法を知っておくと、大事なクライアントを前にしても堂々とスマートに振る舞えるでしょう。
ワインの味は、甘味、アルコール度数、酸味、タンニン、ボディの5つの要素から成り立っています。これらの個性や特徴を見分けるのがテイスティングです。おいしいかまずいかではなく、「状態をチェックする」ためであることを心得ておきましょう。
ワインのテイスティングは、見る→香りを楽しむ→味わうの手順で進めます。英語では「The “S” Step」といい、「See(見る)」「Swirl(グラスを回す)」「Sniff and Smell(香りをかぐ)」「Sip and Swish(ひとくち口に含む、口内をワインで覆う)」「Swallow or Spit(飲む、もしくは口から出す)」という手順です。
「See(見る)」
ワインの色合いや輝き、清澄度を確認します。まず白いものを背景にグラスを傾け、色の濃淡の度合いを見ます。
大事なのは、濁りがないか。濁っている場合は劣化、酸化している可能性があるので要注意。この後の手順で、違和感がないか確認しましょう。
「Swirl(グラスを回す)」
グラスを正井、粘着度を確かめます。グラスの内面にワインの滴跡がしっかり残るほど粘着性は高く、アルコール度数が高いとされています。
「Sniff and Smell(香りをかぐ)」
グラスを傾け香りをかぎます。ワインの香りは、ぶどう本来の香りと発酵段階で生まれる「アロマ」、発酵後に樽や瓶内での熟成中に生まれる「ブーケ」の2つに分けられます。それぞれが持つ香りの個性を楽しみ、違和感がないかチェックしましょう。
「Sip and Swish(ひとくち口に含む、口内をワインで覆う)」
「Swallow or Spit(飲む、もしくは口から出す)」
ワインを一口含んで、口内全体で味わってみましょう。甘味は舌の前方で、酸味は舌の両サイドで、タンニンは歯茎で、アルコールは喉の奥で、そしてボディは後味の長さや飲んだ時の感触で判断しましょう。
新しいワインであれば色と香りで判断し、じっくりテイスティングする必要はありません。若いワインは明るく澄みきっていますが、品質に問題がある場合は濁っています。香りも好き嫌いではなく、不快な香りではないか確認しましょう。
古いワインの場合は、酸化していないかどうかもチェックします。劣化・酸化しているワインは明らかに香りも味も不快なので、すぐにわかるはず。判断に迷った場合はソムリエに確認し、判断をゆだねましょう。
ワインのビジネスマナー
いよいよ宴席がスタート。たとえ会話が盛り上がったとしても、ワインのマナーを守れていなければ、イメージダウンになりかねないので注意が必要です。
最低限のワインのマナーを理解しておけば、ビジネスの場など改まった席でも安心です。
●乾杯ではグラスを当てない
乾杯の際にグラスを当てるかどうかは、使っているワイングラスにもよります。しかし、ビスネスディナーやフォーマルな席で使われるものは、繊細な薄手のグラスが多いので、グラスを当てないほうが無難。少しの衝撃で割れる恐れがあるからです。
ただ、グラスを当てて音を出すほうが縁起がいい、と考える国もあります。クライアントや、ホスト役の方がグラスを当てて乾杯していたらそれに従いましょう。
●ワイングラスは脚を持つ
グラスを持つ際は、ステム(脚)の部分を持ちましょう。ボウル(本体)の部分を持ってきれいなグラスに指紋をつけたり、汚したりするのはマナー違反とされます。また、ボウルをわしづかみにして飲むのは相手に不快感を与える場合が多いので注しましょう。
食事とともにワインを頂く際は、ナプキンで口を拭いてから飲み、グラスに食べたものがつかないように気を配りましょう。グラスを汚すのはマナー違反です。女性は口紅にも注意。もし汚れたらそっとナプキンでふき取りましょう。
●グラスいっぱいにワインをなみなみ注がない
ゲストにワインを注ぐ際、赤ワインはグラスになみなみ注がないこと。グラスを回して香りを楽しむことができなくなるからです。大きなグラスであれば、注ぐ量はグラス半分以下が目安です。
白ワインの場合は、ワインの質やヴィンテージによりますが、常にグラスを回して空気に触れさせる必要がないので適量を注ぎましょう。
●急いでワインを注ぎ足さない
ワインは空気に触れさせながら香りや味の変化を楽しむものです。少し減ったからといってすぐに注ぎ足すのは止めましょう。特に空気に触れさせながら変化を楽しむ赤ワインではNG。白ワインの場合でも、冷えたワインを注ぎたすと温度が変化して味も変わってしまいます。
ただ、ゲストのグラスを空にするのもマナー違反とされているので、接待の際はゲストの飲むスピードに配慮しながら、タイミングよく継ぎ足すようにしましょう。
●お酒に強くない場合は事前に伝えておく
ゲストとして招かれた場合、あまりワインに強くないならば一言伝えて少なめに注いでもらいましょう。2杯目を注がれそうになった時、もう十分であればグラスを手で覆うジェスチャーをして断りましょう。
ワインの基礎を知り、ビジネスに活かすきっかけに
本書では、「ワイン伝統国『フランス』を知る」「食とワインとイタリア」「知られざる新興国ワインの世界」の3章に分けて、ワインの初歩的な知識はもちろん歴史やエピソード、豆知識など、教養として身につけておきたい情報、ビジネスでの会話に役立てられる情報を紹介しています。渡辺さんによると、「これ1冊でビジネスの場で活かせるワインの知識が一通り得られる」とのこと。
海外では、ビジネスの潤滑油として、そして交流を広げるツールとして機能しているワイン。海外とやり取りする機会が増えている今、日本でも早晩、ワインが必須知識になるかもしれません。言葉がうまく通じなくてもワインという共通言語があれば、お互いの距離が縮まることも期待されます。もちろん「ワインが好きだから、勉強してみたい」という人の入門本としても役立つ一冊です。
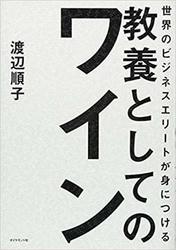
参考書籍:『世界のビジネスエリートが身につける教養としてのワイン』/渡辺順子/ダイヤモンド社
EDIT&WRITING:伊藤理子




















