事業成長に欠かせない改善活動をトータルサポートするマーケティングプラットフォームを提供している私たち。その改善を担うグロースハッカーのネットワークは7000名を超え、新たな働き方を体現。ただ、ここまでの道のりは決して平坦なものではありませんでした。代表取締役CEO須藤憲司がこの5年間を振り返ります。
※本記事は、「PR Table」より転載・改編したものです。
目次
「忖度」していては、クライアントの事業を最大化できない

▲B DASHでの優勝を皮切りに、創業当初、飛ぶ鳥を落とす勢いであらゆるピッチコンテストを受賞していきます
Kaizen Platformという会社を端的に説明するなら、「インターネットマーケティングをベースに、サイトや広告を改善することで、クライアントのビジネスに貢献する会社」。
ミッションとして「世界をKAIZENする」ことを掲げています。いまや、多くの人がインターネットを通じてさまざまなサービスを利用しています。ですから、もしサイトが読みづらくて、どこにどんな情報があるかわかりにくかったり、広告をうっとうしく感じられたりしてしまったら、クライアントにとっては死活問題となりうる。そこで、僕らがクライアントのサイトや広告の課題を抽出・分析してそれらを改善することで、彼らの事業をスケールさせるお手伝いをしていきます。
「忖度」って言葉が流行りましたけど、ビジネスでもそういう局面は度々あります。
たとえば、広告代理店経由でクライアントとやり取りするなかで、「お客さまは複数の改善案を望んでいるので、なるべくたくさん案を出してくれないか」と言われることがある。
けれどもクライアントが本当に望んでいるのは、売上を飛躍的に伸ばすことだったりするんです。そんなとき、言われたことを額面通りに受け取って、忖度して複数案検討しているうちに、どんどん実行するのが後ろ倒しになってしまう。果たしてそれはクライアントにとって本当にメリットのあることなんでしょうか。
できる限りスピーディにサイトを改善して、一刻も早くクライアントに価値を提供する。そのために、僕らは「Kaizen Platform」というプラットフォームを作りました。いまや7000名を超えるグロースハッカーが在籍していて、Kaizen Platformのカスタマーサクセスと連携し、課題抽出から分析、改善、検証までのサイクルを継続的に回すことができます。
僕にとって理想なのは「こびとのくつや」というグリム童話で、靴屋のおじさんが寝てる間にこびとが靴を作ってくれて、その靴が評判になって店が繁盛する話があるんですね。
僕らにとって、グロースハッカーはそのこびとたち。何か課題を持っているクライアントに対して、Kaizen Platformを活用することで、「真のゴール」を達成してもらいたいんです。
「改善」は「納品して終わり」の短絡的な仕事ではない

▲毎年、顧客の事業に貢献したグロースハッカーを表彰。このスタンスはずっと変わりません
僕は前職時代、マーケティングの責任者をやっていました。そこで実感したのは、自社だけでは解決できない問題があまりにも多いこと。やらなくてはいけないことが目の前にあるのに、それを解決してくれるエキスパートは社内にいません。
だからと言って、外部発注するほどの予算はない。Kaizen Platformを立ち上げたとき、「あのときの僕」を助けてくれるようなサービスを作ろうと思ったんです。ですから、僕らはツールをポンと渡して「はい、これでがんばってください」というサービスではない。
改善することは、「納品すれば終わり」みたいな短期的な仕事ではないんです。クライアントや代理店、グロースハッカーも含めてひとつのチームになって、一緒になってゴールを目指さなければいけないんです。
とはいえ、現実的な問題もありました。「絶対にA/Bテストのツール屋さんになるのはやめよう」と思っていたけど、やはり最初はA/Bテストからサービスを提供することが、クライアントにとってもわかりやすかった。
そこから制作会社に電話をかけたり、福岡市との提携でグロースハッカーの育成・発掘に取り組んだりして、少しずつグロースハッカーのネットワークを広げていって。今はクライアントのニーズに応じて、よりきめ細かく最適化したチーム体制を組めるようになってきています。
クライアントには、本当に大切なこと……それぞれの本業の価値を高めることに専念してもらって、僕らがそれを多くの人に伝えることを担う。それこそが本来的に豊かな社会だと考えています。
「もうダメかな」とキャッシュアウトを覚悟。それを救ったのは、現場の社員

▲経営危機を残り超えたのは、現場の意見。そう、現場が会社を救ったのです
立派なことを話しているようですが、もちろん僕もたくさん失敗してきました。つい最近のことですが、2017年の上半期に会社にとっても僕にとっても大きな試練がありました。
ちょうどコストが大きく出て行くタイミングに、複数の大型案件が契約終了を迎え、大きく売上ダウンする見通しになったんです。それらの出来事と同時並行で創業時からのメンバーも去り、新しい社員もなかなか定着せず、組織的にも壊滅状態。
言葉では「大丈夫」と言ってたけど、全然大丈夫じゃなかった。「もうダメかもな」と最悪の事態も覚悟するほどでした。
まず役員会議やマネージャー会議で対応策を検討していたのですが、「ダメな状態も含めて、社内にシェアしよう」と、リーダー以下、現場レベルの社員にも会議の門戸を開いたんです。
すると、管理職レイヤーの話よりもはるかに解像度の高い、具体的な改善案、アイデアがどんどん出てきた。「答え」は現場にあったんです。
そのアイデアというのは、これまで細分化していたサービスを一本化して、それにセールスや開発含めてみんなが注力するというもの。そして、クライアントからのフィードバックを共有し、サービス自体の商品特性や営業アプローチ、提案資料を改善しつづけたんです。
それと同時に、コストも見直しました。結果的に、業績は回復し、経営危機以前よりも経営基盤が強固なものとなったのです。
それまでのKaizen Platformは、ある種「ピン芸人」の集まり的なところがあって、それぞれが異なるノウハウで自分なりの成果を出していた。たしかに、それでもうまくいっていた。
けれどもその経営危機を経て、ノウハウを共有しながら、一つの目標に向かってみんなで注力することで成果を出していく。そんな得難い経験が出来ました。会社にとっては経営危機だったかもしれないけど、真の意味では危機じゃなかった。むしろ変革のチャンスだったんです。
本当に成し遂げたいこと、実現したいことブレずに掲げていれば、もっといい方法はいくらでも見つけられるんじゃないかと、あらためて、そんなことを実感しました。
チャンスはここにある。あなたに「選ばれる」会社でいたい
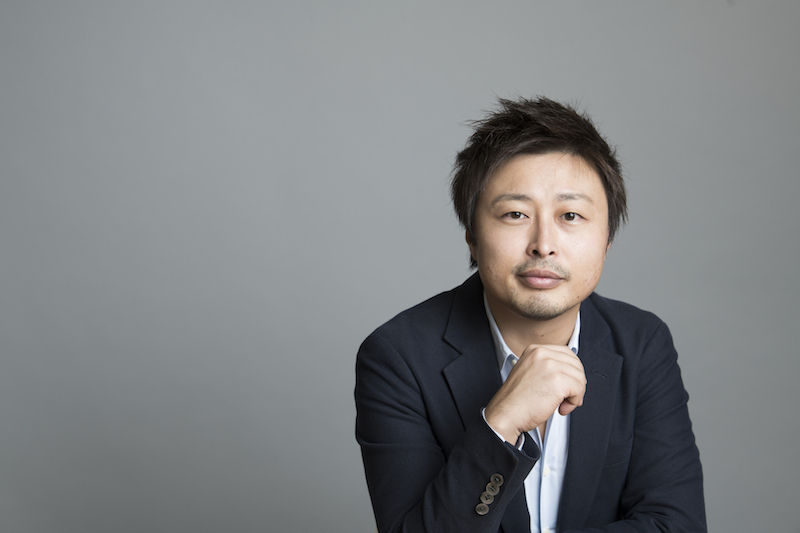
▲権限委譲を積極的に進め、須藤自身も変わり続けています。見据えるのは、まだ見ぬ未来のみ
僕がこの会社で成し遂げたいのは、「21世紀の新しい働き方と雇用の創出」。原点にあるのは、東日本大震災のとき、1週間ほど自宅待機になったこと。必然的に全員リモートワークを余儀なくされたけど、まったく問題なかった。
ひさびさに同僚と顔を合わせると、いつもよりもむしろ健康的にさえ見えて。今まで当たり前のように会社に来ていたのはなんだったんだろう、とあらためて考えさせられた。20世紀の当たり前は会社に出社するだけど、21世紀ではダウトだなと。そんな感じで、想像以上に「当たり前」にがんじがらめになっていて、それを取っ払ってしまえば、もっといいやり方、働き方があるんじゃないかと思えたんですよね。
これからますます、雇用の流動性が高まっていったり、一人ひとりがさまざまな組織に属しながら、個人としての価値を高める時代となっていく。そうなったとき、会社というのは、どれだけワクワクするようなチャンスや経験を与えられるかどうかで「選ばれる」時代になっていくと思うんです。
僕らはこのKaizen Platformを通してそれを提供して、選ばれる会社でいたい。
「新しい働き方」というのは、やるかやらないかのチェックボックスみたいなもの。もちろん「やらない」というのも選択の一つでしょう。でも、そんな中「やる」にチェックした人には、ワクワクするような毎日が待っていて欲しいじゃないですか?
僕らの会社にはさまざまな社員が集まっているけど、それぞれが能力を発揮して、会社のビジョンを体現しています。面白いやつと仕事していると、仕事も面白くなっていく。仕事って、きっとそういうものなんじゃないかな。
会社説明会では語られない“ストーリー“が集まる場所「PR Table」




















