ブレインストーミングでアイデアを出してほしいと言われたものの、どうしたらいいのか悩んだことはありませんか?
アイデア出しについて第二回でも取り上げましたが、今回はチームでアイデアを出すブレインストーミングの方法についてご紹介したいと思います。
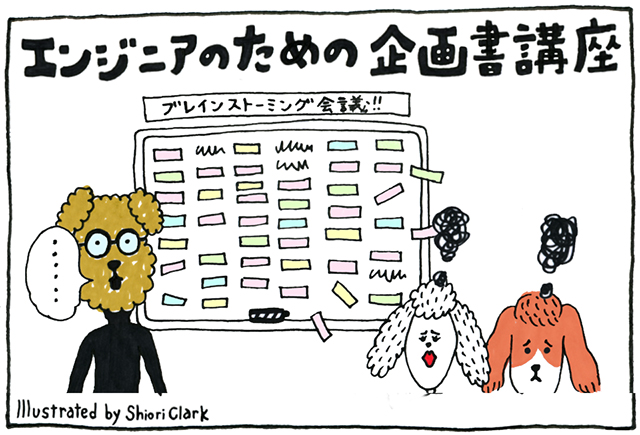
1. ブレインストーミングの基本
![]()
「ブレインストーミングでアイデアを出してほしい」と社長に言われたけれど、何をどうすればよいのやら…。人と話すのが苦手でエンジニアになったようなものなのに困った。
![]()
まずはメンバー集めだね。人数は大体4〜6人くらいがベスト。人が少ないと盛り上がらないこともあるし、逆に多すぎると一人一人がアイデアを話す時間が短くなってしまう。人数が多い場合は、チームを分けてみましょう。
![]()
司会と書記はどうすればいいの?
![]()
司会のことをファシリテーターと言うのだけど、基本的に案件について一番詳しく、企画書を最終的に書く人が担当することが多いです。ファシリテーターは、まず何についてアイデア出しをするか、最初にメンバーへ説明します。
また煮詰まってきたときに話題を変えたり、話がそれ過ぎたときに軌道修正をするのも役目となります。書記はファシリテーターがそのままメモすることが多いかな。みんなが出したアイデアを自分で付箋などにメモするスタイルだと、書記を用意する必要はなくなります。
![]()
アイデアの内容にもよるけれど、メモするためだけに一人参加してもらうのは、確かに不効率なのでみんなでメモするのはよいかな。あと自分がブレインストーミングについて知っているところだと、人のアイデアを批判しない「批判禁止」が有名だよね!
![]()
そう!「批判禁止」はブレインストーミングをする上で、とても大事なルールです。批判を禁止するのは、みんなが臆せず自由にアイデアを出すためとよく言われているけれど、実は批判することに無駄な時間や体力を使わないためであったりします。
最終的に一つの良いアイデアを選べば、それ以外のアイデアに対して反論をする手間が省けると考えてもらえるといいです。また「判断保留」という言い方がされる場合もありますね。
![]()
なるほど、そのアイデアが実現できるかどうかは、最後に気になったものだけ検証すればいいから確かに効率的。ちなみにブレインストーミングというのは「効率的にアイデアを出す会議」ということでよいのかな?
![]()
その通り!

2. いろんな職種の人が集まるブレインストーミングを効率的に行うには?
これからのプロダクトやサービスづくりにおいて、様々な職種の人がアイデアを出し合っていくのが重要と、前回の記事でご紹介しました。普段アイデア出しに慣れている人も、慣れていない人も集まるブレインストーミングで、気をつけることとはなんでしょうか?
![]()
この前、とあるクライアントのアイデア出しに技術顧問として参加したんだけれど、半日ずっと会議室で話して疲れたよ。(実際は話すタイミングがつかめなくて、ずっとうなずいていただけなんだけどね)
![]()
ブレインストーミングに慣れている人同士であれば、あまり多くのことを気にせず進められるけれど、職種も年齢もバラバラのチームでブレインストーミングを行うには一つ秘訣があるんだ。
![]()
その秘訣とは…!
![]()
話す時間を減らすこと
![]()
がーん…!
![]()
もっと言うと、「話す時間」と「考える時間」をしっかり分けて用意するということ。例えば6人で一時間ブレインストーミングをすると、一人平均何分話すことになるでしょうか?
![]()
60 / 6 = 10 分。
![]()
そして、話す以外の時間に何をしているかというと…。
![]()
「人の話を聞いている」。ハッ!考える時間が…ない!
![]()
そう、実際は人の話を聞きながら考えたり、全員が静まったときに考える時間はあるけれど、いつ誰が話し出すか分からない状況、なかなか落ち着いて考えることができないよね。
![]()
話すだけで体力を使う僕のような人種(?)には、しゃべりながら考えるのはなかなか困難だね。
![]()
そのようなわけで、考える時間と思いついたことを話す時間を区切って、交互に繰り返すのはなかなか効果的なんだ。例えば1時間の会議だったら、10分だまってアイデアを考えて、思いついたアイデアを20分話し合う構成を1セットとして、それを2回繰り返すとよい配分になります。考える時間は、それぞれメモにアイデアを書き出していきましょう。

3. 煮詰まったときにやることは?
![]()
実はみんなの話が盛り上がって自分が話せないことより、煮詰まってみんな静かになってしまう方がこわかったりするんだけど。
![]() そう、煮詰まってしまったとき、うまく話を引き出すように視点や話題を変えるのは、ファシリテーターの役目だよね。
そう、煮詰まってしまったとき、うまく話を引き出すように視点や話題を変えるのは、ファシリテーターの役目だよね。
![]()
責任重大だ。
![]()
ファシリテーションがまだ苦手な場合、あらかじめテーマに対してどのような切り口を考えられるか、用意しておくと便利です。例えばあるテーマを持った新サービスのアイデアを考える場合、
- テーマから連想されることを話す(30分)
- まず思いついたアイデアを自由に言ってみる(30分)
- 関連するサービスで、気づいたことを話してみる(30分)
- 最後に、これまで出たアイデアで気になったものをさらに掘り下げてみる(30分)
といったように時間を区切ってアジェンダを用意すると、進行をしやすいかと思います。ただお題を変えるだけでなく、「マインドマップを書いてみる」など手法を変えてみるのも効果的です。次回はブレインストーミングで使えるさまざまなアイデア出しの方法と、アジェンダの作り方をご紹介します。
![]()
次回「苦手克服!ブレインストーミングの方法(後編)」に続く!
⇒ エンジニアのための企画書講座シリーズ一覧はこちら!
 瀬尾 浩二郎(セオ商事)
瀬尾 浩二郎(セオ商事)
大手SIerを経て、2005年に面白法人カヤック入社。Webやモバイルアプリの制作を主に、エンジニア、クリエイティブディレクターとして勤務。自社サービスから、クライアントワークとしてGoogleをはじめ様々な企業のキャンペーンや、サービスの企画制作を担当。
2014年4月よりセオ商事として独立。「企画とエンジニアリングの総合商社」をモットーに、ひねりの効いた企画制作からUI設計、開発までを担当しています。
Twitter: @theodoorjp
ホームページ: http://theodoor.jp/
※本記事は「CodeIQ MAGAZINE」掲載の記事を転載しております。




















