
こんにちは、はせ おやさいです。さまざまなタイプのトラブルに出くわしてきましたが、いまだに悩むのが、部下やパートナーのミスについてどのように対処するかです。
「いま、あなたがしたのは非常に問題のある判断・行動である」ということをどのようにメッセージとして伝えるか、そんなことについて書いてみようと思います。
本題に入る前に、自分が今まで相対した「怖い上司・めんどうな上司」を思い浮かべてみてください。その中に「やたらと怒りっぽい人」はいませんでしたか?
わたしはいます。
何かあればすぐにキレ、怒鳴り散らす。失敗した部下に対して大声で批判を続け、あまつさえ「お前のいる席はない!」と椅子を蹴飛ばしたり、「この場所で空気を吸っているだけでも、お前にはコストがかかっているんだぞ!」と暴言を吐いたり。今、思い出してもゾッとします。
彼に関わる人は全員萎縮して、ちょっとしたことでもビクビクしていたり、その人らしさが発揮できないようになったり、言われることすべてに身構えるようになったりしていました。
「怖い人」「厳しい人」として認知されることが悪いことではないのですが、今、振り返ってみると、彼に言われたことはすべて「キレられた」で片付けられてしまい、本当に正しいことや参考になるような言葉が、耳に届きにくかったように思います。
この経験を経て、「部下や後輩を叱る」ためにはいくつかのポイントがあるのでは?と思うようになりました。それは「叱るべきタイミング」と「その後の作法」です。順番に説明していきますね。
▼ ビジネスシーンで「キレる」ことの是非
その前にまず、前提として「キレる」ことの是非について考えてみましょう。職場をはじめとする「オフィシャル」な場所で、どうしても受け入れがたい対応をされたとき、どのようにその意志を表明するかは、非常に難しい問題です。ビジネスシーンにおいて、感情をあらわにしたり、声を荒らげたりする態度は是としがたく、なるべくフラットに対応したいですよね。
とはいえ、どんなトラブルにも同じテンションで応じてしまうと、「自分がしたミスは大した問題ではなかったのかな?」と思われていまい、緊張感が欠けたり、同じことの繰り返しを招いたりしがち。「なあなあ」を防ぐためにも、問題には毅然とした態度で応じるべきなのですが、のべつまくなしに怒っていても、これはこれで同じ状況に陥ってしまいます。
では、どういった状況なら「強くNOを表明する」ことが望ましいのでしょうか?
▼ 問題を「重要度」と「緊急度」で測る
「強くNOを表明する必要がある場面」の例を挙げてみます。
自分が「上司」であったり「リーダー」的な立場にあり、相手のした問題行動を指導する役割を担っているときには、どうしても「叱る」必要が出てくると思います。この際、相手の行動が、自分の依頼したこと・指導したこと・その場で求められている仕事から逸脱しており、望ましくない行動であった場合は「強くNOを表明」し、その問題点を指摘・改善するための指導をしなければいけなくなると思います。ただし、このときの基本的な考え方として、「人はミスするものであり、責められるのはミスをした本人ではなく、ミスを招いた教え方・ルール・やりかたについてである」ということを前提として置いておきます。
「知らなかった・分からなかった」ことで起こるミスは必ずあります。その前提をもってしてでも強く言わなければいけない瞬間というのは、相手の問題行動が「重要度」「緊急度」ともに高かった場合に限られるではないかと思います。
重要度が高い例は、
- 取引先などに限らず、他者への最低限の礼を失しているとき
- 会社に大きなダメージを与えるようなマイナス判断を独断でしたとき
- 最低限のルールやモラルを欠いた行動を無自覚にとっていたとき
など、改善が見られない場合に後々とは限らず重大な問題になり得る行動です。
緊急度が高い例は、
- 災害や事故など大きな危機を招く可能性があるとき
- 締切や期限がある程度決まっており、誰かを待たせているとき
- 電話や会議など、リアルタイムで判断が求められているとき
などがあります。
この場合、「重要度と緊急度、どちらかだけ」が問題であると思われたのであれば、その場で声を荒らげず、ワンクッション置いた状態で、何が問題であったかを丁寧に指導すればよいのですが、両方が含まれる問題行動については、なるべく早く、その場ででも強い口調で指導し、相手に「NO」を伝える必要があるのではないかと思います。
▼ 「強くNOを表明」した、あるケースの話
経験したエピソードを紹介しますね。
チームにいた若手社員が、あるプロジェクトを進めていたとき、トラブルがあり、指定の時間に納品物が届かないことがありました。状況を聞いてみると、以下のような緊迫した状態でした。
- そもそも当初の依頼時点でこちらのオーダーミスがあり、相手はヒアリングしたその内容で配送を手配していた
- 状況が判明したときにはもう時間が迫っていた
- 必要各所に謝罪の連絡と、スケジュールの組み直しの必要がある
この状態であれば、なにより急ぐのは事態のリカバリであり、どうやって新たなスケジュールを組むかなのですが、彼がとった行動は「配送会社を責める」というものでした。
責められた配送会社は困惑し、「言った」「言ってない」の押し問答を続けているうちに、どんどん時間がなくなっていきます。
ここまできてしまうと、当人も切羽詰まって、冷静な判断ができません。ひたすら「自分に非はない」と主張を続け、ついには弁償だ、とさえ言い出したので、これは重要度・緊急度ともに高い問題行動であると判断した私は、彼をその場から外し、判断できる社員たちでフォローアップを取りました。そして同時に、社外の人間がいない場所で、彼の何が問題であったか、強く叱り、以下の内容を伝えました。
- トラブル収集に動かず自分の正当性を主張するのは優先度の付け方がおかしいということ
- 社外の人間に対応するとき、自分は所属する会社の代表であるという前提を忘れ、失礼な態度を取っていたということ
- その行動によって生じる可能性があった不利益や問題
- その不利益や問題を予測できないのであれば、すみやかに報告・相談をするべきであったが、それをしなかったのは問題行動であったということ
結果オーライかもしれませんが、その場から離したことで、悪意を向けていた他者から視線が外れ、また強くはっきりとNOを表明したことで、相手にメッセージが伝わり、重要さを認識してもらうことができました。
▼ 「叱った」あとの作法も重要
端的にいうと「ミスったら叱られた」で終わってしまうようなエピソードなのですが、その後は同じようなミスは起きず、判断に迷った場合はすぐに報告・相談してくれるようになったので、胸の内はともかく、功を奏したのではないかと思います。
この判断基準で叱る場合、いくつか「セットで採用しなければいけないルール」があります。それは、以下の3つです。
- 「叱る」のはその瞬間のみ発動し、後に引きずらないこと
- 絶対に相手の人格や今までの行動を引き合いに出さないこと
- 強くNOを表明したあと、「なぜなのか」までを丁寧に説明すること
あわせて日ごろの態度として、「相手の良い面はなるべく言葉にして都度伝えておく」ことが効果的ではないかと思います。
* *
強くNOを表明する必要があるシーンは、どうしても自分も感情的になってしまいがち。とはいえ、たとえNOを表明された側に非があったとしても、ネガティブなショックを与えてしまうことに変わりはないので、必ずフォローアップを行ってください。
もちろん上記の例にかぎらず、さまざまな関係性や場面でルールが増えたり減ったりすると思います。突発的なトラブルに対して冷静に対処できるよう、あらかじめ前提と判断基準、そしてルールを明確に作っておき、その後のより良好な関係を作るマニュアルになればと思います。
著者:はせおやさい (id:hase0831)
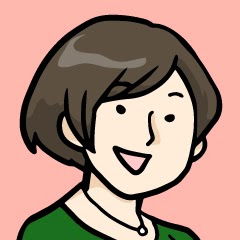
会社員兼ブロガー。仕事はWeb業界のベンチャーをうろうろしています。
一般女性が仕事/家庭/個人のバランスを取るべく試行錯誤している生き様をブログ「インターネットの備忘録」に綴っています。




















