コネがない? カネがない? そんなこと当たり前。
皆さんがどのような規模の会社に勤めているか知りませんが、私は小さな会社に勤めています。ゆえに、管理職としての裁量はかなり持たされてはいるものの、実際にやれることといえば、規模的に限られた中でのこと。それに、自分の上司は20歳以上歳が離れていて、ITのことを全然分かってないし、気づけば社内のPC駆け込み寺のような状態で、自分の業務時間は削られる一方です(涙)。

そんな中、いかに面白く仕事ができるか? 効率的にやりたいことに近づくか?…という情報にはアンテナを張らざるをえません。女、ということも含めて、限られた条件…制約だらけですからね。
さて、管理職の仕事は、このように問題解決の連続です。持ち込まれる相談事をすばやく判断し、対応策の方向性を決めていく。自分自身が対応すべきこともあれば、指示を出す(方向性を示す)だけでいいことも。相手によって、案件によって、頭をフル回転して解決策を考える。
そんな時に役立つのは、やはり知識。
自分の仕事分野に対する専門知識を深めていくのは当然ですが、何かあった時に頼りになるのは、まったく違った分野で問題をどのように解決しているのかを普段から知っておくこと。あの方法、ここで使えるかも…というひらめきのために、最新の方法論をたくさんストックしておきたいものです。
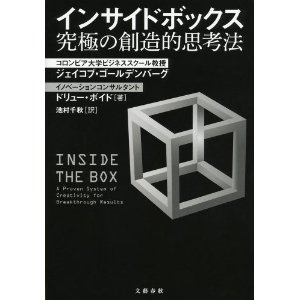
『インサイドボックス 究極の創造的思考法』(文藝春秋)は、コロンビア大学ビジネススクール教授のジェイコブ・ゴールデンバーグ氏と、イノベーションコンサルタントのドリュー・ボイド氏による共著。研究者と、ビジネス現場の叩き上げ2人がタッグを組むことによって、その方法論に深みと説得力を与えています。
彼らによれば、「成功を収めている革新的・独創的商品の半分以上は、たった5つのヒナ型のいずれかによって生み出されて」いて、その手順に従えば、誰でも創造性を発揮してアイデアを生み出すことができるのだとか。しかも、インサイドボックス――制約のある中で考えることによって、より一層、革新的な発想を得られると語っています。
何? その話が本当なら、求めていた! そんな方法を! …というわけで、そのテクニックの中から、「引き算」「一石二鳥」の2つを紹介します。
■要素を取り除く「引き算」のテクニック
製品やプロセスの構成要素を取り除き、残りの要素だけで元どおり機能するかどうかを考えるテクニック。「それを外すわけにはいかないだろう」と思っているものを、あえて外して考えることによって、製品やプロセスに対する「思い込み」を捨てることができます。制約のある、限定された狭い中で、代替するものはあればそれでよいし、引き算されたもの自体を使う人にどんな利益があるか…を考えればまったく新しいニーズを掘り起こす可能性があります。例えば、P&G社では、「活性成分」「香料」「結合剤」の3つしかない洗剤の要素から、洗う成分である「活性成分」を外した衣類リフレッシャーの「ファブリーズ」が生まれています。
■既存の道具とアイデアで「一石二鳥」のテクニック
製品やサービス、プロセスの、既存の要素や部品に新たな役割を持たせるテクニック。構成要素の1つを、外部に機能を移す/まったく新しい機能を担わせる/外部の機能を担わせる…のいずれかで考えることによって、シンプルで実現しやすいアイデアになります。例えば、人間とコンピュータを識別するための「キャプチャ」認証システムは、その文字解読によって、同時に膨大な量の書籍デジタル化に貢献しています。
仕事というのは、ほとんどが制約がある中で行うもの。これらのテクニックをうまく使えば、閉塞した状況からも抜け出せそうです。
文:明灯尋世
とある中小企業で日々、上下に挟まれて突破口を探すアラフォー女局長。知識は、行動に移してこそ身につく。組織の中でも自由であれ。家族は姑、夫、犬一匹。




















