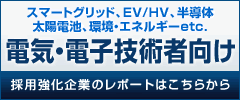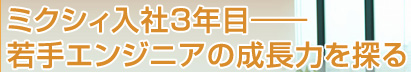 |
 |
|
若手エンジニアが成長する環境とはどのようなものか。エンジニアの成長にとって、開発現場の習慣や風土は大きく作用する。2009年新卒でミクシィに入社したエンジニア3人取材。それぞれの“成長の軌跡”を辿った。
(取材/広重隆樹 文/川畑英毅 総研スタッフ/宮みゆき 撮影/佐藤聡)作成日:11.12.22
|

福島 芳一氏
26歳 
早石 明浩氏
25歳 |
「mixiの成長にエンジニアとして寄与したかった」 早石明浩氏も学生時代からのmixiユーザー。mixiを友人や先輩とのコミュニケーションを深めるツールとして活用していたという。専門学校ではWeb開発を学び、アルバイトでもWebアプリケーションを書いていた。 学生時代の経験は現在のプラットフォーム開発グループでの仕事にも役立っている。最近の大きな仕事としては、2011年8月にリリースされた「mixiページ」の開発がある。個人、サークル、企業などが簡単にmixiのソーシャル機能に最適化された「ソーシャルページ」をつくることができるプラットフォームだ。 3人目の福富崇博氏は大学院時代に統計的機械翻訳、特に言語モデルの研究をしていた。言語の専門家が翻訳規則を記述するルールベースの翻訳と違って、統計的翻訳は膨大な翻訳パターンから翻訳規則を機械的に学習するところに特徴がある。コンピュータの性能向上やアルゴリズムの発達がこれを可能にした。
学生時代から大規模なデータから有用な情報を抽出するデータマイニングの技術にはなじみがあった。 入社してしばらくはmixi内に展開される広告の配信システムを担当し、ソーシャルバナーの開発にも携わった。現在は研究開発グループに所属し、広告開発の経験によって培った経験とデータマイニングの知識を駆使しながら、いかにしてサービスを効果的に実装するかを考える日々だ。 |
|
さて3人の若手エンジニア。もともと優秀な人材であったには違いないが、それでも会社に入って初めてぶつかる難題は少なくなかったはず。その難しい壁を乗り越えることで、若者は成長する。それぞれの成長のきっかけになったエピソードを語ってもらおう。
「『mixiページ』のリリース後は負荷の具合を見つつ様々なところから寄せられたバグの修正やいくつかの改善をいれていました。リリース前に細かな負荷対策などを施していたため想定以上のアクセスに対しても問題なく対応できました」
現在もサービスはダウンすることなく、稼働している。リリース後についても何度となく細かな修正を繰り返した。「mixiページ」は新しいプラットフォームというだけではなく、それ自体が多くのユーザが利用するサービスだ。最適なUIを探るため、ユーザーごとに微妙に異なるUIを提供し、そのアクセスログなどを分析しながら、より使われるのが多いUIを選択していくといった方法をとり、継続的な改善を続けている。 |

福富 崇博氏
27歳 |
最初は1週間かかったことが、次には3日でできるようになる。初めて取り組む課題にでも先が全く見えないという不安はなくて、おぼろげながらも全体が見えている──そんなスピードの向上や視野の広がりを感じたとき、エンジニアは自分のスキル向上を実感するのではないか。しかし、それを実感するのは、プロジェクトの渦中よりは、プロジェクトがひと段落ついてから、という時のほうが多いかもしれない。
「成長のタイミングって、直線的にというよりも、もっとランダムにやってくるように思うんです」と言うのは福富氏だ。「1つのタスクをこなすと必ず1つ成長するというのではなく、3つ、4つとタスクをこなす内に、突然2歩、3歩前に進んでいる自分を発見したりするんですよね」時には階段の踊り場から上に上がれず、全然進歩していないと焦るときもある。しかし、そのように苦しむということは、後から見れば、それ自体人が成長しつつある「しるし」なのかもしれない。
「ミクシィに限らず、プログラミングではコードレビューという作業が重要です。よくわかった人に自分の書いたコードを見てもらって、アドバイスを受ける。誰かに必ず見られると思うと、より美しいコード、ムダを省いたコードを書こうと意識するようになります。その繰り返しの中で、プログラマは成長していくのだと思うんです」
コーディングおよびコードレビューの重要性については、福島氏もこう語っている。
「ミクシィはほとんどのサービスを自社内で開発しています。何年も機能改修に務め、少しずつサービスをブラッシュアップしていきます。あえて言えば、実装が1だとすれば、保守・運用・改修の作業量は4ぐらいに値する。だから、誰もが将来のことを考えてコードを書くようになる」
リリース後にこそ、エンジニアの成長の機会が訪れるといってもいいのかもしれない。
「ユーザーの反応は開発現場にも届いています。ユーザーの声やアクセスログ等から利用動向をみていて、自分がこだわった部分が理解されているなとホッとするときもあれば、なぜ使ってもらえないのか悩むこともあります」
ミクシィには「たんぽぽグループ」という組織がある。開発工程の改善やパフォーマンスチューニングといった共通課題を抽出し、それを解決する専任のエンジニアリング・チームだ。社内的にもリスペクトされる高い技術力をもつエンジニアたちの集団である。新人のコードレビューも、彼らが面倒を見ることもある。
入社早々、担当した案件で早石氏はたんぽぽグループのエンジニアに相談をもちかけることになる。
「相談というよりは議論という形になっていたかもしれません(笑)でもエンジニアにとって論理的に納得のいかないことを曖昧に済ませてしまう、というのはよくないと思うんです。先輩のスーパーエンジニアたちが言うからではなく、論理的にその通りだと思うから納得できる。それができなかったら、徹底的に議論すべきなんです」
こうした技術の前には臆せずにモノを言う習慣や風土は、エンジニアの成長にとって欠かせない要素だ。あえて言えば、年齢や経験ではなく、エンジニアはまずそのコードによって評価され、リスペクトされるべきなのだ。
福富氏の直属の上司・木村俊也氏は業界内でもソーシャルグラフ解析の第一人者と目されるエンジニア。特にグラフ専用データベースGraphDBの活用で注目を集める。その木村氏との日常的なやりとりを、福富氏はこんなふうに語る。
「私たちの研究開発は先行研究の少ない中、手探り状態で課題を探していくもの。ただソーシャルグラフを分析すればいいというだけじゃなくて、それをサービスに実装するとどういう効果が得られるかまで考えなくてはいけません。毎日が試行錯誤の連続。テスト項目自体も自分で考えなくてはいけない。木村さんにはいつも、『君は何をやりたい?』と問われます。そうやってオープンクエスチョンで投げかけてもらえると答えるうちに頭の中が整理されますし、それが新しい発見につながることも少なくないです」
経験豊富なエンジニアが、成長意欲の高い新卒エンジニアに気付きを与え、成長させる文化がミクシィにはある。
ミクシィが組織として用意するさまざまな制度やイベントも若手エンジニアの成長の場だ。例えば2011年8月から始まったのが「Weekend challenge 2.5」(略称WC2.5)。3カ月に1回、業務時間の2.5日分を使って、エンジニアが好きな技術開発を行いその成果をコンテスト形式で競うというもの。
早石氏は早速、 iPhone向けアプリを書いて応募した。iPhoneでいま聴いている音楽の動画をYoutubeで検索し、友人に紹介できるアプリだ。入賞にはいたらなかったが、「好きなアプリを自由に作れて面白かった」と語る。
WC2.5で上位入賞と健闘したのは、同期のエンジニアとチームで参加した福富氏。「スマートフォンアプリ開発者の中で今、汎用アプリ開発エンジンTitaniumがブレークしています。僕たちはTitaniumベースのスマートフォンアプリからmixiのGraphAPIを簡単に利用するためのライブラリ群と、これを使ったサンプルアプリを開発しました」
すでに「Titanium.Facebook」というAPIは世の中に公開されていた。Titaniumの技術書を読むと「さあ、これでTwitterアプリを書いてみましょう」という例題が示されていたりする。福富氏にはそれが悔しかった。mixi用はないのか。だったら自分で「Titanium.Mixi」を作ってしまおうと思ったのである。
社内ハッカソンで技術が磨かれ、その成果は社内の実装基盤を強化するだけでなく、場合によってはオープンソースとして世の中に広がる。しかも入社3年目の社員たちが、そこで水を得た魚のように生き生きとコードを書いているのだ。
福島氏もまたこの「WC2.5」や月に1度社内で開催されるライトニングトークのイベントに刺激を受け続ける一人。
「インターネットの世界は変化が激しい。そんな変化に適応しつつ、よいサービスを提供し続けることが私たちのミッション。そのため社員同士で刺激し合える機会がミクシィにはあります。本気でやらないといけないので大変ですが、それが楽しみでもあります」
よりよいmixiのサービスとは何か。それは一人ひとり答えが違うかもしれない。ただ、「心地よいサービス」へ向けた努力という方向性は変わらない。
「mixiはシンプルだが日本らしく、奥ゆかしさのあるバランスのとれたサービス。居心地のいいつながりを世界に向け提供していきたい」
福島氏はそう語る。
かつてスティーブ・ジョブスのような70年代の米西海岸の若者も、東洋の思想に触れ、そこにおける自律と癒しの精神をパーソナル・コンピュータ技術になぞらえたことがある。国産のSNSだからこそできる心地よいサービスは、今日もこの3人のような若者たちによって進化している。
|
HAL大阪 Web開発学科卒業。09年新卒入社。入社当初はソーシャルグラフをマネジメントする開発案件に従事。現在はプラットフォーム開発グループに異動し、「mixiページ」のプロジェクトを担当した。 |
香川大学工学部信頼性情報システム工学科卒業。09年新卒入社。入社当初からソーシャルグラフをマネジメントする開発案件に従事。現在はソーシャルグラフチームのリーダーとして開発とチームのマネジメントを担当している。 |
筑波大学大学院システム情報工学研究科修了。09年新卒入社。入社当初は広告配信系システムの開発プロジェクトに従事。現在は研究開発グループに所属し、mixiの膨大なデータの解析を担当している。 |
このレポートに関連する企業情報です
・スポーツ ・ライフスタイル ・デジタルエンターテインメント ・投資続きを見る
このレポートの連載バックナンバー
人気企業の採用実態
あの人気企業はいま、どんな採用活動を行っているのか。大量採用?厳選採用?社長の狙い、社員の思いは?Tech総研が独自に取材、気になる実態を徹底レポート。

このレポートを読んだあなたにオススメします
ソーシャルネット時代に「mixi」が目指す姿とは?
ミクシィ原田副社長が明かすリアル・ソーシャル戦略
![]() 「mixi」はソーシャルメディアとして、今後どのような位置付けを目指すのか。他のソーシャルメディアとは、どう差別化していくのか。…
「mixi」はソーシャルメディアとして、今後どのような位置付けを目指すのか。他のソーシャルメディアとは、どう差別化していくのか。…

人のつながりを分析し、「心地よさ」を実証する
ミクシィの“ソーシャルグラフ”データ解析技術とは
![]() ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)では、ソーシャルグラフと呼ばれる人と人との“つながり”の情報が活用されている。…
ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)では、ソーシャルグラフと呼ばれる人と人との“つながり”の情報が活用されている。…

エンジニア目線の勉強会、自社の開放、学習する組織づくり…
ミクシィが取り組むエンジニアを育てる文化・組織とは
![]() 自身のスキル向上のために、日々の学習が欠かせないエンジニアたち。プロジェクトの渦に揉まれて経験を積むのも一つの方法だが、勉強会や…
自身のスキル向上のために、日々の学習が欠かせないエンジニアたち。プロジェクトの渦に揉まれて経験を積むのも一つの方法だが、勉強会や…

ソーシャル時代を見据えた様々な仕掛けと舞台裏
ミクシィとバスキュール「mixi Xmas」開発3年間の軌跡
![]() 「mixi」上で、クリスマスシーズンに実施しているソーシャル・キャンペーン企画「mixi Xmas」。この大規模なイベ…
「mixi」上で、クリスマスシーズンに実施しているソーシャル・キャンペーン企画「mixi Xmas」。この大規模なイベ…

未踏スーパークリエータ衣川氏の“Objective-C特別授業”を再現
3カ月でリリースした「mixi for iPad」開発舞台裏とは
![]() 10月にミクシィが提供を開始した「mixi」のiPad向けアプリケーション「mixi for iPad」。未踏スーパークリエータ…
10月にミクシィが提供を開始した「mixi」のiPad向けアプリケーション「mixi for iPad」。未踏スーパークリエータ…

やる気、長所、労働条件…人事にウケる逆質問例を教えます!
質問を求められたときこそアピールタイム!面接逆質問集
面接時に必ずといっていいほど出てくる「最後に質問があればどうぞ」というひと言。これは疑問に思っていることを聞けるだけで…

あなたのメッセージがTech総研に載るかも