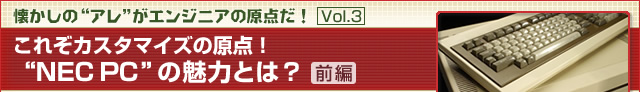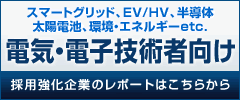|
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
このレポートの連載バックナンバー
懐かしの“アレ”がエンジニアの原点だ!
多くのエンジニアが子供の頃、心を奪われたもの。数多くの懐かしい製品を通してエンジニア魂が芽生えた原点を探ります。

このレポートを読んだあなたにオススメします
懐かしの“アレ”がエンジニアの原点だ!
まさにプログラマの原典!「ベーマガ」の魅力
![]() 100ページ以上に及ぶ「投稿プログラムコーナー」、ほかの追随を許さないほどゲーム攻略に力を入れた「スーパーSOFTコーナー」。さ…
100ページ以上に及ぶ「投稿プログラムコーナー」、ほかの追随を許さないほどゲーム攻略に力を入れた「スーパーSOFTコーナー」。さ…

懐かしの“アレ”がエンジニアの原点だ!
ソフトの数だけ興奮がある「セガゲーム」アーケード編
![]() 「スペハリ」「アフターバーナー」「アウトラン」「BEEP」「メガドライブ」こんな単語に胸ときめくエンジニアは今なお多い…
「スペハリ」「アフターバーナー」「アウトラン」「BEEP」「メガドライブ」こんな単語に胸ときめくエンジニアは今なお多い…

史跡めぐり、DJ、ミニ四駆、電子工作、路線バス…
巡ってプレイしてカスタマイズする醍醐味を追求せよ!
今年10周年を迎えたTech総研では、全国のエンジニア1000名を対象に、子どもの頃に熱中した遊びについて調査した。そ…

家電にはエンジニアゆえのこだわりがある。そうだろ?
性能?静音?エンジニアは自作PCのどこにこだわるか
![]() 既製品を購入するより自作で組んだほうが安かったデスクトップPCも、いまやBTOによって、以前より手軽に自分好みの製品を手に入れら…
既製品を購入するより自作で組んだほうが安かったデスクトップPCも、いまやBTOによって、以前より手軽に自分好みの製品を手に入れら…

懐かしの“アレ”がエンジニアの原点だ!
住まいを変える究極のカスタマイズ!「DIY」の魅力
![]() 「Do It Yourself」の略であるDIY。自分の頭と手を使い、もっと便利で快適に、自分の住まいをカスタマイズするその魅力…
「Do It Yourself」の略であるDIY。自分の頭と手を使い、もっと便利で快適に、自分の住まいをカスタマイズするその魅力…

広める?深める?…あなたが目指したいのはどっちだ
自分に合った「キャリアアップ」2つの登り方
「キャリアアップしたい」と考えるのは、ビジネスパーソンとして当然のこと。しかし、どんなふうにキャリアアップしたいのか、…

あなたのメッセージがTech総研に載るかも