新卒で入社したばかりだけど、退職したい。そんな悩みを抱える若手ビジネスパーソンに向けて、新卒で退職する前に考えたいことや事前に知っておきたいリスクなどを、組織人事コンサルティングSegurosの粟野友樹さんが解説します。

目次
新卒で会社を辞めたいと思うのは甘え?
新卒で会社を辞めるというと、「一時的な感情で決めているのでは」「甘えでは」と思う人もいるかもしれません。実際は、企業側の労働環境の問題から離職をせざるを得ないケースや、個人側のキャリア形成の観点から、転職や資格取得、留学などに向けて離職する前向きな理由もあるでしょう。
厚生労働省のデータ(※1)によると、令和3年3月卒の令和6年6月時点の数字で、新卒入社1年目の離職率は中学卒33.1%、高校卒17.4%、短大等卒18.3%、大学卒10.9%となっています。新卒入社した人たちの1~3割程度が1年目で離職していることがわかります。
一方で、株式会社リクルートの調査 (※2) では、採用動向として第二新卒をターゲットにする企業も増えつつあります。
●リクルートエージェントにおける「第二新卒歓迎と記載がある求人」の推移
※2009-2013年度平均を1とする
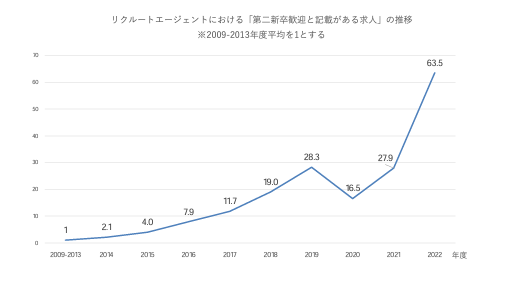
ただリクルートワークス研究所が行った、民間企業における2023年度の中途採用実態に関する調査(※3)では、「必要な人数を確保できなかった」と回答した企業は過去最高値になっていました。
人手不足により新卒採用で充足できない企業も増加しており、入社1年目の離職者に対する転職市場のニーズも変化しています。若手人材を中途で採用できる、という見方をする企業もあり、社会全体が早期離職者を許容する方向で動いているともいえるでしょう。
(※1)出典:厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html)
(※2)出典:株式会社リクルート「Z世代(26歳以下)の就業意識や転職動向」https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20230830_hr_01.pdf
(※3)出典:リクルートワークス研究所「中途採用実態調査(2023年度実績、正規社員)」https://www.works-i.com/surveys/item/240606_midcareer.pdf
新卒で退職を考える前にできること
新卒入社1年目での退職には、意思決定する上での経験や情報の不足という側面もあるかもしれません。早急に辞めてしまったあとに「退職しなければよかった」と後悔しないために、退職を考える前にできることを見ていきましょう。
現職の不満を特定し、改善に向けて工夫する
早期退職の理由として、「希望に合わない配属だった」「やりたかった仕事ではなかった」といった声もよく挙げられます。しかし、組織で働く以上、こうした状況はどの職場でも起こり得るものです。
まずは、自分が何に不満を感じているのか、具体的に書き出してみましょう。「配属先の仕事内容」「上司や同僚との関係」「働き方や環境」など、問題を細かく分けることで、改善できる部分が見えてくるかもしれません。
次に、それぞれの問題に対して何ができるかを考え、できることから行動を起こしてみてください。例えば、上司や同僚に相談する、新しいスキルを学んで別の役割に挑戦する、職場の環境の改善提案をする、などが考えられます。こうした取り組みによって、悩みが解消されたり、仕事へのモチベーションが高まったりすることがあります。
業務変更や異動の可能性を検討する
工夫や改善をしても不満が解消されないのなら、業務変更や異動の可能性を探るのも一つの方法です。
人間関係に不満を持っている場合も、異動によって職場環境が変わり、不満が解消することがあります。人間関係の悩みは、転職した先でも生じる可能性があるので、「今の人間関係が嫌だから」とすぐに退職を決めるのではなく、社内で環境を変える方法を探ってみてもいいでしょう。
転職市場の情報を収集する
退職・転職するかどうかはさておき、現職以外で取り得る選択肢は何か、情報を集め、検討するのもいいでしょう。転職サイト、スカウトサービス、転職エージェントなどを利用することで、お金をかけずに調べたり相談したりすることができます。
自己分析をしてやりたいことを整理する
現職への不満だけで転職すると、次の職場で同じような不満を抱えてまた転職を繰り返すことになりかねません。そこで、これからのキャリアで実現したいことは何か、改めて見つめ直す時間を作りましょう。
自己分析で自分の強みややりたいことが見えてきたら、「今の職場で実現する方法、選択肢はないのか」を考えてみましょう。現職に留まるか、転職か、という複数の選択肢が生まれることで、冷静に意思決定ができるようになります。
社内外の信頼できる人に相談する
社内の信頼できる先輩や上司のほかに、学生時代の恩師や先輩、社外の知人など、社外の信頼できる人に相談をしてみましょう。社会人経験が長い人たちであれば、同じように「辞めたい」と思った経験をしているはず。その経験を踏まえてのアドバイスには、何らかの気づきがあるでしょう。
社外の人であれば、社内の人にはない、より客観的な視点からのアドバイスが得られるかもしれません。今後のキャリアにしっかり向き合うために、有料のキャリアコーチングを受けることを検討してもいいと思います。
仕事は仕事と割り切る
仕事の捉え方を変えて、プライベートを充実させたり、副業していずれ独立・起業することを視野に入れたりと、「現職の仕事は無理のないペースで続ける」という方向性もあり得るでしょう。
ただ、労働基準法に違反しているような劣悪な労働環境や、ハラスメントに遭っている等の場合は、会社や労働組合の相談窓口、外部相談委託先、公的な相談窓口など、適切な相手に早急に相談しましょう。
●労働基準行政の相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html
●ハラスメントに関連する相談機関一覧
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/inquiry-counter

新卒で退職するデメリットとリスク
新卒で退職する場合、キャリアに与える影響としてどのようなデメリットやリスクがあるのでしょう。
「社会人経験の短さ」や「経験・スキル不足」が懸念点となり、転職活動で苦戦するかもしれない
応募した企業によっては「社会人経験の短さ」や「経験・スキル不足」が懸念点となり、選考をなかなか通過できずに精神的に落ち込んだり、ブランクが長引くことで経済的な不安を感じたりする可能性があります。
また、若手人材に対する転職市場の採用ニーズは高くても、全ての人が希望の転職を実現できるかはわかりません。退職した会社よりも労働条件や仕事内容が希望と合致しない可能性もあるでしょう。結果的に不本意な選択をせざるをえなくなるケースもあるかもしれません。
現職で得られたかもしれない将来のキャリアにおけるチャンスや選択肢、可能性を失うかもしれない
例えば1年目は「仕事が合わない」「人間関係が嫌だ」と思ったとしても、継続してみることで市場価値の高い経験やスキルを身につけられる可能性はあります。
やりがいのあるプロジェクトを任され、意欲的に仕事に取り組み成果を出すことで、昇進・昇格などチャンスもあったかもしれません。早期の退職は、そうした将来のチャンスを失うことにつながるともいえます。
「ネガティブな辞めグセ」がつき、ジョブホッパー予備軍になるかもしれない
新卒入社後、比較的早く退職・転職を経験することで、「今の会社が不満なら、とりあえず転職すればいい」「深く考えなくても転職はできる」という成功体験・考えを持ってしまう人もいます。
不満起因の軸・目的のない転職を繰り返し、場合によっては転職を繰り返すことで、目指すキャリアとどんどんかけ離れていく可能性もあります。
それでも辞めたい場合は何をすべき? 最適なタイミングや注意点
新卒入社したばかりで退職することのデメリットやリスクを理解した上で、やはり退職をしたいと考える場合、どんな行動を取り、どのような点に注意すべきなのでしょう。
自己分析を進め、転職理由・転職後のキャリアプランを整理する
前述のように若手人材に対する採用ニーズは高まっており、新卒入社後のすぐに退職・転職をした方が、ポテンシャル採用で希望の転職を実現できたり、未経験の業界や職種へキャリアチェンジのチャンスが多くあったりするとも言えるでしょう。
そういった転職が比較的しやすい環境だからこそ、まずは、自身の就職活動を振り返り、なぜ自分は、「なぜ自分はこの会社に新卒で入社することを選んだのか」を言語化しながら、自分以外の視点として上司や先輩・同僚の仕事のやりがいやキャリアのアドバイス、社外の知人からの意見を受けることをおすすめします。
「転職という選択肢しかないのか。現職をもう少し続けて様子を見るという可能性はないのか」「転職するとしたらどういったキャリアを歩んだらよいのか」など、時間をとって考え整理することで、自分の視野が狭くなっていたことに気づくかもしれません。
「今の会社では希望する仕事がない!」と思い込んでいたり、現職とのコミュニケーション不足やミスコミュニケーションで「上司と価値観が合わないから辞めたい」となっていたりするだけかもしれません。
転職市場の多角的な情報収集に時間をかける
転職サイトやハローワークなどだけではなく、転職エージェント、スカウトサービス、ビジネスSNS、リファラル、新卒サイト(第二新卒歓迎の企業もあります)、企業サイト、SNSなど、幅広い情報源に触れましょう。
情報収集にしっかり時間をかけることで希望の転職先探しにつながる情報を得られたり、自分ひとりだけでは想定できなかった意外な選択肢が見つかったりするかもしれません。
将来的なカムバック転職の可能性を見越して、円満退職を心がける
昨今はカムバック転職に積極的な企業が増えています。将来のキャリアの中で、新卒で入った今の会社に戻りたい、と考えることもあるかもしれません。そのときの選択肢を狭めないように、できるかぎり円満退職を心がけることをおすすめします。
退職代行を使ったり、一般的な退職の手続きを踏まずに突然出社しなくなってそのまま退職したり、といった場合は、カムバック転職の可能性はなくなります。
また、同業界に転職する場合は仕事の現場で前職の人に会ったり、何らかつながっていったりすることもあるので、円満退職で損をすることはないはずです。
就業規則を確認し、退職のタイミングを検討する
退職金は、在籍期間に応じて支払われるケースがほとんどであるため、新卒で入社したばかりで退職する場合は支払われない可能性もあります。また、賞与も離職のタイミングによっては支払われない可能性もあります。就業規則を確認し、退職するタイミング検討しましょう。
まとめ:自分自身と向き合う時間をとって考えてみよう
人によっては、労働環境やハラスメントの有無、家庭の事情などにより、早い段階で退職したほうが良いケースもあります。ただ、そうではない場合は、「すぐ辞めて転職したい」と近視眼的な思考になったり、短期的な感情だけに影響を受けたりせずに、落ち着いて自分の状況を整理することが大切です。
信頼できる複数の第三者に相談をするなどをしてから退職するかどうか決めたほうが、のちに納得感のある判断や選択ができるでしょう。
今後のキャリアを長い目で見れば、「現職で続ける」「転職をする」以外にも、「学び直す(学校に入り直す、資格取得に専念する)」「独立・起業する」「一旦仕事をせずに休む期間を設ける」などさまざまな選択肢があります。
特に経験やスキルの浅い20代の場合、思いがけないところにチャンスが潜んでいる可能性もあります。今この瞬間だけを切り取って急いで「退職する」という選択にとらわれず、自分自身と向き合う時間をとることをおすすめします。
 組織人事コンサルティングSeguros
組織人事コンサルティングSeguros
代表コンサルタント粟野友樹氏
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。




















