アセスメント(評価、査定)は、リスクアセスメントや環境アセスメント、医療・看護アセスメントなど、さまざまな業界で用いられますが、ビジネスパーソンにとっておそらく最も身近なのは、組織の人事に用いられることの多い人材アセスメントです。具体的にはどのような手法で、活用されているのか。ビジネススキル関連のアセスメントサービスを手がける株式会社プレセナ・ストラテジック・パートナーズ代表の高田貴久氏に聞きました。
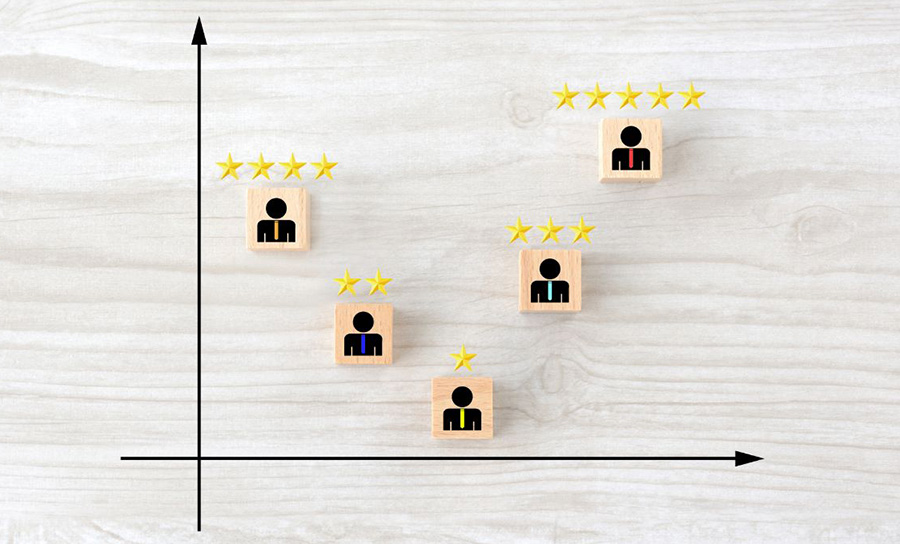
人材アセスメントとは何か
人材アセスメントは、一般的に「人材の能力を評価するためのツール」と理解されていますが、実は「より良い人材育成や人材開発を目指す」ために活用されることが多い手法です。大きく分けると、以下3つのカテゴリがあります。
採用アセスメント
採用アセスメントは新卒採用や中途採用で用いられるもので、特に新卒採用の場合は、対象者が膨大になるため統計処理的な要素が強くなります。適性検査などが代表的なものですが、個人の結果だけでなく、母集団の傾向値も重要な要素になっています。
昇格アセスメント
例えば管理職昇格時のアセスメントなどで、結果次第では生涯年収が変わってきますから、人生がかかったものになります。受ける人も必死で対策をしますし、試験問題が事前に流出するといった不正も起こり得ます。また、評価や査定に対して受験者が疑義を唱えるケースも少なくありません。
研修アセスメント
上記の2つは一般的に本人に評価や査定の詳細を公開しませんが、これは社員に成長してもらうためのものですから、どんな点ができていて、何が不足しているのかなど、評価の結果や詳細を本人にフィードバックします。
上記の3つはそれぞれ目的が異なるため、アセスメントの設問の設計や精度、フィードバックの内容なども違ってきます。
アセスメントを行うメリットは?
人材アセスメントはなぜ行われるのでしょうか。実は、昔は採用アセスメントも昇格アセスメントも必要とされていない時代がありました。経営者や部門長が面談をして、「Aさんは優秀そうだから採用しよう」、「最近Bさんは頑張っており成果も出しているから昇格させよう」といった責任者の主観を中心に判断が行われていたのです。
もちろん現在でも、企業が小規模であれば、経営者や部門長が直接ひとり一人と面談をして、採用や昇格を決めてしまうことも可能です。しかし、責任者個人の主観的な判断や独断では、先入観があったり、見誤りが起きたりしてしまうでしょう。
そのため、今では大企業だけでなく中堅企業なども含めた多くの企業で、会社のビジョンや経営方針に即してどんな人材が必要かという人材要件、どういう能力のある人が管理職になるべきか、中堅社員ならどんな能力を持つべきかという能力要件などが定義されるようになりました。こうした要件を満たしているかどうかを客観的に判断するために、アセスメントが使われるようになってきました。
アセスメントを使うことで、企業としては個々の能力や適性の見える化を行い、必要な要件を満たす人を採用したり、昇格させたりできます。あるいは、できていない人にきちんとフィードバックすることで成長を促すこともできるのです。
近年、アセスメントが注目されるようになった理由
こうしたアセスメントがより重要視されるようになった理由はいくつかあります。
1つ目は、「コロナ禍の影響でリモートワークが増加」し、働いている様子や状況が直接見る機会が減少したことです。社員がどのような能力を発揮しているのか周りの人が見て感じる機会が減り、わかりづらくなってきました。こうした働き方の変化に対応すべく、客観的な判断ツールによって見える化するニーズが高まっているのです。
2つ目は、多くの企業が「自立型人材育成」に舵を切っていることが挙げられます。全員が同じことを学ぶ機会を提供する階層別研修だけでなく、各自が空き時間を使ってそれぞれ必要な知識を身に付ける希望者研修に力を入れる企業が増えてきました。個人の取り組み次第で能力に差がつくため、それを客観的に把握して評価する必要が生まれています。
3つ目が、「プロジェクト型組織やプロジェクト型の働き方」が増え、人材の流動化が進んでいることです。一般的なピラミッド型組織は上司が部下を管理する固定的な組織であるため、それぞれの人となりや仕事を直属の上司が把握できていました。
しかし最近では、例えば「DX推進」などのように目的に応じて人が集められて業務を遂行し、プロジェクトを終えたら解散するプロジェクト型組織形態が増えています。
特にコンサルティング会社やIT系企業などでは特に顕著な傾向がみられます。このような流動性が高い組織では、メンバーの能力が見える化できている方が、仕事がスムーズに進みます。能力を見える化することも、アセスメントの役割の1つなのです。
アセスメントにはどんな評価ツールがあるのか
人材アセスメントの評価ツールはさまざまありますが、ここでは代表的なものを紹介しましょう。

客観テスト(適性検査)
SPIに代表されるテスト形式で行われる検査です。応募者の基礎的な知的能力や人となり、性格特性を把握するために用いられます。応募者に向く仕事や、どんな組織になじみやすいのかなどが分かり、採用や配属、昇格などに利用されています。
他者評価(360度評価)
他者評価や多面評価、360度評価とも言われ、上司や部下、同僚、仕事の関係先などから自分の能力や適性、仕事の評価をしてもらいます。さまざまな関係の人から評価してもらうことで、自己認識とのずれや強み・弱みを新たに知るきっかけにもなります。
ストレングスファインダー®
アメリカのGallup社が出している、個々人の強みを見つけ出す診断ツールです。自分の強みを活かして仕事をするための研修アセスメントなどに使われています。
アセスメントをキャリアに活かすには
IT業界であれば、使える言語やスキルを見える化してフリーランスとして登録した上で、特定の組織に所属せずプロジェクトベースで働くエンジニアも少なくありません。これからはエンジニアに限らず、仕事ができる人は所属組織以外のプロジェクト組織に参画したり、個人事業主として副業をしたりするなど、雇用や働き方の流動性が進むでしょう。
その中で、自分自身は何ができて、何が足りないのかを常時見える化して、強みを磨き、弱みを補っていくことは大切になってきます。ビジネスパーソンにとってのアセスメントのメリットはまさにそこにあります。
高価なアセスメントツールを使わずとも、少しの工夫で自己の能力を客観的に見直すことができます。例えば、無料の自己診断ツールなどを使って、自分の強みを探ってみる。さらに、友人や家族に自分の強みは何かを聞いてみれば、把握できていなかった他者評価を知ることもできます。自己評価と他者評価の差分を見ることで、認識のギャップ、自覚していなかった強みや課題に改めて気づくことができます。
これからの時代、自分のできていないところや足りないスキルをアセスメントで把握し、自ら主体的に学習につなげていくことがますます求められていくでしょう。
▶あなたの知らない自分を発見できる。無料自己分析ツール「グッドポイント診断」
プロフィール
株式会社プレセナ・ストラテジック・パートナーズ
グローバルCEO・代表取締役社長 高田 貴久(たかだ・たかひさ)氏
 東京大学理科Ⅰ類中退、京都大学法学部卒業、シンガポール国立大学Executive MBA修了。戦略コンサルティングファーム、アーサー・D・リトルでプロジェクトリーダー・教育担当・採用担当に携わる。マブチモーターで社長付・事業基盤改革推進本部長補佐として、改革を推進。ボストン・コンサルティング・グループを経て、2006年にプレセナ・ストラテジック・パートナーズを設立。トヨタ自動車、イオン、パナソニックなど多くのリーディングカンパニーでの人材育成を手掛けている。著書に『ロジカル・プレゼンテーション』『問題解決―あらゆる課題を突破するビジネスパーソン必須の仕事術』がある。
東京大学理科Ⅰ類中退、京都大学法学部卒業、シンガポール国立大学Executive MBA修了。戦略コンサルティングファーム、アーサー・D・リトルでプロジェクトリーダー・教育担当・採用担当に携わる。マブチモーターで社長付・事業基盤改革推進本部長補佐として、改革を推進。ボストン・コンサルティング・グループを経て、2006年にプレセナ・ストラテジック・パートナーズを設立。トヨタ自動車、イオン、パナソニックなど多くのリーディングカンパニーでの人材育成を手掛けている。著書に『ロジカル・プレゼンテーション』『問題解決―あらゆる課題を突破するビジネスパーソン必須の仕事術』がある。
▶プレセナ・ストラテジック・パートナーズ 公式サイト

























