「2人に1人は転職をする時代」と言われる中、現状に特に不満はなくても、先輩や同僚が転職をしている姿を見て、「本当に同じ会社で働き続けてよいのだろうか…」と悩むビジネスパーソンは多いことでしょう。今後のキャリアを考える上で、転職するかどうか、後悔しない決断をするには、何を基準に判断し、どう行動すればよいのでしょうか。
今回、『「いつでも転職できる」を武器にする 市場価値に左右されない「自分軸」の作り方』(KADOKAWA)の著者であり、人事・戦略コンサルタントの松本利明さんに、ビジネスパーソンの「転職への迷い」をクリアにするための観点をうかがいました。
プロフィール
 松本利明(まつもと・としあき)さん
松本利明(まつもと・としあき)さん
人事・戦略コンサルタント。HRストラテジー代表。HR総研客員研究員。PwC、マーサー、アクセンチュアなどのプリンシパル(部長級)を経て現職。国内外の企業600社以上の働き方と人事の改革に従事。5万人のリストラと6500名以上のリーダーの選抜と育成に関わった「人の目利き」。最近は「誰もが自分らしく活躍できる世の中」に近づけるため、自分の持ち味を活かしたキャリアの組み立て方を学生、ワーママ、ビジネスパーソンに教え、5000名以上への個別アドバイスをライフワークとして提供し、好評を得ている。『「いつでも転職できる」を武器にする』(KADOKAWA)、『「ラクして速い」が一番すごい』(ダイヤモンド社)、「稼げる人稼げない人の習慣」(日経ビジネス人文庫)などベストセラー多数。英国BBC、TBS、日経新聞社など、メディア実績多数。
目次
キャリアで後悔しない決断をするためには、「目標設定」が欠かせない
私は幅広い年代のビジネスパーソンと交流する機会がありますが、現代はキャリアを検討する上で「転職をするか否か」を迷っている人は、本当に多いと感じます。
転職に踏み切れない理由には、「失敗することへの不安」や「引き止めに合っている」といったこともあるかもしれません。しかし、一番の理由は、転職に至る決め手がないからではないでしょうか。加えて、決断しにくくなった背景には、数年前よりも働き方の選択肢や転職に必要な情報やサービスが増え、比較的容易に転職ができるようになったという現状もあると思います。人間は選択肢が多すぎると、かえって選ぶことができなくなる性質があるのです。
そもそも転職とは、今までの職場で培った力をベースにして、「+α(プラスアルファ)」の成長ができる環境に自分の意志で「異動」ができるものです。転職によって新たな経験を積み、目指す姿に近づける環境を選べば、将来の可能性は大きく広がることでしょう。そのためには、「いつまでにどんな自分になりたいか」を考えなければ、転職するにしろしないにしろ、後悔の元になるかもしれません。転職をするかどうかずっと迷い続けているという人は、転職の決め手が見つかっていないだけでなく、今の会社での目標もはっきりしていないのではないでしょうか。
そこで必要になるのが、自身の目標設定です。しかし、「10年後にトップディレクターになるために、今から●●して~」「5年後には〇〇のチームリーダーになる」といった細かなキャリアプランを立てることは、実は今の時代に合っていません。なぜなら、キャリアを長期的な目線で考えたとき、不確定な要素が多すぎるからです。これからは、計画的なキャリアアップよりも、変化に合わせて自分らしく活躍するキャリアを組み立てる時代です。目標やマイルストーンを細かく決めれば決めるほど挫折しやすい可能性があります。
一方で、これまでの経験をベースに長期的なキャリアを考えてしまうと、大きな可能性に気づきにくいと言えるでしょう。上司や先輩の背中だけを見て、自分の頭だけで考えるとどうしても今の延長の無難なキャリアしかみえてきません。
そうならないためには、キャリアを組み立てる手段を外部からたくさん仕入れることが大切でしょう。その一つとして、「他人に目標設定をしてもらう」方法があります。自己紹介や漠然としててもいいので将来の希望やありたい姿を語り、他人に目標を設定してもらうのです。コツは、会社の中ではなく、利害関係のない、全くの他人に頼ること。業界や経験が違うと目指す将来像が似ていても、目から鱗の選択肢を提供してくれることが多いはずです。自分以外の視点を取り入れ選択肢を増やすだけでなく、後押しをもらうこともできます。全くの他人に声をかけるのが難しいならば、異業種で数名、社外の友人・知人などにSNSで呼びかけ、一度やってみることをオススメします。
すぐに転職したほうがいい?迷ったときに、押さえたい3つの観点とは?
目標が設定できても、転職をするタイミングまでは、なかなか計りにくいものです。転職は大きな決断ですし、迷うのは当然でしょう。しかし、長く迷い続けていると、最良のタイミングを逃してしまう可能性もあります。そこで、転職をするかどうか検討するのに押さえておきたい観点を3つご紹介しましょう。
観点(1)自分の持ち味を活かして強くなれるか?
まず大切なのは、今の会社で自分の「持ち味」を活かして自分らしく成長できるかどうかです。
よく仕事では「強み」を活かせと言われますが、ここでいう「強み」と「持ち味」は違います。強みとは、いわば長所に近いものです。強みは、ほかの人が同じようなものを持っていることが多く、その強みのレベルが自分よりも高いこともあるので、それだけで勝負するのは心もとないでしょう。
一方、持ち味とは「あなたが仕事を通じて提供した価値そのもの」を指します。つまり、強みではなく、自分の持ち味を複数見つけ、それらを掛け合わせて武器として磨いていくことで、オリジナルな真の強さが身につくというわけです。
自分の持ち味を知るには、普段の仕事で周囲からもらう「ありがとう」の声に注目してみてください。“気を利かせてくれて”ありがとう、“速く対応してくれて”ありがとう、“正確に処理してくれて”ありがとうなど、ありがとうの声は自分が提供したものの価値を表します。心理学では、この価値を「心の利き手」とぶこともあり、その人が持つ資質を指します。人はこの「資質=持ち味」に合った技術や知識、スキルを学ぶと速くラクに身につけることができると言われています。
このように、今の会社に在籍しながら「持ち味」を発揮して成長できるのなら残ればいいですし、そうでないなら転職を考えてみると良いでしょう。
観点(2)キャリアの「コア」になる経験ができるか?
将来に向けてキャリアの選択肢を広げたいと考えているなら、一般的なキャリアの前半である30代前半までに自分の売りとなる「コア」な経験をしておくことがオススメです。
「コア」な経験と考えられるものはいくつかありますが、オススメはNO.1がある組織を経験することです。富士山の次に高い山は?と聞かれても答えを知る人が少ないように、No.1とそれ以外では、人脈、経験が違うからです。会社の規模は問いません。世界や日本を代表する大企業はもちろん、中小企業でも業界で世界初、日本初など、何かしらのNo.1を経験しておくことは、これからの時代に必要となる経験として、キャリアの選択肢を増やします。
また、ベンチャー企業の一員として、上場まで会社を大きくしたとしたら、目指す姿によってはそれも武器になります。そうしたコアになる経験が今の会社で積めるのなら、そのまま残っていた方が良いのではと、私ならば思いますが、注意が必要です。
「今いる会社でやれることを全部やってから」と思っていると、気づいたときにはいたずらに年齢が高くなり、結果、転職しにくくなってしまうリスクがあるからです。
目標から逆算して、どのような経験が「コア」となるのかも考えておきましょう。そして、コアになりそうな経験を取りにいく転職を考えてみるのです。
。
観点(3)転職後に感じるギャップや変化への覚悟ができているか?
転職とは、アウェイの環境に自ら飛び込んでいくことでもあります。そのまま転職先の序列に入ってしまうと、例えば同業でも営業なら前職の取引先の担当を外されるなど、思うように活躍できないこともあるかもしれません。期待通りにラクに活躍できない可能性を視野に入れつつ、冷静に判断しましょう。
また、嫌なことから逃げたり、人間関係をリセットしたりする目的で転職をしても、必ずしも不満や不安が解消されるとは限りません。
例えば、苦手な上司から逃げるために転職しても、不思議とどの組織にも、その上司と似たキャラクターがいるものです。ゲームの最後に出てくるラスボスのようなもので、それをクリアする方法を自分が身につけない限り、新しい会社でも前に進めなくなるかもしれません。自分のキャリアやありたい姿に集中するためにも、苦手なことや人への対処法を身につけようというスタンスはできる限り持っておくとよいでしょう。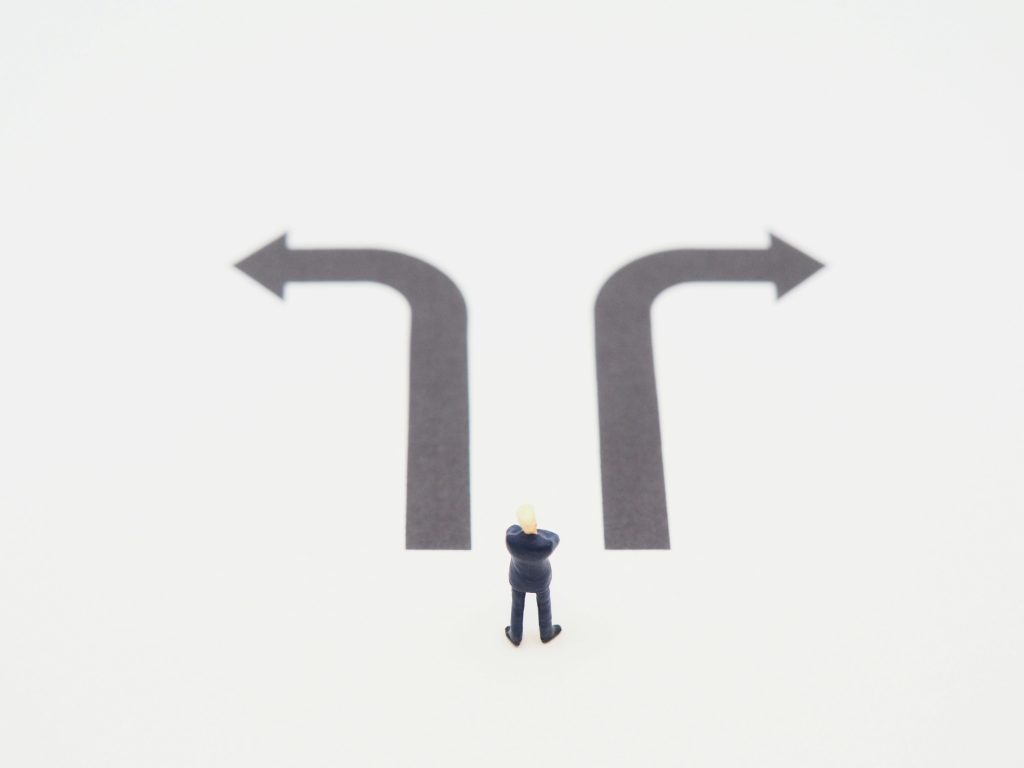
「転職しない」と決めた場合は、社内でどう力をつけるかを考える
もし、あなたが転職をしないと決めたら、前述した「持ち味を活かして強くなる」方法を社内で取り組んでいきましょう。自分の得意なものが1つしかないよりも、できるだけたくさん持ち味を見つけて組み合わせていくのが理想です。そして、それらを活かした活躍ができるのはどんな場かを考えましょう。大企業であれば、社内で色々な部署に移ることで、転職と同じような経験を積むこともできます。社内公募があるなら、挑戦してみるのもオススメです。
普通に社内でキャリアアップを考えると、昇進しようとするほどポジションが限られていき、熾烈な争いになります。そこで発想を転換し、自分の持ち味を活かして、周りのメンバーが苦手な分野にあえて「逆張り」する方法もあります。
例えば、ある建設会社で営業成績が万年ビリだったAさん。閑職に追いやられたのがきっかけで、コツコツと法律面の資格を取り、調査部を経て法律知識が必要な大型案件を扱う営業に異動。40歳でこの部署の部長に大抜擢されたという事例もあります。このように、自分の持ち味に経験やスキルをプラスし、上ではなく横へと移動することでオンリーワンとして活躍することも可能なのです。
もう1つ非常に大切なのは、仕事の中で「ポータブルスキル」を磨いておくことです。
ポータブルスキルとは、簡単に言うと、職種に関わらず通用する「仕事を前に進めていくスキル」のこと。仕事の進め方(PDCA)と人との関わり方(コミュニケーション、対人育成)に分類されています。これらは社会人の基礎であり、どんなキャリアを歩む場合でも必要なものです。逆に言うと、こちらも35歳くらいまでに最低限でも身につけておかないと、どんなに専門性があったとしても次のキャリアステップでは苦労することになるでしょう。
上司や先輩、社内OJTで学ぶことができれば良いですが、十分ではないと感じる場合は、社外に学びの場を求めてみましょう。今はリアルなプロジェクトワークやプレゼン大会を行うスクール、会社の壁を越えた経験ができるプラットフォームも増えています。社外で腕試しをすることで、自分のポータブルスキルがどれだけ通用するかもわかります。また、ともに鍛え合う仲間との横のネットワークを持つこともできます。今後のキャリアを築いていくための大きな財産になることでしょう。
今は「スキル」や「持ち味」の価値も変化するチャンスの時期
今は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、リモートワークやオンライン会議の増加など、働き方は大きな転換を迫られています。ビジネスパーソンの中にも、会社の業績や雇用に不安を感じている人は少なくないでしょう。
しかし、世の中が大きく動くときは、多くのビジネスパーソンたちの「スキル」の価値が変化するチャンスの時期なのです。例えば、インターネットスキルがすでに身についている若い方たちは、早々にリモートワークに適応し、テクノロジーを全面的に味方につけることができているのではないでしょうか?また、一人の時間が増えたことで出社するより業務に集中できるようになり、パフォーマンスが向上し、周りとのコミュニケーションも円滑になったという方もいるかもしれません。
このように世の中の前提が大きく変化したことで、ビジネスでも、これまでとは異なるスキルや持ち味を活かせる場面が増えてきたのです。もちろん今後も状況が変化することによって、新しいスキルはもちろん、まだ埋もれているスキルや持ち味が求められるようになり、際立っていく可能性は十分にあります。今一度、状況を見極めて、チャンスが来たらいつでも転職できるようスキルや持ち味を武器として磨いておきましょう。逆説的ではありますが、そうすることによって「転職をすべきか否か」という漠然とした迷いや不安は、きっと払拭できるでしょう。




















