自由にキャリアを描き、学校の外でも価値を発揮する。 副業・兼業に取り組む「二刀流教員」が子どもたちの新たなロールモデルになった
学校法人新渡戸文化学園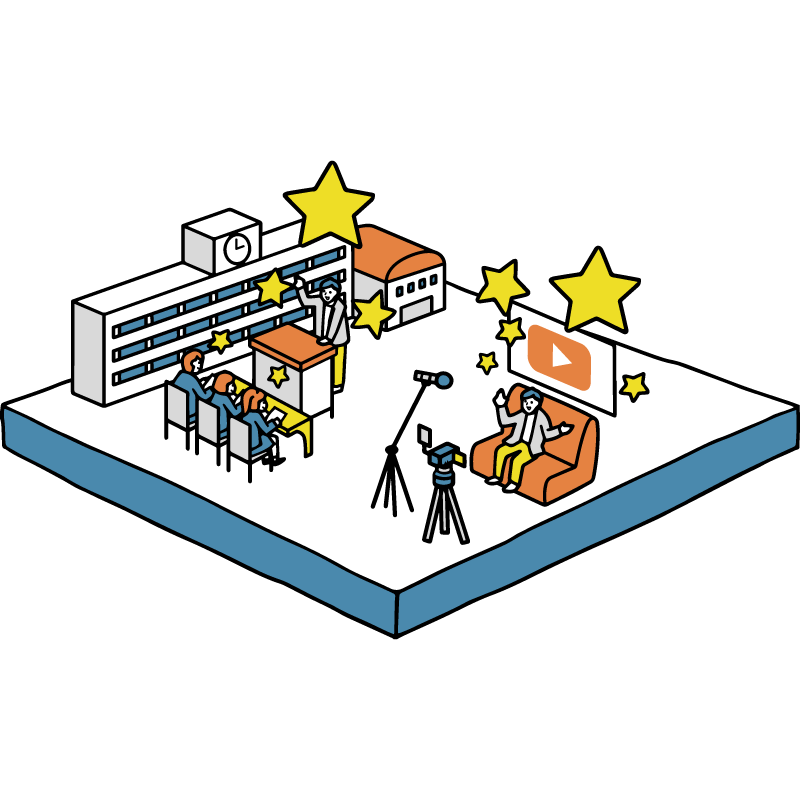
自由にキャリアを描き、学校の外でも価値を発揮する。 副業・兼業に取り組む「二刀流教員」が子どもたちの新たなロールモデルになった
学校法人新渡戸文化学園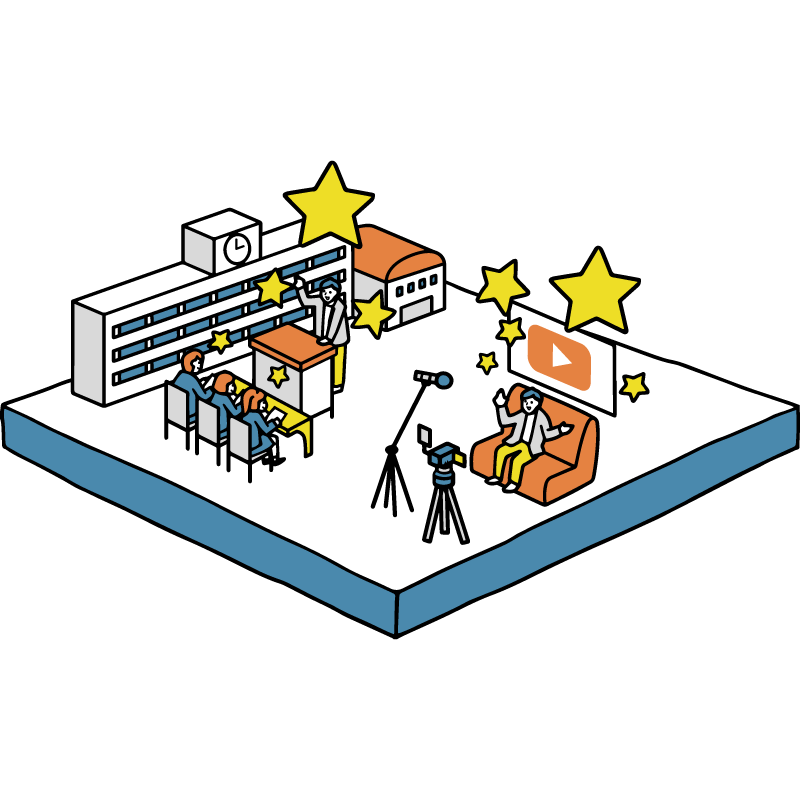
変化を続ける世の中にあって、教育現場に求められる役割は高度化・複雑化を続けている。情報科など新たに必修となる科目や、従来の教科の枠を超えて社会とつながる探究学習の広がりなど、教員が対応すべきテーマは拡大の一途をたどっているのだ。
こうしたなか、子ども園から短期大学までを設置する新渡戸文化学園(東京都中野区)では、これまでにない新たな教員の働き方が定着しつつある。名付けて「二刀流教員」。なんと同学園では現在、副業活動などで教員以外の顔を持つ二刀流教員が全体の44%を占めているという。
この記事を読んでいる人の多くは、「学校の先生が副業をしている」こと自体に大きな驚きを感じるのではないだろうか。まずは、実際に二刀流で活躍している教員の横顔を紹介したい。
新渡戸文化小学校の教員として働く加藤 千尋さんは民間企業出身。大学卒業後に教育事業を展開する民間企業へ就職した。
「大学時代から小学校の先生を目指していたのですが、そのまま教員になったら『社会を知らない人になってしまう』という懸念もあったんです。そこで、まずは自分がやりたかった野外体験を大事にしている教育業界の民間企業に就職しました。教員になる夢を持ち続けながらも、民間での仕事にやりがいを感じながら6年を過ごしました。そんなときに新渡戸文化学園を知り、両方で働いてやりたいことを実現する道はないものかと相談したところ、理事長に『二刀流で働く道もあるよ』と声をかけてもらいました」(加藤さん)
現在、加藤さんは週4日新渡戸文化小学校で教え、週1日は民間企業の学習塾で授業を担当している。学習塾では未就学児も担当しており、「幼・小とつながる子どもたちの成長に立ち会える」ことがやりがいだ。
この働き方が可能となっている背景には、新渡戸文化学園が導入する「チーム担任制」と「教科担任制」がある。小学校において、加藤さんは6年生の国語教科を担当。他に2人のチーム担任がいるため、週1日を別の仕事に割くことができる。
「あえて大変なところを挙げるなら、スケジュールの組み立てでしょうか。自分の中で2つの業務に明確な線を引き、計画立てて設計していかなければいけません。ただ、授業以外の保護者対応なども、チーム担任として同じ学年の教員が支えてくれるので助かっています。Teamsを活用した情報共有など、ツールを有効活用して業務効率化を進めています」(加藤さん)
同じく新渡戸文化小学校の教員である山ノ内 麻美さんは、加藤さんとは逆で「大学卒業後からずっと教員」。2021年9月からは、週4日全学年の英語教科を担当する一方で、週1日は大学の児童英語教育入門演習の講義を担当している。
小学校教諭と大学教員。どちらにもやりがいを感じていた山ノ内さんは、以前は非常勤として働くことで両立していたという。
「過去にも大学で教えた経験があったので、教員という仕事の魅力や、小学校で英語を教える仕事の意義を学生に伝えたいという思いが強いんです。そのため小学校教諭としては非常勤勤務を続けてきたのですが、新渡戸文化学園は二刀流で働けると知り、副業をさせていただく前提で応募しました」(山ノ内さん)
2つの現場を行き来することで、「教員としての展望が広がった」と山ノ内さんは話す。ゆくゆくは教員を目指す大学生に対して、教育実習以外にも学校現場で子どもたちと向き合う経験を頻繁に積ませてあげたいと考えている。また、小学校の児童に対しては、多種多様なバックグラウンドを持つ人達と英語という共通言語をコミュニケーションツールとして使って、遊んだり、学習したりする経験を体験させてあげたいと計画している。

新渡戸文化中学校・高等学校で英語を教える山本 崇雄さんは、25年にわたる公立校勤務を経て現職。英語で英語を教える独自のアクティブ・ラーニングに取り組み、近年では「教えない授業」としてメディアに取り上げられることも多い名物教員だ。
山本さんは、理想とする授業を実現するために教材開発にも取り組んできた。公立校勤務時代から、外部企業にアドバイスを求められることも多かったという。
「ところが教員の世界では、こうしたアイデアが搾取されてしまう傾向があるんです。企業とミーティングを重ねた結果、最終的にアイデアをすべて無償で持っていかれてしまったこともあります。また、公立校で勤務していると、本を執筆したり外部で講演したりする際にも一つひとつ手続きをして、承認を待つことが必要。タイムリーに自由に動けない窮屈さも感じていました」(山本さん)
そんなときに新渡戸文化学園と出会い、安定した公立校教員の立場を捨てて飛び込んだ。現在は新渡戸文化学園での授業のほかに、複数の学校でも授業を実施。その学校の教員を対象に教員研修や保護者講演会を行うこともある。
「私立校に勤務する教員が別の私立校でも教えるなんて、普通に考えればあり得ないことなんです。でも理事長はまったく躊躇することなく承諾してくれました。いい教育を日本中に広めたいという共通の思いがあるのです。」(山本さん)
山本さんの活動はこれだけにとどまらない。居酒屋を経営する企業のCSR活動を一緒に企画したり、外部から依頼された教科書執筆や教材制作に取り組んだり。複数の企業とも雇用契約を結んでいる。
「公立校時代とは違って、自分の価値を提供する際にはお互いのニーズに応じて対価をいただくようにしています。ここでは外部の講演会に登壇する際にも面倒な手続きは必要ありません。新渡戸文化学園での勤務日数が減ればその分だけ給料も減りますが、ほかの活動と合わせて、以前と変わらない収入を実現しています」(山本さん)

自分自身が新たな学びに挑戦しながら教員として働き続けている人もいる。
2021年4月から新渡戸文化中学校・高等学校で教える高橋 伸明さんは、現在、大学院の博士後期課程で学んでいる最中。毎週、大学院のゼミにも参加しているという。
新渡戸文化学園に来る前は都立校の教員だった高橋さん。進学だけでなく就職を目指す生徒も多い進路多様校と、上位の大学を目指す生徒が中心の進学校を経験した。
「進路多様校ではキャリア教育の重要性を学びました。その後、赴任した進学校は打って変わって、上位の大学に入ること自体が目的になってしまっている生徒もたくさん。何のために大学へ進むのかが不明確なまま、ひたすら教科学習に打ち込む現場を見て、『教育のあり方は本当にこれでいいのだろうか?』と疑問を持ったんです」(高橋さん)
大学院の博士後期課程に進学することについて、周囲からは「考え直したほうがいい」と言われたそうだ。「高橋の教員キャリアはまだ30年あるんだぞ。安定した環境に身を置いたほうがいいんじゃないか」と。
「でも私は、将来は大学教員も見据え、若手教員の育成にも携わりたいと考えています。現在は貧困状態に置かれた子どもたちをサポートするNPO法人の活動にも携わっています。子どもたちだけではなく、教育に携わる自分自身のキャリアの可能性を幅広く考える意味でも、多様な先生が活躍する新渡戸文化学園の環境に魅力を感じました」(高橋さん)

紹介した4人以外にも、新渡戸文化学園では多くの教員が副業に取り組んでいる。また、社会人から直接学べる授業として「Happiness Bridge」というプログラムを導入し、多様な人材を教壇に招いている。
従来の学校運営の常識から考えれば、その取り組みは異例づくしだ。なぜ一連の取り組みを始めたのか。多様な人材を迎え入れてきた平岩 国泰さん(理事長)は、「教員がいきいきと働けるようにすることが目的」だと話す。

「これからの時代を担う子どもたちに求められるのは、自分の力で社会をより良くできる実感を持ち、物事を自律的に考えて判断する力です。そうした子どもたちを育てていくためには、多様な経験を持つ教員が社会のリアルを伝えていくことが必要だと考えました。何より重要なのは、教員自身がいきいきと働き、充実した大人として子どもたちに向き合うこと。これまでの学校で当たり前とされてきた縛りや制限には、あまり意味を感じませんでした」(平岩さん)
一方で、世の中では教員の長時間労働が大きな問題となっている。もとより多忙である教員が副業をすることについて、健康管理や労務管理の面で懸念はなかったのだろうか。
「先生たちが語っていたように、本学園では業務効率化のためにさまざまな取り組みを進めています。労働時間は明確に見える化し、超過勤務の実態があれば早急に察知できるようにしていますし、副業が忙しくなる場合には本業の時間を減らす決断もできます。
また、チーム担任制をはじめとしたフォロー体制によって、1人の先生に過度に依存することのない学校運営を実現しています。オンラインを活用して『学校にいなくても学校に関われる』体制も作っています」(平岩さん)
こうした一連の取り組みから、既存の教育現場は何を学んでいけるのだろうか。公立校を含めて、他校でも学校ダイバーシティを進めていくためには、第一歩として何をすべきなのか。平岩さんはこの問いかけに対して「まずは思想の部分を取り入れられるのではないか」と答える。
「私たちの取り組みをすべて真似することは難しいかもしれないし、すぐに本学園のような学校が増えるとは考えていません。しかし、どんな環境の学校でもあっても、『子どもたちを主語にして取り組みを考える』ことは、今すぐにでもできるのではないでしょうか。
子どもたちを主語にして考えれば、これまでのように教員の働き方やキャリアを制限する体制は必要なくなっていくはず。手を付けられる部分から小さく改革を進めていくこともできます」(平岩さん)
新渡戸文化学園では今後、培ってきたノウハウをもとにして「学校発の学校改革コンサルティング」を手がける構想もあるという。教員がいきいきと働き自由にキャリアを描くことで、子どもたちに新たなロールモデルを見せていく——。そんな学校が増える未来も、案外近いのかもしれない。
(WRITING:多田慎介)
※ 本ページの情報は全て表彰式当時の情報となります。
警察官の仕事への意識を変え、定時退庁や有給休暇取得を推進! 遊び心あふれる異例の広報紙『週刊副署長』を1人で発行し続けた管理職の思い
徳島県警察公務員だけでもボランティアでもない、「副業で起業」という第3の道。 ビジネスの力で地域課題の解決を目指す横須賀市職員の新たな挑戦
一般社団法人KAKEHASHI「社長にはついていけない」。崩壊寸前だった中小企業のストーリー。 10年年表で全員の夢を共有し、掲げた目標を達成し続ける強いチームへ!
株式会社京屋染物店従業員の幸せのために、社長はあえて「トラックと売り上げ」を手放した。 健康経営を実践する日東物流の改革ストーリー
株式会社日東物流自由にキャリアを描き、学校の外でも価値を発揮する。 副業・兼業に取り組む「二刀流教員」が子どもたちの新たなロールモデルになった
学校法人新渡戸文化学園なぜ片頭痛は相談しづらい?有志メンバーの疑問から生まれた「ヘンズツウ部」の活動が、「みえない多様性に優しい社会」をつくる取り組みへと発展!
日本イーライリリー株式会社オンラインだけでなく、リアル空間でも顕在化していたコミュニケーションの課題。 「4人1組」の公式コミュニケーションが職場の活気を取り戻した
日本生命保険相互会社「言われた通りに100%できる人」をもっと評価したい! 1日100食限定、毎日18時までに退勤できる飲食店を実現した佰食屋の思い
株式会社minitts(佰食屋)高校生だって活躍できる。創意工夫が新たな仕事のやりがいにつながる。 人事担当の「介護の楽しさを伝えたい!」という思いから生まれた施策が現場を変えた
株式会社ツクイ