オンラインだけでなく、リアル空間でも顕在化していたコミュニケーションの課題。 「4人1組」の公式コミュニケーションが職場の活気を取り戻した
日本生命保険相互会社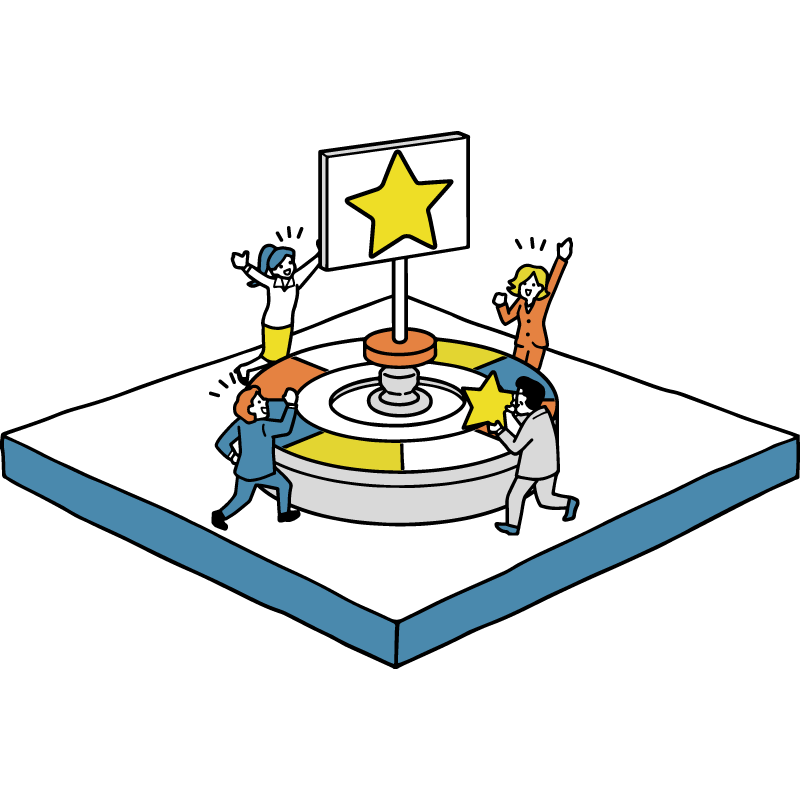
オンラインだけでなく、リアル空間でも顕在化していたコミュニケーションの課題。 「4人1組」の公式コミュニケーションが職場の活気を取り戻した
日本生命保険相互会社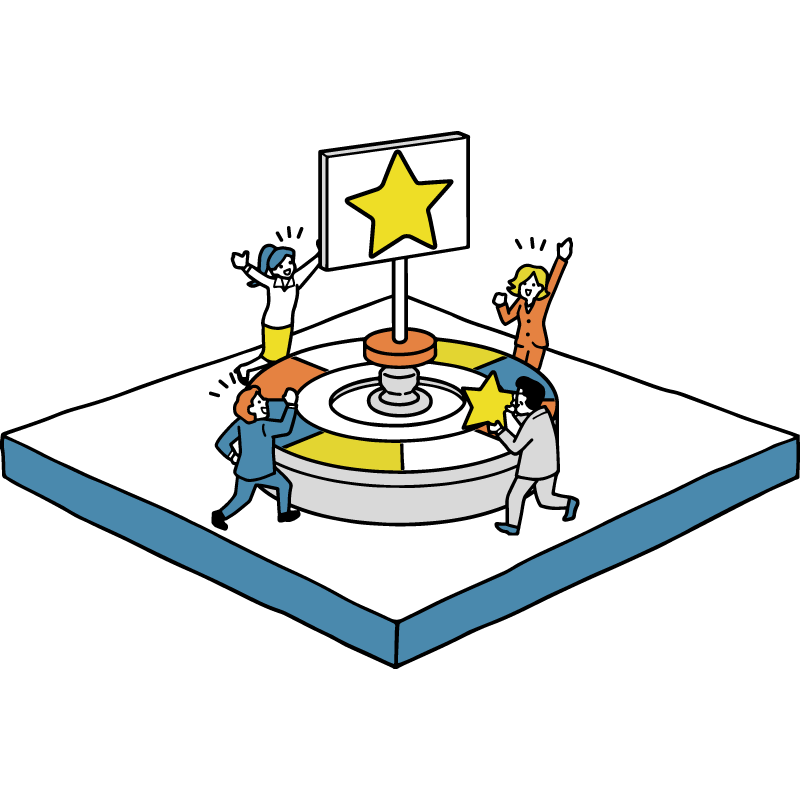
コロナ禍でリモートワークが広がり、オンライン上でのコミュニケーションの課題が盛んに指摘されるようになった。上司と部下の関係性の希薄化を懸念し、1対1で会話をする「1on1」を取り入れる職場も急増している。
だが、コミュニケーションの課題が発生しているのはオンライン空間だけではなく、また上司と部下や、組織メンバーのヨコの繋がりである。
日本生命保険相互会社(以下、日本生命)では、オンラインによるコミュニケーション課題に加えて、オフィスに出社している職員の間で、感染拡大へのおそれから「会話を萎縮する動き」が見られていたという。こうしたコロナ禍でのコミュニケーション課題を受けて始まったのが、4名1組で幅広いテーマについて語り、互いの人となりを理解する場「コミュニケーション4」だった。
約7万人の職員数を誇る日本生命。近年では人材の多様化が進み、さまざまな価値観を持つ人が集まる組織となるとともに、マネジメントの難易度は高まり続けていた。加えてコロナ禍ではワークスタイルも変化。リモートワークにおけるコミュニケーションはもちろん、オフィスでのコミュニケーションにも課題が表れていたという。
「当社は7万人の職員のうち約5万人が営業職です。お客さまを支える重要な役割を担っていることから、コロナ禍でも一定数が出社して働いています。オフィス内では感染防止に向けた行動を徹底する一方で、新型コロナウィルス感染症対策の観点から、ざっくばらんに話せる機会や雰囲気は減少し、隣に座っている人ともメールのやり取りで会話するなど、コミュニケーションの萎縮が見られました」
そう話すのは、コミュニケーション4の取り組みを主導する宇田 優香さん(人材開発部 輝き推進室 室長、ダイバーシティ推進部長)。この状況を変えるため、すでに導入していた上司・部下の面談だけでなく、「ヨコ」「ナナメ」のつながりを強化する施策が必要だと考えていた。
「コロナ禍でも実施できるコミュニケーション施策として考案したのが『コミュニケーション4』です。現状の職場風土を変えていくことはもちろん、大きな目的としてインクルージョンの促進を置いていました。互いの人となりをよく知ることで部署内のコミュニケーションを活性化し、闊達に会話・議論ができる職場風土を醸成。それによって生産性向上や働きがい向上、新たなアイデア発掘などにつなげたいと考えていました」(宇田さん)

コミュニケーション4の特徴は、明確な運営マニュアルが定められ、開催方法や話し合うテーマなどが分かりやすくパッケージ化されていることだ。「年5回以上実施」「4名単位で参加」「1回につき30分の意見交換」を基本として、各地の拠点へ展開されている。
眞砂 捷さん(人材開発部 輝き推進室 課長補佐)は、運営マニュアルやパッケージの作成にあたって中心的な役割を果たした
「運営マニュアルを明確に示しているのは、会社として共通の方向に進むため。加えて、現場が混乱しないようにするためでもあります。現場にかかる負荷をできるだけ小さくすることで、スムーズに実施してもらいたいと考えたのです。もちろん、事務局から提供しているテーマと異なる内容を現場で自由に話してもらっても問題ありません」(眞砂さん)
運営マニュアルでは、進め方として「必ず全員が話すこと」「否定は厳禁」などの基本的なルールを提示。30分の時間を有効活用するためのタイムテーブルも示されている。
加えて眞砂さんが力を入れたのは、各回のテーマ設定だ。たとえば第1回の「テーマトークでお互いを知る」回では、「好きな食べ物・嫌いな食べ物」「最近のマイブーム」「ストレス解消法」といったテーマからルーレットで選べるというゲーム性を持たせた。
「参考にしたのは、昔放送されていたテレビ番組のサイコロトークです。オンラインで実施するグループがあることを踏まえて、Excelシート上でテーマを選べるルーレットを作成し、提供しました」(眞砂さん)
こうしたコンテンツは、輝き推進室内で約1カ月をかけて意見を出し合いながら固めているという。SDGsや健康経営などのテーマを取り扱う際は社内の専門部署にもアドバイスをもらう。現場へリリースする前には輝き推進室内で試験運用し、分かりにくさがないかを検証するという徹底ぶりだ。

コミュニケーション4の取り組みを各現場はどのように受け止め、活かしているのだろうか。実際に運用を進めている部署の声を紹介したい。
日本生命京都支社の次長を務める立松さんは「コミュニケーション4は、組織力の向上に間違いなく役立っている」と手応えを語ってくれた。
「輝き推進室からコミュニケーション4のパッケージが届いたときには、その問題意識に共感しました。京都支社ではさまざまな職種で中途入社者が増加し、障がいのある職員も年々増えていて、多様な価値観を持つ人が集まる組織となっています。そうしたなかでコロナ禍となり、支社内のコミュニケーション活性化を課題としていました」
立松さんは導入時をそう振り返る。
とはいえ、多様な参加者が集まる場で、これまでは話したことのないテーマのコミュニケーションが盛り上がるのか、不安もあったという。運営実務を担当した支社お客様担当室長の宮道さんは、「プライベートについて話すことには、抵抗を持つ人もいるかもしれないと感じていた」と話す。
「ただ、実際に開催してみると、『自分のことを話せてよかった』『話を聞いてもらえてよかった』という感想が想像以上に多かったのです。私が考えていた以上に、みんながこの取り組みを好意的に捉えてくれました。コミュニケーション4がパッケージ化されていたことで、運営側としては戸惑うことなく実施できたと思います」(宮道さん)
印象に残っている場面として、立松さんは障がいのある職員が参加したコミュニケーション4を挙げる。そこでは参加者の得意なことや困っていることが盛んに共有されていたという。
「障がいのある職員は、前職の経験から『京都中の地理に詳しい』ことが強み。一方では障がいのため満員電車に乗れず、朝は早く出社しているのだと話していました。朝一番に来ても出社している職員は少なく、仕事は手持ち無沙汰になりがちです。一方で別の職員は、朝一番に対応しなければならない業務をたくさん抱えて困っていました。そうした情報が共有され、互いの勤務時間帯を生かして助け合うようになったのです」(立松さん)
現在はチーム内などの近しい間柄で実施しているコミュニケーション4。京都支社では今後、チームや部署を超えて、支社全体を考える場を設けていきたいと考えている。

回を重ねるごとに活発なコミュニケーションが交わされるようになったコミュニケーション4。現在では、輝き推進室が提供する運営マニュアルやテーマに沿ったものだけではなく、独自に会話する場を設けたり、自分たちの働き方について話し合ったりする場が生まれているという。
「所属独自のテーマを設定しコミュニケーション4を実施した事例や、コミュニケーション4の場で盛り上がり、その後はオンライン飲み会につながっていったというエピソードも聞いています。この取り組みをきっかけにして、社内のコミュニケーションのあり方が変わりつつあると感じています」(眞砂さん)
「もともと人が好き、話すのが好きという職員が多いためか、公式のコミュニケーション空間があることを喜んでくれている人が多いようです。コロナ禍で感染防止を強く意識し、必要以上に人とディスタンスを取っていた職員も少なくなかったのでしょう。そんな職場へ、人事の立場から『話していいんだよ』とガイドラインを示したことで、心のつかえが外れたのではないかと思います」(宇田さん)
今後、日本生命ではコミュニケーション4の活動をどのように進展させていくのだろうか。宇田さんは一つの有力アイデアとして「全国版コミュニケーション4」を検討していると教えてくれた。
「今は職場のチーム内など、やりやすいところから取り組んでいますが、今後は組織全体の活性化を図っていきたいと考えています。所属を飛び越えて全国からさまざまな職員が参加できれば、これまでにない価値が生まれるはず。今後もテーマを吟味し、魅力的なパッケージを提供していきたいですね」(宇田さん)
(WRITING:多田慎介)
※ 本ページの情報は全て表彰式当時の情報となります。
警察官の仕事への意識を変え、定時退庁や有給休暇取得を推進! 遊び心あふれる異例の広報紙『週刊副署長』を1人で発行し続けた管理職の思い
徳島県警察公務員だけでもボランティアでもない、「副業で起業」という第3の道。 ビジネスの力で地域課題の解決を目指す横須賀市職員の新たな挑戦
一般社団法人KAKEHASHI「社長にはついていけない」。崩壊寸前だった中小企業のストーリー。 10年年表で全員の夢を共有し、掲げた目標を達成し続ける強いチームへ!
株式会社京屋染物店従業員の幸せのために、社長はあえて「トラックと売り上げ」を手放した。 健康経営を実践する日東物流の改革ストーリー
株式会社日東物流自由にキャリアを描き、学校の外でも価値を発揮する。 副業・兼業に取り組む「二刀流教員」が子どもたちの新たなロールモデルになった
学校法人新渡戸文化学園なぜ片頭痛は相談しづらい?有志メンバーの疑問から生まれた「ヘンズツウ部」の活動が、「みえない多様性に優しい社会」をつくる取り組みへと発展!
日本イーライリリー株式会社オンラインだけでなく、リアル空間でも顕在化していたコミュニケーションの課題。 「4人1組」の公式コミュニケーションが職場の活気を取り戻した
日本生命保険相互会社「言われた通りに100%できる人」をもっと評価したい! 1日100食限定、毎日18時までに退勤できる飲食店を実現した佰食屋の思い
株式会社minitts(佰食屋)高校生だって活躍できる。創意工夫が新たな仕事のやりがいにつながる。 人事担当の「介護の楽しさを伝えたい!」という思いから生まれた施策が現場を変えた
株式会社ツクイ