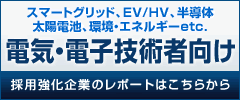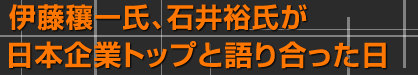 |
 |
|
マサチューセッツ工科大学(MIT)・メディアラボが1月に東京で開いたイベント。日本の企業トップをゲストに招き、聴衆に広くオープンにされた初のイベント。その熱気をレポートする。
(取材・文/広重隆樹 総研スタッフ/宮みゆき 撮影/栗原克己)作成日:12.02.28
|
メディアテクノロジー研究で世界最先端を走るマサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ。タンジブル・ユーザーインターフェイスの開発者、石井裕氏が副所長を務め、昨年からは、伊藤穰一氏が第4代所長に就任したことから、日本のエンジニアや研究者にとってもさらに身近な存在になった。
そのメディアラボが1月17日、東京・汐留の電通ホールで「MIT Media Lab @Tokyo 2012」を開催した。これまでも日本国内でスポンサー企業を対象にしたクローズドなミーティングはたびたび開いていたが、今回はより幅広いゲストと聴衆を迎えての開催。メディアラボの未来像やその価値を、より多くの人々に伝え、今後そこから生まれる成果を日本経済の活性化に結び付けることを目的としたものだ。
冒頭、挨拶に立ったのは1985年にメディアラボを設立した、ニコラス・ネグロポンテ氏。彼は建築学部出身で、ディジタル革命のインパクトを『ビーイング・デジタル』に著し、革新的な知見をもたらした。
|
ネグロポンテ氏は日本での開催であることを意識し、MITへの海外留学生で日本からの学生が多かった1980年代の終わりを振り返る。この頃、メディアラボの寄付金収入の内、45%は日本企業からのもの。50人いるリサーチ・フェローの内、14人が日本人で、日本語はラボ内の第2言語といわれた。「日本との絆は、メディアラボのDNAのようなものだ」とネグロポンテ氏は言う。
しかしその後、日本との関係は相対的に薄まることになる。日本企業がイノベーションを生み出せなくなったことともそれは相関関係があるのかもしれない。 |

マサチューセッツ工科大学
メディアラボ初代所長 ニコラス・ネグロポンテ氏 |
|
メディアラボ初代所長のネグロポンテ氏がバトンを渡すように紹介したのが、第4代所長の伊藤穰一氏だ。伊藤氏がまず指摘したのは、インターネットの重要性だ。人類の歴史は「インターネット創成前とその後に時代区分される」とまで言う。その上で、先のネグロポンテ氏の話を受け、「重要なポイントは、インターネットは単なる技術ではないということだ。インターネットは一つの哲学であり、アートや社会との関係を切り離すことはできない」と述べる。それに伴って、イノベーションのあり方も変わらざるを得ないというのだ。
国家や大企業がエキスパートを集めて、中央集権的に研究開発を進めるのが、「前インターネット」型のイノベーションだとすれば、「ポスト・インターネット」に主流になったのは分散型のイノベーションだ。 |

マサチューセッツ工科大学
メディアラボ第4代所長 伊藤 穰一氏 |
中央管理型イノベーションと、分散型イノベーションの競争で、分散型が勝利した。かつて中央研究所の奥深い部屋で議論され、独占されるのが常だった技術が、こうして小さなベンチャー企業や学生にも参加できるような形でオープンにされていく。
「中央管理型は、あらゆるリスク、あらゆる可能性を設計しながらものを作っていく。そうではなく、とりあえず作ってやりながら考えるというのがインターネットの流儀。MITの同僚、デビッド・クラークの言葉に『Rough Consensus, Running Code=(ゆるやかな合意でとにかくソフトウェアを書け)』というのがあるが、まさにこれはインターネットにおけるイノベーションのあり方を示している。インターネットで本当に影響のあるサービスや技術は、少人数で開発されていることが多い。Webブラウザ、TCP/IP、そしてTwitter然りだ。大学やベンチャー企業の中の少人数のチームが、オープンなプロトコルの中でゆるやかに育っている」
イノベーションのコストが相対的に小さくなっているのも、「ポスト・インターネット」世界の特徴だ。伊藤氏はベンチャーキャピタリストの立場から、「どれが当たるか分からないが、いろいろなことをやってみて、その中でうまくいくものを応援する」という手法についても語った。伊藤氏は、インターネットは知識社会のあり方までをも変容させたと指摘する。
「知識を頭に蓄積することにはさして意味がない。必要なときにネットワークから引っ張ってくる力(The Power of pull)こそが重要。あらかじめ見通しのつく全体地図を求めるのではなく、手元にたしかなコンパスさえあればいい」
こうした知識社会を渡り歩き、イノベーションを生み出すためにもう一つ重要なのが、アジャイル(俊敏性)だ。
「じっくりと何年もかけて企画書を作り、それからお金を集めようとしても、たいていは失敗する。いまインターネットで成功している会社は、最初の企画と、実際の事業内容は全く違うものになっていることが多い。投資家たちも、最初の企画がうまくいくとは思っていない。どんどん企画内容が変わっていく。その時のアジリティ(Agility)をどう備えていくかということが大切なのだ」
最後に伊藤氏は創発型の民主主義に基づくメディアラボの組織体制についても触れた。メディアラボでは一人の研究者が複数の専門分野に精通しており、さらに異分野の研究者がそれぞれ違う学問領域をクロスさせながら議論していく。議論する上で重要なのは、論文だけでなく実際にモノを作って話すこと。そうすることでより精密な議論が可能になる。
「メディアラボの個々の研究は一つのコンテナだと考えればよい。それらがネットワーク化して一つのプラットフォームを形成している。これからは異業種の会社が一緒になってメディアラボをプラットフォームとして、お互いがコラボレーションを重ね、新しいエコシステムを作っていくという形ができればよいと思う」と、話を締めくくった。

マサチューセッツ工科大学
メディアラボ副所長 石井 裕氏 |
改めて紹介するが、今回のカンファレンスのテーマは、「The Power of Open, Scaling the Eco System」。「ポスト・インターネット」の時代において、循環する産業や技術のエコシステム(生態系)をいかに生み出すかを、目下の最大の課題としてとらえ、そこに迫る議論を巻き起こすことが狙いだった。
こうした議論に、「イノベーションを生み出す源泉とは何か」という観点からアプローチしたのが、「変革とビジョン」と題したメディアラボ副所長・石井裕氏の講演だ。同氏の高速プレゼンテーションの様子はTech総研でもたびたび紹介しているので、読者にもおなじみのものだろう。 |
そうした時代に求められる人間の資質を、石井氏は、
1)「出杭力」(でるくい力)=打たれても打たれても、突出し続ける力、
2)「道程力」=原野を切り拓き、まだ生まれていない道を独り全力疾走する力、
3)「造山力」=誰もまだ見た事のない山を、海抜零メートルから自らの手で造り上げ、そして初登頂する力──として抽出する。いわば「石井三力」だ。
「道程力」とは聞き慣れない言葉だが、石井氏の表現によれば、「100mトラックを人より速く走る事は真の競創ではない。誰も分け入った事の無い原野を一人切り拓き、まだ生まれていない道を一人全力疾走すること、それが競創だ。そこには観客も審判もストップウォッチも存在しない」
という厳しいもの。それはこれまでの私たち=日本企業の競争概念を変えるものだ。このように、飢餓感や屈辱感をバネにしながら、一人未踏の原野に分け入ろうと決意する者たちが、高いレベルでコラボレーションしていくことにこそ、技術革新の鍵はある。
「技術革新とはコラボレーションであり、オープンな環境のもと、アイデアを交換して一緒に物事を構築することだ」
アート、デザイン、サイエンスが坩堝のなかで融合する。分野や専門性の垣根を越えていく。哲学的な領域まで踏み込んで、「ポスト・インターネット」の未来社会を設計する──こうしたメディアラボの姿は、21世紀のルネッサンス的な思考の母胎になりうると、石井氏は強調した。
イベントでは、伊藤穰一氏、黒川清氏(政策研究大学院大学アカデミックフェロー)、宇治則孝氏 (NTT・代表取締役副社長)、角川歴彦氏 (角川グループホールディングス・取締役会長)、新浪剛史氏 (ローソン・代表取締役社長CEO)、森隆一氏 (電通・特別顧問)による対論およびパネルディスカッションも行われた。さらに、終日に渡り、MITメンバーや日本企業のキーパーソンを交えたディカッションが続いた。
|
イベントでは、MIT Media Labの教授、教員、メンバー、ゲスト、生徒たちが様々なトピックについて取り組むアンカンファレンスも開催された。アンカンファレンスとは、事前に発表者や講演内容が決まっておらず、当日参加した人が自分の話したい内容を発表する。一般的なセミナーとは異なり、講師と聴講者の距離は大変近く、発表中でも聴講者からの質問に応じたり、参加者全員で作り上げるカンファレンスである。 |

César A. Hidalgo氏 、Benjamin Waber氏
「経済の将来予測」 |

菅野 薫氏 (株式会社電通)
「製品にコミュニケーションをビルトインする」 |

国松 敦氏 (株式会社東芝 セミコンダクター社)
外村 喜秀氏 (NTT未来ねっと研究所) 「元・現客員研究員と議論する過去・現在・未来への期待」 |

羽田 昭裕氏 (日本ユニシス株式会社)
「グリーンマーケティングとエネルギーハーベスティング」 |

Natan Linder氏 、Ryan Chin氏
「現実を通した拡張と相互作用」 |

Kent Larson氏
「住宅および自動車(そしてシャツまで)の スマート・カスタマイゼーション」 |

Joseph A. Paradiso氏
「パーペイシブ・センシングとスマート・エネルギー」 |
このレポートを読んだあなたにオススメします
「隠喩概念空間連続跳躍」の超絶技法から生まれるイノベーション
石井裕教授と語るライフイベントとテクノロジーの未来
1月26日、リクルートマーケティングパートナーズが主催するイベントで、マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ副…

今、世界で起きていること。これから世界で起こること
出井伸之×石井裕が語る、「次」のために何が必要か?
元ソニーCEO出井伸之氏とMIT石井裕教授が「今、世界で起きていること。日本に見えていない世界の視点」を語り合う特別対…

あらゆるボーダーが消えていくネット社会のグローバリゼーション
出井伸之×石井裕 日本からは見えていない世界の視点
Apple、Twitter、Facebook etc. 世の中を大きく動かすビジネスやサービスは、いまやほとんどが海外…

現地対談!グローバル人材に必要なのは、他流試合を厭わないこと
MIT石井裕教授と語る“世界で闘える人材”育成とは
マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ。世界を刺激し続けているデジタル技術の研究・教育拠点だ。今回はそのMIT…

日本品質とスペック至上主義の呪縛を超えろ!
石井裕×及川卓也が語る「イノベーションの流儀」とは
「未来を創り出す」ために、いま何をすべきなのか。これからのイノベーションはどこからどのように生まれるのか。MIT石井裕…

あなたのメッセージがTech総研に載るかも