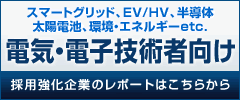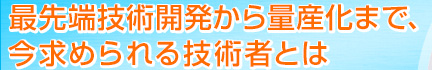 |
 |
|
東芝の好業績を支えるNAND型フラッシュメモリ。その国内唯一の生産拠点、四日市工場では今年度も大規模なエンジニア採用計画がある。2Dメモリの微細化と3Dメモリの量産化に向けて、いま求められる人財像を工場幹部に聞いた。
(取材・文/広重隆樹 総研スタッフ/伊藤理子 撮影/早川俊昭)作成日:14.06.25
|
東芝は5月に、2013年度(2014年3月期)は売上高で前年比13.5%増となる6兆5,025億円を達成したことを発表した。連結営業利益も前期比13%増の2,908億円と、前年比47%の増益を達成。さらに2014年度は、1990年度を上回る過去最高益を目指す。
東芝の業績復活の中心的役割を担うのが、NAND型フラッシュメモリ(以下NAND)事業。NANDを生産する「セミコンダクター&ストレージ」部門の前期の営業利益は2,258億円となり、全社利益の8割近くを稼ぎ出す格好となった。
まさに東芝グループの稼ぎ頭、セミコンダクター&ストレージ社の、そのなかでも最重要の開発・生産拠点である四日市工場。いまここでどんな開発が行われ、そこではどんな技術者が求められているのか。東芝のメモリ開発の現在と今後について、渡辺寿治・先端メモリ開発センター技監と、柴山耕一郎・四日市工場長附に話を聞いた。

東芝セミコンダクター&ストレージ社
メモリ事業部先端メモリ開発センター 技監 渡辺 寿治氏 |
四日市工場でこれまで量産されていたNAND型フラッシュメモリは、線幅ルール19nm(ナノメートル)。その構造を維持したまま、さらに微細化を進めた19nm第2世代の量産も並行して行われてきた。NANDにおける微細化の進化はやむことなく、この4月には世界で初めて15nmプロセスを用いた128ギガビットの製品を開発。今後19nm第2世代から切り替えて順次量産が始まる予定だ。 こうした微細化技術を極めながら、同時にメモリセルを3次元方向に多段積層する3次元NANDの開発も進めるというのが東芝の戦略。いわば15nmによる「微細化」と3Dメモリによる「高集積化」を同時に追求しようというのだ。 それにともなって四日市工場における生産体制も着々と増強されている。敷地内で「Y5」と呼ばれる第5棟のクリーンルームは昨年から始まった第2期分の工事が完了次第、15nmプロセスの量産に使われる。一方、3Dメモリについては3D構造固有の専用工程を確保するため、「Y2」を建て替える工事がこの9月から始まる。「Y2」は、従来型メモリを生産する既存の「Y3」「Y4」と連携し、今後3Dメモリ生産体制の重要な一角を担うことになる。このように既存設備を最大限活用することで、3Dメモリへの移行期の不要な投資を抑えようという狙いがある。 |
世界最小クラス15nm NANDの量産が進む一方で、3Dメモリ時代に備えた開発と生産体制構築も同時に行われるなか、それを支える技術者はまだまだ足りない。従来の2D NANDから3D NANDへシフトする社内技術者も少なくないが、同時に東芝は、外部からメモリ開発に長けた技術者を求めている。
「2Dメモリの微細化をさらに進めるためには、プロセス開発ではエッチング、リソグラフィー、デバイス開発ではメモリセル、CMOSトランジスタ、評価・シミュレーション技術などの要素技術と、さらにそれらを組み合わせるインテグレーションのノウハウが求められます。ピンポイントにここだけを強化というのではなく、キャリア入社者の力を借りて自社技術の多様性を広げたいというのが私たちの考え方です」
と言うのは、渡辺寿治・先端メモリ開発センター(AMDC)技監だ。
一方、3Dメモリについては、国内では東芝しかやっていない“門外不出”の技術。だから外からは見えないことが多く、自分の技術がどのように適合するか判断がつかない技術者も多いはずだ。
「しかし2Dと3Dで技術が切断されているわけではなく、これまでの経験はすべて活きると考えていいと思います。DRAMであれ、ロジックLSIであれ、イメージセンサであれ、それぞれの分野で最先端の技術開発をしてきた人には、デバイスに対する基礎知識と応用力をお持ちです。
例えば、多結晶シリコン上にトランジスタを作成する技術、あるいはアスペクト比の高いキャパシタ開発の技術などは、3Dメモリ開発に最も近い。そのほかにもさまざまな経験が活かせるはず。それに加えて仕事に取り組む熱意がある人なら、3Dメモリの技術をすぐにキャッチアップできると思いますし、これからの開発を牽引してくれるはずです」
四日市では、2Dメモリの微細化、3Dメモリの量産が目下の課題だが、半導体技術のロードマップはさらに先に続く。例えば、ReRAM(抵抗変化型)など、次世代を視野に入れた研究開発も進む。
「東芝には最先端分野を研究する半導体研究開発センターがあり、それと私の所属する開発部門、あるいは工場の試作部門や量産部門が緊密な関係を持ちながら動いています。研究─開発─量産のそれぞれのフェイズを人が行き来し、知見を積み上げるというローテーションもよく行われます。次世代メモリを単なる研究室の中の構想や実験だけに止めず、将来の製品化を見据えて開発していきたいと考えているような人にとっても、ここはよい場所だと思います」
と、渡辺氏は言う。

東芝セミコンダクター&ストレージ社
四日市工場 工場長附 (兼 解析・検査計測技術部長) 柴山 耕一郎氏 |
四日市工場における本格的なキャリア採用計画は昨年度に続くもの。事業拡大の方針を受けての採用強化という流れに変わりはないが、昨年度と今年度では募集対象に若干の違いもある。 プロセス開発を行う半導体工場は一種の化学プラントともいえる。純水、ガスのようなユーティリティ、空気清浄化技術や薬品の管理ノウハウなども欠かせない。さらに今後、建屋の増改築や各種設備の台数が増えるにつれて、工場そのものの維持・管理技術もこれまで以上に求められる。半導体設計やプロセス開発だけでなく、機械系エンジニアやプラントエンジニアにとっても、東芝・四日市は注目の職場ということができる。 |
これまで四日市工場の技術者にインタビューする機会が何度かあったが、そのたびに職場の雰囲気について尋ねてきた。転職希望者にとっては、これはけっこう重要な関心事だからだ。
「工場幹部が臨席する重要会議だと、普通、若手の担当者は萎縮しがちですが、ここに限ってはそんなことはないですね。幹部がいようがいまいが、フランクに話し合っている。幹部社員もそれを見とがめることなく、きちんとその話を聞いている」
と柴山氏が言えば、
「何千人もが勤務する大きな組織だからこそ、そこかしこでのコミュニケーションをよくしないと仕事が回っていかないんですよ。こじんまりと籠もるというより、ワイワイみんなでやるという雰囲気ですね」
と渡辺氏。
四日市工場を活性化させるカギはコミュニケーションにある。渡辺氏が面白いことを言っていた。
「円筒形の茶筒があったとして、上面から覗く人には、それは“円”にしか見えない。側面からしか見ていない人には“四角”にしか見えない。コミュニケーションが不足していると、それぞれがこれは“円”だ“四角”だと言い張って埒が明かない。一方向からの見え方にはほかにはない特徴もあるけれど、同時に限界もある。互いの認識をすり合わせ、全体を見ようとすることがコミュニケーションだと思うんです」
別の視角からモノが見えている経験者を採用し、その視点を活かしてより総合的な視野を開いていく。キャリア採用にはそういう面もあるのだ。
あえてもう一つキーワードを加えるとすれば、「インターナショナル」。
「設計・開発におけるサンディスクとの協業に加え、製品の後工程ではアジアの製造拠点とも密接に連携しています。装置メーカーは北米に多いですし、ユーザー企業はそれこそ全世界に広がっている。海外のお客さんや協力企業と会うために海外出張も頻繁ですよ。ここは世界につながっているんです」
と、渡辺氏は語っている。
国内半導体業界の再編が続く中で、自らの専門的な技術領域と会社の投資方針が合わずに、転職を考える半導体技術者は少なくない。NANDの国際的競争優位性を保持しながら、国内で一貫して研究開発・量産体制を続ける東芝は、彼らにとって“希望の星”であることは間違いない。
ただ単に「残っているのは東芝だけしかなかった」というネガティブな選択で、ここを選んでほしくはないと、関係者は口をそろえる。東芝だからこそやってみたいことがあった──というポジティブな姿勢を見せてほしい。そして、四日市でしか得られなかったものをぜひ自分の手でつかんでほしい。
「私自身も半導体技術者として最初はDRAMを担当し、その後、海のものとも山のものともわからないころからNANDに関わってきました。それがようやく製品化され、世の中に広く普及するまでを見てきました。NAND型フラッシュメモリはデジタルカメラ、スマートフォン、SSDなど各種応用製品に使われることで人々のライフスタイルを変えて来ましたし、これからも変えていきます。サーバ・ストレージなどの企業向け利用も今後広がり、世界中のビジネスのあり方までを変えようとしています。それだけ世の中に影響力のある仕事ができて本当によかった。これからここで働く技術者にも、そうした醍醐味を味わって欲しいと思いますね」
と、渡辺氏。
「四日市工場が設立されて今年で22年になります。地元に密着した工場ということで、環境問題には以前から気を遣ってきました。例えば工場の拡張にあたっては、そこに絶滅が危惧される希少動植物がないかを調べ、それをきちんと保存するなどしましたし、地元の人たちと一緒に工場周辺の里山づくりにも参加しています。また、地域の小中学校で出前授業を開いたり、工場の夏祭りには近隣の皆様をお招きして地域との交流に努めています。企業の一員というだけでなく、地域の一員になるという思いでぜひ参加してほしいと思います」
と、柴山氏。
東芝セミコンダクター&ストレージ社四日市工場。ここが日本の半導体産業にとって、これから先も“希望の星”であり続けるためには、次の技術開発に向けて共に歩み出す技術者が必要だ。
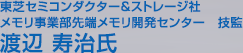
1982年入社。半導体技術研究所、半導体研究開発センターなどにてメモリ技術開発に従事。以降、メモリ事業部、先端メモリ開発センターで先端メモリのデバイス開発を経て、2012年より現職。
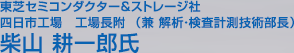
1988年入社。回路部品事業部などを経て、四日市工場にて半導体メモリの生産技術、品質管理技術に従事。2013年より現職。
このレポートに関連する求人情報です
キオクシア株式会社 ◆フラッシュメモリ世界シェア2位◆売上高1兆2821億円(2023年)◆世界最大級の開発・製造拠点を持つ日系半導体メーカー★Web面接実施中
![]() 半導体メーカー総合職/営業推進・販促・貿易・物流・財務・総務
半導体メーカー総合職/営業推進・販促・貿易・物流・財務・総務
- 仕事の概要
- 総合職(営業推進・販売促進・需給管理・貿易管理・物流管理・財務・総務/不動産担当)
- 対象となる方
- 営業・販促・需給管理・物流管理・輸出管理・資金管理・会計・決算・不動産業務などの経験者◎業界…
- 勤務地
- ■本社…東京都港区芝浦3-1-21/JR「田町駅」徒歩2分■四日市工場…三重県四日市市山之一…
- 年収例
- 850万円/37歳(既婚・子2人/月給40万円+各種手当+賞与) 610万円/28歳(独…
このレポートに関連する企業情報です
メモリ及び関連製品の開発・製造・販売事業及びその関連事業 ◆主な関係会社 日本:キオクシア岩手株式会社 キオクシアシステムズ株式会社 キオクシアエンジニアリング株式会社 キオクシアエトワール株式会社 等、海外:アメリカ・ヨーロッパ・シンガポール・台湾・韓国・中国・イスラエル・イギリス続きを見る
このレポートの連載バックナンバー
人気企業の採用実態
あの人気企業はいま、どんな採用活動を行っているのか。大量採用?厳選採用?社長の狙い、社員の思いは?Tech総研が独自に取材、気になる実態を徹底レポート。

このレポートを読んだあなたにオススメします
仕事と育児を両立。計算機リソグラフィを究めて20年
東芝のきらめく女性エンジニアと、進化する半導体技術
![]() 今、改めて企業における女性社員の活躍や、責任ある立場への抜擢が推進されている。東芝グループにおいては女性役職者の割合が…
今、改めて企業における女性社員の活躍や、責任ある立場への抜擢が推進されている。東芝グループにおいては女性役職者の割合が…

東芝はなぜ、TSV技術による世界初の16段積層メモリを開発できたのか
「融合」で進化する、東芝の半導体パッケージング技術
![]() 東芝がこの8月に世界に先駆けて発表した、16段積層のNAND型フラッシュメモリ。そこにはTSVと呼ばれる配線技術をはじ…
東芝がこの8月に世界に先駆けて発表した、16段積層のNAND型フラッシュメモリ。そこにはTSVと呼ばれる配線技術をはじ…

転職後14年目と転職1年目社員がディスカッション
転職者は東芝でのキャリアパスをどう描くか
![]() 「これから先も日本で半導体の研究開発に携わるのなら、東芝しかないと思った」──東芝セミコンダクター&ストレージ社への転…
「これから先も日本で半導体の研究開発に携わるのなら、東芝しかないと思った」──東芝セミコンダクター&ストレージ社への転…

ソフトウェア系部門長が語る、東芝におけるシステム・ソフトウェアの未来
東芝の半導体・ストレージ事業を創るソフトウェア技術
![]() 大規模なエンジニア採用を続ける東芝セミコンダクター&ストレージ社(S&S社)。今回は、ファームウェア、ソフトウェア関連…
大規模なエンジニア採用を続ける東芝セミコンダクター&ストレージ社(S&S社)。今回は、ファームウェア、ソフトウェア関連…

東芝四日市・半導体技術幹部が徹底議論
東芝の先端メモリ研究開発戦略と転職技術者への期待
![]() NAND、BiCS、さらに次世代新規メモリの開発に向けて怒濤の進撃を続ける東芝セミコンダクター&ストレージ社。メモリの…
NAND、BiCS、さらに次世代新規メモリの開発に向けて怒濤の進撃を続ける東芝セミコンダクター&ストレージ社。メモリの…

あなたのメッセージがTech総研に載るかも