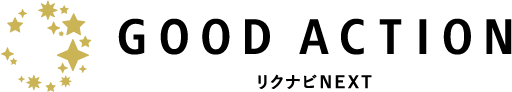第10回GOOD ACTIONアワード 表彰式レポート

2024年3月5日、第10回「GOOD ACTION アワード」の表彰式を開催しました。多数のご応募の中から、最終審査を経て選出された「入賞」3取り組みと「Cheer Up賞」4取り組みを発表。各受賞取り組みを推進された皆さまや審査員のコメントを交えて、当日の模様をご紹介します。
入賞
「子どもは預けたいけど、働きたくない」と言われた保育園。余裕を持った人員配置やICT化で保育士の働きやすさを実現し、「遠くても、通いたい保育園。」へ
社会福祉法人山ゆり会

受賞のポイント
- ・国基準の1.5倍の人員配置と処遇改善
- ・他業種のナレッジやICTを導入
- ・キャリアパスシートの運用
→現場の負担軽減を実現し、紹介で新規入職が続く職場へ。キャリア支援により保育士のモチベーションも向上。
審査員コメント:アキレス 美知子氏
この10年で保育園の数は増え、待機児童数は減りました。一方で保育士さんは取り合いとなり、有資格者の6割が保育の現場で働いていない現状があります。そうした中で山ゆり会は就業規則の見直しやICT活用、処遇改善などの工夫を重ねました。この取り組みの中で注目すべきはキャリアパスを提示していること。保育士さんは日々の仕事で子どもに向き合うことにやりがいを覚えると思いますが、それだけではなく、頑張りを通じて自分の成長を実感できる機会を作っていることに感激しました。
受賞者コメント:社会福祉法人山ゆり会 法人本部長/松山 圭一郎氏
地域によっては待機児童問題が解消した途端に定員割れとなる保育園もありますが、働き手である保育士はなかなか見つかりません。私はこの法人の2代目として2009年に現職に就任し、2013年頃から10年かけて職場を変えてきました。取り組みの結果、現在では職員の約3割が現役保護者や元保護者、そして約2割がスタッフからの紹介で入職しています。出産や結婚を機に一度離職した人も、時間の経過とともに再び戻ってきてくれる職場となりました。私たちの取り組みが業界発展の一助になれば何よりです。
誰もが自分らしく働ける「実働5時間の林業」。企業としての成長を手放す姿勢に共感し、全国から和歌山へ人材が集う
株式会社中川

受賞のポイント
- ・「木を植える」新たな事業形態を確立
- ・1日6時間労働、休みやすい日当制へ
- ・社員の独立・起業を支援
→高い給与水準を実現して県内外から人材確保。さらに9都県で7社が独立を果たし取り組みが各地域へ波及。
審査員コメント:守島 基博氏
この取り組みの素晴らしさは、「働きがい」と「働きやすさ」をともに追求していることにあります。日本企業はさまざまな面で働きやすさを追求してきましたが、人はそれだけでは弛緩してしまうのも事実。株式会社中川では独立のチャンスを与えるなどして働く喜びをもたらしています。また、働く人に真に寄り添っていくためにビジネスモデル自体を変えている点も本当に素晴らしい。木を切って市場に送り出す林業から、木を植える林業へと転換し、ビジネスの範囲を広げながら成長限界点も設け、ビジネスとしてのサステナビリティを向上させています。
受賞者コメント:株式会社中川 創業者 森林施業プランナー/中川 雅也氏
自然を相手にする林業は、きつい仕事内容や危険な作業などのネガティブなイメージを持たれがちです。しかし私は、林業にはまだまだ可能性と伸びしろがあると思っています。私自身が林業に挑戦して理想的な働き方を実現したように、これからも全国各地に「林業が楽しい」と考える仲間を増やし続け、子どもたちの世代に豊かな自然資産を残していきたいと考えています。
半分の労働時間で売上倍増。漁師の常識を覆す「完全受注漁」が家族に幸せをもたらした
邦美丸

受賞のポイント
- ・消費者へ直販する完全受注漁に転換
- ・地元同業者へナレッジ共有
- ・異業種からの新規参入者も受け入れ予定
→労働時間を削減しながら売上・利益は大幅増。働き方改革を成し遂げたことで家族の笑顔を取り戻した。
審査員コメント:株式会社リクルート リクナビNEXT編集長 藤井 薫
働き方改革に「働く」の中だけで取り組んでも限界があります。顧客の需要をつかみ、供給のための労働をうまく組み合わせなければいけません。邦美丸さんは漁業の常識を越えてここに挑みました。私が特に印象に残ったのは、ご夫妻のお子さんが描いた「笑顔のパパの似顔絵」エピソードです。家族と職場が幸せにつながり、さらには将来的に漁業をやってみたいと考える人も増やしている。明るい未来を呼び込んだ学びの多いアクションだと感じました。
受賞者コメント:邦美丸/富永 邦彦氏
長時間労働に追われていた頃は、子どもが描く私の絵に「眉間の深いしわ」が刻まれていました。いつも険しい顔をして過ごしていたのだと思います。しかし完全受注漁を始めてからはそのしわがなくなり、私の笑顔を描いてくれるようになりました。子どもたちは大人の姿を本当によく見ているのだと感じます。今回の受賞を励みに、全国の個人事業主や生産者の方々に希望を届けられたらと考えています。
Cheer Up賞
人に教える喜びや自身の成長を実感できる職場へ 障がい者スタッフが、障がい者新人スタッフを育成する「チューター制度」の導入
アルティウスリンク株式会社

受賞のポイント
- ・障がい者が新人を育成するチューター制度を創設
- ・ガイドブックを作成し研修実施
- ・教える側の心理的安全性を担保
→障がい者の働きがいが向上しチューターを目指す人も増加。取り組みのさらなる拡大や他社へのナレッジ共有に期待。
審査員コメント:アキレス 美知子氏
私も複数社の人事部で障がいをもっている方と一緒に働いてきました。それぞれに個性や強みが違い、どのように接すればいいかつかみづらく、失敗も多かったと思います。そのため今回のチューター制度からは大きな気づきをいただきました。できない理由を考えてあきらめるのではなく、マニュアルの整備を行うなどし丁寧に進めることでこの取り組みが実現しています。支えてもらっている人たちが「支える側に回る喜び」を感じることの意義はとても大きいはず。これからも取り組みを広げていただきたいと思っています。
受賞者コメント:アルティウスリンク株式会社 DE&I推進部 事務サポートユニット/前島 みよ氏
チューター制度は、さまざまな個性を持つメンバーと向き合う中で「誰かの成長を支えながら自分自身も成長してほしい」という思いから生まれました。初めての試みに対して真摯に取り組み、私たちが想定していた以上の成果を上げてくれたメンバーに感謝しています。今回の受賞を励みに、これからもメンバーの成長の可能性を信じてサポートを続けていきたいと思います。
育休取得の罪悪感を発想の転換で和らげる!育休を取った社員の同僚に最大10万円を支給する「お祝い金制度」で、みんなで支え合える職場へ
三井住友海上火災保険株式会社

受賞のポイント
- ・産育休取得者ではなく周囲の社員に祝い金を支給
- ・育休取得の促進を仕組み化
- ・研修などの機会も強化
→育休取得者を心から応援する風土が醸成されつつある。「休みを取る権利」への意識がさらに拡大することを期待。
審査員コメント:守島 基博氏
この取り組みで重要なのは「職場」に注目したことではないでしょうか。日本企業は職場でもっている部分が大きく、仕事も個人ごとではなく職場単位に与えられ、現場のマネジャーが割り振っている企業が少なくありません。そのため職場が良い雰囲気を維持し、健康であることが欠かせないのですが、最近はリモートワークや有給取得の拡大、飲み会の減少などによって良い雰囲気を作りづらいのも事実です。職場の再生が求められている今、この仕組みから学べることは多いはずです。
受賞企業コメント:三井住友海上火災保険株式会社 人事部主席スペシャリスト(主席HRストラテジスト)兼人事改革推進チーム 企画チーム/丸山 剛弘氏
育休職場応援手当制度は、社員に子どもが産まれたときに影響を受ける「周囲の社員」を考慮し、職場の雰囲気をいかに良くしていくかを考えた結果生まれた制度です。いわば職場における人と人の関係性への投資だと考えています。この受賞を機に、今後も職場の社員がいきいきと働けるように取り組み、人と人のより良い関係性を実現していきたいと思います。
離職率95%から奇跡の大変身!信頼関係を土台にした「働き方改革」と人財を生かす「働きがい改革」を進める中小製造業4代目の挑戦
筒井工業株式会社

受賞のポイント
- ・コーチングを軸に、認め合う風土を醸成
- ・社員を信頼して経営情報を開示
- ・社員が主体となるプロジェクトを多数実施
→離職率を大幅改善し生産性向上も実現。関係性の質を高めることで、さらに社員が主体性を発揮する未来へ期待。
審査員コメント:株式会社リクルート リクナビNEXT編集長 藤井 薫
離職率95%とは、一体どんな状態だったのでしょうか。その当時は本当に苦しみ、経営者も悩みながらやってこられたのだと思います。この取り組みは信頼関係が土台になっている点が印象的でした。社長自身が全社員に「助けてほしい」と頭を下げ、その思いが職場に伝播し、従業員同士も助け合えるようになりました。社内で30ものプロジェクトを動かし、透明性を担保して互いの関わりを促す取り組みも秀逸だと感じます。私たちも信頼関係のあり方を考え直してみるべきなのかもしれません。
受賞企業コメント:筒井工業株式会社 代表取締役社長/前島 靖浩氏
かつては非常に情けない状況でした。当時を振り返ると、その原因は一方的な指示命令、頭ごなしの指導にあったと思っています。その後は社員に自主性と一体感を持ってもらうために試行錯誤してきましたが、改革の途中で「本来は誰もが自主性を持っている」と気づきました。それからは社員を信頼するようになり、信頼を土台として職場全体が変わっていきました。個々の仕組みも大切ですが、それよりも私自身が経営者として、人としてどうあるべきかが大切だったのだと感じています。
1年目社員が「青春18きっぷ」を握りしめてひとり旅へ! 挑戦する若手の姿は組織風土改革へつながっている
山陰パナソニック株式会社

受賞のポイント
- ・一人旅で若手が自ら考える機会を提供
- ・SNS活用で若手の発信をシェア
- ・サポートの輪を広げるメンター制度を創設
→旅の達成感や人間関係向上によって22卒の離職ゼロ、若手発の提案も増加。今後はベテランの意識変革にも期待。
審査員コメント:株式会社リクルート リクナビNEXT編集長 藤井 薫
旅を通じて若手がインスタグラムで発信し続ける。それに対してベテランも反応しながら、少しずつ若手の発言を引き出し、周囲も支援していく。とても「SNS的な取り組み」だと感じました。従来の職場はクローズで上下関係があり、会議室でしか発言できないような雰囲気がありますが、SNSはオープンでフラットでカジュアルですよね。私自身も若い人に負けず、オープンでフラットでカジュアルでありたいと思います。今後はベテランの皆さんの奮起にも期待しています。
受賞者コメント:山陰パナソニック株式会社 経営管理本部 人財戦略部 人事課 多様性推進担当 主事/船井 亜由美氏
今の若手はコロナ禍の影響もあり、オンライン中心でなかなかリアルな体験が得られない傾向にあると思います。情報はたくさん得られるものの、肌で感じる体験が不足しているのではないでしょうか。そこで「ひとり旅研修」を企画しました。社内からは反対や懸念の声が多く、さまざまな困難もありましたが、結果的に研修に参加した若手はいきいきと各職場で活躍しています。今後もさまざまな活動を通じて社内を活性化させていきたいと考えています。
【審査員座談会】
2024年3月5日に開催された第10回「GOOD ACTION アワード」表彰式。受賞した7取り組みの発表に続き、過去10回にわたって審査員を務めてきた守島基博氏とアキレス美知子氏を迎え、リクナビNEXT編集長の藤井薫を交えて座談会を行いました。これからの職場づくりには何が必要なのか。3氏の視点をご紹介します。

(審査員のみなさま)
学習院大学 経済学部経営学科 教授/一橋大学 名誉教授 守島 基博氏
三井住友信託銀行取締役/横浜市参与/G20 EMPOWER日本共同代表/内閣府男女共同参画推進連携会議議長 アキレス 美知子氏
株式会社リクルート リクナビNEXT編集長 藤井 薫
未来の職場づくりのヒント
個人に寄り添うだけではなく、時には「対峙」することも必要
藤井:第10回GOOD ACTION アワードの受賞取り組み発表を終え、今回もたくさんの学びがあったと感じています。個人が思いを持って声を上げたり、経営者自身が声を発して行動を起こしたり。中には「生活を犠牲にしない働き方を取り戻す」という悲痛とも言える思いから始まったアクションもありました。一方、企業側も働く一人ひとりの声に寄り添い、業界の常識だったビジネスモデルや働き方を一気に変えているところが印象的でした。
アキレス:GOOD ACTIONアワードに取り組んできたこれまでの10年を振り返っても、大きな変化を感じますね。かつての企業が主体になっていた状況から、企業と個人の関係が対等になってきたと感じます。人材不足の世の中で、ほしい人材に気持ちよく働いてもらうためにはどうすべきか、どのようなインセンティブを提供していくべきかを企業は意識しなければならない時代となりました。今回の受賞取り組みでは、ビジネスモデルを変えてまで良い関係を作り、個人の成長を促す試みも見られました。
守島:私も、企業と個人の関係性について改めて考えさせられる事例ばかりだったと感じています。共通しているのは、個人が上げた声を企業が真剣に受け止め、対応しているところではないでしょうか。
ワークライフバランスや働き方改革など、これまでも日本企業は働く人の要望を受け止めてきたと思います。しかし個人がどのように働きたいか、どんなふうに成長したいかについては、あまり耳を傾けてこなかったのかもしれません。この状態が続くと、結果的に職場を去っていく人も出てきてしまう。個人が本来持っている強みを直視し、個に寄り添うだけでなく、時に対峙しながら進めていくことが大切なのでしょう。
藤井:最近は制度がどんどん進化して働きやすい職場が増えたものの、単にホワイトなだけでは働きがいは伸びないということですね。一人ひとりの花を咲かせるには、個人が本当に何をしたいのかにフォーカスしなければいけない。働き手のことを従業員と呼んできましたが、これからはむしろ個人が主役という意味で「主業員」と呼ぶべきなのかもしれません。

働き手の先にいる顧客までを含めて関係性を見直していくべき
アキレス:この10年における変化という意味では、職場における多様性が当たり前になってきたことも挙げられると思います。ジェンダーや国籍などの表面的なものだけでなく、一人ひとりが多様な価値観を持っていることが理解されるようになりました。この理解の上で、一人ひとりは本当は何を成し遂げたいのか、何を大切にしているのかを会話できる職場であれば、施策はいかようにもカスタマイズできるのではないかと思います。
もしかすると人によっては、「仕事は50%でいいからあとの50%で別のことをやりたい」と考えているかもしれません。こうした価値観を理解し、受け止めていくことも大切。日本の大企業では伝統的に全員に平等な施策を意識してきたと思いますが、その時代は終わったのかもしれません。働き手個人もまた「自分は何がしたいのか」を自律的に突き詰めていかなければいけません。
藤井:そんな時代の職場に求められることは何なのかを考えると、職場は個人の生活にまで広がっていることを改めて認識することが大切だと感じます。コロナ禍のリモートワークではまさにこれが現実になり、仕事中に子どもの声が聞こえてくることも当たり前になりました。会社を中心にするのではなく、個人の生き方を中心に「働く」を設計すべきではないでしょうか。
守島:歴史を顧みると、仕事が生活から切り離されたのは産業革命以降なんですよ。それまでは農業でも自家工業でも、仕事と生活は地続きでした。おそらくこれからは、ITの進化によって再び仕事と生活が地続きになる時代がやって来ると見ています。
仕事と生活の区分がなくなっていく時代には、働き手のあり方も必然的に変わっていくでしょう。これまでは働き手を指す言葉として“Labor”(苦役者)や“Worker”(労働者)があてられてきましたが、今後の理想的な働き手は“Player”(楽しむ人)。個人は何を自分の楽しみとするのかを考えるべきだし、企業はプレイするための場所として職場を作っていくべきだと思います。
藤井:今回のGOOD ACTIONアワードでは、漁業や林業、保育などの分野で、未来の働き手や顧客までを見据えた取り組みが紹介されました。今後は顧客もまた“Player”として巻き込まれていくのかもしれませんね。
守島:「顧客と働き手」という分け方が意味をなさなくなってきたのだと思います。誰もがこの社会を構成する生活者であり、生活者の一部が自社で働いてくれているに過ぎない。生活者自身も人生をプレイするための場を見出していく必要があり、その結節点となるのが職場だということです。

アキレス:顧客なしでビジネスが成り立たないのは自明の理ですが、日本では「お客様は神様」の考えが根強く、その分の重圧が働き手にかかってしまう面があります。働く人がハッピーでやる気に満ちあふれていれば顧客サービスも改善していくはず。私たちは働き手とその先にいる顧客までを含めた関係性を見直していくべきなのでしょう。
「今」が素晴らしいだけでなく、アクションがさらに進化していくことを期待
藤井:10年目を迎えたGOOD ACTIONアワードを振り返り、次の10年への期待をお聞かせください。
守島:GOOD ACTIONアワードのテーマは「働くあなたが主人公」。過去10年の受賞取り組みにはたくさんの主人公がいました。しかし最近では、さまざまな職場で自分勝手な主人公も増えているように感じます。時代の変化とともに企業は大きく変わらざるを得ませんでした。次の10年は、働き手が自律することへの変化を求められる時代になるのではないでしょうか。
アキレス:あっという間の10年でした。GOOD ACTIONアワードの楽しいところは審査会。価値観や意見の異なる審査員同士で、時間をかけて一つひとつの取り組みをじっくりと深掘りさせていただいています。業界や企業規模を問わず、これからも新たな視点をもたらしてくれる応募が集まることを期待しています。過去に受賞した方々も、アップデートした現在をまた見せていただけたらと思っています。
藤井:GOOD ACTIONアワードは、その企業や取り組みの「今」が素晴らしいから光を当てているわけではないんですよね。この後の変化にも大いに期待して、アクションそのものの進化を期待しています。私たちもアクションからいただいた学びを日本中、世界中に広げていければと考えています。
※ 本ページの情報は全て表彰式当時の情報となります。