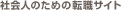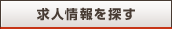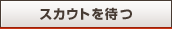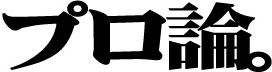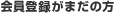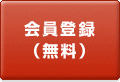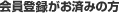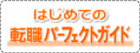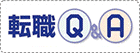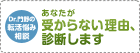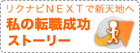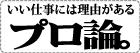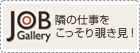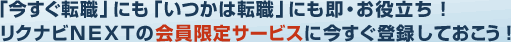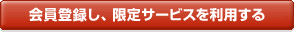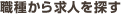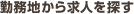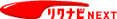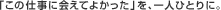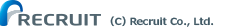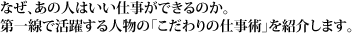
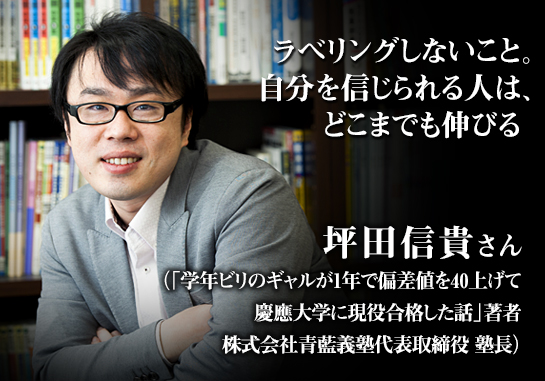



偏差値30だったギャルを
慶應大学に入学させた塾講師として、
一躍、脚光を浴びている坪田氏。
教育の道に進むきっかけは何だったのか

ラベリングが可能性を狭める。日本に蔓延するこの意識を変えたかった
ラベリングが人の可能性をどれだけ狭めるか。日本に蔓延するこの意識を変えたくて、僕は塾を開いたんです。
「ラベリング」とは、簡単に言うと、先入観を持つということ。多くの人は外見やプロフィールだけを見て、「キミは○○な人間だね」って、決めつけてしまいますよね。言われた方は「自分は○○なんだ」と認識してしまう。それが人の成長を妨げてしまうことが多いんです。
例えば、著書に出てくる教え子の「偏差値を40上げて慶應大学に入ったさやかちゃん」は、見た目がギャルだったために、有名大学なんて絶対無理だとほとんどの人から思われていました。さやかちゃんだけではありません。多くの子が、見た目や偏差値、通っている学校などから「できない子」だと決めつけられてしまう。これは、教育の場だけでなく企業社会でも同じだと思います。
「先入観を捨てれば誰でも伸びる」を証明したくて、塾を開いた
「ラべリング」の問題に気づいたのは、20代前半のころ。高校生に勉強の仕方を教えたことがきっかけです。
実は、私は高校生の時、英検3級も受からないような英語力でした。そこから1年間独自の方法で勉強をし、最終的にはTOEICで満点を取りました。その勉強法を高校生たちに教える機会があって。そのとき口を揃えて「もともと先生の頭がよかったからできたんじゃない?」と言われたんです。それを聞いた瞬間に、「これが日本の教育の問題点だ」と確信しました。
勉強法を教える以前の問題です。この子たちも「ラベリング」しちゃってるんです。TOEIC満点という結果だけを見て、「坪田先生はもともと頭が良い」と能力を判断してしまっている。そして自分の現在の姿だけを見て、できないと決めつけてしまっている。
でも、実際はそうじゃない。彼らもやり方が悪いから英語力が上がらないだけ。僕は、「ラべリングをやめて、勉強法を変えれば誰でも伸びる」ということをどうしても証明したかった。そのために塾を開いたんです。要はデータ収集です(笑)。サンプル数が僕一人だけだと、証明になりませんからね。
現在までに1000人ほど塾で教えましたから、かなりの数のデータが集まりました。そのなかの一人が「偏差値を40上げて慶應大学に入ったさやかちゃん」ですが、ほかにも「自分は勉強ができない」というラべリングをやめることで伸びた教え子はたくさんいるんです。いかに、親や先生の先入観が子どもをダメにしているかということですよね。
絶対伸びると信じる人が身近にいると強い
私が大事にしているのは、「この子はできる、できない」とラベリングしない代わりに「絶対伸びる」と信じることです。そしてそれを伝える。親でも教師でも上司でもいいですが、自分を信じてくれる人が身近にいるだけで、伸び方に大きな違いが出ます。
でも、そこには信頼関係がなくてはダメ。信頼していない相手からいくら「大丈夫だよ」と言われても、本人には届きません。
信頼関係の築き方は簡単です。目線を合わせるんです。幼い子どもに話をするときに、立ったまま話しませんよね。かがんで目線を合わせます。それと同じです。幼い子ではない場合は、かがむ代わりに価値観を合わせます。そのためにすることは、それぞれの「特性」を見極めるんです。
「特性」を知ることは難しいことではありません。その人が興味や関心を持っていることを、一緒になってやってみればいい。僕の場合は、生徒がはまっているというゲームもやるし、漫画も読みます。好きだというアイドルについても語るし、街中に出て一緒にソフトクリームを食べに行くこともあります。
同じ目線で話すことができるようになると、人は心を開いてくれます。こちらの言うことを素直に聞いてくれるようになるんです。それこそ、「君は絶対伸びるよ」というと、「この人は、本当に伸びると思ってくれている」と、ちゃんと信じてくれるんです。
よく素直な人じゃないと伸びないんじゃないかと聞かれますが、そうではありません。斜に構えた人なら、こちらも斜に構えればいい。信頼してほしい方、経験豊富な方が合わせることが重要なんです。



指導者に必要なのは、
いかに「価値観の振り幅」を持てるかだと、
坪田氏は言う。
では、伸びる人と伸びない人は、
どう違うのか。

「自分は伸びる」と自己暗示できれば、人はどんどん成功する
それはもう、「自分は伸びる」と信じられるかどうかです。周りの人がそう思ってあげることも大切ですが、まずは自分。誰でもない自分自身が自分のことを信じられることが重要なんです。「自分はできない」というラべリングを打ち破ることが大切なんです。
なかには、もともと自己効力感(自分はできると思う力)が低い人もいます。あまりほめられず、怒られてばかりいた人は、自己効力感が低くなりがちです。親から毎日1時間以上も怒られていたなんて人は、どんなことでも「私には無理」だと思ってしまう。
そんな人にはこう話します。例えば2歳の子が「おはしが持てないの」とわんわん泣いていたら、キミはどう思う?って。大抵の人が「いつかできるようになるのに、できないと思い込みすぎている」と言うでしょう。「キミもそれと同じでしょ?自分だっていつかできるようになるよ」と。この話をすると、すごく納得してくれます。
ただ、一度はそうやって納得しても、もともとの自己効力感が低いと、どうしてもネガティブな考えが浮かびがちです。そんなときは、「リフレーミング(違う枠組みで見ること)」していけばいいんです。例えば、「明日のプレゼンテーション、失敗したらどうしよう」と思ったら、すかさず「でも、成功したらすごい武器がまた一つ増えるぞ」とリフレーミングするんです。ポイントはそれを「声に出して言う」こと。声に出すことで、自己暗示をかけるんです。
自己暗示なら一人でもできますよね。いつもポジティブな自己暗示をかけている人は、本番でも強い。いろんなことが面白いほどうまくいきます。これはビジネスの世界でも通用することなんですよ。
小さな達成感が集まって、天職になっていく
そうやって最初は自己暗示をかけながらいろんな経験を積み重ねると、さまざまなことができるようになります。そうして初めて、仕事が面白くなってやる気がどんどん出てきます。成功する人は最初からものすごいやる気があったのだろうとみんな思っていますが、実はそういう人のほうが少数。多くの人は、やり始めていろんなことができるようになって初めて、やる気が出てくるんです。
人って、できないことはやりたくない生き物なんですよ。テニスを始めても、全然ボールが打てなくて、ひざすりむいて、なんていうことばっかりだったら、楽しくないから続かないですよね。でも、今日はボールを打ち返せるようになったとか、サーブができるようになったとか、小さくてもいいから達成感があると、どんどん楽しくなっていく。やる気が生まれてくるんです。だから、目標は細かく刻んでおくといい。小さな達成感をたくさん味わっていくうちに、それが天職につながっていくのだと思います。天職は見つけるものではなくて、自分で意識的に作っていくものなんですよ。


坪田信貴著
ギャル風の格好をした偏差値30の女子高校生さやかちゃんが、ある日坪田先生の勤務する塾に訪れる。坪田先生はさやかちゃんに慶應義塾大学への進学を勧め、さやかちゃんは受験を決意する。しかし、さやかちゃんは、聖徳太子を「せいとくたこ」と読んだり、日本地図もまともに書けないほどの知識力だった……。坪田流独自のメソッドを駆使し、さやかちゃんが見事慶應義塾大学に合格するまでが記されたノンフィクション。心理学を応用した坪田流メソッドは、ビジネス社会でも使えるものが多い。仕事ができないと思っている人、部下がうまく育たないと思っている人、必見です。
KADOKAWA刊
- EDIT/WRITING
- 高嶋ちほ子
- DESIGN
- マグスター
- PHOTO
- 和田佳久
自分の「こだわり」を活かせる企業に出会うために、
リクナビNEXTスカウトを活用しよう
リクナビNEXTスカウトのレジュメに、仕事へのこだわりやそのこだわりを貫いた仕事の実績を記載しておくことで、これまで意識して探さなかった思いがけない企業や転職エージェントからオファーが届くこともある。スカウトを活用することであなたの想いに共感してくれる企業に出会える可能性も高まるはずだ。まだ始めていないという人はぜひ登録しておこう。