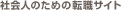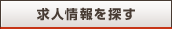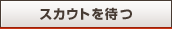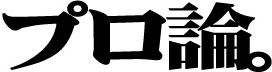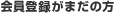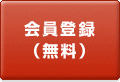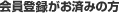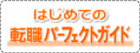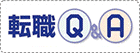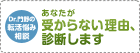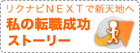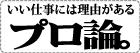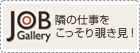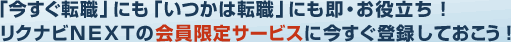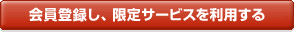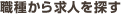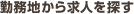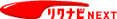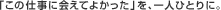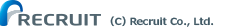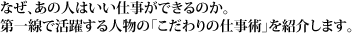
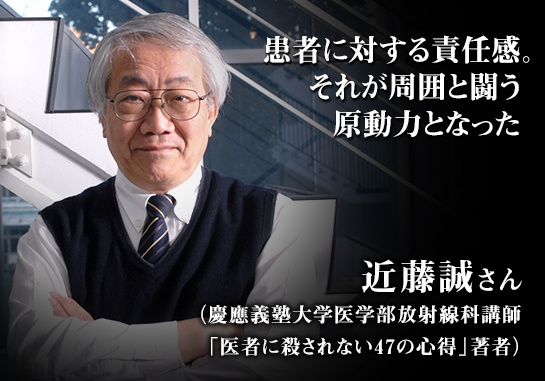



医療の常識を覆した本、
「医者に殺されない47の心得」が
100万部を超える大ベストセラーに。
医療界の猛反発を受けても
患者に真実を伝えたいと語る、
医師の近藤誠氏に聞く

医者も放射線科も、“消去法”で選んだ道だった
もともと、医者にはいやいやなったんです。父親が開業医だったから、その後を継げと言われましてね。でも、一日中家にいる仕事はつまらない。会社に勤めようと工学部や法学部に進学する道も考えましたが、父の姿しか見てこなかったから、会社員としてやっていける自信もない。それで結局、慶應大学の医学部に進んだんです。いわば消去法で選んだ道です。
放射線科を選んだのも消去法。僕は学生結婚して子どももいたから、保育園の送り迎えなどを考えると、規則正しい生活ができて時間に余裕がある放射線科しかなかった。そのときは、今のようにがん治療を専門にすることや、がん治療の改革を世の中に訴えるようになるなんて、全く考えもしませんでした。
保身に走る医者への憤り、患者への責任感が、自らを奮起させた
そんな僕がなぜ医療改革を目指すようになったのか。きっかけは、1979年に放射線治療を学びにアメリカ留学をしたことです。アメリカは日本と違ってがん患者に対する放射線治療が盛んでした。当時の日本は、がんに対して手術で臓器を摘出してしまう治療がもっぱら。しかし、データを見ると、摘出手術も放射線治療も生存率はほぼ同じ。それなら臓器は残したほうがいい。この治療方法を日本中に広めようと考えたんです。
帰国した僕は、まずはじめに外科医など医者たちを説得しようと試みました。彼らは放射線治療の効力を知らないために、何でもかんでも切ってしまうのではないかと思ったからです。でもそれは誤解でした。彼らは放射線治療の良さをわかってはいたけれど、日本に入ってこないよう、バリアを張っていたんです。理由は自分たちの仕事が減ってしまうから。
例えば外科医に「放射線治療をやりませんか?」と提案したら、「若い人の練習のためにも手術は必要なんだ」と言われてね。「これは、もうダメだな」と思いました。手術の目的が患者のほうを全く向いていないんですから。
こんな活動を続けていくうちに、院内の自分に対する空気もだんだん厳しいものに変わっていきました。でも、あきらめるわけにはいかない。患者への責任があるからです。主治医になると、その人の生死が僕にかかってきます。生死を預けてくれている人たちがいるのに、やらないわけにはいかない。
僕は医者たちを説得するために、議論の場を設けたり論文を発表したりさまざまな取り組みを行いました。放射線治療の範囲は全身にわたり、勉強することはとても多い。一方、相手は各臓器の専門家。生半可な知識では負けてしまいます。相当な時間を研究に費やしました。完璧に準備して、カンファレンスや勉強会に臨みました。そして医者たちと熱烈な議論を繰り返した。でも、向こうは決して曲げません。切ることをやめようとしないんです。
そんななか、姉が乳がんになったんです。姉に乳房温存療法(放射線を用いた治療法)のことを話すと、その治療法を選択すると言う。治療の結果、姉のがんは転移しませんでした。今でも健在です。
その後もあきらめずに、放射線治療(=温存療法)での患者の数を少しずつ増やしていき、その成績をもとに論文を書いたり、新聞で発表するようにしたんです。世間の注目も少しずつ集まってきた実感がありました。
院内で総スカンを食らっても、これまで治療した患者たちとつながっている
しばらくして、ある事件が起きました。新聞の記事を見て慶應病院に来た乳房温存療法を希望する乳がんの患者を、受付が外科に回してしまったんです。患者は「近藤先生に温存療法をお願いしたい」と何度も言っていたのに、病院が「乳がん=外科」だと決めつけてしまったというわけです。
私はアルバイトの学生からそのことを聞いて、手術日も決まっていたのだけれど、彼女を救出して別の病院で放射線による乳房温存療法を受けさせました。しかし、それで終わる問題ではありません。きっと、彼女以外にも記事を見て自分を頼ってきたのに、外科に回されて乳房の全摘出をされた人がいるんじゃないか。結局、取材を受けるだけでは、自分の肩書だけ見て、患者が慶應病院に来てしまう。「慶應大学をはじめ、どこの大学病院の外科でも乳房を全摘してしまう」と、大学病院の現状を「実名」を挙げて書かなくてはならない。でもそんなことをしたら、慶應病院の外科から猛反発を食らいます。出世の道も絶たれるかもしれない。放射線科に入った当初は、出世なんて全く考えていなかったけど、このころは出世して教授になって社会的発言力を身につけ、医療改革をしたらどうかとも考えるようになっていたんです。
出世に関しては、教授になるより講師のほうが、かえって気楽にいろんな活動が続けられるかもしれないと考え直すことができた。でも、なかなか断ち切れなかったのは「孤独」への恐怖です。院内で村八分になる。ほかの診療科だけでなく放射線科でも腫れ物のように扱われる。その孤独に耐えられるか。最初はその自信がなくてね。でも、そこで思ったんです。「たとえ院内で孤立しても、これまで治療してきた人たちとつながっているじゃないか」と。
ずっと目的意識なくやってきたけれど、ここになって初めて生きる意味を考えた。これまで自分が生きてきたことに意味があったかはわからない。でも、僕と会ってよかったと思ってくれる患者が一人でもいたら、それは意味のある人生だったんじゃないか。これから何が起こっても、それを支えに生きていけるのはないか。そう考えて「乳ガンは切らずに治る」という論文を書き、88年に「文藝春秋」誌上で発表することにしたんです。



文藝春秋での論文は、
病院内外で波紋を呼んだ。
その後、著作などで世間に訴え続け、
がんの放射線治療も温存療法も、
日本でもメジャーなものになった。
既存権力との戦いの中、
近藤氏が大切にしてきたこととは?

仕事でウソはつかない。間違いに気づいた時点ですぐに訂正する
私が仕事の面でいちばん大切にしてきたこと、それは、ウソをつかないこと。そして間違いに気づいたら、すぐに訂正すること。これは患者との関係でもそうだし、著作においてもそうです。
どこかでウソを言うと、そこがほころびとなって後の仕事に響いてきます。だから、ウソはつかないほうがいい。ウソと間違いは違います。間違えるのはしょうがない。人間は間違える動物だからね。だけど間違いに気づいたときにはすぐ素直に訂正しなくてはならない。その姿勢が大事なんです。
僕がこれまで発表してきた著作は何十冊もあるけれど、研究を重ねていくうちに、これは間違いだった、という箇所がいくつかありました。でも、気づいた時点できちんと訂正して前に進むようにしてきたんです。それを怠ると足をすくわれてしまいますから。
がん治療に対する姿勢に関してもそうです。最初は僕も教科書通りに「全摘出は正しい」という考えに染まっていた。でも、実際に患者と向き合ったり、アメリカ留学をしてみると、違うんじゃないかと思うようになっていった。だから、訂正することにしたんです。
感情だけで突っ走ってはダメ。完璧な準備が伴わないと主張は通らない
間違いに気づいたら訂正する。言うのは易いですが、それにはいろんな困難が付きまといます。特に僕の仕事は人の生死に関わるものですからね。実際に患者に行われている治療行為、それが間違っているとわかっても自分一人があやまればいい問題ではない。その方法を支持している医師を巻き込むわけですから、大変な騒動になります。若い時は巻き込む相手が上司に当たるわけですから、かなり厳しいものでした。
それなのに、どうして間違いを正そうと決意できたのか。結局、人は理屈では動かないんです。その時の自分には、医者たちに対する怒りがありました。そして患者への同情もあった。この2つが車輪となって、走り出したんです。でも、2輪車ではダメ。それでは不安定で倒れてしまいます。つまり、感情に駆られて主張をしても、小さなほころびから相手につけこまれるだけ。誰に押されても倒れない4輪車で走り続けるために、あと2つの要素が必要なんです。
3つ目の要素は、完璧主義であること。つまり、主張を通すために完璧な論文を書くということです。そのためには、膨大な資料を読み込んだうえに、論理力も磨く必要がある。それに費やしてきた時間は10万時間くらいでしょう。自分の主張が誰からも突っ込まれないように、完全無欠を目指すんです。先ほど言ったように人間は間違える動物ですから、なかなか難しいことなのですが、完全無欠を目指すという気持ちが大事なんです。最後の1つは負けず嫌いだということ。患者のことを第一に考えない医者たちに負けたくない、という気概です。これは苦しいときに、最後の粘りにつながります。この4つの車輪が揃って初めて、長く走り続けることができるんですよ。


近藤誠著
「医者によく行く人ほど、早死にする」「老化現象ですよ、と言う医者は信用できる」 「がんほど誤診の多い病気はない」「がん検診は、やればやるほど死者を増やす」「ビタミン・ミネラルの摂りすぎで早死にする」「大病院にとってあなたは患者ではなく被験者」など、医療の常識を覆す話が満載。素人にもわかりやすい語り口調で100万部を超えるベストセラーになった本だ。本音の医療で世の中に一石を投じる近藤先生の姿勢を知る意味でも一度は読んでおきたい本だ。
アスコム刊
- EDIT/WRITING
- 高嶋ちほ子
- DESIGN
- マグスター
- PHOTO
- 栗原克己
自分の「こだわり」を活かせる企業に出会うために、
リクナビNEXTスカウトを活用しよう
リクナビNEXTスカウトのレジュメに、仕事へのこだわりやそのこだわりを貫いた仕事の実績を記載しておくことで、これまで意識して探さなかった思いがけない企業や転職エージェントからオファーが届くこともある。スカウトを活用することであなたの想いに共感してくれる企業に出会える可能性も高まるはずだ。まだ始めていないという人はぜひ登録しておこう。