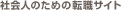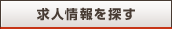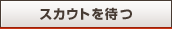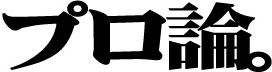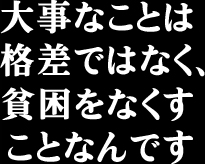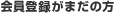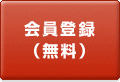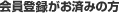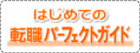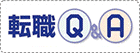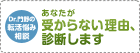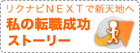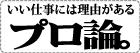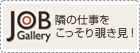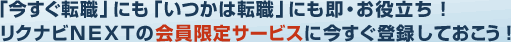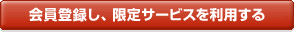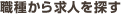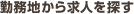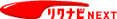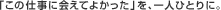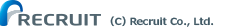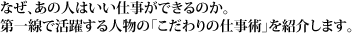
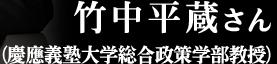



構造改革を推し進め、「失われた10年」から
日本経済を浮上させた小泉内閣の
経済閣僚として活躍したのが、竹中氏だ。
不況に苦しむ今の日本の状況を
どう見ているのか。

非正規社員の多さは、制度に問題がある
今の経済を航海中の船に例えれば、船室の一部がちょっと明るくなってきた、という感じだと私は思っています。しかし実は、船は沈み続けているんですね。油断したら大変なことになります。
実は日本経済は80年代も90年代も沈んでいました。しかし、公共事業を打つことで、一瞬は回復をみせた。株価も短期的に反応した。それを景気が戻ってきたと勘違いしてしまった。
ところが、もう長い間、日本は沈み続けているんです。そして残念ながら、日本はそのことに気付かず、過去からほとんど学ばなかったんです。
今の政治を見ていると、私は、かつて東京都を率いた美濃部知事を思い出さざるを得ません。公害条例から老人医療の無料化まで、美濃部都政は都民から支持を得られる政策を次々に実行しました。ところが、最後は予算が組めなくなり、数十年にわたり、東京都の財政に大きな「負の遺産」を作ってしまった。今の政権はこのときの都政にとても似ています。
麻生政権と鳩山政権も、よく似ていますね。「みんな困っているだろうから私が面倒をみてあげましょう」と、お金をばらまくフレームワークはほとんど同じ。違いは政権交代で、ばらまく先が「業界」から「家計と農村」になっただけです。その様子はまるで社会主義。
社会主義を国が行うとはじめは必ずよく感じます。今まで心配していたことを、何も心配しなくてよくなるからです。国がすべての面倒を見てくれるから当然です。社会主義は、最初はみんなハッピーになる。しかし、10年後に国民はそのコストの大きさに気がつくんですよ。
自助自立でやっていこうと推し進めた小泉内閣の構造改革は、今なお「失業を増やした、格差を広げた」と言われています。日本は極めてインテリジェンスのある国だと思いますが、どうしてこんな誤った意見が社会に定着したのか。理由は2つあると思います。改革が嫌な人たちがキャンペーンを張ったこと、無邪気なワイドショーのコメンテーターたちがそれに乗ってしまったことです。
しかし結局、コストを払うのは国民です。アメリカのカーライルが有名な言葉を残しています。「経験こそが最良の教師である。しかし、それは高くつく」と。しかも問題は、コストにとどまりません。雇用という多くの国民が関わる問題が国会で議論されていますが、聞いていると愕然とします。派遣と非正規雇用の区別すらされていない。ましてや派遣と請負の違いなど、ほとんどわかっていない人が多いんです。
格差はないほうがいい。しかし、格差はどうしてもできてしまうもの
ではそもそもなぜ、非正規社員はこれほど増えたのか。実は日本では正規社員が大変な既得権益を持つからです。会社がつぶれそうになってもクビにならないという世界に例がない権益です。
1970年代の東京高裁で解雇権の乱用を防ぐために出された判例は、雇用する側には極めて厳しいものでした。結果として、企業は簡単に採用ができなくなった。そこで、判例の対象にならない非正規社員を増やさざるを得なかったんです。
それを今では、まるで競争の結果、非正規雇用が生まれたかのように言われるようになりました。しかし、違います。これは制度が生み出しているんです。この制度を平等にすることこそが改革なんです。
改革を断行した国がある。オランダです。(編集部注:オランダは1990年代、パートタイム労働者の賃金や待遇を改善する取り組みを進め、失業率を低下させた)日本は「日本版オランダ革命」をやるべきでした。ところが、できなかったんですね。
格差の問題も今なお、あおられていますが、これにはサッチャーが有名な言葉を残しています。「金持ちを貧乏人にしたところで、貧乏人が金持ちになるわけではない」。むしろ、厳しい世の中で頑張って高い所得を上げている人はもっと頑張ってもらえばいい。そうすれば、雇用も増えるし、その人たちの所得から税収も増えるからです。
格差はないほうがいい。しかし、格差はどうしてもできてしまいます。むしろ大事なことは、格差をなくすことではなく、「貧困をなくす」ということなんですよ。



「日本は貧困調査を一度もしたことがない」
と竹中氏はいう。
情緒の議論ではなく、
事実に基づいて、
議論をしなければいけない、と。

今の生活水準を維持するには努力するしかない
世の中は貧困が増えて大変だ、と言っていますが、では日本に何百万人いるのか、と聞いても国は把握できていない。日本では情緒的にわあわあと言っているだけで、誰も何も解決しようとしない。重要なことは、事実を正確に知るということです。
ビジネスパーソンも、世界の現実を知る必要があります。現在、世界はすさまじい競争をしています。ブラジル銀行東京支店のオペレーターはブラジルにいる時代なんです。デジタル化が進んだ今、隣の部屋に電話をかけるコストも、地球の裏側に電話をかけるコストも同じ。だから、オペレーターはどこにいてもいい。ならば、オペレーターの給料は世界水準になる。ブラジルと同じにならざるを得ません。
世界最高の生活水準を維持しようと思ったら、それにふさわしいだけの能力を付ける必要がある。そうでなければ、生活水準が下がるのは当たり前です。もはや、そういう世界になっているんです。それが嫌ならば、努力するしかない。しないなら、貧しさを覚悟しないといけない。
この努力を国を挙げて進めてきたのが、韓国でした。97年のアジア通貨危機でグローバリゼーションの怖さを思い知った。だから法律も教育も、企業の制度や慣習も変えた。人材も大抜擢する。それも日本では考えられないようなレベルで、です。
それなのに、相変わらず日本はのんびりしています。日本はグローバリゼーションをなめてかかっている。だから、今なお船は沈んだままなんです。
そして正社員も、その既得権益の維持が極めて難しくなっていることに気づく必要があります。年功序列、終身雇用が成り立つには、人口ピラミッドが三角でなければならないからです。逆三角形の日本では、もう成り立たないんです。今こそ、それをリーダーが言わないといけない。日本の民主主義が間違っていると思うのは、国民の意見だけを聞いていることです。政治リーダーは御用聞きではいけないんです。民意を大切にしつつも、民意を指導することこそ、実はリーダーの役割です。
企業を大切にすることで、生活はよくなる
日本は今ひどいことになっています。しかし、日本をよくするのは難しくないと私は思っています。例えば、もっと企業を大事にする。法人税も下げる。企業の保護よりも生活を、という空気がありますが、では生活の基盤となる賃金はどこから得ているのか。企業なんです。
そして忘れてはならないのは、企業は世界のどこにでも行けるということ。自分たちの最も都合のいい場所に移れるんです。
困るのは、国境を越えられない普通の国民です。普通の国民を守るには、日本に強い企業がいないとダメなんです。それが経済の大原則です。生活が大事だから、企業を強くしなければいけない。世界から、雇用を生む企業に来てもらわないといけない。世界の企業は日本に進出したいんです。でも、法人税が高すぎる。しかも規制もある。その上、派遣も禁止、なんてことになるなら、誰がこんな国に来るでしょうか。それもまた、世界の現実なんです。
それでも働く立場として世界に目を見やれば、今なお日本はいい国です。勉強しようと思えばできて、ちょっと働いたら車が持てる。それは世界から見れば夢のような国です。その素晴らしさを若い人は再認識してほしい。だからこそ、新しいことを恐れず、積極的に挑んでほしい。
ある電機メーカーの標語に「夢見ながら、耕す人になれ」があります。絶対に理想を忘れるな。自分は何をやりたいのか、夢を追え。その代わり、自分の足元もちゃんと耕せ。それがいつか必ず結びついてくる、と。人間はどちらかというと二律背反で、どちらかしかできない。だからこそ、この言葉を常に意識してほしいと思います。

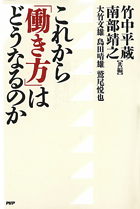
竹中平蔵 南部靖之 共編
労働格差、派遣切り、リストラ、少子高齢化による人口減少、「超氷河期」といわれる雇用状況…。ますます不安が高まる日本の「仕事」の現状と未来を、労働と経済のプロたちが分析、その解決策を探り、やりたい仕事ができる世の中をつくるための提言を行う。正社員であっても、あぐらをかいていては生き残れない時代に、どのような「働き方」をすれば幸せになれるのか。将来に不安を持っている人、今の生活に不満を持っている人、会社から実力が認められずに憤りを覚えている人、必見の書だ。
南部氏、竹中氏のほか、島田晴雄氏、鷲尾悦也氏、大竹文雄氏が執筆。PHP研究所刊
- EDIT
- 高嶋ちほ子
- WRITING
- 上阪徹
- DESIGN
- マグスター
- PHOTO
- 栗原克己
自分の「こだわり」を活かせる企業に出会うために、
リクナビNEXTスカウトを活用しよう
リクナビNEXTスカウトのレジュメに、仕事へのこだわりやそのこだわりを貫いた仕事の実績を記載しておくことで、これまで意識して探さなかった思いがけない企業や転職エージェントからオファーが届くこともある。スカウトを活用することであなたの想いに共感してくれる企業に出会える可能性も高まるはずだ。まだ始めていないという人はぜひ登録しておこう。