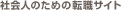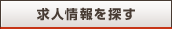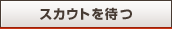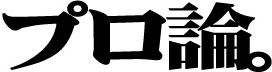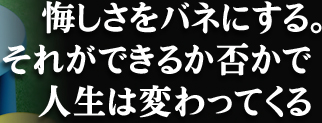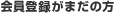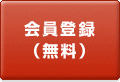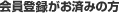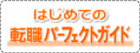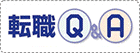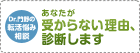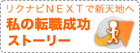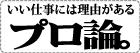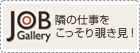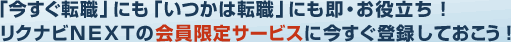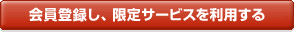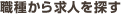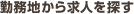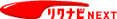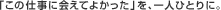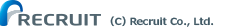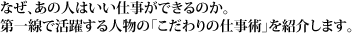
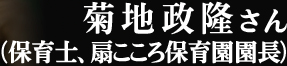



「まあせんせい」の愛称で、
テレビや雑誌などに多数出演。
「保育園にも男性保育士がいるべきだ」。
その信念をもとに、女性中心だった
保育業界の改革に取り組んでいる。

ケガが転機となり、保育士の道へ
僕は、子どもが好きでこの世界に入ったわけではないんです。どちらかというと、好きじゃない。それこそ、うちの保育園の子たちは大好きだけど、外で子どもと会ったときに、自分から触れ合おうと思うほどではないんです。僕は子どもが好きなのではなく、「保育」という仕事が好きなんですよ。
大学2年生まで、「将来は教員になってテニス部の顧問になろう」と考えていました。小学校から大学までずっとテニスをやっていましてね。高校ではテニス部の部長もやったし、大学のテニス部でも毎日夜遅くまで練習を続け、まさにテニス中心の生活でした。
それが一変したのが、大学2年生の夏。練習中に右手中指を骨折して、けんを切ってしまったんです。骨折は治ったものの、切れたけんは完治しなかった。ラケットを握っても力が出ない。僕のテニス人生は突然、終わってしまったんです。大きな挫折でした。
ずっとテニス三昧の日々でしたからね。夏休みに入って、実家に戻ってみたところで何もすることがない。昼間はぷらぷらして、夜中になると車で首都高を飛ばし憂さをはらして過ごしていたんです。そんな僕を見かねたのか、母が保育園の手伝いをしてくれないかと言い出しました。
実は、僕の家は保育園なんです。父親が園長で母親が保育士。住居は建物の3階部分にあって、1、2階で保育園を営んでいた。小学校のころは保育園の中を通って帰っていたし、土曜日には園の子どもたちと一緒にご飯を食べられるような環境でした。でも、中学校になると、女性ばかりの保育士さんの中に入るのが恥ずかしくて、保育園から遠ざかっていたんです。
それが母からの誘いがあって、保育園を手伝うようになり、保育士に対するイメージが変わりました。保育士は一見子どもたちと遊んでいるだけのように思えても、実は綿密な保育プログラムにのっとって子どもたちの成長を促していた。遊びを通じて子どもたちがいろいろなことを学べるよう、日々工夫を重ねていたんです。保育園は単なる「託児施設」ではなく、心を育てる「保育の場」なんだとわかって、俄然、興味が沸いてきました。
新卒で入った保育園を、1年で辞めてしまうことに
保育の仕事に関心を持った僕は、大学の専攻を替え、保育士の資格を取得します。卒業後は、男性保育士として活躍することを夢見ていました。
しかし、実際は男性保育士の就職口がない。あちこち回ったのですが、「前例がない」「受け入れ態勢が整っていない」ということで断られてしまうんです。結局、実家に紹介してもらい、ある保育園に就職しました。そして、さまざまな経験から、育児に関する専門性をもっと身につけた方がいいと感じた僕は、就職と同時に、夜間の大学院にも通うことにしたんです。
朝6時に起床、朝7時から午後4時まで園の仕事、その後は立ち食いそばを食べて大学院へ。深夜に帰宅して持ち帰った仕事を片づける。そんな生活が1年続きました。しかしその後保育園を辞めてしまうんです。
女性だらけの職場で、働きづらかったこともありますが、僕が大学時代から考えて実現しようとしていたことを、ことごとく受け入れてもらえなかったことが大きかった。保守的な世界で、一人で闘うことの大変さを痛感しました。
園の子どもたちには、申し訳ない思いでいっぱいでした。現場に出たことで男性保育士の必要性も強く感じるようになっていた僕は、1年で園を辞めてしまった自分の弱さを責めながら、その悔しさをバネに「男性保育士の必要性」を世の中に訴えていくことを決意したんです。



その後、大学院を経て、
再び保育園に就職する。
27歳のとき、男性保育士を
支援する会社を設立。
注目を集めた。

保育園に男性がいないほうが不自然
子どもは、5歳までの間にだいたいの性格が形成されます。もともとの性格もあるけれど、育つ環境というのは非常に重要なんですね。その大切な時期に、朝から晩まで一緒に過ごす保育士の存在は大きい。保育園は「第2のおうち」なんです。ですから、家にお父さん、お母さんがいるように、保育園にも男性がいるのが自然でしょう。いないという固定概念を変えたいんです。
今は共働きの家庭が増えてきて、男性も子育てに参加しなくてはならなくなった。でも、実際はどうやって子どもと接すればいいのかわからない男性も多い。男性が育児休業を取得するのに、いい顔をしない上司も多いと聞きます。それは、子ども時代に男の人が子育てをする様を見ていないからなんです。男性保育士が子どもをあやしている姿を小さいころから当たり前のように見ていれば、ちゅうちょなく子育てに参加できる大人になる。ひいては男女共同参画社会も実現できます。保育士は日本の未来を変える仕事なんですよ。
何でもポジティブに考えるクセをつける
法改正もあって、保育園は単なる託児所ではなく、保育のプロとして、小さい子どもを持つ親の相談役として地域社会に貢献する役割を担うようになりました。僕が各地で講演をしたり、地元の子ども向けの無料コンサートを開いたりするのもその一環なんです。でも、保育業界はもともと保守的ですから、僕のようにいろんな取り組みをして、そのことをメディアを使って世間に広めようとすると、風当たりが強いのも事実です。よく「これまでで、いちばん大変だったことは、どんなことでしょうか」と聞かれますが、いつも壁ばかりだったから、ひとつはとても選べないんですよ(笑)。
でも、挫折や壁というのは、いくらでもチャンスに変えられると思うんです。嫌な思いをしたときに、いかにその悔しさをバネにするか。それができるかどうかで、人生は大きく変わってきます。僕はあえて、自分に試練を与えることで成長することができました。挫折も乗り切ったら、いい思い出になるんです。
何をやってもうまくいかないと思う人は、何でもポジティブに考えるクセをつけるといいですよ。最初は難しいかもしれないけど、試しに一度やってみてください。意外と好転するものですよ。僕も、けがをしてテニスをあきらめなければならなかったときに、親から「どんなに辛いことでも、ポジティブにとらえていかなければダメだ」と言われてやってみたんです。そしたら、いろんなことを学ぶことができた。天職にも巡り合うことができたんです。
まずは、外に出て体験してみること
僕は「子どもたちのためになる社会を作りたい」という夢を持っているのですが、その夢のためのルートはたくさんあります。どの道を行ってもいいと思うんですが、いざ、チャンスが訪れたときのために、準備だけは常にしておかねばならないと思っています。大学院の博士課程にも通い始めたのもそのためです。
準備の時間なんてなかなか取れないと思うかもしれませんが、時間は意外と作れるもの。僕の場合は、園長を務める保育園以外にも、講演会の講師、短期大学の准教授、保育園のプロデュースなど、いくつもの仕事を兼業していますが、時間を区切って集中して仕事をすることでやりくりしています。コツは、「睡眠時間は削らないこと。やるべきことを朝、書き出すこと。そして限られた時間の中で、自分を追い込んでいくこと」です。集中すると、かえっていい考えが浮かぶものですよ。
やりたいことや夢がどうしても見つからない人は、まず、外に出て何かを体験することをお勧めします。体験をすれば、気付きが生まれます。少しでも興味を持てたり感動したりしたことがあったら、関連する場所に行ってみる。それを繰り返すと、やりたいことが見えてきます。実は僕も、本当は家にいるのが好きな性格なんです。でもいろんなことを体験するために、思い切って、外に出るようにしているんですよ。
どうしても気分が乗らないときは、自分にささやかな楽しみを与えてあげるといい。僕は通勤途中に、近所のお店で大好物のミルクセーキを飲むんですが、そうするとテンションが上がるんです。後はお風呂に入るときにちょっと高いシャンプーを使ってみるとかね。些細なことでいいから、日常で気持ちをリセットさせる「ちょっとした楽しみ」をたくさん作っておくと、ポジティブに生きられますよ。

- EDIT/WRITING
- 高嶋千帆子
- DESIGN
- マグスター
- PHOTO
- 栗原克己
自分の「こだわり」を活かせる企業に出会うために、
リクナビNEXTスカウトを活用しよう
リクナビNEXTスカウトのレジュメに、仕事へのこだわりやそのこだわりを貫いた仕事の実績を記載しておくことで、これまで意識して探さなかった思いがけない企業や転職エージェントからオファーが届くこともある。スカウトを活用することであなたの想いに共感してくれる企業に出会える可能性も高まるはずだ。まだ始めていないという人はぜひ登録しておこう。