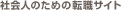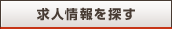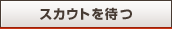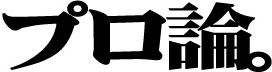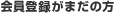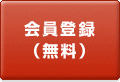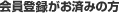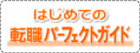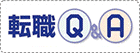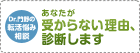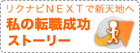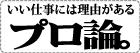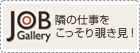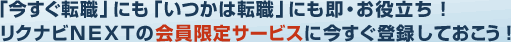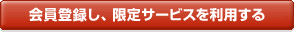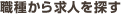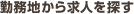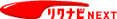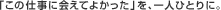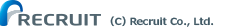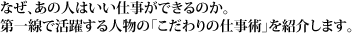
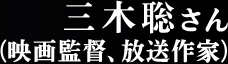



テレビドラマ『時効警察』、
映画『亀は意外と速く泳ぐ』、『転々』など、
次々と話題作を送り出してきた。
脱力系の笑いが満載の「三木ワールド」は、
いかにして生まれたのか。

目標なんて、そんなものどうだっていいじゃない
僕の場合は、「なりゆき」なんです。よく将来の目標を持てって言うでしょう。でも、目標を持たなきゃならない理由なんて、何一つとしてないと思うんですよ。「目標なんて、どうだっていい。今が面白ければ」。僕はずっとそれで、ここまできたんですよ。
20歳のときから、テレビ番組の放送作家をやっていたんだけど、それもたまたまなんです。大学の掲示板に「放送作家に興味がある人、来たれ! 研修生募集」みたいなポスターが貼ってあって。それを見た友人が「受けに行きたいけど、一人じゃイヤだ」というから、付き添いで一緒に受けに行ったんです。そしたら、友人は落ちて僕だけが受かってしまった。ダメなアイドル歌手のパターンですね(笑)。
だから、この世界に興味があって入ったわけでもないし、やり出すまで放送作家がどういう仕事なのかも知らなかったんです。テレビっ子でもなかったし、ドラマもそんなには見ていなかった。強いて言えば、『巨泉×前武ゲバゲバ90分!』とかそういうお笑い番組が好きで、よく見ていましたから、人を笑わせるということに興味はあったんでしょうね。
言い続ければ、大抵のことはなんとかなる
僕は「遭遇運」がいいんですよ。いいタイミングでいい人との出会いがある。20歳で放送作家の事務所に入って、最初はリサーチのような仕事をしていたんだけど、そのときに竹中直人さんのラジオ番組が始まるから参加しないかと声を掛けてもらったんです。コントを作ったりする若手の作家が必要だったみたいで。
それで、竹中さんやシティボーイズ(注:大竹まことさん、きたろうさん、斉木しげるさん、3人のコントユニット)の人たち、劇作家の宮沢章夫さんと一緒に仕事をするようになった。この出会いは大きかったですね。そこには、従来の放送作家にはない「自由さ」があったんです。「自由に物を作る面白さ」を知って、こういう仕事なら楽しいかもって思えた。
時代も良かったんですよ。そのころ日本はバブル景気で、僕が担当していた深夜番組の枠なんて、視聴率がどうのなんて、うるさいことは言われなかったんです。放送事故さえ起こさなきゃいいから、みたいな感じで好き勝手にできた。それで、この時代に関わった人たちから、「僕たちの仕事にとって第一義的なものは、自分が面白いと思っていることを提示することなんだ」と、物作りに対する根本の考え方を学んだんです。
じゃあ、自分が面白いと思うことをどうやって表現していくのか。具体的な表現手法なんかは、全部自己流です。1989年から2000年まで担当したシティボーイズの舞台演出も、特に誰かに教わった、ということはないですね。お客さんの反応を見ながら、なんとなくこういうことなのかなと手探りでやっていったんです。
僕は、誰かのやり方をマネして何かをするのが苦手で。それはもう、昔からそうなんです。脚本の書き方も映画の撮り方も誰かに教わったわけではない。全部自己流。それが合ってるかどうかなんて、全然わかんない。でも、いいんですよ。自信持って「面白いです」って、言っちゃえば。
大事なのは、「変えないこと」なんです。たとえスベっても変えちゃダメ。ウケないことでも言い続ければ、聞いてる方が「あれ?(笑わない)自分の方が間違っているのかな」ってことになる。こっちが正論になるんですよ。
まあ、ずっと待っていても、どうにもならないこともありますけどね。だけど仕事に関しては、言い続ければ大抵なんとかなるもんですよ。
何とかして動かそうという強い気持ちだけは持ってないと
初めて映画を撮ったときも、そうでしたね。ずっと舞台演出をやってきて40歳近くになって、映画というメディアも面白そうだなと思うようになった。それで、「小ネタ集」のようなコントを集めた映画を作れないかとプロデューサーに話を持ちかけたんです。すぐには企画が通らなかったけど、しばらく言い続けたら「そんなに言うならやってみようか」と、話に乗ってくれる人が現れた。
ちょうどそのとき、映画がフィルムからデジタルに移行したというラッキーな一面もありましたけどね。フィルムだと温度管理など難しいことがいろいろとあるけど、デジタルなら映画業界以外で育った人でも参入しやすかったんです。それで僕も、舞台演出の手法を取り入れて映画を撮ることができた。自分のやり方を変えなくても、周りの方が変わってくれて、やりたいことができるようになるってこともあるってことですね。
そのときに、何とかして誰かを動かそうという強い気持ちだけは必要ですよ。それがないと、他人はなかなか動かないから。僕の映画みたいにくだらないことだと言いづらいんですけどね。でも、それでも声を大にして言う。「くだらないんですけど、ぜひやりましょう」って(笑)。



「コントを集めた映画」。
自らの作品をそう表現する。
いくつもの「小ネタ」が積み重なって、
ストーリーが展開していく。
それが三木作品の魅力だ。

欲しいと思っている車は、よく見かける
「小ネタ」はどこから拾ってくるのか。よく聞かれますけど、僕は日常生活で面白いものにたくさん出会うんです。街を歩くだけで、思わず笑ってしまう変なものって、結構、見つかるんですよ。
やはり、興味の問題なんだと思います。欲しいと思っている車はよく見かけるでしょう。それと同じで、自分の興味がどこにあるのかってことです。自動販売機を設置する仕事の人は、道を見て「あと何個くらい自動販売機を設置できるかな」って考える。「こんなに人通りが多いのに、なんでもっと自動販売機を置かないんだろう」とかね。でも、僕にはそんな目線がないから、「このビル、エアコンの室外機がやけにたくさんあるなあ」って、そっちの方に目がいってしまうわけです。
興味って、人それぞれなんですよ。社会には、そのいろんな興味を許容する包容力があった方がいい。よく日本は明かりの色を統一しないから風景が雑然としているっていうでしょ。でも、それでいいと思うんです。いろんな色の光があるから面白いんですよ。
テンションを上げるきっかけは、意外と些細なもの
今度撮った映画『インスタント沼』の中で、「ある人にとってはゴミでも、ある人にとっては宝物。それぞれ物差しを持つことが楽しい」っていうセリフがあるんです。ファッション雑誌の編集者をクビになった主人公がアンティークショップを始めて、そう気付くんだけど、結局、人のマネをしててもつまらないってことですよね。誰かのやり方をマネしたって、その人にかないっこないんですから。自分のやり方だったら、常に自分が一番なんですよ。
映画の中の主人公は、雑誌が廃刊になったり、母親が入院したりと、数々の不幸が押し寄せてジリ貧の状況なんだけど、些細なことがきっかけとなって、生活が面白いものに変わります。テンションを上げるきっかけが欲しいって、よく人は言いますけど、そういうのって実はとっても些細なことだったりするんです。
結局、人生が面白いかどうかなんてのも、意識の問題なんですよ。以前、『亀は意外と速く泳ぐ』という映画を撮りましたけど、それは主婦がスパイになる話なんです。彼女は自分がスパイだと意識した途端、スーパーの買い物一つでも、ものすごく気を使うようになる。なんてことのない日常が、スリリングなものに一変するんです。
まあ、どうしてもテンションを上げる方法が見つからなかったら、何もしないで寝ちゃうこと。これも『インスタント沼』のセリフにあるんですが、「一晩寝れば大抵のことは忘れられる」。そういうもんです。一晩寝ることによって客観的になれるっていうんですかね。不幸を客観視できるようになるんです。そしたら「これってそんなに騒ぐほど辛いことか」と思えるようになりますから。そうすると楽になりますよ。



三木聡監督作品
編集長を務めていたファッション雑誌が売れ行き不振で廃刊、母親が沼に落ち意識不明の重体、好きだったカメラマンも同僚にとられて失恋と、数々の不幸が押し寄せてきた主人公ハナメ。ジリ貧生活の中、偶然出てきた母親の書いた古い手紙から、実の父親が別の人物であることを知る。住所をもとに訪ねていった先には、胡散臭い骨董屋の店主がいた。彼の破天荒な助言を聞いているうち、彼女のつまらない生活が一変していく。脱力系の笑いが満載の三木監督作品、オリジナル脚本の最新作がいよいよ公開に。
監督・脚本/三木聡 出演/麻生久美子、風間杜夫、加瀬亮、松坂慶子、相田翔子、笹野高史 など 配給/アンプラグド、角川映画 2009年5月23日(土)よりテアトル新宿、渋谷HUMAXシネマほか全国ロードショー
©2009「インスタント沼」フィルムパートナーズ
- EDIT/WRITING
- 高嶋千帆子
- DESIGN
- マグスター
- PHOTO
- 栗原克己
自分の「こだわり」を活かせる企業に出会うために、
リクナビNEXTスカウトを活用しよう
リクナビNEXTスカウトのレジュメに、仕事へのこだわりやそのこだわりを貫いた仕事の実績を記載しておくことで、これまで意識して探さなかった思いがけない企業や転職エージェントからオファーが届くこともある。スカウトを活用することであなたの想いに共感してくれる企業に出会える可能性も高まるはずだ。まだ始めていないという人はぜひ登録しておこう。