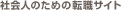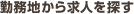転職トップ > 転職成功ノウハウ > 転職成功パーフェクトガイド > どーする!?応募・面接準備 > 面接で、ホントに腹が立った応募者たち
転職トップ > 転職成功ノウハウ > 転職成功パーフェクトガイド > どーする!?応募・面接準備 > 面接で、ホントに腹が立った応募者たち
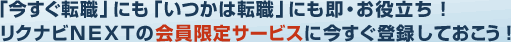
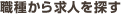
※このページへのリンクは、原則として自由です。(営利・勧誘目的やフレームつきなどの場合はリンクをお断りすることがあります)
転職トップ > 転職成功ノウハウ > 転職成功パーフェクトガイド > どーする!?応募・面接準備 > 面接で、ホントに腹が立った応募者たち
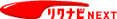 |
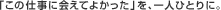 |