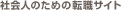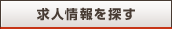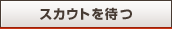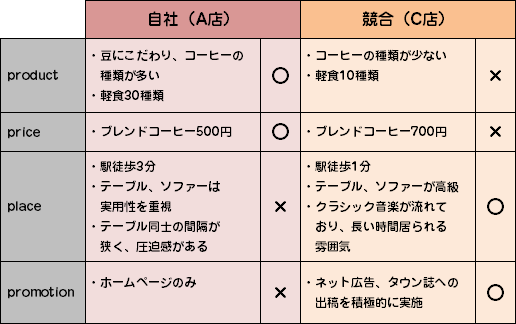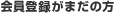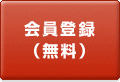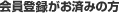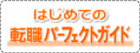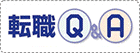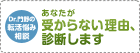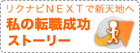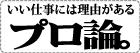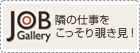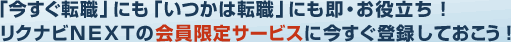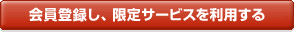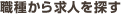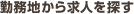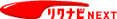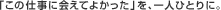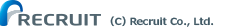転職トップ > 転職成功ノウハウ > 転職パーフェクトガイド > 求人の探し方・選び方 > 「3C」「4P」の戦略基本フレームで自社の経営戦略を自分なりに評価する方法
自社の経営戦略を自分なりに評価する方法
企業の経営戦略を見れば、その会社が将来成長しそうか、生き残っていけそうかを判断できる場合が多い。ではどんな視点で戦略を分析すればいいのだろうか?成長できる方向に進んでいるかどうか、自分の力で見極めるための方法を紹介しよう。
2012年3月7日

戦略の善し悪しが企業の将来を左右する!
見極めに必要な視点とは?
変化が激しい今のような時代においては、企業がどんな戦略を持って前に進もうとしているかを知ることが、その企業の善し悪しを判断する有益な材料の一つになるだろう。正しい戦略が立てられる会社は、成長力がある。こう断言してもいいかもしれない。
もし、「専門家でもないのに、経営戦略が正しいかなんて判断するのは無理に決まっている」などと考える人がいたら、ぜひ思いを改めてほしい。なぜなら、ポイントさえ押さえれば、経営戦略の妥当性を評価することは誰にでもできるからだ。自分の生き方・働き方に関わってくる大事なことだからこそ、他人任せにせず、自ら判断したいもの。今回は、そのための方法を説明していこう。
【STEP1】「3C分析」で自社の現状を把握する
覚えておきたい3つの視点
自社の経営戦略の方向性が間違っていないかを自分自身で見つけるためには、まずは自社についての分析が必要だ。自社が、今現在どのような経営環境に置かれているのかを調べるために欠かせないのが、次にあげる「3C」だ。すでにご存知の方も多いだろうが、実際に使ってみると、特に「competitor(競合)」を適切に設定できていないケースもあるという。
・customer(顧客):自社の製品やサービスを利用する潜在顧客はどんな人なのか。顧客数や地域構成などの市場規模や、市場の将来性はどうなっていくのか。
・company(自社): 自社の売上高や市場シェア、ブランドイメージ、技術力はどれくらいのものなのか。自社の経営資源はどんな特性があって、どの程度の量があるのか。
・competitor(競合):競争相手はどんな商品(サービス)を提供できるのか。現在の競争状態はどうなっているのか。
自社の経営戦略を調べる方法とは
ここからは、具体的を交えながら説明していこう。
【例】値下げ戦略を断行するか迷っているコーヒーショップA店の場合
<コーヒーショップA店の現状>
・お店は都心からも近い私鉄沿線で、駅から徒歩3分の場所にある
・豆の仕入れ先に特にこだわっており、ブレンドコーヒーは一杯500円。軽食のメニューも約30種類あり、ある程度充実している
・半年前、200メートル先のご近所に「コーヒーの安さがウリのチェーン店のコーヒーショップB店」ができる。ブレンドコーヒーは一杯200円。それによって売り上げは徐々に下がり始めた。
<A店の3C分析をしてみよう!>
・customer(顧客):毎日決まった時間に来て、同じものを頼む常連客が多い。また、近所に出版社などが入っているオフィスビルがあるため、仕事の打ち合わせや、待ち合わせ場所として長時間利用するお客が多く、「気軽な短時間の時間つぶし」で利用する人は少ない。B店ができて以来、10代や20代の学生や若者の利用が激減し、30代・40代の男性が席を占めるようになった。
・company(自社):売り上げは半年前と比較すると約3割減。顧客1人あたりの平均単価は700円程度。軽食のメニューを頼む人はだいたい3人に1人。どちらかといえば「落ち着いた雰囲気で、本格派のコーヒーが楽しめる店」というイメージを持たれている。
・competitor(競合): 顧客は200メートル隣のチェーンのコーヒーショップB店とは異なる。自社の状況と照らし合わせて考えると、B店は、競合とすべきところではないのではないか。むしろ顧客層が同じ「駅前のホテルのラウンジにある喫茶店C店」がライバルになりそう。
<A店が取るべき戦略>
真の競合である「駅前のホテルのラウンジにある喫茶店C店」との差別化を図る必要性がある。
【STEP2】「4P」の視点から自社と競合を比較してみる
比較することで「正しい戦略」が見えてくる
“自社の強み”や“本当の競合”を明確にすることができたら、次は競合と自社とを比較検討してみよう。競合との関係性の中で、強みや弱みをはっきりさせることができれば、どの方向を目指して戦略を立てればいいかが見えてくるもの。比較検討を行う際は、次の「4P」について考えることが大切だ。
・product(製品・サービス・品質)
・price(価格・割引)
・place(立地・流通・販路)
・promotion(広告宣伝)
この「4P」それぞれについて、競合と比較して「優れていれば○」「弱い場合は×」を記入し、表を埋めていこう。表にして並べることで、自社の強みや弱みが競合相手と比べてどうなのかが把握でき、課題が見えてくる。つまり、「とるべき戦略」がわかるというわけだ。今現在の戦略の内容と照らし合わせれば、自社の経営戦略を客観的に判断することが可能になる。
コーヒーショップA店の例を使って、表を作成してみよう
STEP1でとりあげたコーヒーショップを例にすると、上記のような表ができる。
それぞれ、○と×の部分を比較検討していけば、「○の部分を活かす」「×の部分を改善する」という戦略の方向性が見えてくるはず。
上記をふまえ、競合相手を意識した戦略として、例えば以下が考えられそうだ。
<○の部分を活かす>
●コーヒーの質を上げる
例…他店ではなかなか飲めないような珍しい豆を仕入れる、日替わりでメニューを変えて常連客が飽きないように工夫する
●おかわりサービスを導入する
例…価格を下げるのではなく、長時間の利用客のためにおかわり無料サービスを導入する
<×の部分を改善する>
●お店の内装を変え、居心地のいい空間を演出する
例…座り心地のいい椅子やソファーに変える、高級な食器でもてなす、BGMはジャズにする、外での打ち合わせが多い業界関係者を中心に営業をかけて認知度を上げる
●集客のための新しい広告宣伝手法を実施する
例…ソーシャルメディアでの広告を実施する、近隣住民へのポスティングを実施する
このように順序立てて考えていけば、「近所に低価格のお店ができた→値下げで対抗」といった安易な戦略立案だけではない、本来の強みを活かした戦略がわかる。自分自身でイチから企業が進むべき方向性を考えることは難しい。しかし、進もうとしている方向が正しいかどうかを客観的に見極め、判断することは、一人でも十分にできる。そのためのポイントになるのが「3C」であり「4P」なのだ。
企業の戦略によって、社員に与えられるミッションは変わる。働き方が変われば、得られるやりがい・スキルも大きく変わってくるだろう。現在の会社に対してだけでなく、転職先を見極める際にも有効な「経営戦略を評価する方法」、ぜひとも頭に入れておこう。
「自社の経営戦略を評価する」モノサシを持とう
「経営戦略を評価する」というと、とても大げさなように聞こえるかもしれない。しかし、この不安定な時代においては、時代の流れを読んだ戦略のもとで、心から納得できるミッションを遂行できることが、自分自身を大きく成長させることにつながるはずだ。物事を客観的に見て判断することは簡単ではないが、コツさえつかめばできるようになってくる。今回紹介した「3C」「4P」といった視点を上手く取り入れて、納得して働ける環境を探してみよう。
リクナビNEXTスカウトで、さまざまな企業を比較検討してみよう
リクナビNEXTスカウトを利用すれば、これまでに知らなかった業界や職種について知るチャンスが増えるだけでなく、幅広くビジネスについての理解が深まる。新期事業の立ち上げメンバーの募集などでは、今後の企業の戦略が語られることも多い。多くの企業と接点を持つことで「経営戦略を評価する」知見もたまっていくはずだ。まだ始めていない方は、さっそく登録してみよう。
- EDIT
- 高嶋ちほ子
- WRITING
- 志村 江