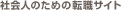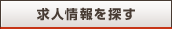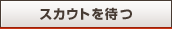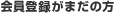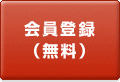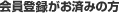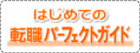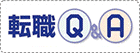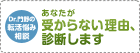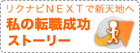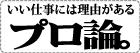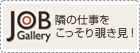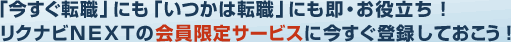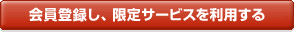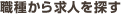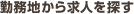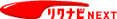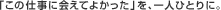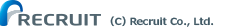転職トップ > 転職成功ノウハウ > 転職パーフェクトガイド > 転職活動 基本の「き」 > 人間関係の悪化原因を解明するための9つの方法
人間関係の悪化原因を解明するための9つの方法
仕事をするうえで、大敵といえるのが人間関係のストレス。周りとの人間関係がうまくいかず、ストレスを感じてしまった時、その理由をじっくり考えてみたことはあるだろうか。自分自身の行動や発言を振り返ってみることで、関係が悪化してしまった原因を突き止めることができれば、今後よい関係を構築していくための対策も考えられるはず。今回は人間関係が悪化している原因を発見するための思考法/行動術を、3人のプロにうかがった。
2011年10月26日

<ADVISER>

|
株式会社グロースサポート |

|
心理カウンセラー |

|
臨床心理士、カウンセラー |
思考・行動変革トレーニングのプロ・木村英一氏に聞く
苦手な人と「こういう関係になりたい」と目標設定する
ストレスには2種類あります。いいストレスは,行動を促す原動力になる、「パワーに変えられる」ストレスです。一方、悪いストレスはやる気を削ぎ、心身に多大なダメージを与えます。後者の悪いストレスは、場所を変えればなくなるわけではありません。一度乗り越えていかない限り、どこにいても繰り返し起こるものなのです。
人間関係のストレスの場合は、ストレスを感じている相手との関係において「こうありたい」という目標を設定しなおすことが、一番の原因追及のためのヒントになります。例えば上司と関係が悪くなり始めた場合、「どういう関係になればいいのか」を考えてみるんです。「朝、あいさつをして、返してもらえるような関係になる」といったことで構いません。目標設定できたら、「なぜ今あいさつできる関係になれないのだろう」ということを深く考えてみましょう。今、関係が悪化している原因が見えてくるはずです。
今やっている仕事と期待されているレベルとのズレを認識する
仕事のアウトプットに対する認識の違いが、人間関係を悪化させる原因になっているケースもあります。職場の人間関係でストレスを感じる根っこになるものは、「自分に期待されていることがわからない」ことへの不安によるものが多いのです。自分のしている仕事が本当に求められているものなのか、ふたを開けてみて「そうじゃない」と言われたらどうしようという不安です。そういう「期待値のズレ」が生じないよう、今やっている仕事が本当に求められているものなのか、評価をする人に常に確認しておくことが大事です。上司がどんなアウトプットを求めているか、すり合わせた内容については紙やメールなどで形に残し、関係が悪化していると感じた際には、その内容を確認し、関係が悪化している原因となっているかどうかを探ってみましょう。
自分の「悪い点」「改善すべき点」を近しい人に聞く
人間関係を悪化している原因を探るためには、自分を知ることは大前提です。最も良い方法は、できるだけ多くの人に「自分の悪いところ」「自分が改善すべきところ」を聞くことです。仲のいい人だけでなく、別の部署の上司や、一緒に仕事をしている取引先の人などでもいいでしょう。ただし、「実は○○さんとの人間関係に悩んでいて、その原因を探るために教えてほしい」とは決して言わないこと。親しい人ほど、同情されて終わりになってしまうからです。あくまで「今後、自分が成長するための糧にしたいので教えてほしい」というふうに意見を求めることです。いろいろな立場の人の客観的な意見は、面白い発見につながるでしょう。自分の考えに偏りがあることを確認できたり、立ち居振る舞いにどんな問題があったかを気づくきっかけになるはずです。
心理療法/カウンセリングのプロ・心屋仁之助氏に聞く
「○○であるべきだ」という考えを疑う
あなたの“思い込み”や“固定観念”が人間関係を悪化させてしまっている原因かもしれません。人間関係が悪化している場合、双方に何らかの歪みが生じています。それがどうして起こるのかといえば、「○○であるべきだ」という“決めつけ”が理由であることが多いのです。「こうあるべきなのに、そうではない」という、あなたの期待値と周囲の現実が噛み合わず、人間関係や職場でのストレスを引き起こしてしまうのです。
例えば「上司が自分のことを理解してくれない」と悩んでいるとしましょう。その場合、「上司というものは、部下のことを理解するべきだ」という基準で考えてしまっているため、ズレが生じてしまっているのです。「会社からの評価が低すぎる」というストレスの場合も、「会社というものは、社員の能力を正当に判断し評価するべきだ」という思い込みが原因。「部下が言うことを聞かない」場合も、「部下は上司に従うものだ」と決めつけてしまっているために齟齬が生じるわけです。まずは、自分自身の中にある“思い込み”や“固定観念”を探し出してみましょう。そして、それが見つかったら、「○○であるべきではないのかもしれない」とまずは疑ってみるようにしてみてください。自分だけの勝手なこだわりが崩れていくはずです。フラットな状態で考えることによって、関係が悪化している原因が見えやすくなります。
「嫌われてもいい」と口に出して言う
自分自身ではうまくやっているつもりでも、なかなか周囲と打ち解けられなかったり、うまくかみ合っている感じがしないなんてことがあるかと思います。実は、人というものは無意識のうちに「嫌われたくない」という基準で行動してしまっているものなんです。例えば「面倒がられると悪いので、仕事を頼まないでおこう」「無理な要求だとわかっているが、断るのはやめよう」「否定されるのがこわいので、会議では発言しないようにしよう」などということはありませんか。そして、そんな振る舞いを続けているうちに、自分自身をどんどん抑圧してしまい、我慢がつのって、無意識のうちに「どうせ自分なんて…」「体制がおかしいんだ…」と、すねやすくなってしまうものなのです。「人に嫌われたくない」と思えば思うほど、知らず知らずのうちにストレスが増え、結果、周囲との接し方がどんどんズレて、人間関係が悪化してしまうのです。
すでにその状況になっている場合には、まずは、「嫌われたくない」と思っている自分を認識してあげましょう。それができたら、いい意味で「嫌われてもいい」と開き直ってみるのです。例えば「嫌われてもいい」と一人で声に出して言ってみる。それだけで、これまでは「してはいけない」と考えていたことが、「してもいい」ことに早変わりします。この開き直りが肩の力を抜き、周囲とのコミュニケーションを前向きなものに変えるのです。周囲の人と円滑なコミュニケーションが取れるようになれば、今までなぜ関係が悪化していたのかも見えてくるはずです。
苦手な人の「どこが嫌なのか」を人に話す
実は、他人の「嫌だなあ」と感じる部分というのは、自分自身の中で抑圧している部分であることが多いのです。例えば、細かく注意する上司の存在がストレスだという場合、ホントは細かく人に干渉したいのに、「嫌われたくない」などと無理に我慢していることが多いのです。つまり、「人のどこが嫌か」を知ることが、自分の潜在的な、根本にある願望を知るヒントになるのです。
そのために、気兼ねなく話せる友人同士で、「自分が嫌いな人はどういう人か」を話してみるといいかもしれません。そして、話した内容を自分自身の行動と照らし合わせてみてください。自分自身を客観的に見つめる中で、実は「自分にはできないことを平気でできる人がうらましいだけだった」なんてこともあるものです。それがわかるだけでも、人との接し方が変わるきっかけになるのです。
臨床心理学のプロ・向後善之氏に聞く
自分自身の「自動思考の癖」を知っておく
人にとって、対人ストレスというものは大きな不安であり、恐怖です。原因追及のヒントになるのが、そうした不安・恐怖と直面した時に、「自分自身がどういう考え方(自動思考)になるか」を分かっておくこと。以下に代表的なものを挙げてみますので、自分がどれに当てはまるかを考えてみてください。
1.先行きを悲観する(やっぱり私はこういう運命なんだ)
2.自己否定する(私は最低な人間だ)
3.自責の念にかられる(私が全部悪いんだ)
4.あきらめる(何をやっても無駄だ)
5.強くあきらめる(どうせ私は何をやってもダメだ)
6.完璧主義になる(何とかしなければならないのに…)
7.思い込みが強くなる(みんな私を嫌っているんだ)
8.否定的結論を先取りする(私に改善できるわけがない)
9.恐怖を先取りする(絶対に悪いことが起こるに違いない)
10.思考停止する(どうしよう、どうしよう…)
11.被害者的思考に陥る(何で私ばっかりが)
12.後悔する(何てことをしてしまったんだ)
上記のような「自動思考の癖」を自己認識するだけで、対人ストレスへの対処法が変わってくるのです。自分のタイプを認識することでそれまでとは人間関係の取り方が変わり、状況が改善に向かう場合が多いです。まずは自分自身の自動思考を知る。これが関係悪化の原因を追究するうえで大切なことです。
「感情」を否定せず、「行動」をコントロールする
人が前に進むための一番大きな原動力は、実は「感情」なんです。感情を抑圧しようとしたり、無理にねじ曲げようとすれば、自分自身との折り合いがつかなくなります。人間関係が悪い時こそ、まずは「相手に腹が立っている」という感情をきちんと受け入れること。これが原因追及のために大事なのです。一度感情を受け入れることで、冷静になることができ、腹が立っている相手のどこに腹が立っているかが見えてきます。冷静に考えて「納得のいかない」と思った部分が、関係が悪化している原因となっていることが多いです。原因が究明できていれば、その後は冷静な判断で「行動」をコントロールすることができるようになります。無理に相手を好きになろうと努力することは逆効果ですし、それでは根本的な解決にはならないのです。
多様性に寛容な人に「私のどこを変えるべきか」を聞く
人に聞くことで原因追究をしようという場合、「私のどういうところを変えてみるといいと思う?」と、ストレートに聞いてみるのがいいでしょう。ただし、問題は「誰に聞くか」。もちろん気兼ねなく話せる人が一番いいのですが、大事なのは「日頃から主義主張の強すぎる人」「よく『○○するべきだ』と言う人」は避けるべきだということです。人間関係が悪化した原因を探るためには「客観性」が大事。「多様性に対して寛容である人」を選んで相談し、客観的な視点でアドバイスをもらうことが、前向きに原因追及するためには必要です。
人間関係悪化の原因把握は、これから良い関係を築くための第一歩
ストレスなく働けるのが一番なのは言うまでもない。ただ、実際にストレスを感じている場合は、向後氏が言うように「無理に自分自身の感情を変えようとしない」ことが大事。そのうえで、冷静に物事を見るように努力してほしい。人はストレス状態になると肩に力が入り、背中が丸まって下を向きがち。意識が上半身に集中しすぎることで、地に足がつかなくなる。そんな状態では、まともな判断を下すのも難しいもの。まずは深呼吸したり、人に話すことで一旦立ち止まってみて、冷静な状態で次の行動を考えてみよう。今回のアドバイスを参考にして人間関係が悪化している原因を突き止めることができれば、それが周囲と円滑な関係を築くための第一歩となるはずだ。
リクナビNEXTスカウトを有効活用して
自分に合った新しい環境を探してみよう
「リクナビNEXTスカウト」に登録することで、思わぬスカウトが届くことがある。これまでに意識しなかった企業について知るきっかけになるだけでなく、思いがけない魅力を発見し、新たに興味を持つことがあるかもしれない。もし、今の職場で人間関係について悩んでいるのなら、新しいステップに踏み出すためきっかけにしてみるのもいいだろう。新しい環境で、今までとは違った新たな人間関係を築ければ、さらに毎日が面白くなっていくはずだ。
- EDIT
- 高嶋ちほ子
- WRITING
- 志村 江