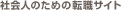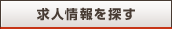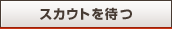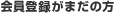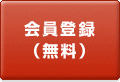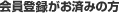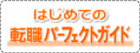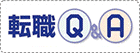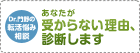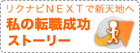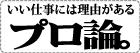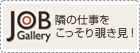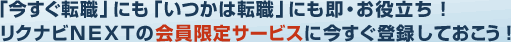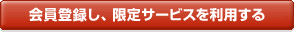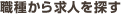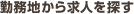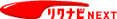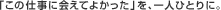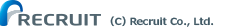転職トップ > 転職成功ノウハウ > 転職パーフェクトガイド > 転職活動 基本の「き」 > 営業職のための自分売り込み術
営業職のための自分売り込み術
営業職を経験することで身につくスキルは沢山ある。中でも、普段当たり前のように取り組んでいる「お客様に商材を売りこむ仕事」は、実は転職活動にもそのまま応用可能なのだ。今回は、営業手法を応用した転職活動テクニックを紹介する。
2011年12月21日

<ADVISER>

|
株式会社キープレイヤーズ |
営業経験者ならわかる!「自分を売り込む」ための5つのポイントとは?
営業職で身につけたスキルは、転職活動にそのまま応用できる
営業職は「自社の商品やサービスなどの魅力を伝えることで、商品の購入を促し、利益に結びつける仕事」をしている。放っておいても売れてしまう商品でない限り、あの手この手を駆使して、顧客に商材を買ってもらうための策を考えるはずだ。営業職に従事した経験がある人にとってはきわめて当たり前の話だが、実はこの考え方はそっくりそのまま、「転職活動」に当てはめることが可能。つまり、「自分という商品」を、転職したい企業に対して売り込むと考えれば、転職活動でやるべきことが自ずと見えてくるのだ。
そこで、数多くの営業職を転職成功に導いただけでなく、自身も営業経験が豊富な人材コンサルタントの高野秀敏氏に、優秀な営業担当が行っている営業手法について話をうかがった。営業をするときの流れについても、あわせて整理していこう。
1、商品の特性を知る
商品を営業するために必要なことは、まずその商品の特性を知ることだ。優秀な人は、商品の資料を読むだけでなく、その商品を作った人に話を聞いてみるという。「例えば、扱う商品がソフトウェアだったら、設計・開発・運用保守に携わっているエンジニアに話を聞いてみるといいでしょう。その商品を作ることになった背景、独自性、優位性など、その商品の長所だけでなく、競合商品と比べて短所となる点も確認しておきます。他社製品との違いを明確にしておくことが重要です」(高野氏)。
2、ターゲット(顧客)を決める
次に、顧客選定の仕方を考えてみよう。営業職が顧客を決める際には(A)業界、(B)会社の規模、(C)エリアの3つの視点で絞っていくのが基本的なパターンだ。
商品の特性によって、重宝される業界は異なる。例えば同じ「接着剤」という商材を取り扱っていても、「価格は安いが、粘着力が弱い」「粘着力は強いが、異なる素材のものは接着できない」などの特性によって 必要とされる業界は異なるため、売りこみ先は変わってくるのだ。「金融、通信、不動産、出版など、営業したい商品がどこの業界で重用されるのかを考えてみるといいですね」(高野氏)
3、相手のニーズを知る
ホームページやプレスリリース、ソーシャルメディア上の情報など、インターネットを使って顧客情報を調べるのはもちろんのこと、優秀な顧客と会う前に、ターゲットの会社の展示会やイベントなどリアルに接触できる場に参加してみるのだそうだ。「何らかの形で事前に会社の雰囲気を知っておくと、相手のニーズをつかみやすくなります。また営業先の商品を使ってみるのもいいですね」(高野氏)
4、企画書作成&プレゼンテーション
顧客に営業する時に、手ぶらで訪問する人はいない。受注に結びつけるためには、しっかりとしたプレゼンテーション資料を作成していくことが重要だ。優秀な人は、想定した相手のニーズに応じて、自社製品のどの長所を強調した資料を作るか検討して、企画書を作り分けている。「私は、“30秒、3分、30分”をキーワードに、3パターンの資料を作成して持っていきます。あまり時間をいただけない相手には30秒で読めるプレゼン資料をお渡しして、概要をつかんでいただきます。それで相手の心をつかんだら、次は3分で読める資料をお渡しする。相手の都合に合わせてプレゼン資料の分量を考えて渡すことは非常に重要です」(高野氏)
5、提案をする
実際に訪問して顧客と話を聞き、実際のニーズを聞き出す。「顧客のニーズを探るコツは、“提案をしながら聞き出す”ことです。質問をするだけでなく、こちらから解決策を提案することで、その提案がずれていたとしても話が広がり、顧客が気づいていなかった真のニーズを聞き出すことができます。新たなニーズを発見できたら、それに合わせて商品のどの長所をアピールするのかを変えていきましょう」(高野氏)
営業の流れを“転職活動”に置きかえてみよう
これまでの高野氏のアドバイスをもとに、実際の転職活動の流れと置き換えながら「自分を売り込むための方法」について考えていこう。
1、商品の特性を知る
転職活動をする上で、もっとも大切なのが「自己分析」。自分でキャリアの棚卸しをしてみることは大前提。「商品の特性を知る」フェーズで「さまざまな人に話を聞くこと」が重要だったように、「自分」という商品について第三者に客観的な意見をもらうことが大切だ。「まずは信頼できる同僚に自分の長所、短所を聞いてみましょう。関係がいいならば上司に聞いてみるのも手。その際は、「もっと会社に貢献できるように自分の長所と短所を抑えておきたい」というスタンスで話をうかがうといいでしょう。いずれにせよ、自分より仕事ができると思う人に聞くのがポイントです。第三者に話を聞くことで、ほかの人にはない自分自身の強みや魅力を明確にしておきましょう」(高野氏)。もちろん人材紹介会社に登録して、人材コンサルタントに自分のキャリアを見てもらうのも有効だ。
2、ターゲット(顧客)を決める
転職先は同じ業界を考えがち。しかし、自分自身の長所は何かを考えると、それを活かせる業界は異なるはずだ。全く想定していなかった異業界にも活躍の舞台があるかもしれない。
「営業という仕事は非常に汎用性が高い職種です。積極的に異業種への転職も視野に入れて考えていくといいでしょう」(高野氏)
3、相手のニーズを知る
応募先が今回の募集で求める人物像について、インターネット上の情報や求人欄、雑誌などに掲載された経営者インタビューなど、あらゆるツールを駆使して情報収集をする。営業では、課題を聞き出すために実際に担当者に会って話を聞くが、転職活動では、応募前に採用担当者に会うのはなかなか難しい。その際に有効なのが、採用情報に書かれている“募集の背景”だ。その企業がどんな理由で人を採用したいのか、というのはその企業の「人材ニーズ」。自分の売りになるスキルと企業側のニーズが合致しているほど、採用される可能性が高まるといえる。
4、企画書作成&プレゼンテーション
プレゼン資料にあたるのが、自己PRや職務経歴書だ。応募先企業のニーズに合わせて、自分という商品の強みや魅力についてわかりやすく伝えるだけでなく、自分を雇うことでもたらされるメリットについても明確にしておこう。「人事担当者はたくさんの応募者の職務経歴書に目を通すわけですから、書類の枚数は少なく簡潔に、そして強みが何なのかすぐにわかるように書き方を工夫しましょう。自分の強みに下線を引いたりして見やすくするのがポイントです。また、実績は数字で示し、成果だけでなくプロセスも具体的に書くといったことも重要です」(高野氏)
5、提案をする
顧客のニーズに合わせて自社製品のどの長所を強調するかを変えていったように、面接の場でも企業のニーズに合わせて、自分の強みやアピールするポイントを変えていくことが重要だ。「事前にいくら想定してアピールポイントを考えていっても、いざ面接をしてみると、自分が思ってもいなかったことに相手が興味を示すこともあります。2次面接の前には、1次面接で聞かれたことを思い出し、どんな答えをしたら相手のニーズと合うのか、話す内容をブラッシュアップしていくといいでしょう」
【実践編】
「旅行代理店の営業」からの転職を検討しているAさんの場合
1、商品の特性を知る
自分自身の成功体験から、強みを以下のように洗い出してみた。
2、ターゲット(顧客)を決める
3、相手のニーズを知る
上記の条件から、提案の自由度とこれからの成長が期待できそうだということを考えて「ソーシャルゲーム業界の営業職」を応募先に決定。複数の企業を比較検討した。絞り込んだ1社について、募集背景から相手企業が求めるニーズを読み取った。
4、企画書作成&プレゼンテーション
5、提案をする
提案は面接での質疑応答に応用できる。「あなたの経験は弊社でどのように活かせますか」と聞かれた時には、「自分」という商品のメリットを伝えることを意識して回答する。
自分の営業活動の中に「転職成功」のカギがある
実際の営業手法を転職活動に取り入れられることは意外と見落としがちだが、実践イメージが沸きやすく、実に有用性が高い。ポイントだけを頭に入れておくだけでも、応募先の選び方やキャリアの棚卸しの仕方など、転職活動のためのさまざまな取組みへの意識が大きく変わるはず。さらに、上手に「自分」を売り込める人は、採用担当者に「営業スキルが高そうだ」という印象を与えやすいものなのだ。
リクナビNEXTスカウトを活用して
あなたのスキル・経験に注目した企業からのオファーを待とう
営業職での経験を活かしてさらなるステップアップを目指したい…と思ったら、リクナビNEXTスカウトの活用を。自身のスキルをアピールした匿名レジュメを登録しておけば、その内容を評価した企業からオファーが届く仕組みだ。営業職で身につくスキルは汎用性の高いものが多いため、過去の業務内容、経験の深さだけでなく、自身の業務範囲や役割、その成果までを明確に記すことが、業種・職種を問わず、オファー獲得のポイントになりやすい。思わぬ企業からオファーが届くこともあるので、チャンスを逃さないためにも、今すぐ登録してみよう。
- EDIT
- 高嶋ちほ子
- WRITING
- 志村 江