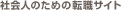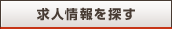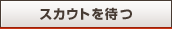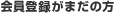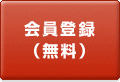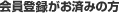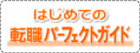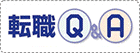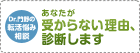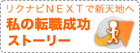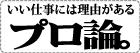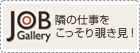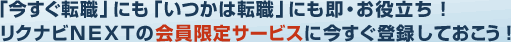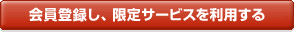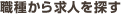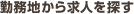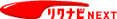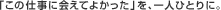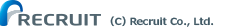転職トップ > 転職成功ノウハウ > 転職パーフェクトガイド > 転職活動 基本の「き」 > 猪子寿之×片桐孝憲対談「個人よりチーム力で挑め」
猪子寿之×片桐孝憲対談「個人よりチーム力で挑め」
IT・Web業界において、独自のスタンスを貫く経営を展開しているチームラボとピクシブ。今回、両社代表の猪子氏と片桐氏の対談を通して、これからの若いエンジニアに期待したいこと等についてざっくばらんに語っていただいた。
2013年4月3日

<ADVISER>

|
猪子寿之氏 |

|
片桐孝憲氏 |
「何かわからないけど面白いことしてそう」な若いエンジニアが好き
―まず今回、IT・Web業界でご活躍されているお二人が、若いエンジニアに対してどのようなイメージや評価をされていますか?
片桐:これは猪子さんと全く同じ考えなんだけど、そもそも僕たちは「若いエンジニアが好き」ということは断言できます。うちにも若いエンジニアが数多く活躍していますけど、中でもアルバイトで入ってもらっている16歳のエンジニアがすごいんですよ。何を作るにも早いし、技術の習得スピードも速い。それに自分より後に入社したのに、強気なのがいい(笑)。
猪子:そうそう。うちにも20代前半の若いエンジニアがいっぱいいて、特に最近一緒に仕事する機会が多いんだけど、何言っているかわからない(笑)。でもその「何言ってるかわからないけど、わけわからんもの作っている」っていうことがいいし、作っているものを見ているだけで楽しくなる。
そういえば片桐さん、「音ゲーやばい!」ってよく言ってる若いエンジニアがいるよね?
片桐:ああ(笑)、社員でもバイトでもないんだけど、社内にオーストラリア人で、ユーザーからの寄付だけで音ゲーを作っているエンジニアがいる。最初見たとき、純粋に「うわあ、すげえ!」ってすごくわくわくしたんだよね。
でもチームラボでも、「トイレが今空いているかどうかすぐわかるツール」とか若いエンジニアが作っているのをみて、ビジネス抜きにしてやっていることが面白いなと(笑)。
―両社ともそれだけ才能のある若いエンジニアが自由に活躍されている背景には、何か理由があるんでしょうか?
猪子:強いて挙げるなら「文化を育てる」ことに対して、何より興味がある点かな。短期的にユーザー数を増やすとか、PVを増やすとか、売上や利益を増やすことよりも、文化を育てたいという思いが強いよね。
そういう意味でpixivはまさにイラストを介してコミュニケーションを図る文化を築こうとしている。
片桐:確かに猪子さんも僕も、数字とか利益よりも面白いこと、楽しいことをとことん追求するタイプだから(笑)。例えばGoogleもFacebookも、それぞれが理想の文化を築こうとしているし、どちらかというと僕たちはそちらに近いかも。
猪子:pixivの場合、ただイラストをアップして見せるだけならFacebookでもTumblrでもいいし、もしかしたらそっちの方が便利かもしれない。でもそうではなくて、あくまでイラストを主役にして言葉を交わさなくても通じ合える場を作ったことが文化だし。
僕がよく使う「アート」と言う言葉も文化と同じような意味合いで、言葉とか論理とかで説明できないような価値をいつも探しているし、そこに意味があるんだと思いますね。
日本では、斬新なサービスを生み出していくことが難しい環境
―文化を大事にされる姿勢は、ともするとビジネスを運営していく上で、難しい面も出てくると思います。これまで苦労したり悩んだりされたことも多いのではないでしょうか?
片桐:pixivが短期間で急成長を遂げた2008年、資金繰りが厳しくなった時があって。サービス自体が大きくスケールアップすることはわかってましたけど「このサービスをどうやって収益化したらいいのか?」わからなくて(笑)。それで資金集めのためにベンチャーキャピタルを回ろうとしたんです。でもその時、猪子さんに猛然と止められて。
猪子:ははは。 数年ぶりに、役員が全員集合して!
片桐:その直後、広告ビジネスが軌道に乗ってなんとかこれまで運営を続けていくことができました。去年の夏なんか暇すぎて会社に来てもTwitterやFacebookばっかりしてて、猪子さんに相談してたほどですから(笑)。
猪子:僕らもしょっちゅう、キャッシュアウトしそうになることあるんですよ(笑)。でも、もう個人の力ではどうにもならないからなー。
―お二人がご苦労されているWeb業界では昔も今も、数多くのWebサービスが世界中で生まれています。その中でお二人が注目しているサービス等はありますか?
猪子:実は僕、あんまり他のWebサービスのこと知らないんですよね。よく片桐さんに聞いたりしてます(笑)。強いて言うなら、ブラウザの外側にあるものや、ブラウザ内で完結しないものに興味がありますね。空間やモノとネットワークが繋がる世界に。
片桐:僕は「BOOKSCAN(ブックスキャン)」とかかな。サービス自体というより、世界一本がスキャンされている状態、そんな工場みたいなところが好き。スキャンしてる人も含めて、システムとして動いている感じが良い。
猪子:でもBOOKSCANのようなサービスは、日本独自の特殊な環境だから、というのもあるよね。他の国は最初からデジタル化して売ればいい話だし。日本だけはかたくなに未来に抵抗しているから、グローバルの常識と日本の常識とのかい離が生まれる。
片桐:確かにそれはありますね。
チーム力を最大限生かしつつ、各自の得意分野で勝負する
―そうした厳しい環境の中では、なかなか斬新なサービスを生み出すのは難しそうです。
その中で今後、若いエンジニアが活躍していくためにはどうすればいいのでしょうか?
片桐:「一人で完結する仕事」ではなく、チームで仕事をしたほうがいい。ネットの世界には、先ほど触れた音ゲーのように、とんでもないサービスを生み出す有能なエンジニアがたくさんいるし、その中で普通のエンジニアが一人で勝負を仕掛けても、まず勝てない。
せっかく会社にいるんなら、チームとして動くべきだし、その方が結果的にすごいものが生み出されると思いますね。
猪子:一人で完結する仕事というのは、ネットに無数にいる優秀な人達に勝てないし、その人達によって非経済な領域にされてしまう。つまり、仕事じゃなくなってしまう。
―具体的には、どのようにチームの力を活用していけばいいのでしょうか?
片桐:ピクシブには“その道のスペシャリストたち”が集まっている。そうなると、社内には数人だけしかその道のスペシャリストがいないことになります。だからこそ、より深く専門知識や技術を追求するために、外部のコミュニティへの参加を推奨しているんですね。
コミュニティで新しい技術をキャッチアップして、会社内に還元する。その技術を実際にビジネスとして活用して効果を出す。さらにその結果をコミュニティにフィードバック。そうやって会社とコミュニティ、そしてエンジニアの三者に対して利益を還元していく。つまり会社の中で“スペシャリスト”としての活躍が求められつつ、コミュニティの中でスペシャリストとしての知識・技術・情報感度を磨いていく、いわば“ハイブリッド型のワークスタイル”によって、エンジニアがうまくチームの力を活用していけばいいんじゃないかな。
猪子:チームラボも各メンバーはそれぞれ得意の専門領域を持っているし、専門領域は、本当に、数学から建築まで多岐にわたっている。そして、違った専門領域同士が、各自の得意領域をぶつけ合い、共に考え、共に創ることでしかできないようなことが少しずつでもできていったらいいなと思っているんだよね。でも、まだまだプロジェクトが違うと、自分でできる範囲でやってしまうところもあって難しいんだけど。
僕自身は本当、昔と比べてはるかにチームラボという組織に依存する割合が高くなってきていて(笑)。今では自分一人で考えることなんて全くなくなっていて、必ず社内のメンバーとディスカッションをして、プロトタイピングを見ながらまた、みんなで考える状態になっていて。もはや、1人で考えることなんてできなくなっている。だから若いエンジニアにも、一人では考えられないようなことをチームによって考えられるような人になってほしいし、一人では創れないような創り方ができるようになってほしいよね。
スカウトを活用して、チーム力を活用できる環境に出会うチャンス!
組織の力を活用するチャンスが高い企業への転職を目指すならば、スカウトを活用してはいかがでしょうか?
匿名レジュメを登録しておけば、あなたの経験やスキルを評価した企業や、リクナビNEXT提携の転職エージェントから声がかかります。レジュメ内に、自分の専門分野やスキルを具体的にどう生かしたいのか書いておけば、あなたの力を生かせる企業から注目される可能性が広がります。
まだ始めていないという人は、今すぐ登録してみましょう。
- EDIT&WRITING
- 山田モーキン
- PHOTO
- 勝尾仁