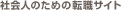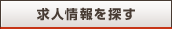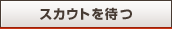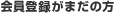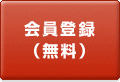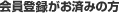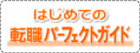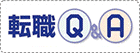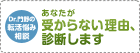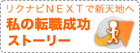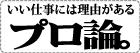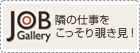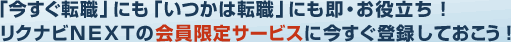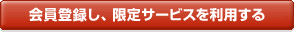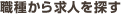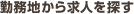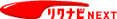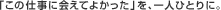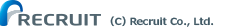転職トップ > 転職成功ノウハウ > 転職パーフェクトガイド > 転職活動 基本の「き」 > ヒューマノイドを開発せよ!電気エンジニアの意外力
ヒューマノイドを開発せよ!電気エンジニアの意外力
エンジニアに人気の高いヒューマノイドロボット。ただ、残念ながら開発に携われる人は少数派だ。そこで今回は電気系エンジニアを対象に、実際の開発内容と参入へのアドバイスを取材した。仕事は大変だけどかなり面白そうだ。
2013年1月23日

電気の力でヒューマノイドロボットを作ろう!
実物のガンダムを作りたい! モビルスーツを動かしたい!
――有限会社はじめ研究所
今年末までに目指すのは、4m×300kgの「ガンダム」
|
今でも多くの熱狂的なファンを集めるTVアニメ「機動戦士ガンダム」。実物を作りたいと願った少年はこれまでに何万人、何十万人といただろうが、それを実現しつつあるエンジニアは坂本元氏しかいないのではないか。 そして昨年8月、大阪の「西淀川ものづくりまつり2012」でその下半身を公開。「はじめロボット43号」である。サイズは全長が約3.5m、重量は約250kg。坂本氏と、西淀川区の町工場が集まった「西淀川経営改善研究会(NKK)」が共同で開発した。 坂本氏は2005年、「2年ごとに身長を2倍にする」という計画を立てる。2007年に全長1mの「はじめロボット25号」、2009年に2m10cmの「33号」を開発し、2010年から4mサイズをスタートした。上半身を加えた約4m×300kgの「43号」の完成を今年末までに目指しており、次の目標が8m。その次がガンダムの「実寸」ある18mで、夢が実現する。 |
|
苦心しているのは、付属のモータードライバの制御

使用しているサーボモーター

開発中のジョイスティック

プロジェクトのメンバーと工場内で撮影
身長を2倍にすると体積と重量は8倍になる。メカ的に大きな課題は軽量化で、脚部には薄さ2ミリのアルミを使うと同時に、箱形にするなどして強度を高めた。一方、電気的に大きな課題はモーターだった。「33号」では出力60Wのものを12個組み込んだが、「43号」では1kWを10個にして、関節などの仕組みも変えた。身長が伸びるだけでなく、操縦する坂本氏の体重も加わるからだ。
「そのために産業用ロボット用のサーボモーターに変えたのですが、これがネックになりました。33号まではモーターを制御するモータードライバを自作していたのですが、今のドライバはモーターとセットのもの。チューニングの幅が狭いのです」
ロボットの操作はコックピットのジョイスティックで行う。スティックの動かした角度をPCで計算し、腰や脚の関節などの角度を決めて、そのデータをモータードライバに送り、モーターを動かす。腰の周辺につけたジャイロセンサーが角度を検出し、情報をフィードバックしている。
小型ロボットから培ってきたノウハウがあるので、この連携はうまくいくという。しかし、産業用ロボットの特徴は同じ動作を何度も正確に行い、異常が出たらすぐに止まること。これが二足歩行に向かないとのことだ。
「脚が地面に接触したときの振動や、全体の揺れなどのショックで、ロボットが止まってしまうのです。また、人間もそうですが、片足で立つ時には踏ん張るので力が入りますが、足が地面に当たる瞬間は膝の力が抜けます。今のドライバではこの動作をさせるのも難しいのです」
このため、センサーで揺れを検出して揺れ止めをしたり、脚のクッションを強化するなどを考えているが、ドライバの自作も視野に入れている。ただ、「お金も時間もないので避けたい」とのことだ。
「今は脚を10〜20cm上げて歩行する仕組みですが、もっと早く走れるようにしたい。すると、地面に当たる振動が大きくなるので、余計難しくなります。電気系エンジニアの方に解決策を教えてほしいですね(笑)」
上半身の動きにはマスタースレーブ方式を採用
|
こうしたモータードライバの制御は、ヒューマノイドロボットにおける電気系エンジニアの活躍の中心だ。また、坂本氏のような重工業出身の強電系だけでなく、弱電系の人材も技術が活かせるという。 43号ではカメラを頭部、肩、胸などの数カ所につけて、その視覚情報をコックピットのPCモニターに送る。それを見ながらジョイスティックを操作するのだが、その角度データなどをPC、マイコン、モータードライバ、モーターへと伝える電気系統でも腕が活かせそうだ。 「上半身は動きの自由度が多彩ですし、コックピットから見えない部分も多いので、腕と腕、腕と胴体が当たる危険もあります。計算での制御も考えましたが、逆に計算を不要にするマスタースレーブ方式にしました」 |
|
人間にそっくり! アンドロイド型ロボットは技術が違う
――株式会社ココロ
「エアサーボ」で柔らかい表情、しなやかな動作を実現
|
ヒューマノイドロボットには、二足歩行ロボットのようなフィジカルな動きを目指すタイプがある一方、人間の豊かな表情や繊細なしぐさを追求する「そっくり型」もある。後者の代表が株式会社ココロの「アクトロイド」だ。同社はアンドロイド研究の第一人者である、大阪大学の石黒浩教授との共同開発企業としても知られる。 「すでに発表している『アクトロイド-DER3』以降も数体のアクトロイドを開発しており、未公表の2012年製作モデルでは、より的確な表情変化で喜怒哀楽を表現しています。口形状の再現、特に母音発声時の精度を上げて、唇を突き出す『お』の発音形状を表現できました」 「空気は体積変化がとても簡単に起きるので、一般常識から考えると機械を制御するには向きません。しかし、モーターや液圧といった駆動元と異なり、動作をしなやかに柔らかくできます。弊社では空気に関するアルゴリズムを長年培い、確立してきました」 |
|
工夫したのは可動箇所のセンサーと省配線回路設計
アクトロイドの命題は外見を人間により近くし、親近感を損なわないようにすること。そのため電気系統においては、少しでも柔らかくしなやか、かつやさしい動作をするためのフィードバックができるセンサーを開発した。
「可動箇所にはエアシリンダがあり、各々にポテンショメーターと呼ばれる、アナログ値が測定できて絶対値が取れるタイプのセンサーを、抱かせる形で配置しています。10カ所動かす場合は10個のセンサーが必要になります」
すべてのアクトロイドは仕様に応じてカスタマイズしているので、可動箇所や動きの種類は異なるが、DER3の場合で55点にも上る。ここで問題になるのは、センサーを含めた必要な機構を、必要な機能を満たしつつロボットの中に収めること。金子氏は「省スペースが必須なので、サイズと性能のバランスが難しい」と語る。そこで、省配線回路設計による総合制御を考えた。
センサーには最低で電源線と信号線が必要だが、センサーの数だけ信号線がある状態では配線が増えてしまい、ロボットの動きを束縛する。狭い可動部位の配線では動作に伴う断線の危険性も出てくる。省配線回路はこうしたリスクを低減する目的もあるのだ。
「具体的な省配線設計としては、複数のセンサー情報を各部位単位に集約し、1本でメイン回路につなげるようにしました。人間で言えば神経網のような形ですね。今はセンサー信号の集約しかできていませんが、駆動やカメラなどの分野にも適応できるシステム開発を目指しています」
リアリティと近視眼的な精緻さを追求する姿勢が大切
「エアサーボ」という空気を使った駆動方法に合わせた、回路やセンサーの開発。これだけでなく、外形に合わせた省スペース設計も電気系エンジニアの知恵の出しどころというわけだ。そして、アクトロイド開発にはほかにはない特徴がある。
「接近して対峙しても人間的なリアリティが表現されていること。ただ動かすだけでなく、ユーザーの気持ちを考えた近視眼的な精緻さを追求すること。こうした姿勢が開発エンジニアに求められます」
また、同社のロボットはイベントなどでも使われるので、ユーザーがロボティクスの専門家ではなく、一般来場者である場合も多い。そのため、「高性能ながら扱いやすいものであるべき」とのこと。制御の向上は性能だけでなく、操作性や安定性にもつなげる必要があるというのだ。
「今後も表情機能、特により鮮明な喜怒哀楽の表現や、音声発音時の唇形状の模索は続けます。また、体全体のアクティブな動き、フィジカルな動作の開発もしているんです。将来的には、マラソンくらいさせたいと思っています」
電気系エンジニアがヒューマノイドロボットに参入するには
――千葉工業大学未来ロボット技術研究センター(fuRo)
ヒューマノイドは統合技術の塊、幅広い知識が不可欠

千葉工業大学
未来ロボット技術研究センター
上席研究員
清水正晴氏

fuRoが参画したNEDO委託事業(次世代ロボット共通基盤開発プロジェクト、次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト)において開発されたモータードライバ基板。大きいものが初代、小さいほうが出力が約2倍の最新型
小型ヒューマノイドロボット「morph」を始め、福島原発内の探査ロボット「Rosemary」や「Sakura」、オリジナル電子工作キットの「f-palette」など、さまざまな分野でロボット開発を進めるfuRo。NEDOのプロジェクトへも数多く参加し、民間企業やほかの研究機関との共同開発にも積極的だ。
上席研究員の清水正晴氏に、ヒューマノイドロボット開発における電気系エンジニアの役割について教えてもらう。技術レベルはやはり高そうだ。
「ヒューマノイドロボットはメカ、エレ、ソフトの統合技術の最たるもの。基礎的な研究や技術開発を積み上げ、ベースとなる基板の開発に10年掛かると言われます。参入してスタートラインまで10年ですから、『死の10年』と呼ばれます(笑)」
だからこそ、各分野にスペシャリストがいる総合家電メーカーや自動車メーカーが、ヒューマノイドロボットを開発できるのだという。そして、各分野の密な連携が開発のカギとなる。
ロボットは動いて、止まって、曲がる。これらは主にモーターをモータードライバで制御することで実現するが、止まる時には場所を検出するセンサーを使う場合もある。すると、分解能を考慮したり、検出はアナログなのかデジタルの信号処理にするのかなど、思考する技術範囲が広くなる。
「同じ電気系でもそうですし、メカやソフトなど専門以外の知識もある程度必要になります」
その分、電気系エンジニアが専門性を発揮できる分野は多い。中心となるのが複雑な制御を行うモーターのドライバ開発だ。
電気系エンジニアへのアドバイスは「手を動かすこと」

fuRoが開発したサーボ―モーターの試作品。モーター、モータードライバ、ハーモニックギヤ、ギヤの角度を測る絶対角度センサーが内包。出力トルク最大30[Nm]

fuRoが開発中の大型ロボット脚部のプロトタイプ1号機「core」。全長1.9m、重量230kgで、100kgの可搬重量性能を持つ
モーターの制御技術は、家電、機械、産業用ロボットなど多くの分野で使われるが、逆転と正転をさせること、速度に加えて角度を制御することなどがロボット開発の特徴だという。
「また、ロボットは動き続けるわけではなく、歩かせていても負荷の掛かる動きとそうでない動きが偏在します。重視するのはトルクかスピードか、電圧か電流か、どこに何アンペアで定格(仕様)を持ってくるのか。こうしたトレードオフの選択を常に迫られます」
同じロボットでも一般的な産業用ロボットであれば、電源やモータードライバを外に出し、据え置きのコントローラーに入れることも可能だ。高出力、高電力で動かす場合は特にそうなる。しかし、自立型や移動型ではモーターに加えてこれらをロボットに組み入れることが多いため、機器のサイズや重量の制約も極めて高くなる。
こうしたモーターの制御にはさまざまな要素がある。まず、強電と弱電があり、何十アンペアと電流が流れるアナログ回路、マイコンなどのデジタル回路、ファームウェアが一体となっている。
「アナログ回路ならFET(電界効果トランジスタ)で電流の流れる方向をスイッチします。ブラシ付きDCモーターならHブリッジで行いますが、理想的には時間ゼロでも、実際にはナノ秒単位の時間が掛かります。そのため、時間ゼロでソフトを組むと回路がショートしたり、発熱して電流を消費したりする。デジタルだけで考えるとこうなるので、オシロで波形を見るなどして作業を進めます。こうした地道な作業の経験が欠かせません」
スイッチングに時間が掛かると知っていても、自社の仕様書の時間をそのまま信用しているエンジニアは結構多いと清水氏。しかし、なぜそのスペックになったのかは知らないし、疑わない。実際に手を動かすと原理原則がわかってくるという。
「スイッチの切り替えはマイコンで行うので、そのファームウェアを書いてみてもいいでしょう。あるいは、モーターの動きから位置や角度のセンサーの分解能などを考えてみる。こうしたことがわかると一歩踏み出せます」
世界中で始まったヒューマノイドロボットの開発競争
|
センサーには視覚や聴覚のほかにも、回転や直動の動きを測る位置センサー、トルクや受ける力を測る力センサーなどがあり、これらの情報のフィードバックを回路と連動させることは不可欠。もちろん、デジタル回路やバッテリーの電源回路も電気系エンジニアの担当だ。思いのほか、活躍できる舞台が多いとわかるだろう。 そのため、開発には制約が多くなる一方で、本格的な利用はこれからだ。それでも、ヒューマノイドロボットの開発が世界的に過熱しているのは、ここで得た高度な技術力をほかの分野に転用できるからと、まだ見ぬ用途への期待が大きいからだろう。 |
|
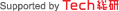
簡単、便利、チャンスあり!
今すぐに「レジュメ登録」で準備をしておこう
ヒューマノイドロボットを作りたい!
しかし、実際には募集が少なく、技術のハードルも高い。
こんな「希少価値」的な仕事を見つけるのは大変ですね。
スカウト登録と使うと、こうした企業からのチャンスが飛び込んでくるかもしれません。転職エージェントからのオファーも期待できます。
まずは匿名レジュメの登録をしてはいかがでしょうか?
- EDIT&WRITING
- 高橋マサシ
- PHOTO
- 平山 諭(fuRo)