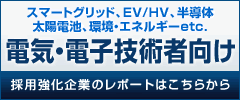ジュネーブモーターショーで魅せた自慢のコーナリング! |
 |
トヨタの超小型EVが発進!
|
フロントに大きな2輪、リアは小さな1輪の、「超小型3輪EV」

ジュネーブモーターショーに出展されたトヨタ自動車の超小型EV「i-ROAD」
―― ジュネーブモーターショーで「i-ROAD」はとても注目されたようですね。
谷中 おかげさまで好意的な意見が非常に多く、いろいろなメディアでも取り上げていただきました。とてもうれしく思っています。
―― i-ROADは前輪が2つ、後輪1つの3輪構造になっています。この理由を聞かせてください。
谷中 クルマの運動はブレーキを掛ける「制動」のときに最もGが出るんですね。その次がコーナリングで「旋回」するとき。つまり、クルマが一番不安定になりがちなのが旋回制動、すなわち、コーナリング中にブレーキを掛けるときです。
この旋回制動時に物理的にクルマを安定させる目的で、フロントを2輪にしました。一方のリアのタイヤは、機構の成立性やシンプルさを追及するなどの結果から1輪になりました。
私は「i-Swing」(パーソナルモビリティのコンセプトカー:2005年の第39回東京モーターショーに出展)や、「i-REAL」(同:2007年第40回東京モーターショーに出展)の開発にも携わってきました。これらが3輪だったという理由もありますが、i-REALを出展したときにはまだi-ROADのアイデアはなかったですね。
―― 前輪は16インチ(80/80R/16)と大きく、逆に後輪は10インチ(130/70R/10)とかなり小さめです。
谷中 後輪のサイズを小さくした理由のひとつは、スペースの関係からです。i-ROADは2人乗りで、ドライバーの後ろにも人が乗れます。そのシートの下に後輪やサスペンションが入るので、外形の大きなタイヤにするとクルマの背が高くなり、重心も上がって、安定性が悪くなります。
そこで後輪は外形を小さくしたわけですが、一方では安定性を保つために、タイヤの幅は前輪に比べて格段に太くしました。タイヤのサイズで言えば、実は前輪はもう少し小さくしたかったのです。ただ、インホイールモーター(各2kw)やブレーキなどが入りますから、これ以上は厳しかったですね。
クルマ1台分にi-ROADを4台駐車、課題は開閉するドア
 トヨタ自動車株式会社 |
―― こうした部品や機構、機能などから全長(2350mm)が決まっていったのですか? 谷中 いえ、結果論ではなく狙っていきました。街中でバイクのように使う場合、例えばヨーロッパでは、道路の脇にバイクの専用駐車場があるんですね。そこに駐車することも想定して、大きめのスクーターサイズに収めようとしました。 ―― 駐車時も想定して、開発を進めてきたわけですか。 谷中 駐車スペースに関しては、クルマ1台分のスペースにi-ROADを横に4台並べて停めるというコンセプトです。ただ、ドアを大きく開けないと乗り降りできないのでは、車間をある程度取る必要が出てきます。これではいくら横幅(全幅)を狭くしても4台は停められません。 ―― 横幅ですか? 850mmとなっていますね。 |
こだわったのは「横幅」、クルマとバイクの「いいとこ取り」へ


谷中 i-ROADは短距離用の小型モビリティです。ターゲットユーザーは特に限定していません。例えば、自宅から最寄駅までの通勤用、幼稚園や保育園への子供の送り迎え、雨の日の買物などに利用していただければと思います。
―― 確かに。i-ROADにはルーフとドアがあるので全天候型ですし、ヘルメットも不要ですね。最高時速は45kmで、これらの用途には問題ないと思います。
谷中 こうした用途を考えても、1車線を占有するクルマと同じような横幅にするより、クルマとうまく共存しながら道路の端も走れるバイクの幅にしたほうが、うまく道路が使えるのではという仮説が出ました。
ただ、私はバイクは素人ですから、手探りで始めました。バイクの横幅や、ライダーがハンドルを握ったときの腕の張り出し具合などを調べたわけです。そうしたら、横幅はまず1mを切っていて、850mmくらいに収まっていることがわかりました。
このようなことから、クルマでもバイクでもない、両方の「いいとこ取り」をしたモビリティというコンセプトが生まれてきました。
―― ただ、クルマの幅を狭くすると倒れやすくなりますね。
谷中 カートのような低重心ではなくある程度の重心高がありますから、確かにそうなります。この解決は重心高とホイルベースなどの物理的な関係から決まりましたが、より大きな課題は、「ドライバーが違和感なく乗れること」でした。こればかりは試してみないとわかりませんから、実験車をつくってトライアンドエラーを繰り返しました。
コーナリングでのボディの傾きについても同様です。バイクのように車体を大きく倒すようには考えませんでした。実際、最大に傾斜させて26度くらいでしょうか。街中では20度も傾けば十分だと思います。
傾けるだけならさほど難しい話ではないのですが、人間の感覚に合うようにするのが難しかったですね。
「アクティブリーン機構」で快適なドライビングが実現



―― 旋回Gに合わせて、車体の傾きをECUで自動制御しているとか。
谷中 はい。運転中にハンドルを操作すると、ある車速である旋回Gで曲がるのだと次の運動が予測され、最も適した傾きの角度が決まります。
そこに向けて独自開発した「アクティブリーン機構」の動作を演算して、自動的にアクチュエートしていきます。クルマの姿勢はジャイロセンサーやGセンサーを使って認識しています。
―― ドライバー自らが車両のバランスを保つ必要はないと。
谷中 そうです。2つの前輪に取り付けたストラット(通常は直立でシンプルな機構のサスペンション)の上部を可動にして、2つのストラットの間をバーでつなぎます。
私たちはこれを「シーソー」と呼んでいますが、シーソーの間に回転軸があり、減速機を介してモーターとつながっています。例えば、ハンドルを右に回すとある旋回Gで曲がりたいのだと認識され、演算の結果シーソーが右に傾き、右のタイヤが下がって、左タイヤが上がります。こうしてボディが自動的に倒れるわけです。
―― この機能は路面の段差や凹凸にも対応できるのですね。
谷中 幅の狭いモビリティでは路面の段差があると、幅のあるクルマよりもボディの傾きが大きくなります。道路の端を走る場合には凹凸も多くなるでしょう。するとクルマ自体が不安定になるだけでなく、ドライバーも不安な気持ちになります。段差の吸収は小型モビリティ開発の課題なのです。
一般的なクルマではタイヤが持ち上げられるとボディが傾きますが、i-ROADはボディの角度はジャイロセンサーで認識しています。段差や凹凸があるとそれを察知してアクチュエーターを動かし、ボディを平衡に保つようにしています。傾きを常時認識し、自動制御しているわけです。
―― アクティブリーン機構にはサスペンションの機能も含まれているのですか?
谷中 秘密です(笑)。ここにサスペンションの機能はありませんが、その機能はもちろん備えています。
―― パワートレインにはインホイールモーターを用いています。また、バッテリーはリチウムイオン電池で、一充電での走行距離50km(時速30kmでの定速走行時)です。これらの開発は御社でなさったのですか?
谷中 インホイールモーターはグループ会社との共同開発です。リチウムイオン電池の開発については再び秘密です(笑)。
i-ROADはゴールではない、実証実験に向けた開発が続く


―― 谷中さんのご経歴を簡単に教えてください。
谷中 大学の機械工学科を卒業して、1993年に弊社に入社しました。最初の7〜8年はシャーシの設計、次の3〜4年は主にシャーシの制御システムの開発をして、その後はマーケティング部門に移りました。社会のトレンドを探って、それを技術で生かすことを考えるチームです。
技術開発のみですと、お客さまや社会のことを考えてはいても、どうしても触れる機会は少なくなります。ですから、街に出たり、いろいろな人にお会いしたり、自動車だけでなく別の業界を調べたり、幅広く勉強させてもらいました。トレンドをコンセプトカーに盛り込むために、i-Swingやi-REALの企画開発も担当しました。
それから、製品企画の先行領域を、中長期的に考えるような仕事に移りました。名刺に「Z-AD」とありますが、「Z」は車両開発の取りまとめをするチーフエンジニアを意味しています。「AD」はアドバンストの意味で、先行的にクルマを考えていくチームという意味です。
―― 2014年末から3年間、フランスのグルノーブル市で実証実験が始まるようですね。公共交通機関とリンクさせた近距離移動用にi-ROADを提供するとか。カーシェアリングのための情報管理システムも御社が開発すると聞きました。
谷中 今後の都市交通の課題を考えたとき、クルマというハードウェアの単体はもちろんですが、サービスやシステムを提案する必要も出てくると思います。公共交通を視野に入れた実験的な試みも考えられます。こうした取り組みの結果に生まれたのが、グルノーブル市のプロジェクトです。
現段階でのi-ROADはあくまでもコンセプトカーです。実証実験に向けて現在も開発中ですし、リアルな道路環境で安心して使ってもらうことを考えています。i-ROADはゴールではありません。100点満点でいえばまだ50点くらい。これからが本格的なスタートです。
このレポートを読んだあなたにオススメします
発見!日本を刺激する成長業界
低速EVが発進!コストダウンと法整備で普及を目指せ

話題のi−REAL、PIVO2、CR−Z…開発者に突撃取材!
やっぱりクルマが好きだ!東京モーターショー2007
2005年に引き続いて、第40回目となる東京モーターショーが開催された。Tech総研では国内自動車メーカー4社の開発エンジニアに…

第3世代「EV3」が新発売!プログラマのスキルアップにも!
増井雄一郎が熱中するレゴ マインドストームの魅力
レゴ社とMITが開発した「レゴ マインドストーム」。各種センサー、サーボモーター、CPU、パーツなどが揃ったロボット開…

電極チップで網膜を刺激して光、ロボットハンドを意思で制御
見える!動く!人工眼とハイテク義手で人間が進化する
失明した人への人工視覚、手を失った人への筋電義手……。今、機械と人間を融合させた「バイオニックヒューマン」への技術が急激な進化を…

週刊 やっぱりR&D 求人トレンド解析室
工作機械/日本のお家芸に“次世代型”が次々に誕生!
![]() 日本の製造技術の高さを支えてきた、工作機械の技術進化が止まらない。ナノスケールのNC、金型レス加工など、独創的なテクノ…
日本の製造技術の高さを支えてきた、工作機械の技術進化が止まらない。ナノスケールのNC、金型レス加工など、独創的なテクノ…
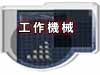
応募者は「イケた!」と思ったのに……なぜ不採用?
スキルが高い人材でも「NG」を出した人事の証言
求人の募集要項にあるスキルは満たしていたのに、なぜか結果は不採用。そんな経験をした人も多いのでは? では、採用に至らな…

あなたのメッセージがTech総研に載るかも