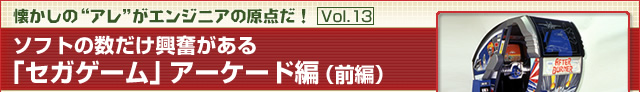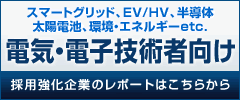|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
���̃��|�[�g�̘A�ڃo�b�N�i���o�[
�������́g�A���h���G���W�j�A�̌��_���I
�����̃G���W�j�A���q���̍��A�S��D��ꂽ���́B�������̉����������i��ʂ��ăG���W�j�A�����萶�������_��T��܂��B

���̃��|�[�g��ǂ��Ȃ��ɃI�X�X�����܂�
�������́g�A���h���G���W�j�A�̌��_���I
�\�t�g�̐���������������u�Z�K�Q�[���v�ƒ�p�@��
![]() �Z�K�̃A�[�P�[�h�Q�[���ɔM�����������U��Ԃ����O��B����́u���K�h���C�u�v�Ȃǂ̉ƒ�p�Q�[���@�ƁA�������琶�ݏo����c
�Z�K�̃A�[�P�[�h�Q�[���ɔM�����������U��Ԃ����O��B����́u���K�h���C�u�v�Ȃǂ̉ƒ�p�Q�[���@�ƁA�������琶�ݏo����c

�������́g�A���h���G���W�j�A�̌��_���I
���ꂼ�J�X�^�}�C�Y�̌��_�gNEC PC�h�̖��͂Ƃ́E�O��
![]() 80�N��́u�}�C�R���v�u�[���ɓo�ꂵ�����X��PC�B���̒��ł��uPC-8001�v�uPC-98�V���[�Y�v�Ƃ��������@�����X�c
80�N��́u�}�C�R���v�u�[���ɓo�ꂵ�����X��PC�B���̒��ł��uPC-8001�v�uPC-98�V���[�Y�v�Ƃ��������@�����X�c

�������́g�A���h���G���W�j�A�̌��_���I
�v���O�����́g����́h�������Ă��ꂽMSX�Ƃ́E�O��
![]() 80�N��ɓˑR�K�ꂽ�u�}�C�R���v�u�[���B���̎���ɏ��߂ăp�\�R���ɐG��A�M�������o���̂���G���W�j�A���������Ƃ��낤�c
80�N��ɓˑR�K�ꂽ�u�}�C�R���v�u�[���B���̎���ɏ��߂ăp�\�R���ɐG��A�M�������o���̂���G���W�j�A���������Ƃ��낤�c

�������́g�A���h���G���W�j�A�̌��_���I
�������̃t�@�~�R���Q�[�����G���W�j�A�̌��_���I
![]() ���w���̂���A��������V�t�@�~�R���B�t�@�~�R����ʂ��ď��߂ăR���s���[�^��v���O�����Ƃ������̂ɐG�ꂽ�Ƃ����G���W�c
���w���̂���A��������V�t�@�~�R���B�t�@�~�R����ʂ��ď��߂ăR���s���[�^��v���O�����Ƃ������̂ɐG�ꂽ�Ƃ����G���W�c

�������́g�A���h���G���W�j�A�̌��_���I
�܂��Ƀv���O���}�̌��T�I�u�x�[�}�K�v�̖���
![]() 100�y�[�W�ȏ�ɋy�ԁu���e�v���O�����R�[�i�[�v�A�ق��̒ǐ��������Ȃ��قǃQ�[���U���ɗ͂���ꂽ�u�X�[�p�[SOFT�R�[�i�[�v�B���c
100�y�[�W�ȏ�ɋy�ԁu���e�v���O�����R�[�i�[�v�A�ق��̒ǐ��������Ȃ��قǃQ�[���U���ɗ͂���ꂽ�u�X�[�p�[SOFT�R�[�i�[�v�B���c

�l�����������̓]�E�E�҂̏p��31
�o���Ȃ��悤�ɃR�b�\���]�E�����������ł�����@�̊�
�ݐВ��ɓ]�E����������ꍇ�A���̉�ЂɃo���Ȃ��悤��������T�d�ɐi�߂������́B�Ƃ��ɂ͉Ƒ���F�l�ɂ������Ŋ����������P…
![�o���Ȃ��悤�ɃR�b�\���]�E�����������ł�����@�̊�](../contents/ts/img/rec_rnn/rec_rnn_02.jpg)
���Ȃ��̃��b�Z�[�W��Tech�����ɍڂ邩��