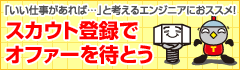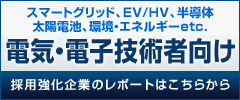|
 |
|
ソーシャルアプリに携わるエンジニアで、知らない人はいない「GREE」。その国内有数のサービスを技術面で支えるのがグリーCTO、藤本真樹氏だ。オープンソース「PHP」のコミッターとしても知られる藤本氏に、エンジニアのキャリアと仕事の醍醐味を語ってもらった。
(取材・文/上阪徹 総研スタッフ/宮みゆき 撮影/栗原克己)作成日:09.12.09
|
|
|
|
|
|
|
|
このレポートに関連する企業情報です
2004年2月に、ソーシャル・ネットワーキング・サービス (SNS) 「GREE」を公開、日本だけでなく米国・欧州などグローバル展開を進め、世界で億単位のユーザー数を目指すソーシャルメディア事業をはじめ、ソーシャルアプリケーション事業、プラットフォーム事業、広告・アドネットワーク事業等を展開しています。続きを見る
このレポートの連載バックナンバー
人気企業の採用実態
あの人気企業はいま、どんな採用活動を行っているのか。大量採用?厳選採用?社長の狙い、社員の思いは?Tech総研が独自に取材、気になる実態を徹底レポート。

このレポートを読んだあなたにオススメします
ソーシャルアプリの未来を担うグリー採用の舞台裏
なぜ、グリーはSIer出身者を続々と採用するのか?
![]() モバイル版「GREE」の本格化で急成長を続けるグリーが、SIer出身者を続々と採用しているという。畑違いのように思える企業向けS…
モバイル版「GREE」の本格化で急成長を続けるグリーが、SIer出身者を続々と採用しているという。畑違いのように思える企業向けS…

『釣り★スタ』『踊り子 クリノッペ』開発リーダーを直撃取材!
グリーエンジニアが明かすソーシャルアプリ開発舞台裏
![]() 2006年にモバイル版「GREE」展開を本格化し、急成長を遂げたグリー。その原動力となったモバイル向けソーシャルアプリ『踊り子 …
2006年にモバイル版「GREE」展開を本格化し、急成長を遂げたグリー。その原動力となったモバイル向けソーシャルアプリ『踊り子 …

シンプルなゲームロジック、バッグエンドの高い技術力、UI設計…
GREEの「釣り★スタ」が長年支持され続ける理由とは
![]() リリースから今年で6年目を迎え、いまなお人気の高い「釣り★スタ」。動きの早いソーシャルゲーム業界の中で、なぜヒットし続…
リリースから今年で6年目を迎え、いまなお人気の高い「釣り★スタ」。動きの早いソーシャルゲーム業界の中で、なぜヒットし続…

グリーとOpenFeintは「世界の人を幸せにする夢」を共有する
OpenFeintジェイソン・シトロンCEOに独占インタビュー
![]() 「僕の究極の夢は、ソーシャルゲームを通して世界の人々を幸せにすること」──世界9000万人のユーザーに愛されるモバイルゲーム・プ…
「僕の究極の夢は、ソーシャルゲームを通して世界の人々を幸せにすること」──世界9000万人のユーザーに愛されるモバイルゲーム・プ…

Webビジネス、BtoCサービスに携わりたいエンジニアに大チャンス!
SNS先駆者グリー田中社長がエンジニア採用強化宣言
![]() 会員数1500万人を越えた「GREE」。テレビCMなどの大規模プロモーション活動を展開し、ネット業界でも異例の急成長を遂げたグリ…
会員数1500万人を越えた「GREE」。テレビCMなどの大規模プロモーション活動を展開し、ネット業界でも異例の急成長を遂げたグリ…

広める?深める?…あなたが目指したいのはどっちだ
自分に合った「キャリアアップ」2つの登り方
「キャリアアップしたい」と考えるのは、ビジネスパーソンとして当然のこと。しかし、どんなふうにキャリアアップしたいのか、…

あなたのメッセージがTech総研に載るかも